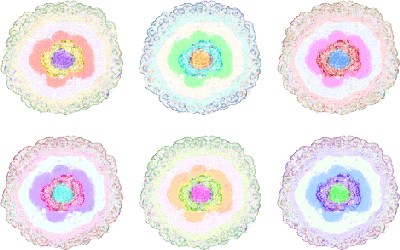
御子≠ヒロイン、メリーバッドエンド
どこまでも降り注ぐ氷六花の終着地は、人間がへばり付いて生きてきたこの大地である。重力と風に身を任せ、やがて地に到達した雪は、積もり積もると白銀の絨毯を織り成す。
白濁とした上空には、薄暗い雲が張り付いていた。
――ふたりの出逢いも、このように雪が舞う冬季のことだった。
険峻を雪で隠した隘路は、沈黙を好んでいるかのようだ。
まるで、この世界を否定しているがの如く、漆黒の法衣を身に纏っている人物は、ぽつりと独り其の世界を汚していた。
『こんにちは。一人旅ですか?』
横をすり抜けた途端に降ってきた言葉に、なまえは眩い銀世界に目を細めながら答えた。
『…いいえ、家に帰る途中です』
もしも、男が黒に身を包んでいなかったのなら、なまえはすんなりと答えなかっただろう。男の姿は、宛ら世界に反逆を起こしているに他ならないほど場違いに思えたからだ。
『そうですか。いきなり呼び止めてすみません。道中、お気をつけて』
特に話を広げるわけでもなく、笑顔を向けた男は空を仰いだ。
話しかけられた意味も解らないままに、なまえは訝しげな表情を刹那したが、其れ以上気に止めることも無く歩き出す。
すると、さくさくと踏みしめる道に自分と一回りも違う足跡を見つけた。無意味に振り向いた先には、やはり白銀の世界に黒が孤独を背負っている。ここに絵師がいたのならば、この光景を描き止めたいばかりに筆を握っていただろう。
これは、ひとつの芸術だった。とある決心を塗り固めた、男の決意だった。
なまえがこれに気づくのは、もう少し先のことである。
ふたりの邂逅は、あれから三日後のことだ。町に出かけていたなまえが、運悪く数人の男に絡まれた後に生じる。
「退いてください。急いでますので」
明らかに強引な軟派の言葉で呼び止められたなまえは、開口一番に上記を放った。少しでも怯えた表情や態度を見せれば、男達は付け上がることを、また幾度か似たような出来事は終始飽きるほど同じ展開であることをなまえは知っている。後半の言葉は、其れを踏まえた上で声を張り上げたのだった。
無論、返ってきた言葉は悪態ばかりで、なまえは、あからさまに眉間の皺を寄せた。人類皆兄弟と喩えられると同様に、なまえの目の前に立ちはだかっている男達もまた、過去の男と兄弟なのではと感じられるほど聞き飽きた言葉が降ってきたのだ。
何を言っても、きりがないと思ったなまえは、その辺にあった木箱を持ち上げると、未だ悪態を捲くし立てている男の顔面に投げつけた。まさかの展開に両隣にいた男たちが大声を上げる最中、なまえは忽然と姿を晦ました。
逃げたのである。
ひたすらに駆けた体は、刺すような低度を解すには良い塩梅だった。荒々しく吐き出された白い靄が、その様子を物語っている。
途中、後方を向いて逃げ切れたことを確認すると、なまえはようやっと立ち止まり安堵のため息を吐いた。
もうじき源頼朝が、ここ、平泉を攻めてくるという噂がある。其れを思えば、町中の男共よりも、鎧を身に付け、刀を手に襲ってくる恐怖の方が断然上だ。
「倒さなかったんですね」
ふいに沸いた声の方向に振り返ると、そこには三日前に出遭った格好と同じく、漆黒の法衣を身に纏った男が立っていた。
しかし、なまえは男が現れた事実よりも、耳に届いた言葉に驚愕していた。
「倒さないって…あたしは普通の……」
「なるほど。月日は君を女性に変えたようです」
男は、底が見えない笑みを浮かべる。「――なまえ」
「お久しぶりです。随分、綺麗になりましたね」
目線を逸らしたなまえは、小さく舌打ちをした。前回のように、他人の振りをしていればよかったと、脈ゞと後悔は流れている。
「…あの日、あたしだって気づいてたんじゃない」
吐き捨てた言葉に、更に後悔が圧し掛かった。話など広げるべきではなかったとしても得手勝手な口唇は言うことも利かずに動いてしまっている。
「いったい何が目的なの、鬼若」
「ふふ、懐かしい名ですね。武蔵坊弁慶だと以前、名乗ったはずですが」
「そんなの忘れたよ」
やれやれ、とかぶりを振った弁慶は、突如どこに隠し持っていたのか薙刀を手に取り、なまえに向けて一突きした。反射的にしゃがみ込んだ後ろでは、なまえが近くどこかで聞いたことのある男の声が響いている。
なまえが振り向くと、先程の男がうめき声を上げていた。
「ちょ、えええええええ」
何を言えばいいのか、込み上げてきたものがありすぎて百面相をしているなまえに対し、弁慶は悪びれた態度を取ることなく薙刀を下ろす。そして、また笑顔を一つ。「よかった」
「鈍ってはいないようで安心しました」
「安心したのは、あたしの方だ!」
「大丈夫ですよ。君が避けなくても、当たらないはずでしたから」
以前の弁慶、つまり鬼若と呼ばれていた頃の彼ならば、「はず」など付けず躊躇無しになまえごと刃を突き立てていただろう。策や邪魔者を払うためなら何をしてでもやり遂げた男だった。
成長したものだ、と考えるよりもやはり現状の突っ込みは追い付かない。
「はずってなに?!」
まあまあ、となまえを宥める弁慶は、ゆっくりと歩き出した。まるで付いて来いと云わんばかりの雰囲気に、仕方なく鉛の付いたような足をなまえは持ち上げた。
「僕達が幼い頃、よくちゃんばらをしましたね。九郎も一緒に――」
「あれをちゃんばらで片付けるなんて…」
当時の"ちゃんばら"をなまえは今でも鮮明と憶えている。
喩えるなら、小さな戦だった。京にてなまえも、弁慶と徒党を組んでいたのだ。
怒号と共に何十人もの若者が、若いが故に刃を振り落とした。当時、弁慶も九郎も、まさか互いが主従関係になるとは思いもよらなかっただろう。
気づかない場所に幾つもの情熱と痣を作り、勝利を飾りたかった、あの青い春。
「それにしても変わるもんだね。まさか鬼若――弁慶が鬼から仏みたいな面構えになってるんだから」
隣に並んだ鬼若、否、弁慶は幼名の如く、まさに鬼の強さと形相を持っていた。其れがどうだろう。なまえが見上げれば、あの頃とは真逆の穏やかさが滲んでいる。牛若と対立を繰り返していたときとは比べ物にならない程だ。
「仏、ですか。ふふ、九郎が聞いたら笑うでしょうね」
こうした対応も、どこか居た堪れない。昔は、笑うといえば、嘲笑が多かった。
なまえからすれば弁慶は名と共に変わってしまったと感じている。ただ、時々食えない笑みを浮かべるのは唯一変わっていないようである。
「…どうして会いにきたの」
なまえは、寂しさと同時に出会った偶然に違和感を抱いていた。あの日の邂逅は、今日のように仕組まれたものがあると踏んでいる。あの弁慶のことだと。
「知ってたよ。もっと前に弁慶たちは平泉に来ていたんでしょ? 今さら、あたしに――」
なまえの言葉を遮るように弁慶は口を開けた。「どうして、ですか…」
ぴたりと両脚を止めた弁慶に、つられてなまえもまた脚を止める。
共に歩いてから一度も目線を合わせなかった弁慶が、ようやく向けた面貌は酷く真面目なものだった。
「君に会うのに、理由は必要ですか」
まるで何年も離れた恋人同士が交わす言葉のようだが、なまえと弁慶は、そういった間柄ではない。
九郎と旅立ったあの日、ふたりはまるで明日にでも会うような挨拶で決別した。
『では、また』
『うん、またね』
未だ十代だったなまえは、二人から疎外感を感じていた。其れは今も胸にしこりとして残っている。
――自分が女である故に、共に行けないのだろうか。
足手まといや荷物と思われるのなら、現実を受け止めて何もない素振りを見せようと、其れはなまえなりの精一杯の祝福だった。もう会うことは無いと決め込んでいたのもある。また、と言ったものの会えるとは思っても見なかった。
なぜなら九郎は、源家の血を引き庶民とはかけ離れた存在であり、九郎に付き添うことになった弁慶もまた同義。
「君が平泉にいるという情報を聞いて、居ても立ってもいられなくなりました。会うつもりはなかったんですけどね、会いたくなったんですよ」
「勝手な男」
「なんとでも罵って構いません」
そっぽを向いたなまえに弁慶は苦笑すると、まるで暖めるかのようになまえの手を取った。反射的に、なまえの手に力が籠る。何年かぶりの、体温だった。
「もうすぐ、ここは戦火にさらされます。その前に君は逃げてください」
「…鬼若は? また昔みたいに策でもあるの」
思わずなまえが口走った幼名に注意する事無く、言葉とは裏腹に微笑む面貌からは柔らかな返答。「ありませんよ」
「なにもないんです。"鬼若"には」
「何もないって……じゃあ、どうするの? 何もないその先には、いったい何があるというの」
意外だとも、また何も無いその先にある絶望を知った。
微笑む虚像がなまえの双眸に映る。
「大丈夫ですよ。"武蔵坊弁慶"には、策があるんです」
薙刀を一本持ち、弁慶は堂入り口で独り立っている。源軍に囲まれても尚、彼は堂々とした出で立ちでそこにいた。
愛用の薙刀を構え、次から次へと襲い掛かってくる敵を薙ぎ倒すその姿形は、まるで鬼。
突然、「鬼だ」と誰かが呟いた。
鮮血を拭う事無く、ただ一撃で確実に急所を狙い八倒する。幼い頃、弁慶が鬼若と名付けられた由来はここにもある。
「ここからは、誰も通しませんよ」
薄ら笑いを浮かべ、刀を宙で回す。
これは"武蔵坊弁慶"の策であった。弁慶の背後に構えている館に源軍が狙う源九郎義経はいない。
策というには程遠い最終手段だった。
『本当に大丈夫なんだろうな』
『そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。後ほど合流します。僕には、とっておきの策がありますから』
弁慶は九郎に最後の嘘を吐き、逃がしたのだ。
自らが囮になり、時間稼ぎをすることで主君の命が救われるというのなら、これ程安いものはないと踏んだ。
――誰が望んだ結末だろう。
ふと、弁慶は思ったがこれが今まで奪ってきた命の重さに比べれば、軽いものだと感じた。
数多の命を奪った。全ては君主のため、己の策を完璧にするため――理由は全てが全て身勝手なものだった。奪ってよい命など、この世には無い。
だが、綺麗事では済まされないのが世界だ。
突然、肩に痛みが走った。どうやら弓兵が集結してきたらしい。たかが一人を倒すため、これほどの兵をよく集めたものだと、弁慶は苦笑する。
(ああ、寒いですね)
十日ほど前、握り締めたあの華奢な手のぬくもりを思い浮かべる。小さな手だった。十代の頃、別れの手を振ったあの頃よりも柔く、守りたいと思う手だった。今でも、守りたいと思う人だった。
「……っ」
限界突破した体力と気力――生を失い始めた体は、次々に飛んでくる矢傷の出血が決め手だった。四肢や背には、無数の矢がのめり込んでいる。
徐々に視界が揺れ始めたが、倒れこむ体を薙刀で踏ん張り、弁慶は地に根を張った。
そろそろ山越えを果たしたろうか、ともう会えぬ九郎を想う。其れから再度、別れを告げた彼女を想う。
哀しませるために邂逅を仕組んだわけではない。この世界の片隅で生きて欲しかった。最後、誰に会いたいかと一人絞り込むなら、彼女だった。
「…――弁慶」
突然、靄が周囲を覆う。弁慶の双耳を通り抜けたのは天女のように優しげな声。
「弁慶」
天からの声だろうか。そう思いながら、ぼろぼろの体を引きずり、弁慶は手を伸ばす。
靄が張った視界で鮮明と見えたのは、お釈迦でも何でも無い求めていた彼女だった。
「…ここは、浄土でしょうか」
「違うよ」
「では冥府――」
「それも違う」
震える弁慶の指先になまえは、しっかりと指を絡め、微笑む。
「莫迦だね、弁慶。何が策よ」
「…僕は、君に逃げろと言ったはずです……どうして、なぜ逃げなかったんですか」
怒気が含まれている反論を飛ばしながら、ずるりと崩れ落ちた体をなまえは寸のところで受け止めた。だが、弱ゞしく振り払った手は、そして弁慶は完全に憤慨していた。
「逃げろと、生きて欲しいがために君に策を言ったのに…――」
悔やむ気持ちを辛苦と共に耐えながら、弁慶は口唇を噛み締める。
予想外の展開に、なまえを逃す策を懸命に考えるが浮かんでくるのはどれも皆、確実性の無い逃げ道ばかりだった。
僅かな沈黙。「…あたしの作った煙玉は、ほんの少ししか持たない」
「逃げよう、とでも? 莫迦なことを…君だけでも逃げてください」
「あたしは弁慶と心中しにきたんじゃない…!」
痺れを切らしたなまえは、声を張り上げると弁慶の手を掴み、駆け出した。
――卑しくも、生きるために。
ふたりとも無傷とは言えなかったが、なんとか追手を撒けたのはなまえが用意周到に仕掛けた罠と道具、そして幸運だろう。
矢傷を負った弁慶は、なまえに支えながら両脚を地に踏ん張り、山道を登っていた。
厚塗りの雪化粧が周囲を覆う山中は、戦の真っ最中だというのに、やけに沈着としている。まるで先程までの怒号や悲鳴が無い。
なまえは薄気味悪いとも思ったが、其れよりも、ただ生へと執着していた。
「この山を越えたら、ひとまず安心だと思うから」
「…どこに、行く気……ですか」
「さあ? どこに行こう」
口許に三日月を作り、おどけて見せたなまえに弁慶は相変わらずだと笑う。
通が無いのならば作ればいい――其れが弁慶が持ち合わせて無いものであり、羨ましいとさえ感じている。昔も今もずっと、自分には無いものを求め続けていた。其れを全てなまえが持っていたのだ。
今更ながら弁慶は、後悔に沈んだ。もしも九郎と共に行くことを誘っていれば、別れなければ――何か変わっていたのでは無いだろうかと。
だが何もかもは後の祭りだ。時間を共用する間は、あまりにも突然で短過ぎた。
「落ち着いたらさ、軍師なんてやめてひっそり暮らそうよ」
生き生きとした表情で前方を――未来を見据えながらなまえは続けた。
「昔から薬に詳しいでしょ? だったら、それでなんとか食っていける」
弁慶にとって未来を語る端正ななまえの横顔は眩し過ぎたが、顔を背けることなくなまえを魅入る。傷だらけの頬や肩が唯一許せなかった。
何にも傷つける者は許さない。昔からあった信念が今もまだ弁慶の心に根付いているようだ。
大切な仲間であり、また女性だった。
「あたし? あたしは薪割りとかどうだろう。あれ、スカッとするんだよね」
弁慶は苦笑すると、ふと無邪気に話し続けるなまえの面貌がぼやけてゆくことに気がついた。瞬きを繰り返して視界になまえを捉えようとするが、鮮明になることは無い。
「――…て、それ仕事じゃないか。でもほら、お金がなくても幸せならいいじゃない」
しあわせ? と、弁慶は四字を口にしてみる。
己に問うように幸せの在り方について脳を巡らせてみたが、何も思いつくことは無かった。なぜなら、弁慶は生まれてから幸せなど考えたことも無かったのである。
ずるりと弁慶の体が地に這いつくばった。四肢に力が入らないことは、何かを掴みかけている手のひらが物語っている。
「…疲れた?」
なまえは特に驚く事無く、問いかけた。弁慶が、こくりと頷く。「…ええ」
「どう、やら……そのようです」
「じゃあ、」
言いながら、なまえはその場に座り込むと、弁慶の頭を双腿の上に乗せる。そして、額に手のひらを置くと、ゆっくり撫でた。
ふたりの視線が蔦のように絡み付いて繋がった。数秒、見詰め合うとなまえが満面の笑みを送る。
「少しだけ…少しだけ眠るといいよ」
「……起こしてください。絶対に、君が」
「もちろん。叩き起こすんだから」
弁慶の手が顫動しながらも、桃色の頬に到達する。なまえが思わず其の手を握ってみたが、氷塊のような手は温度を与えてこない。
一方、弁慶はあたたかさを確認すると満足気に微笑んだ。
「…目覚めたら、まず何をしましょう…か」
「うん? そうだなあ…」
なまえは、目を細めながら考える素振りを見せる。
特に返答が欲しかったわけではない弁慶は、なまえの答えを待たずにして開口した。
「僕は…僕の場合は……君に、言いたいことが、あるんです」
「なに? いくらでも聞くよ」
弁慶の瞼が徐ゞに下りてゆく。「…それは……次の機会にでも」
ぼやけた視界から次に見えたのは、やはりなまえの笑顔が映し出された。
「…君と過ごしたら、きっと…飽きることのない日々が……待っているんでしょうね」
なまえは頷く。しかし、なまえ自身、何に頷いたのか到底分らないでいた。
今、この瞬間を繋いでいたかった。「ねえ、弁慶」
「弁慶ったら。…もう眠ったの?」
弁慶は、応えない。
「……約束だからね。もう少ししたら、起こすんだから」
語尾には、震えた声が交っていた。
なまえは前のめりになると、弁慶の頬に自分の頬をすり寄せた。すると、それが合図かのように上空から無垢な六花が舞う。花と称するに相応しい氷の結晶は、しんしんと戯れ止むことを知らず、四囲を幻想の世界へと誘う。
やがて天地は何も無い、白き闇へと埋もれた。どこまでも続く果てが、ふたりを待っていた。