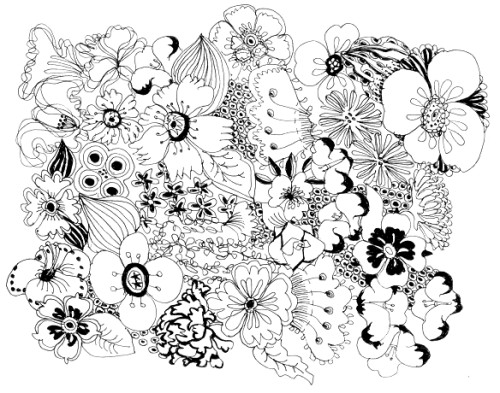
これはとあるOLとその飼い猫と喫茶店のイケメン店員の、ある雨の週末のお話。
土曜日。
この一週間、天気がぐずつき、なまえの機嫌はすこぶる悪い。
「ポアロっ、『ポアロ』に行くよー」
ばたーんと勢いよくドアを開けてなまえがリビングに入ってきた。
完全にくつろぎモードだったポアロは文字通り飛び上がった。みぎゃーと叫び、ソファーの下へ逃げ込んだ。驚きに瞳孔が開き、暗がりの中で爛々と光る。
なまえはポアロの慌てように笑いながら謝った。
「家にいると気が滅入る。こんなときは、爽やかイケメンを観賞して癒されるぞー!」
ポアロは恨めしそうにソファーの下から睨んでいたが、それをきいた途端、転がるように出てきた。不機嫌から一転、ゴロゴロと喉を鳴らしなまえの足にすりよる。
「ポアロも大好きだもんねー、安室さん」
勿論、と言わんばかりに力強くにゃんと鳴いた。
ここのところ、天気がよくなく、客足が鈍い。今もぽつりぽつりとしかいなかった。暇だなと、何気なくに通りの方を見ていると、常連さんの一人がキャリーケースを下げて歩いていた。思わずカウンターから抜け出して店のドアを開けた。突然開いたドアに、その常連さんは吃驚して持っていたキャリーケースを落としてしまった。みぎゃっと抗議するような鳴き声がケースから聞こえた。
「すみません、驚かせてしまって。大丈夫かい、ポアロ?」
先ず、常連さんに頭を下げてからしゃがみ、キャリーに声をかけた。一瞬の沈黙の後、ガタガタと猫が中で暴れだした。
「何やってんのよ。此処じゃ出さないわよ。あ、こんにちは、安室さん」
常連さん―なまえさんは僕に挨拶した後、キャリーの天井をばしりと叩いた。中からまた抗議の声があがった。
店の裏にまわり、キャリーから出てきたのは、毛並みの綺麗なロシアンブルーだった。アーモンド型の双眼は金色と青色のオッドアイだ。にゃーと甘えた声をだし、僕の前にちょこんと座る。食べ物を扱っていることを知っているからか、そう躾られているのか、こちらがおいでというまで触れてこない。賢い猫だ。
「大丈夫だよ。おいで、ポアロ」
そういうと、ゴロゴロ喉を鳴らしながら身体を擦り付けてきた。顎の下を擽ってやると、眼を細め首を伸ばす。
「ほんと、安室さんのこと好きよね〜」
苦笑しながら甘える飼い猫を見つめるなまえさん。雨が続いて家にいると気が滅入るので、ポアロに来てみたんです。安室さんに会えて嬉しいですと、満面の笑みを浮かべていった。
ポアロもそれに賛同するようににゃん、と鳴いた。
「毎日雨で憂鬱ですよ…」と、ホットミルクティーをスプーンでかき混ぜながらぼやくなまえさん。中小企業に勤める25歳のOLで、猫のポアロと一緒に近くのアパートに住んでいる。
時々、ポアロと共にここにやって来る。飲食店だから猫は入れないので、裏口で待たせている。途中ふらりと何処かへ行ってしまうが、なまえさんが店を出る頃にはきちんと戻ってきている。
「ポアロはほんと賢いですね」
猫がいるはずの裏口の方を見ながらいった。飼い猫を誉められて嬉しいのか、なまえさんは得意気に胸を張った。
「バッチリ仕込みましたからね〜。ポアロ自身も素質があったのも大きかったんですけど」
にこにこ笑みを浮かべ、頬杖をついて僕を見上げた。「アニマルテラピーって結構いいですよ。側にいるだけで癒されますし。安室さんもお疲れならば、いかがです?うちのポアロ。器量良しの美猫ですよ」
ふっと表情を真面目なものにすると、濃褐色の双眸が胸の内を見透かすかのように見つめてきた。
「…考えておきますね」
少し居心地が悪くなり、目を反らした。確かについ最近まで組織と公安の仕事が立て込んでいて忙しく、疲労していたのは事実だ。顔には出していないつもりではあったが…。
そんな僕を見てなまえさんは小さく声を漏らした。
「今更遠慮は無用なのにねぇ…」
どこか引っ掛かる台詞だ。もしかしたら、彼女は知っているのかもしれない。ポアロと僕の秘密を。
その言葉の意味を読み取ろうと、じっとその双眼を見つめた。
「ふふっ」
怯むことなく見つめ返し、笑い声をたてると、すっと裏口の方へ視線を流した。
「そろそろポアロが戻ってくるかな」
そういうと、ミルクティーを飲み干した。
「ご馳走さま。お会計お願いします」
何となくはぐらかされた感じは否めないが、立ち上がった彼女を留め置くこともできないので、レジの前に立った。
「…ありがとうございました。また、お越しくださいね」
かるく頭を下げたなまえさんを見送る。
ドアの外にはいつの間にかポアロが座って待っていた。
日曜日。
7日連続の雨に、朝から不機嫌な飼い主をスルーして、ポアロは散歩に出ることにした。自分用のレインコートの前に座ると、ポアロのやりたいことがわかったのか、なまえはそれを着せてやった。みゃーと鳴くと、気をつけていってらっしゃいとひらひらと手を振られた。
しとしとと小雨が降るなか、ポアロは水溜まりを避けながら歩いていた。チリチリと首輪に付けられた鈴がなる。大抵の猫は雨を嫌うが、ポアロはそうでもない。公園に足を伸ばし、ある遊具の中に潜り込んで丸くなりそして眼を閉じた。
――ぴちゃん、ぽちゃん
雨音が反響してポアロを包み込む。ゆったりと静かな時が流れた。このひとときは存外気に入っている。雨音の奏でるメロディーをBGMに、うとうとと微睡む。
ぱしゃっと水音がして、人の気配が近づいてくるのがわかった。ポアロは耳をぴくりと動かすだけ。
「やっぱりいたな」
聞きなれた声がした。そっと中に入ってくると、ポアロの側に座り込んだ。
首を上げると、褐色の肌に色素の薄い金髪、青灰色の眼をした青年が視界に入った。その表情は少し暗い。ここはポアロと彼の秘密の隠れ家。雨の日限定の。
初めてあった日もやっぱり雨が降っていて、一人と一匹で雨宿りをしたのだ。
「何となくいるような気がしたから来てみた」
自分を偽る必要がないこの場所ではいつも、本来の口調でたわいないものから他人には聞かれたくない胸の内も―相手が猫だからか―話した。それに降っている雨も秘密を覆い隠してくれる。ポアロは黙って耳を傾けていた。
一頻り喋った青年の表情はすっきりしたものになっていた。
「何時もすまないな。話をきいてくれて」
青年が礼をいうと、ポアロはにゃーと短く鳴いてこたえた。
「ところで、君の飼い主のことだが、どうやらこの密会に気づいているようだぞ?気づかないうちに見られたようだな」
茶化すようにいうと、ポアロは小首を傾げ青年に視線を向けた。そして、みぁーおと一声鳴くと、今日はこれでおしまいとばかりにくるりと体を丸めてしまった。
青年――安室はその態度に、なんか飼い主ににているなと、小さく笑うとポアロの頭をひと撫でして、遊具から出た。頑張れよというように鳴き声が後ろから聞こえてきた。ふっと表情を弛めたが直ぐに引き締め、足早にと公園を出ていった。
「こんにちは、安室さん。うちの猫見ませんでしたか?」
ポアロと別れて、少し離れた所に止めた車に戻る途中で飼い主のなまえに出会った。
「ポアロなら、そこの公園にいましたよ」
歩いてきた方を指差して教えた。なまえは安室が指した先を首を少し伸ばして眺め場所を確認した。
「へー、今日はここにいたんだ。ということはポアロと会ってたんですね?」
悪戯っぽく笑いながら安室を下から覗きこんだ。
やはり一人と一匹の密会はとうになまえにはばれていたようだ。
「うちの子を甘い言葉でたぶらかしてたんでしょう?」
からかっているのが丸分かりの雰囲気を醸し出しているので、安室も悪乗りしてみた。
「ええ、ポアロはとても魅力的ですからね。是非お付き合いしたいので、お許し頂けませんか?」
「駄目だといったら?」
「駆け落ちするまでです」「猫と?」
「はい」
真顔で言い切った安室に、なまえは吹き出し、安室もまたつられて笑いだした。
「ポアロでよければいつでもレンタルしますよ」
なまえの申し出に、安室は今度は躊躇いもなく頷いた。
雨はいつの間にか止み、雲の切れ目からは青空がのぞいていた。
にゃーんと鳴き声がして、レインコートをまとった猫が二人の方へ走ってきた。