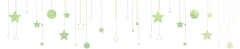今年は私からお返しするね、と宣言して早1ヶ月。
私達は、相も変わらず大量の仕事に追われていて中々息をつく暇も無く。
明日に控えるはホワイトデー!とルンルン気分半分、落ち込み半分で帰路についていた。
リザのお陰でなんとか定時には帰れるけれど、それでも毎日クタクタで正直帰ってスイーツを作れる気分でもない。
それはロイも同じようで、肩を一人揉んでいる姿をここ最近よく見る。
さてさて、どうしたものか……と考えていた時にふらりと寄ったお馴染みの焼き菓子店。
そこでとても魅力的なスイーツを見かけたのだ。
『これ…』
「新作なんですよ!しかも、ホワイトデー限定品です!」
『新作……限定……』
無条件で惹かれてしまうそのワードに、もう目の前の新作スイーツしか見えなくなってしまって、売り文句のポップをじっと見た。
『…これを食べるだけで、こんな効果があるんですか?』
「ええ!そりゃもうバッチリ!秘伝のものを沢山塗り込んでますからね、何処のものよりも効果ありますよ〜!」
ふむ。
ただの焼き菓子に見えるけれど、中々侮れないのね。
これを食べるだけで、こんな効果があるのならロイに食べさせたいし私も食べたい。
そう思った私は『じゃあこれを3つ下さい』と仲の良い店員さんに言えば、店員さんはとびきりの笑顔で頷く。
「ふふ、ラブラブですね!」
袋詰めされたそれを受け取った時そう言って肩を叩かれたので、私は照れくさくてにやけながら『えへ、』と気の抜けた笑いをしてしまった。
『と言うことで、私の手作りではないですが…バレンタインのお返しです!』
「ありがとう」
ホワイトデー当日の夜、食事を手早く済ませてひと休みしているロイにそれを渡す。
3つ買った内の2つはロイに、1つは私に。
笑顔で受け取ってくれたのを確認してからロイの隣に座る。
『何かね、かなり甘いから珈琲や紅茶と合わせるのが良いんだって!』
「だからななしもコーヒーなのか」
それを渡す前に淹れておいた二人分のコーヒー。
普段は進んで飲まないものだけれど、最高の組み合わせで食べたいので今日はちょっと頑張って無糖だ。
「…それで、これは……」
『これはね〜…』
白い袋に1つ1つ、丁寧にラッピングされたそれを取り出す。
じゃん!という掛け声と共に登場したのは、チョコレートの焼き菓子。
カップケーキとは違う…これは
「フォンダンショコラ、かな?」
『正解!ホワイトデー当日の限定品なんだって!』
フォンダンショコラ。
しっとりとしたチョコレートの生地の中にとろりとしたチョコレートソースが入っている、何とも美味しいスイーツなのだ。
『温めても美味しいらしいんだけど、その場合効果が薄くなるから注意だって言われたの』
「効果…?」
『これを食べるとね、体がスッキリして…おまけに一緒に食べた相手ともっと仲良くなれちゃうんだって!』
お店で見た売り文句をそのまま口に出す。
食べるだけでそんな効果あるなんて凄すぎる!と思ったのを覚えている。
「……何か怪しくないか、それ」
『確かにちょっと疑ったけど…!でもいつもの焼き菓子店の商品だし、変なものではないと思う!』
だからほら!食べよう! とそれを小皿に乗せてフォークと共にロイに渡す。
少しだけ渋るロイを急かして一口食べさせて、ごくん、と喉が上下したのを確認した私もそれに続いて自分の分を頬張った。
…変なものではないと思う!なんて言ってた自分を殴りたくなる!!…なんて、その時の私は思ってもみなかった。
味はとっても美味しくて、言われた通り少し甘すぎる気もしたけど無糖の珈琲との組み合わせは最高で、ぱくぱくと食べられた。
それはロイも同じのようで渡した2つをぺろりと平らげてくれたのだが。
『…体スッキリした?』
「特に変化は無いな」
『うむむ…』
食後10分程経ってもこれと言った変化は見られず、なーんだ、と肩を落とす。
『ロイの仕事疲れをスッキリ取ってくれたら、と思ったんだけど…』
「その気持ちだけで嬉しいよ、ありがとうななし」
『っ……!?』
嬉しそうに微笑んだロイが私の頭を撫でようとしてその手が触れた瞬間、無意識に体がびくりと跳ねた。
ドッドッド、と心臓が激しく動き始める。
「ななし…?」
『な、何だろ急だったからびっくりした、みたい?』
あは、と笑えばロイも何だかホッとした様子で今度こそ私の頭を撫でる。
『、ん…』
ロイの手が動く度にぞわぞわとする。
不快感とか、そういうのじゃないのは確か何だけど……何かがおかしい。
それにさっきから何だか、
「少し暑いな…」
『え、あ…ロイも?私も何かぽかぽかする』
そう、何だか暑い。
ぽかぽかする、なんて聞こえの良い言葉を使ったけれど、実際は少し汗ばんできている。
未だに激しく動き続ける心臓、ぞわぞわする熱い体。
何だか、何だか変だ。
『ど、どうしちゃったんだろ』
「お互い疲労が溜まっていたんだろう、今日は早めに休もうか」
『うん…』
「じゃあ片付けは私がやるよ」
『えっあ!私がやる………ぅ、ひゃっ!?』
「う、…!?」
お皿を取るロイの手と私の手が触れた瞬間、まるで触れあったそこから電気が走ったかのようにびくりと手が跳ねる。
それはロイも同じだったようで、持っていたお皿ががちゃん!と音を立てて机に落ちた。
幸い割れておらず、そっちに関してはホッと一息ついたけれど……
『ど、どうしちゃったの、私達』
自分達に何が起こってるのか全く分からなくて立ち尽くす私。
だけどロイは、そんな私と自身の手を交互に見て暫くした後頭を抱えた。
「あー…そういう」
『え?な、何か分かったの?』
「いや…」
何とも歯切れの悪いロイに首を傾げる。
なにかマズイ事なのだろうか。
『ロイ…?』
「…先程のフォンダンショコラの売り文句を確認したいんだが」
『え?えっと…体がスッキリして、食べた相手と仲良くなれる……って書いてあったけど』
「……はぁ、」
『な、なに?何が分かったの?』
一人頭を抱えるロイは、何も分かっていない私を見て一言。
「…薬だ」
『……薬?』
薬って、なんの?
て言うか、こんな症状になる薬なんてあったっけ?
「ただの薬じゃない、これは媚薬」
『び……やく…………びっ媚薬!?そ、それって…あの、私の知識が間違ってなければ、えっと……』
「性欲増進効果、一部では惚れ薬とも呼ばれるものだな…」
食べる前に気づくべきだった、と顔をしかめるロイを見ながら頭がぐるぐると回る感覚に陥る。
そんな、急に言われても…
でもそうだとしたらこのうるさい心臓も、垂れるほどの汗も何と無く説明が付く。
『と、とんでもないもの、買っちゃった…?』
え、えへ、とひきつった笑いをする私を見たロイは、今日一番深いため息を吐いた。
「取り敢えず、時間が経てば治まるだろうから大人しくしていよう」
『わ、わかった』
「私はここに居るから、ななしは念のため一人で寝室に」
『え…二人で居たら駄目なの…?』
こんなの初めての体験だし、何だか心細いから一人は嫌だ。
そんな軽い考えでロイの顔を覗き込む。
…あれ、何だか顔が赤い
「……だめだ」
『一人じゃ不安で…』
「今は耐えてくれ」
『で、でも……』
「…頼む、から」
はあ、と息を漏らしたロイは耳まで真っ赤で、体が少し震えていて見ていて心配になるほどだった。
『ロイ、大丈夫…?』
「気づかないままの方が、楽、だったかもな」
はは、と笑ったロイはずっと下を向いていて此方から表情は見えないけれど、きっと凄く辛いだろう。
私は1つしか食べていないけれど、良かれと思ってロイには2つ食べてもらったから…まさかこんな事になるなんて。
「…兎に角、ななしは寝室に」
『こんな状態のロイ、放っておけない…!』
「放っておいてくれた方が…今、は助かるんだが…」
『う……そ、それもそうかもだけど……』
「ななしの為に言ってるんだ、」
『私の為…?』
何で私のため?と眉を潜めれば、それを気付いたのだろうロイがため息を吐いて顔をあげた。
正直にびっくりしてしまった。
だって、そこに居るのは私の知ってるロイじゃない。
いつもの優しい顔じゃなくて、何だかギラギラした…そう、まるで獲物を見つけた動物みたいな…
獲物?
『あっ……!』
そこで漸く気が付いたのだ。
ロイが酷く我慢をしていることに。
「…気付くの、遅すぎる」
『い、いや……だって、こんなの初めて、だし…その』
「性欲増進効果があるって言ったろ」
『それはっ、その……ひとりでしたくなる、的なあれかと…』
「…」
『す、すみません……』
じとり、と睨まれて小さく謝る。
でも本当に分からなかったんだよ!と言うと、ロイは分かってる、と呟いた。
「変なところで鈍感なのは、ななしの長所でもあり短所だからな」
『う……』
「……で、そろそろ、限界なんだが」
『えっ』
「…私は何度も忠告したからな」
『や、あの…』
「行くぞ」
『あっ、う…』
がしり、と手首を掴まれる。
甘いような電撃が体に小さく走って体が震えたけれど、ロイはそれを気にすること無く立ち上がって私の前を歩く。
手を引かれる形で着いていく私は、ロイの背中すら見るのが恥ずかしくてずっと下を向いていた。
『ろ、わっ』
薄暗い寝室に入ると、私が声を掛けるよりも先に手を強く引かれてベッドへと勢いよく倒される。
普段なら腰掛けてから優しく押し倒されるのに、なんて思っている間に私に馬乗りになったロイは、私の首元に顔を埋めた。
媚薬のせいかそれだけでも体が震えたが、ロイはそんなのお構い無しにそこにキスを何度もする。
『ん、や…ふ……ん、…』
「…いつもより、敏感だな」
『それ、は…媚薬が…あ、あっ』
ちゅう、と強く首筋を吸われてびくりと体が跳ねる。
ちくりと感じる痛みすら今は気持ちが良いと感じてしまって、無意識に声が出た。
『そこ、見えちゃ…あ、ぅ…!』
「我慢、出来ないから…諦めろ」
『や、あっ』
痕を付けたすぐ近くに、また痕を付けられる。
何度もちゅう、ちゅうと吸われて可笑しいくらいに体が跳ねた。
首筋だけだったそれが、段々と下に降りていく。
元々キャミソールにカーディガンという薄着だった為、脱がされる事無く胸元にロイの唇が寄せられて沢山の痕を付けられる。
『ん、んう……ふ、』
こんな事で簡単に声が漏れてしまうのが恥ずかしくて両手で口を塞ぐ。
それに気付いたロイは、塞いでいた手を取って纏めて頭の上へと片手で縫い付けた。
「それじゃキスが出来ない」
『んっ……は、ぅ』
はぁ、とロイの熱い吐息が耳にかかってぞくりとする。
そのまま耳をぺろりと舐められて体を震わせると、今度は唇にロイの唇が当てられた。
触れるキスなんてない、最初から蕩けるようなキス。
『んむ、んっ…は、ぁっ……』
口の中を暴れまわるロイに脳まで掻き回されてるような感覚に陥って頭がぽーっとしてくる。
口の端から二人の唾液が垂れていくけれど、その唾液が肌を滑る感覚ですら既に快感に変わっているのに気が付いた。
どうしよう、気持ちいい。
さっきまで普通だったのに、ロイの方が辛そうだったのに。
そんな風に考えるけれど、考えが纏まるよりも先にロイからの愛撫で頭が真っ白になりそうだ。
いつの間にかフロントホックを外され、露になっていた私の胸の先をロイがぺろりと舐める。
『あっふ、ぅ……っ!!』
びくりと体が揺れて足に力が入った。
ちゅう、と先端を吸ったり口に含んだまま転がしたりと遊ばれている間、足は震えるほどピンと伸びていて腰はガクガクと震えていて。
『ん、あっあっぁ…ひ、ーーーっ!!』
かり、と先端を軽く噛まれた瞬間体が反るように動いてびくびくと震え、目の前がチカチカと真っ白になる。
かくんと力が抜けて息が上手く出来ない。
『は、はぁ、はっ…』
「ななし…」
『ろい…?ん、む……ふ、』
ふと呼ばれたその切な気な声にロイを見る。
ロイは少しだけキスをした後、こつんと額同士をくっ付けるようにして目を閉じた。
「…したい」
『…うん』
「だが、恐らく普段のように優しく出来ない」
『…』
「ななしが、欲しくて、欲しくて…堪らないんだ」
ぽたり、とロイの頬から流れてきた汗が私の頬に垂れた。
私の下腹部に当たっているそれは、見なくても分かるくらい硬く膨れ上がっていてピクピクとしている。
こんな時でも私の意思を尊重してくれるの、と胸が痛いほど締め付けられて、気付けば私から唇を重ねていた。
『ロイが苦しくなくなるまで、沢山、沢山…したい』
「…良いのか?」
『ん……辛いの全部吐き出せるまで…しよ?お願い…』
元はと言えば私が勘違いをして媚薬入りのお菓子を買ってきてしまったせいだし、正直私もまだ満足出来ていなかった。
「…ありがとう」
ふわりといつものように優しく笑ったロイは、ちゅ、と触れるだけのキスをして片手を私の秘部へと添わせる。
ちゅくり、と音を立ててロイの指が入ってくる感覚のすぐ後に来る快感に思わず声が出た。
『あっあ、ん、だ、めっ……また、きちゃ……あ、え?』
出し入れされる大好きなロイの指にくらくらと酔っていると、かくかくと腰が揺れ始めてしまって。
もうだめ、と強い快感に備えて目をキツく閉じたけどそれが来ることは無くて思わずどうして?声が漏れる。
「一緒に気持ちよくなりたい、なんて……らしくないな」
『そんなこ、ふ、あっ』
「っ…」
私の言葉を遮って宛がわれたロイのそれが、くぷ、と音を立てて私の中に入ってくる。
媚薬のせいで敏感になっているからか、それとも限界ギリギリで焦らされたからか、それが入りきるまでに何回か軽くイってしまった。
「ななしのナカ、ぎゅうぎゅう締め付けてくる」
『そ、れ…言わなくてっ…いいっ』
「あー…本当に、止まれそうにっない、」
『ん、ひゃっあ、あっい、きなっり、ふ、あっ』
ぐちゅぐちゅと水音が耳に響く。
揺さぶられる体は、ぞくぞくと快感を溜めていく。
普段では考え付かないくらい、快感に顔を歪めるロイを見てぎゅう、とナカが締まる感覚がした。
「っき、つ…」
『ご、め、あっあ、あっ、ふ、あっ…ん、ぅ』
唇が重なる。
下から突き上げられる度に勝手に漏れてしまう声に合わせて口が開いて、そこからロイの温かい舌がぬるりと入り込む。
ぢゅる、といやらしい音を立てながら口内を貪られる。
体の全てが溶けてしまいそうなくらい気持ちよくて、涙がポロリとこぼれた。
「ななし、愛してる…っ」
『っ、あっ、ひ、あぁっ』
そんな事を好きな相手から囁かれたら、誰だってどきりとしてしまう。
ロイが私の体でどうしようもないくらい気持ちよくなってる。
そう考えるだけでお腹の奥がきゅんとするし、快感に拍車が掛かるのだ。
『あっ、も…まっ、て』
「待て、ない…っ」
『んあぁっだ、だめっ、ほんとにっきもち、良すぎ、てっ…あ、ぅっ、あたま、まっしろ……やっあ、あ……ーーーー!』
「っ」
体が無意識に弓のように反り上がり、手と足に力が入る。
真っ白な視界の中、びく、びく、と腰が揺れて中が収縮した。
一瞬止まっていた息を勢いよく吸ったと同時に止まっていた行為が再開されて抜けていた力がまたこもる。
『ふ……あっ!?ま、まって、今、いったばっか……!』
「知ってる…っ」
『や、あっだめ、こ、んなっあっ、きもち、のっ、んあ、あっおかしく、な、るっ』
こんなに激しく求められたのは初めてで、いつもと違う行為に頭と体がパンクしそう。
休む暇もなく与えられている快感にどうにかなってしまいそうだ。
「っ…ななし、」
『は、い……っん、む……ん、んぅ、は、んっんっ』
溶けちゃうようなキスを何度もしながら、それのスピードが上がった事でロイの限界が近いんだと感じる。
私は、ロイの首に手を回して体を密着させるように引き寄せた。
もっと、もっとロイを感じたい。
「ん、む……っ」
『ふっ、んっ、ーー!!!』
ロイが私の最奥を突いた瞬間、また頭が真っ白になってびくびくと腰が揺れる。
そしてロイも、最奥でびくびくと震えて欲を吐き出した。
『ん、ふ……は、ぅ…んむ、』
ロイが私の奥底へと種を残している間も、角度を変えて何度も何度もキスをした。
唇を離すと混ざりあった唾液がロイの舌先から零れ落ち、私の舌へとろとろ流れ込んできて私はそれをごくりと飲み込む。
いつもならここで終わるのだろうけど、
「…ななし」
『ん…私も』
まだ熱が下がりきらない私達は、それを合図にもう一度唇を重ねた。
何度も達してしんどいはずの体は、まるで何事も無かったかのように快感に溺れていく。
それはロイも同じの様で、硬くなったままのそれをもう一度、私へと宛がうのだ。
『いっそ、こわれちゃいたい、』
私から不意に出たそんな言葉に、ロイは応えるように唇を重ねた。
『……ん、』
ゆっくり目を覚ます。
暗かったはずの寝室は窓からの光でキラキラと明るく照らされていて、外では鳥や車の音が忙しなく聞こえる。
ベッドの中には誰も居なくて何回か瞬きをして、いつの間に朝になってたんだろう?なんて大あくびをしながら起き上がろうと力を入れた。
『……あれ?』
起き上がれない。
力が入らない、と言った方がいいのかな、この場合。
『な、なんで……ん〜…いっ!!』
精一杯力を込めてみたが、腰がズキンと痛んで折角の力が抜けてしまった。
これはどうしたものか、と悩んでいると寝室の扉がガチャリと開いて軍服姿のロイが顔を出す。
「ななしおはよう、身体は大丈夫…じゃあ無いよな」
『えっと…起き上がれないというか、腰が痛いというか……』
「そりゃそうだろう、ずっと同じペースで朝方までしてたんだ、限界も来るさ」
『朝、方……!?』
え?そんなに?記憶無いんですが……!とぐるぐる考えていると、それに気付いたロイが眉を下げてくすりと笑った。
「薬のせいだとはいえ随分と無理をさせてしまったからな、今日は1日休んでるといい」
『えっいや、私今日出勤!ロイが休みでしょ!』
「私がななしの代わりに出勤するから問題ないさ、まあ代役としては頼りないかもしれないがな」
『いやいやいや……頼りになるけど…!だめだよ、私が……いっったぁ!』
慌てて起き上がろうと力を入れた瞬間、キーンとした痛みが腰を襲う。
力無く倒れた私を見てロイはまた笑って私の頭を撫でた。
「無理は禁物だ」
『……ロイだって沢山したのに、』
「私は男だからな、ななしよりも体力も筋力もあるし、それに」
『それに?』
「ななしほどイってない」
『ー!』
耳元でそう囁かれてかあっと顔が熱くなる。
ロイはそんな私の米神にちゅ、と触れるだけのキスをした。
「というわけだ、ゆっくり休むといいよ」
『……お言葉に甘えて』
「水はここに置いておくし、昼は冷蔵庫に用意してあるからちゃんとたべるんだぞ」
『い、至れり尽くせり……』
「それじゃ、行ってくる」
そう言って笑ったロイに、私も笑い返す。
『ん、行ってらっしゃい!』
パタンと扉を閉めた後に、ガチャンと玄関を閉じて鍵を閉める音がした。
『服まで着せ直してくれてるし……』
何だか申し訳ないなという気持ちに刈られ、それならば夕飯は私がご馳走を作ろう!と決める。
まだ起き上がれないので、冷蔵庫の中身を思い出しながら献立を考える事にした。
『デザートは……当分無しでいいかな…』
昨日のガトーショコラで痛い目を……いや、痛くなんて全くなかったんだけど、兎に角暫くは無しでいいか。
でもたまには、本当にたまに、たまーに!1年に1回くらい!またあのガトーショコラを食べたいなぁ。
あんな風に快楽に溺れる姿を見てしまった私は、きっとまたあのロイに会いたくなるのだろう。
『……朝まで全部覚えてないのは、勿体無かったな』
そんな言葉が口から漏れて、一人くすくすと笑った。
2020/03/14
私達は、相も変わらず大量の仕事に追われていて中々息をつく暇も無く。
明日に控えるはホワイトデー!とルンルン気分半分、落ち込み半分で帰路についていた。
リザのお陰でなんとか定時には帰れるけれど、それでも毎日クタクタで正直帰ってスイーツを作れる気分でもない。
それはロイも同じようで、肩を一人揉んでいる姿をここ最近よく見る。
さてさて、どうしたものか……と考えていた時にふらりと寄ったお馴染みの焼き菓子店。
そこでとても魅力的なスイーツを見かけたのだ。
『これ…』
「新作なんですよ!しかも、ホワイトデー限定品です!」
『新作……限定……』
無条件で惹かれてしまうそのワードに、もう目の前の新作スイーツしか見えなくなってしまって、売り文句のポップをじっと見た。
『…これを食べるだけで、こんな効果があるんですか?』
「ええ!そりゃもうバッチリ!秘伝のものを沢山塗り込んでますからね、何処のものよりも効果ありますよ〜!」
ふむ。
ただの焼き菓子に見えるけれど、中々侮れないのね。
これを食べるだけで、こんな効果があるのならロイに食べさせたいし私も食べたい。
そう思った私は『じゃあこれを3つ下さい』と仲の良い店員さんに言えば、店員さんはとびきりの笑顔で頷く。
「ふふ、ラブラブですね!」
袋詰めされたそれを受け取った時そう言って肩を叩かれたので、私は照れくさくてにやけながら『えへ、』と気の抜けた笑いをしてしまった。
『と言うことで、私の手作りではないですが…バレンタインのお返しです!』
「ありがとう」
ホワイトデー当日の夜、食事を手早く済ませてひと休みしているロイにそれを渡す。
3つ買った内の2つはロイに、1つは私に。
笑顔で受け取ってくれたのを確認してからロイの隣に座る。
『何かね、かなり甘いから珈琲や紅茶と合わせるのが良いんだって!』
「だからななしもコーヒーなのか」
それを渡す前に淹れておいた二人分のコーヒー。
普段は進んで飲まないものだけれど、最高の組み合わせで食べたいので今日はちょっと頑張って無糖だ。
「…それで、これは……」
『これはね〜…』
白い袋に1つ1つ、丁寧にラッピングされたそれを取り出す。
じゃん!という掛け声と共に登場したのは、チョコレートの焼き菓子。
カップケーキとは違う…これは
「フォンダンショコラ、かな?」
『正解!ホワイトデー当日の限定品なんだって!』
フォンダンショコラ。
しっとりとしたチョコレートの生地の中にとろりとしたチョコレートソースが入っている、何とも美味しいスイーツなのだ。
『温めても美味しいらしいんだけど、その場合効果が薄くなるから注意だって言われたの』
「効果…?」
『これを食べるとね、体がスッキリして…おまけに一緒に食べた相手ともっと仲良くなれちゃうんだって!』
お店で見た売り文句をそのまま口に出す。
食べるだけでそんな効果あるなんて凄すぎる!と思ったのを覚えている。
「……何か怪しくないか、それ」
『確かにちょっと疑ったけど…!でもいつもの焼き菓子店の商品だし、変なものではないと思う!』
だからほら!食べよう! とそれを小皿に乗せてフォークと共にロイに渡す。
少しだけ渋るロイを急かして一口食べさせて、ごくん、と喉が上下したのを確認した私もそれに続いて自分の分を頬張った。
…変なものではないと思う!なんて言ってた自分を殴りたくなる!!…なんて、その時の私は思ってもみなかった。
味はとっても美味しくて、言われた通り少し甘すぎる気もしたけど無糖の珈琲との組み合わせは最高で、ぱくぱくと食べられた。
それはロイも同じのようで渡した2つをぺろりと平らげてくれたのだが。
『…体スッキリした?』
「特に変化は無いな」
『うむむ…』
食後10分程経ってもこれと言った変化は見られず、なーんだ、と肩を落とす。
『ロイの仕事疲れをスッキリ取ってくれたら、と思ったんだけど…』
「その気持ちだけで嬉しいよ、ありがとうななし」
『っ……!?』
嬉しそうに微笑んだロイが私の頭を撫でようとしてその手が触れた瞬間、無意識に体がびくりと跳ねた。
ドッドッド、と心臓が激しく動き始める。
「ななし…?」
『な、何だろ急だったからびっくりした、みたい?』
あは、と笑えばロイも何だかホッとした様子で今度こそ私の頭を撫でる。
『、ん…』
ロイの手が動く度にぞわぞわとする。
不快感とか、そういうのじゃないのは確か何だけど……何かがおかしい。
それにさっきから何だか、
「少し暑いな…」
『え、あ…ロイも?私も何かぽかぽかする』
そう、何だか暑い。
ぽかぽかする、なんて聞こえの良い言葉を使ったけれど、実際は少し汗ばんできている。
未だに激しく動き続ける心臓、ぞわぞわする熱い体。
何だか、何だか変だ。
『ど、どうしちゃったんだろ』
「お互い疲労が溜まっていたんだろう、今日は早めに休もうか」
『うん…』
「じゃあ片付けは私がやるよ」
『えっあ!私がやる………ぅ、ひゃっ!?』
「う、…!?」
お皿を取るロイの手と私の手が触れた瞬間、まるで触れあったそこから電気が走ったかのようにびくりと手が跳ねる。
それはロイも同じだったようで、持っていたお皿ががちゃん!と音を立てて机に落ちた。
幸い割れておらず、そっちに関してはホッと一息ついたけれど……
『ど、どうしちゃったの、私達』
自分達に何が起こってるのか全く分からなくて立ち尽くす私。
だけどロイは、そんな私と自身の手を交互に見て暫くした後頭を抱えた。
「あー…そういう」
『え?な、何か分かったの?』
「いや…」
何とも歯切れの悪いロイに首を傾げる。
なにかマズイ事なのだろうか。
『ロイ…?』
「…先程のフォンダンショコラの売り文句を確認したいんだが」
『え?えっと…体がスッキリして、食べた相手と仲良くなれる……って書いてあったけど』
「……はぁ、」
『な、なに?何が分かったの?』
一人頭を抱えるロイは、何も分かっていない私を見て一言。
「…薬だ」
『……薬?』
薬って、なんの?
て言うか、こんな症状になる薬なんてあったっけ?
「ただの薬じゃない、これは媚薬」
『び……やく…………びっ媚薬!?そ、それって…あの、私の知識が間違ってなければ、えっと……』
「性欲増進効果、一部では惚れ薬とも呼ばれるものだな…」
食べる前に気づくべきだった、と顔をしかめるロイを見ながら頭がぐるぐると回る感覚に陥る。
そんな、急に言われても…
でもそうだとしたらこのうるさい心臓も、垂れるほどの汗も何と無く説明が付く。
『と、とんでもないもの、買っちゃった…?』
え、えへ、とひきつった笑いをする私を見たロイは、今日一番深いため息を吐いた。
「取り敢えず、時間が経てば治まるだろうから大人しくしていよう」
『わ、わかった』
「私はここに居るから、ななしは念のため一人で寝室に」
『え…二人で居たら駄目なの…?』
こんなの初めての体験だし、何だか心細いから一人は嫌だ。
そんな軽い考えでロイの顔を覗き込む。
…あれ、何だか顔が赤い
「……だめだ」
『一人じゃ不安で…』
「今は耐えてくれ」
『で、でも……』
「…頼む、から」
はあ、と息を漏らしたロイは耳まで真っ赤で、体が少し震えていて見ていて心配になるほどだった。
『ロイ、大丈夫…?』
「気づかないままの方が、楽、だったかもな」
はは、と笑ったロイはずっと下を向いていて此方から表情は見えないけれど、きっと凄く辛いだろう。
私は1つしか食べていないけれど、良かれと思ってロイには2つ食べてもらったから…まさかこんな事になるなんて。
「…兎に角、ななしは寝室に」
『こんな状態のロイ、放っておけない…!』
「放っておいてくれた方が…今、は助かるんだが…」
『う……そ、それもそうかもだけど……』
「ななしの為に言ってるんだ、」
『私の為…?』
何で私のため?と眉を潜めれば、それを気付いたのだろうロイがため息を吐いて顔をあげた。
正直にびっくりしてしまった。
だって、そこに居るのは私の知ってるロイじゃない。
いつもの優しい顔じゃなくて、何だかギラギラした…そう、まるで獲物を見つけた動物みたいな…
獲物?
『あっ……!』
そこで漸く気が付いたのだ。
ロイが酷く我慢をしていることに。
「…気付くの、遅すぎる」
『い、いや……だって、こんなの初めて、だし…その』
「性欲増進効果があるって言ったろ」
『それはっ、その……ひとりでしたくなる、的なあれかと…』
「…」
『す、すみません……』
じとり、と睨まれて小さく謝る。
でも本当に分からなかったんだよ!と言うと、ロイは分かってる、と呟いた。
「変なところで鈍感なのは、ななしの長所でもあり短所だからな」
『う……』
「……で、そろそろ、限界なんだが」
『えっ』
「…私は何度も忠告したからな」
『や、あの…』
「行くぞ」
『あっ、う…』
がしり、と手首を掴まれる。
甘いような電撃が体に小さく走って体が震えたけれど、ロイはそれを気にすること無く立ち上がって私の前を歩く。
手を引かれる形で着いていく私は、ロイの背中すら見るのが恥ずかしくてずっと下を向いていた。
『ろ、わっ』
薄暗い寝室に入ると、私が声を掛けるよりも先に手を強く引かれてベッドへと勢いよく倒される。
普段なら腰掛けてから優しく押し倒されるのに、なんて思っている間に私に馬乗りになったロイは、私の首元に顔を埋めた。
媚薬のせいかそれだけでも体が震えたが、ロイはそんなのお構い無しにそこにキスを何度もする。
『ん、や…ふ……ん、…』
「…いつもより、敏感だな」
『それ、は…媚薬が…あ、あっ』
ちゅう、と強く首筋を吸われてびくりと体が跳ねる。
ちくりと感じる痛みすら今は気持ちが良いと感じてしまって、無意識に声が出た。
『そこ、見えちゃ…あ、ぅ…!』
「我慢、出来ないから…諦めろ」
『や、あっ』
痕を付けたすぐ近くに、また痕を付けられる。
何度もちゅう、ちゅうと吸われて可笑しいくらいに体が跳ねた。
首筋だけだったそれが、段々と下に降りていく。
元々キャミソールにカーディガンという薄着だった為、脱がされる事無く胸元にロイの唇が寄せられて沢山の痕を付けられる。
『ん、んう……ふ、』
こんな事で簡単に声が漏れてしまうのが恥ずかしくて両手で口を塞ぐ。
それに気付いたロイは、塞いでいた手を取って纏めて頭の上へと片手で縫い付けた。
「それじゃキスが出来ない」
『んっ……は、ぅ』
はぁ、とロイの熱い吐息が耳にかかってぞくりとする。
そのまま耳をぺろりと舐められて体を震わせると、今度は唇にロイの唇が当てられた。
触れるキスなんてない、最初から蕩けるようなキス。
『んむ、んっ…は、ぁっ……』
口の中を暴れまわるロイに脳まで掻き回されてるような感覚に陥って頭がぽーっとしてくる。
口の端から二人の唾液が垂れていくけれど、その唾液が肌を滑る感覚ですら既に快感に変わっているのに気が付いた。
どうしよう、気持ちいい。
さっきまで普通だったのに、ロイの方が辛そうだったのに。
そんな風に考えるけれど、考えが纏まるよりも先にロイからの愛撫で頭が真っ白になりそうだ。
いつの間にかフロントホックを外され、露になっていた私の胸の先をロイがぺろりと舐める。
『あっふ、ぅ……っ!!』
びくりと体が揺れて足に力が入った。
ちゅう、と先端を吸ったり口に含んだまま転がしたりと遊ばれている間、足は震えるほどピンと伸びていて腰はガクガクと震えていて。
『ん、あっあっぁ…ひ、ーーーっ!!』
かり、と先端を軽く噛まれた瞬間体が反るように動いてびくびくと震え、目の前がチカチカと真っ白になる。
かくんと力が抜けて息が上手く出来ない。
『は、はぁ、はっ…』
「ななし…」
『ろい…?ん、む……ふ、』
ふと呼ばれたその切な気な声にロイを見る。
ロイは少しだけキスをした後、こつんと額同士をくっ付けるようにして目を閉じた。
「…したい」
『…うん』
「だが、恐らく普段のように優しく出来ない」
『…』
「ななしが、欲しくて、欲しくて…堪らないんだ」
ぽたり、とロイの頬から流れてきた汗が私の頬に垂れた。
私の下腹部に当たっているそれは、見なくても分かるくらい硬く膨れ上がっていてピクピクとしている。
こんな時でも私の意思を尊重してくれるの、と胸が痛いほど締め付けられて、気付けば私から唇を重ねていた。
『ロイが苦しくなくなるまで、沢山、沢山…したい』
「…良いのか?」
『ん……辛いの全部吐き出せるまで…しよ?お願い…』
元はと言えば私が勘違いをして媚薬入りのお菓子を買ってきてしまったせいだし、正直私もまだ満足出来ていなかった。
「…ありがとう」
ふわりといつものように優しく笑ったロイは、ちゅ、と触れるだけのキスをして片手を私の秘部へと添わせる。
ちゅくり、と音を立ててロイの指が入ってくる感覚のすぐ後に来る快感に思わず声が出た。
『あっあ、ん、だ、めっ……また、きちゃ……あ、え?』
出し入れされる大好きなロイの指にくらくらと酔っていると、かくかくと腰が揺れ始めてしまって。
もうだめ、と強い快感に備えて目をキツく閉じたけどそれが来ることは無くて思わずどうして?声が漏れる。
「一緒に気持ちよくなりたい、なんて……らしくないな」
『そんなこ、ふ、あっ』
「っ…」
私の言葉を遮って宛がわれたロイのそれが、くぷ、と音を立てて私の中に入ってくる。
媚薬のせいで敏感になっているからか、それとも限界ギリギリで焦らされたからか、それが入りきるまでに何回か軽くイってしまった。
「ななしのナカ、ぎゅうぎゅう締め付けてくる」
『そ、れ…言わなくてっ…いいっ』
「あー…本当に、止まれそうにっない、」
『ん、ひゃっあ、あっい、きなっり、ふ、あっ』
ぐちゅぐちゅと水音が耳に響く。
揺さぶられる体は、ぞくぞくと快感を溜めていく。
普段では考え付かないくらい、快感に顔を歪めるロイを見てぎゅう、とナカが締まる感覚がした。
「っき、つ…」
『ご、め、あっあ、あっ、ふ、あっ…ん、ぅ』
唇が重なる。
下から突き上げられる度に勝手に漏れてしまう声に合わせて口が開いて、そこからロイの温かい舌がぬるりと入り込む。
ぢゅる、といやらしい音を立てながら口内を貪られる。
体の全てが溶けてしまいそうなくらい気持ちよくて、涙がポロリとこぼれた。
「ななし、愛してる…っ」
『っ、あっ、ひ、あぁっ』
そんな事を好きな相手から囁かれたら、誰だってどきりとしてしまう。
ロイが私の体でどうしようもないくらい気持ちよくなってる。
そう考えるだけでお腹の奥がきゅんとするし、快感に拍車が掛かるのだ。
『あっ、も…まっ、て』
「待て、ない…っ」
『んあぁっだ、だめっ、ほんとにっきもち、良すぎ、てっ…あ、ぅっ、あたま、まっしろ……やっあ、あ……ーーーー!』
「っ」
体が無意識に弓のように反り上がり、手と足に力が入る。
真っ白な視界の中、びく、びく、と腰が揺れて中が収縮した。
一瞬止まっていた息を勢いよく吸ったと同時に止まっていた行為が再開されて抜けていた力がまたこもる。
『ふ……あっ!?ま、まって、今、いったばっか……!』
「知ってる…っ」
『や、あっだめ、こ、んなっあっ、きもち、のっ、んあ、あっおかしく、な、るっ』
こんなに激しく求められたのは初めてで、いつもと違う行為に頭と体がパンクしそう。
休む暇もなく与えられている快感にどうにかなってしまいそうだ。
「っ…ななし、」
『は、い……っん、む……ん、んぅ、は、んっんっ』
溶けちゃうようなキスを何度もしながら、それのスピードが上がった事でロイの限界が近いんだと感じる。
私は、ロイの首に手を回して体を密着させるように引き寄せた。
もっと、もっとロイを感じたい。
「ん、む……っ」
『ふっ、んっ、ーー!!!』
ロイが私の最奥を突いた瞬間、また頭が真っ白になってびくびくと腰が揺れる。
そしてロイも、最奥でびくびくと震えて欲を吐き出した。
『ん、ふ……は、ぅ…んむ、』
ロイが私の奥底へと種を残している間も、角度を変えて何度も何度もキスをした。
唇を離すと混ざりあった唾液がロイの舌先から零れ落ち、私の舌へとろとろ流れ込んできて私はそれをごくりと飲み込む。
いつもならここで終わるのだろうけど、
「…ななし」
『ん…私も』
まだ熱が下がりきらない私達は、それを合図にもう一度唇を重ねた。
何度も達してしんどいはずの体は、まるで何事も無かったかのように快感に溺れていく。
それはロイも同じの様で、硬くなったままのそれをもう一度、私へと宛がうのだ。
『いっそ、こわれちゃいたい、』
私から不意に出たそんな言葉に、ロイは応えるように唇を重ねた。
『……ん、』
ゆっくり目を覚ます。
暗かったはずの寝室は窓からの光でキラキラと明るく照らされていて、外では鳥や車の音が忙しなく聞こえる。
ベッドの中には誰も居なくて何回か瞬きをして、いつの間に朝になってたんだろう?なんて大あくびをしながら起き上がろうと力を入れた。
『……あれ?』
起き上がれない。
力が入らない、と言った方がいいのかな、この場合。
『な、なんで……ん〜…いっ!!』
精一杯力を込めてみたが、腰がズキンと痛んで折角の力が抜けてしまった。
これはどうしたものか、と悩んでいると寝室の扉がガチャリと開いて軍服姿のロイが顔を出す。
「ななしおはよう、身体は大丈夫…じゃあ無いよな」
『えっと…起き上がれないというか、腰が痛いというか……』
「そりゃそうだろう、ずっと同じペースで朝方までしてたんだ、限界も来るさ」
『朝、方……!?』
え?そんなに?記憶無いんですが……!とぐるぐる考えていると、それに気付いたロイが眉を下げてくすりと笑った。
「薬のせいだとはいえ随分と無理をさせてしまったからな、今日は1日休んでるといい」
『えっいや、私今日出勤!ロイが休みでしょ!』
「私がななしの代わりに出勤するから問題ないさ、まあ代役としては頼りないかもしれないがな」
『いやいやいや……頼りになるけど…!だめだよ、私が……いっったぁ!』
慌てて起き上がろうと力を入れた瞬間、キーンとした痛みが腰を襲う。
力無く倒れた私を見てロイはまた笑って私の頭を撫でた。
「無理は禁物だ」
『……ロイだって沢山したのに、』
「私は男だからな、ななしよりも体力も筋力もあるし、それに」
『それに?』
「ななしほどイってない」
『ー!』
耳元でそう囁かれてかあっと顔が熱くなる。
ロイはそんな私の米神にちゅ、と触れるだけのキスをした。
「というわけだ、ゆっくり休むといいよ」
『……お言葉に甘えて』
「水はここに置いておくし、昼は冷蔵庫に用意してあるからちゃんとたべるんだぞ」
『い、至れり尽くせり……』
「それじゃ、行ってくる」
そう言って笑ったロイに、私も笑い返す。
『ん、行ってらっしゃい!』
パタンと扉を閉めた後に、ガチャンと玄関を閉じて鍵を閉める音がした。
『服まで着せ直してくれてるし……』
何だか申し訳ないなという気持ちに刈られ、それならば夕飯は私がご馳走を作ろう!と決める。
まだ起き上がれないので、冷蔵庫の中身を思い出しながら献立を考える事にした。
『デザートは……当分無しでいいかな…』
昨日のガトーショコラで痛い目を……いや、痛くなんて全くなかったんだけど、兎に角暫くは無しでいいか。
でもたまには、本当にたまに、たまーに!1年に1回くらい!またあのガトーショコラを食べたいなぁ。
あんな風に快楽に溺れる姿を見てしまった私は、きっとまたあのロイに会いたくなるのだろう。
『……朝まで全部覚えてないのは、勿体無かったな』
そんな言葉が口から漏れて、一人くすくすと笑った。
2020/03/14