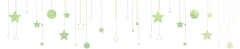『…という訳でして』
うう、皆の…特にハボックの視線が痛い。
いつもより遅めに到着した私達を待っていたのは、予想してた通り驚いて慌てふためく仲間の皆で。
やれ隠し子だの、いつの間にだの…本当に言いたい放題言われた。
…主にロイが。
「…まあ事情は大体理解したけど……本当に大佐とななしの子供じゃないっスよね?」
『全然理解してくれてない!!』
「いや、何て言うか…だってそっくり過ぎて…」
『そ、それは私も思うけどー…!』
女の子は私にほんのり似ているし、男の子は何処と無くロイに似ている。
それは私も凄く感じている事だけど、でもそれは間違いなく有り得ないのだ。
「ま、そうだよな…大佐の遺伝子が組み込まれてたら、もっと女癖の悪そうな顔に…」
「おい、聞き捨てならんぞそれは」
「おんなぐせってなに…?」
『えっ、』
「子供は知らなくて良い言葉よ」
私の腕の中に居る男の子が純真無垢な瞳でそう聞くから、思わず言葉が詰まってしまって焦ったけれどリザのフォローにより難を逃れた。
男の子は、そっかー…と笑ってこてんと私の胸へ顔を預けた。
「随分ななしに懐いているのね」
『そうなの!何でだろ、お母さんに似てるからかな?』
「ママ…」
すりっと私に頬擦りする男の子を見て、リザと笑う。
「ななしの推測通りみたいね」
『だね』
優しく頭を撫でてあげると、流石は子供。
どんどんと眠くなってきた様でとろんとした瞳になってきて、優しく背中を叩きながら暖めてあげる。
何処かの本で見た知識しか無いけれど、それでも知識が全く無いより全然ましで助かった。
『…寝ちゃった』
「こちらも、すっかり」
ロイの方を見れば、ロイの軍服をしっかりと握った状態でぐっすりと眠る女の子。
安心しきっているその顔があまりにも可愛くて、また胸の奥がきゅーんとした。
「大佐、こちらに…ほら、ななしも」
「すまん、助かる」
『わ、ありがとう…!』
執務室のソファには、いつの間にかリザが愛用してるブランケットが敷いてあって。
そこに子供二人を寝かせて、上から私のブランケットを掛けてあげる。
すやすやと眠るその姿は正に天使そのもので、ロイと顔を見合わせて笑った。
「所で、司令部内にも託児所っぽい所ありましたよね?」
『えっと…それは勿論、一番最初に向かったんだけど』
「子供達が、絶対離れない!と何をしても離れなくてな」
『ロイの軍服、あの時凄い伸びてたよね…』
特に女の子の方が離れたがらなくて、可愛い顔を真っ赤にしてロイにしがみついてたのだ。
「子供にすらモテんのかよ…」
「ま、そういう事だ」
「そう言えばななし、この子達の名前は?」
『それが…一切答えてくれなくて』
名前を知らないと呼ぶのが大変だからと何度もしつこく聞いてみたんだけど、答えは一貫して得られなくて。
『いずれ知るからって言うばかりだったんだよ』
「でも、この子達は一方的に大佐達の事を知っていたんですよね?」
「ああ、好物から自宅までの道のり…そして自宅での行動まで」
「そこまで知ってるとなると、一度自宅に招き入れた友人とか…」
『うーん…子連れはヒューズさんしか…』
皆でうーん、と唸る。
考えれば考えるほどこの子供達の事が分からなくて、頭を悩ませるばかりだ。
「まあ話を聞く限り、一日預かるだけみたいだし本人達が言いたくないのなら無理して聞く事も無いのかもな」
『うん、私達もそう思って聞くのはやめたんだ』
「…さて、話はこれくらいにして今は目の前の仕事を片付けちゃいましょうか。」
「ですね、この子達が起きたら俺達は兎も角大佐とななしは仕事なんて言ってられなくなりそうですし」
『ファルマンの言う通りだね…んーっよし!ぱぱっと片付けちゃいますか!』
「ははーん、成る程…状況は理解した。だけどあれだな、こんなに大きくなるまで秘密にしてたなんて親友として悲しい…」
『だー!違いますって!何で皆信じないんですか!』
お昼になって休憩となった私達は、あることをお願いする為にヒューズさんの元へと来たんだけど…ここでもやっぱり信じてくれなくて、何だか悲しくなってくる。
「悪い悪い、そんなムキになるなって!にしても冗談抜きで似てるな…ほら、このぱっちりとした目なんかななしにそっくりだ」
「んふふ、でしょ!いつも似てるねってほめられるのー!」
にまーっと嬉しそうに笑う女の子。
ありゃ、またお母さんと間違えてるのかな?なんて私は思ったけれど、目の前の男性二人は何だか変な顔をしていて。
「…おほん、それにあれだな!男の子の方はロイに似て綺麗な顔立ちだ!」
「ふへへ…」
「……ママが好きな飲み物は〜?」
「ココア…」
「…………パパが大好きな人は〜?せーの!」
「ママー!!」
『ひょっ、え?わ、私?』
ヒューズさんの問い掛けに、ロイに抱っこされている女の子が元気よく返事をして私を指差す。
そうなると当然二人の視線は私に向くわけで。
『えっ、あの……また、間違えてるみたいだね…?』
「…ロイ、こりゃあ」
「……恐らく同じ事を考えている」
『あ、あの…?』
「え?何だって?ふむふむ、おお!それは大変だ!直ぐに行かなくては!」
『えっ?えっ!?』
二人して変な顔をしたと思ったら、今度はヒューズさんが女の子に耳を傾けてそんな事を言い始めた。
当の女の子は、その勢いに圧倒されているようでポカーンとしていて。
「そういう事で悪いな、ななし!女の子とロイは借りてくぞ!」
『えっ!?』
「すぐ戻る!多分15分くらいだ!」
『そ、それってすぐって言うんですかー!?……い、行っちゃった』
角を曲がって行った三人は、正に嵐のように去っていって、ぽつんと二人取り残される。
ふと男の子を見てみれば、驚くことに気にする様子もなく私に抱きついていて。
『皆行っちゃったね』
そう言って苦笑いをすると、男の子はふんわりと笑った。
「えへへ、ふたりっきりだね…」
『……!!』
胸がきゅんきゅんしたのは言うまでもない。
「いやー待たせたな!」
『あっお帰りなさい!』
暫くして帰ってきた三人は、さっきと変わらない様子……いや、何だかロイが変な顔をしてる。
女の子がトテトテと此方に近寄ってきたので、目線を合わせるように屈むと男の子にこそっと何かを伝えた。
『え?なになに?』
「バレちゃったんだって…」
『え?』
「もー!言っちゃだめじゃん!」
「ご、ごめん…」
バレちゃった?何が?と首を傾げると、ヒューズさんがアレだよ、アレ!と言葉を詰まらせて頭をかく。
「んー……あれだ、あー…乙女の秘密だ!」
「また馬鹿げた…」
「こら、ロイ合わせろ!」
「おとめのひみつー!ね!ロイお兄さん!」
「…そうだな、そういう事にしておこう」
「お前…子供の言う事は聞くのかよ…」
乙女の秘密…?
『わ、私も一応女子で…』
「ひみつはひみつなの!」
『え、ええー……』
状況を見ても、その乙女の秘密を知らないのはどうやら私だけみたい。
…男の子はまあ良いとして、ロイとヒューズさんは乙女じゃないよね…?
そんな疑問が浮かんだけれど、ロイが何だか聞いてほしくない様な顔をしていて。
『よく分かんないけど、乙女の秘密ならしょうがないね!』
「…うんっ!」
とりあえず此処は話を合わせよう、とそう言ってみると女の子は笑顔で頷いた。
でも何だか寂しいなぁ〜なんて、子供相手に思っていると抱き抱えてる男の子が私の頬を小さい手で優しく包んだ。
「お姉さんには、ぼくがついてるからだいじょうぶだよ」
『う……!』
キラキラとした瞳で、天使のような可愛らしい顔でそう微笑むから、また胸がきゅんとして男の子をぎゅっと抱きしめた。
『可愛いすぎる…!』
「えへへ…」
男の子もそれに応えてくれるようで、すりすりと顔を寄せてくれて。
ああ、なんて可愛いの!
「ロイ…見ろ、子供のあの顔…」
「…でろんでろんに蕩けてるな」
「ありゃあロイ似だな」
「……否定しきれない所が少し複雑だ」
「あのこ、ママのこと大好きでいっつもパパと取り合ってるもん」
「……」
「…想像、出来るわ」
「おい」
空もすっかりオレンジ色になった頃、仕事も大体片付いたので少し早めに勤務を終えることになった。
『よし!それじゃあヒューズさんのお家まで行こー!』
「おー!」
「おー…」
実はお昼にヒューズさんを探していた理由は、この子達の事で。
一日預かる事になったし、もし迷惑じゃなければ子供達を連れていっても良いか、と。
あの優しいヒューズさんの事だから、きっと快くオーケーしてくれる…と信じて行ったのだが、回答は斜め上をいった。
「え?当然参加すると思ってグレイシアに連絡入れといたけど」
その言葉には、流石のロイも目を丸くしていた。
え?いつの間に!?と聞いてみれば、さっき三人で席をはずした時にな!と笑われて。
『ヒューズさんって、行動力が凄いよね…』
「それが良いところでもあり悪いところでもあるな、今回は良いところだが」
相変わらず抱っこをせがむ子供達を抱えて、ヒューズさんのお家まで歩いていく。
ハロウィン仕様になっている商店街を歩くと、子供達はそれはそれはキラキラした瞳で周りをキョロキョロしていて凄く可愛い。
『そういえば、本当にこの子達のご両親と連絡取れたんだよね?』
「ん?ああ…ちゃんと話は通してあるよ、帰るのが遅くなるから是非パーティーに連れていってほしいと言われた」
『なら良いんだけど…』
結局、この子達のご両親とは会うことも無く。
突然電話が来て、ロイはお話したらしいけど…まさかロイの知り合いだったとは。
『…本当に知人だったんだよね…?』
「ああ、電話を受け取るまですっかり忘れていてな」
『なんでそんな大事な事忘れるかな…』
「…ほら、そうこうしてる間に着いたぞ」
妙に話を逸らされた気もするけれど、まあこの際それは良いか…と割り切って私達はヒューズさんのお宅のあるマンションへと足を踏み入れた。
「ななしお姉ちゃん、エリシアとお揃い!」
「わたしかわいいあくまさん!」
「ぼく、きゅうけつき……」
『うんうん、皆似合ってるよ!』
「ななしちゃんも可愛らしいわ」
ガヤガヤと騒がしい部屋の隅でヒューズと酒を飲む。
壁には一面紙で出来た装飾品が飾られていて、部屋の中心にはケーキ等のお菓子が並んでいる。
「全部グレイシアさんの手作りか」
「そうだぞ!エリシアも手伝ったと思う、どうだ最高だろ!」
そう言って私の背中を手加減無く叩くヒューズは、既に出来上がっている様で顔が赤い。
「…こんな事、あり得ると思うか?」
ふと、目の前ではしゃぐ子供達に目を向ける。
楽しそうにはしゃぐその姿に思わず目を細めた。
あの女の子から聞いたものは、信じるにはあまりにも非現実的で…あまりにも希望のある未来で。
私が夢を見、描いている理想の未来そのもので……これは、私が作り上げてしまっている幻想なんじゃないか、そんな馬鹿げた事を考えてしまうほど内心混乱している。
「…実際に起きてる。これは紛れもなく現実だ」
「…」
「錬金術があるんだ、どんな事が起こったって不思議じゃない。未来ともなりゃ今よりも色々な物が進化しているだろうしな」
「…信じてみても良いんじゃないか、これが、あの子達がお前達の未来だってよ」
「…ああ、そうだな」
私の描いているものの先には、この子達が待っている。
そう思うと、何だかむず痒くて心が温かくなる。
…自分でも気持ち悪いとは思うが。
「信じてみるよ、いや、現実にさせる。この景色を、必ず。」
「そうだな!その時はまた、こうしてパーティーをしよう!はしゃぐ家族達を見ながら酔っぱらうのも悪くは無いだろ?」
「…そうだな、悪くない」
ヒューズの気持ちを少し理解した気がして、小さく笑った。
ヒューズと居るとどうも気が緩んで全てを口に出してしまうのは、きっとヒューズが全部を真面目に受け取ってくれるからなのだろう。
「ま、今回はあれだ!ハロウィンが運んだ奇跡って事で!」
「何だ、それ」
『ロイ!』
「ん、どうした?」
『ほら、せーの、』
「「トリック・オア・トリートー!」」
可愛らしい魔女姿のななしに呼ばれて視線を向けると、両手を出した子供が二人。
大方、ななしに教え込まれたのだろう。
横を見ればヒューズもエリシアちゃんに両手を出されている。
「どうする?ロイさんよ」
「どうするも何も、あいにく手持ちが無い」
「俺も同じだ」
そう言って手を上げると、キラキラと輝いている子供達の瞳が更に輝いた。
『無いときは〜?』
「いたずらだー!」
「だー…!」
「おっ、と…ふ、ふは…や、やめ…」
「こちょこちょー!」
『あはは!ロイってば変な顔ー!』
「パパにもやっちゃうぞ〜!」
「魔女っこエリシアに悪戯されるぅ〜!うわぁ〜!」
「ふふ、もう悪ノリして…」
『楽しかったー!』
んーっと手を空へ伸ばしてふう、と息を吐く。
外はすっかり暗くなっていて、朝と同じくらい冷え込んでいる気がする。
『大丈夫?寒くない?』
「うん!」
「大丈夫…」
少し厚手の上着を着ている子供達は、寒さなんてものともせずに上機嫌だ。
私もそんな時代があったよ…と懐かしみながら、マフラーに顔をうずめた。
『良かったのかなあ、二人分の上着貰っちゃって』
「処分に困っていたそうだし、大丈夫だろ。あとで改めてヒューズに礼を言っておくよ」
『その時は私も!今回は凄く頼っちゃったし、お礼したいから』
パーティーに参加させてもらって、美味しい料理までご馳走になって。
最後に上着まで譲ってくれるなんて、何処までいい人たちなんだろう。
『ほんと、楽しかったなぁ…』
ぽろりと言葉が漏れる。
だって、本当に楽しい一日だったのだ。
凄く大変だったけど、すごく充実していて楽しかった。
それもこれも、この子達が居たからなんだろうなあ。
『ずっと一緒に居れたら良いのにね』
「…ななし、」
『…え?あ、いや、待って!変な意味じゃなくてね?今日凄く楽しかったから、また会いたいねって話でね!?』
誘拐とか、そんな気は無いので!本当に!と慌てて弁解していると、ロイは吹き出すように笑って私の頭を撫でた。
「大丈夫さ」
『…?』
「現実にしてみせるから」
『なに、言ってるの?』
優しく笑うロイは、何だか全てを知っている様な…そんな気がして。
ロイと一緒なら、またこんな日が来るかもしれない、なんて考えがよぎった。
ふと、子供達が私たちの服の裾を引っ張って、素直に顔を向ければニコニコしている二人と目が合う。
「お姉さん、お兄さん!今日はありがとうございました!とっても楽しかったです!」
『ど、どうしたの?急に…』
「二人がね、わたしたちと出会う前からなかよしなの知れてとってもうれしかった!」
『出会う、前から…?』
「またいつか必ず来るから…その時はまた沢山遊んでね!」
『えっちょ、状況が理解出来ないんだけど…!』
何故かお別れの雰囲気になっている、気がする。
ご両親も来ていないのにいきなりどうしたんだろう。
そう戸惑っていると、ロイがしゃがんで二人の頭を撫でた。
「ちゃんと帰れるか?」
「うん!なんか帰れそうな気がする!しんぱいしなくてもへいきだよ!」
「それは頼もしいな」
わしゃわしゃと撫でるロイに、それを嬉しそうに受ける二人。
内容には全くついていけてないけど、その姿に何だか胸が温かくなった。
「だってね、わたしたち…パパとママの子供だもん!」
「ねー…」
『…!』
……なんで今まで気づかなかったんだろう、この子達は、
『あなた達は、私達の……わっ!』
突如現れた青白い光が子供達を包む。
何とか目を開けたいけど、光が強すぎて直視が出来ない。
目を閉じてても、痛いくらいに眩しいその光は段々と弱くなっていく。
やっと目を開いた時には、目の前には子供一人居なくて。
『……行っちゃったの?』
「みたいだな」
最後の最後で気付いたのに、それを伝えられなかった。
ちゃんと、帰れただろうか。
「大丈夫だよ」
『え、』
「ちゃんと帰れたさ」
ロイがそうやって頭を撫でるから、ちょっとだけ寂しい気持ちが目から溢れてしまって、バレないように慌てて拭った。
『ハロウィンだからって、不思議な事が起こりすぎでしょ』
「そうだな」
『…また、会えるよね?』
そんな私の、少しの不安はロイの言葉で溶けて消えていく。
「必ず会えるさ」
心の奥にストンと落ちたその言葉は、温かくて優しくて…私の心を安心させるには充分だった。
ハロウィンがもたらした、小さな奇跡。
どんな原理かは分からないし、夢だったのかもしれない。
それでも、この楽しくて温かかった夢を私達が忘れる事は一生ないのだろう。
『はぁ、早く会いたいなぁ』
「すぐに会える方法ならあるだろ?」
『え?…え!?いや、そ、その…!』
「色々起こりすぎて、魔女姿もあまり堪能できなかったしな、今からでも」
『ちょっ、と!余韻に浸らせてよ、もー!!』
多分、会えるのはもう少し先だけど。
必ず出会ってみせるから、それまで待っててほしいな。
2019/10/31