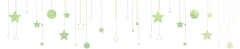『暑いときは、やっぱり怖い話だと思うの!』
ソファで読書に没頭するロイの目の前で仁王立ちしてそう言ってみると、ロイは本を支えている指をぴくりと動かした。
「怖い話なんて聞いたら一人でトイレに行けなくなるだろ」
『え?ロイが?』
「ななしが!!」
…怒られてしまった。
まあロイが怖い話一つでトイレに行けなくなるなんて無いだろうけど…あったら面白いけど。
というか私だって別にトイレくらい一人で行けるのに、一体どんなイメージを持たれているんだろう。
『あのね、ロイ。私、別に怖い話くらいでトイレに行けなくなったりしないからね?』
「…風呂は?」
『おふろ………ロイがお風呂のドア向こうで待っててくれれば平気!』
「待ってるなんて御免だなあ…そんなの生殺しと一緒だろ」
どうしてロイがドア向こうで待っててくれると生殺しになるのかは考えない事として、兎に角私は怖い話がしたいのだ。
『ねー!いいでしょ!』
「…そもそも、何でそんなに話したがるんだ」
『ロイが怖がる姿を見たい!!』
ふん!と胸を張ると、ロイのため息がワンテンポ遅れて聞こえた。
そう、ロイの怖がる姿が見たい。
ふとそう思ったのだ。
「あいにくだが、私は怪談くらいで驚いたりはしないぞ」
『私もそう思いましたよ、ええ!今日あれを聞くまではね……』
今日のお昼、司令部の中にある食堂でアームストロング少佐と同席した時に聞いた話がある。
それは身体中の毛の一本一本が逆立つような…そんな恐ろしい話だったのだ。
思わず食事も喉を通らなくなってしまうような、そんな話。
『私は思ったの!この話ならロイもきっと顔面蒼白になる……!』
「…」
何だかロイが呆れたような視線を送っているような気がするけど…無視しよう。
「つまりは聞いた話が怖いから、それを私と共有してトイレも風呂も共に行動しようと言うことか」
『ち、違うし!トイレもお風呂も、ドアの向こうで待っててくれれば良いの!』
「結局トイレも待つことになるのか…」
『と、とにかく!良いでしょ!ね?怖い話しようよー!』
ロイの体をゆさゆさと揺らせば、持っていた本を机に置いてまたため息を吐いて。
「一緒ならいいよ」
『え?一緒って?』
「風呂」
そう言ってにやりと笑うロイ。
私はと言うと、それがどういう意味かがすぐには理解できなくて。
でも回転していない頭でやっと理解すると、顔に熱が集まっていくのを感じた。
『や、やだ!』
「じゃあ怖い話はまた今度だな。さて、寝る前に風呂に入ろうか。先に行っておいで、ここで待ってるから」
『う…うー!!!』
ロイにしては珍しいくらいの意地悪に思わず唸る。
ポカポカとロイの体を殴ると、当の本人は面白そうに笑い始めた。
「どうする?二人で楽しく風呂に入るか、それとも一人で怯えて風呂に入るか」
『うぐぐ……』
そんな選択肢を出されたら、前者しか選べないじゃない!
そう思いながら睨めば、ロイは至極面白そうに笑って私を見つめていて。
『…いじわる』
「好きな子はいじめたくなるってよく言うだろ?」
『知らないし!!…絶対怖がらせてやる!!』
その余裕そうな表情を、不安と恐怖の表情に変えてやる!!
そう意気込み、なるべく低く…そしてゆっくりと話し始めた。
『…眠れない』
真っ暗な中ぼんやりと天井を見つめながらそう呟く。
横に居るロイは、私のそんな呟きを聞いてため息を小さく吐いた。
「結局、話す為に思い出して余計怖くなったみたいだな」
『…なんでロイは平気そうなの!』
「あまり怖くなかった。何だあの話は…なんで出てきた幽霊と一緒に食事をするんだ」
『知らないよー!それが怖いんじゃん!幽霊が隣に座って、食べてたご飯を横取りするんだよ!?怖くて眠れないよ!!!』
「それで怖がるのはななしくらいだと思うんだが」
この通り、結局ロイは怖がらせる事が出来ず。
思い出した私だけが震える羽目になったし、二人でお風呂に入る事になって軽くのぼせてしまったし。
お布団に入ったのは良いものの、ロイにピッタリくっついてないと怖くて無理だし。
『何でこんな時に限って雨が降るんだろう…』
いつもなら月明かりで淡く照らし出されている寝室も、雨雲のせいで真っ暗で殆ど何も見えない。
遠くの方でゴロゴロと雷の音も聞こえて、ちょっとだけ嫌な予感がする。
「ほら、こっちおいで」
握っていたロイの手に引かれて、ロイの腕の中へと入る。
温かくて、良い匂いのする体。
とくとくと一定の速度で動く心臓の音。
全てに安心して、ロイの胸にぐりぐりと頭を擦り付けた。
『うう〜…』
「まだ怖い?」
『さっきより怖くない…』
「それは良かった」
私の頭を撫でていたロイの大きな手が、私の背中に回ってきてトントンと優しく叩かれる。
言わば子供を寝かしつける時のアレだ。
『…私子供じゃない』
「でも安心するだろ?」
『まあ…と言うか、こういうの知ってるんだ』
「そりゃこれくらいの知識はあるよ」
『…もしかして、子供の時マダムにして貰ったことがあったり?』
「…ノーコメント」
暗くて顔は見えないけれど、声色からするにちょっと照れてるなこれは。
そうか、ロイにもそんな時代があったんだー…なんて考えたけど、想像は出来なくて。
あとでマダムに聞いてみよう!と意気込んだ。
「…マダムに聞くのは無しだからな」
『な、何で?』
「ななしなら聞きかねない」
『そ、そんなことしないし』
「…明日にでも電話しておくよ」
あーじゃあ明日はロイよりも先にマダムに連絡しておかなくちゃ…
そう言いたかったけど、急な眠気に襲われた私は途切れ途切れに言葉を繋いだ。
「おやすみ、ななし」
今にも寝そうな私に気づいたロイは、優しくて甘い声色でそう囁いてから私の額にキスを落とした。
一瞬目の前が明るくなったような気がして目を覚ます。
気のせいだったのか、未だに部屋は暗くて。
暫くぼーっとしていると、暗闇に慣れてきたのか抱きしめてくれているロイの寝顔がぼんやりと見えてきた。
耳を済ませて外を確認すると、未だに雨は降り続いているようだ。
雷の音も寝る前よりも近く感じる。
明日は傘必須だなぁ…雨が酷いようならタオルも持っていかなくちゃ。
そんな事をぼんやりと考えている間に脳が覚醒してきたらしく、完全に目が覚めてしまって。
おまけに水分を取りたくなってしまった私は、ロイを起こさないように起きた。
が、部屋の中は思っていたよりも暗くて…正直怖い。
こんな時に限って今日の話を鮮明に思い出してしまって、体が震えた。
…どうしよう、ロイを起こしちゃおうか。
そう思ったけれど、大の大人が怖いからという理由で恋人を起こすのも恥ずかしい。
私は、意を決して一人で行く事にした。
部屋を出て真っ先に電気を点ける。
明るい部屋は案外怖くなくて、ほっとした私は何を考える事なくキッチンへと向かった。
無事に水分も取った私は、近くの窓まで行って外を確認する。
が、思ったよりも酷いみたいで雨以外何も見えない。
所謂豪雨というやつで。
『やっぱり傘だけじゃ不安だし、レインコートも用意しておこうかな』
そう思い立った直後。
『う、わっ…!』
外が明るく照らし出されたと思ったら直ぐに小さな地響きと共に大きく雷が鳴り、明るかった部屋が真っ暗になって。
所謂停電だと気づくのに時間はかからなかった。
一切光の無い空間に一人。
なんだか、知らない所に一人で放り出された気分になって心臓が早くなる。
おまけに、こんな時にまたあの怖い話を思い出してしまって、ぶるりと体を震わせた。
『むりむりむり…』
ロイが居たから平気だったものの、一人となると怖いし…こう暗いと私の周りがどうなっているかも分からず、嫌な方向へと物事を進めてしまって。
後ろに居たらどうしよう、横に、下に、上に……ネガティブは更なるネガティブを呼ぶようで、嫌だと思いつつも想像してしまう。
もう何も考えずに早く寝室に戻ろう。
そう思って前を向いた時、遠くの方でゆらゆらと揺れる小さな炎が見えた。
それはどうやら、私の方へとゆっくりゆっくり向かってきているようで。
『えっ……』
サーっと血の気が引いていく感覚に陥る。
驚きのあまり、体が硬直してしまって動かない。
目を逸らした隙に隣まで来るんじゃないか、と不安になって目も逸らせずにただ炎を見つめていた。
大分炎が近くなった所で奥の方からぬるりと手が伸びてきて、それに驚いて後退りした挙げ句、足がもつれて尻餅をついてしまって。
痛さよりも何よりも恐怖が勝って、私は何も見えないようにと目を強く閉じた。
「ななし?」
ふとロイの声が聞こえて反射的に顔を上げると、驚いたような表情のロイが手燭を持って立っていた。
そのゆらゆらと揺れる小さな炎を見て、幽霊じゃなかったと思った途端に何だか力が抜けてしまって。
「盛大に尻餅をついたみたいだが…何処か痛めてないか?」
手燭を置いて私の背中に手を回してくれるロイ。
蝋燭の灯りで照らし出されているロイは、何だかいつもよりも暖かく感じて…気づいたら私の目から涙がポロポロと零れていた。
私もびっくりしたけれど、何よりもロイがびっくりした様子で。
でも何かを察したようで、優しく抱きしめられた。
「驚かせてしまったかな」
何度も何度も優しく頭を撫でてくれるから、それに酷く安心してロイの背中に手をまわす。
ふっと笑う声が耳元でしたけれど、聞こえないふりをした。
「可愛いなあ」
『…あのね、驚いてないからね、その、怪談とか幽霊とか…全然、』
「ふは、それ気にしてたって言ってるようなものだぞ……いたっ!」
泣くほど怖がってしまった事をどうにか隠そうと言い訳をしたけれど、ロイはそれをも見透かして笑って。
それが悔しくて、背中を叩いた。
『もう!もう!!…あ、』
痛がるロイを横目に、お構い無しで殴り続けていると電気が復旧した様で一気に周りが明るくなる。
それによって、今ロイと抱き合っているのがとてつもなく恥ずかしく感じてロイの胸を押した。
だけど、どんなに強く押してもロイが離れることは無くて。
『は、恥ずかしい!離して!』
「さっきは怖がって泣いてしがみついて来たのになあ」
『あれはアクシデント!だ、だれだって暗闇の中炎があったら驚く!』
「まあそれもそうだな」
『だから離して…!』
そう言って今一度力を入れるけど、やっぱり離れなくて。
何故か私の力じゃ少しも動かない悔しさでロイを睨むと、優しく笑っているロイに触れるだけのキスをされた。
「涙目で睨まれてもなあ」
『うー!!、わっ』
突如ふわりと体が浮いて、ロイの顔が目の前に来る。
背中と太ももを支えられていて、お姫様だっこをされているというのに気づくまで時間はかからなかった。
『や、な、なにして』
「ななしの事だ、恐らく腰が抜けて立てないだろう?押す力もそれほど無かったしな」
『なるほど、それで……じゃなくて!だったら担ぐのでもいいじゃん…!わざわざこんな、』
「女性を、ましてや可愛い恋人を担ぐなんて事するわけ無いだろ?」
そうだった、ロイはそういう性格だった。
どんなときでも女性扱いしてくれるのは凄く嬉しいけど、でもやっぱりお姫様だっこは何度されても慣れなくて。
でもまだ一人じゃ歩けそうにないし、選択肢はこれしか残ってない。
仕方なくロイの首に手をまわすとロイは満足そうに笑った。
「さ、寝室に行こうかお姫様?」
『寝室まで送り届ける王子様なんて聞いたこと無い!』
「そこは小さく頷く所だろ」
『そんなの分かんないし!』
「まあ、こういう所も可愛いんだけどな」
そういう事言うから、私はいつだってロイにドキドキしてしまうのだ。
「ふは、顔が真っ赤だ」
『う、うるさい!!』
「にゃにするんひゃ」
『あはは!』
楽しそうにからかってくるロイのほっぺを摘まんでびょいーんと引っ張る。
じと、と見てきたロイだけど全く言えていないその姿が可愛くて大笑いしてしまった。
そのあと小さな声で、寝室行ったら覚えてろ、と言ったような気がしたけど……私は聞こえないふりをして目を閉じた。
2019/08/13
ソファで読書に没頭するロイの目の前で仁王立ちしてそう言ってみると、ロイは本を支えている指をぴくりと動かした。
「怖い話なんて聞いたら一人でトイレに行けなくなるだろ」
『え?ロイが?』
「ななしが!!」
…怒られてしまった。
まあロイが怖い話一つでトイレに行けなくなるなんて無いだろうけど…あったら面白いけど。
というか私だって別にトイレくらい一人で行けるのに、一体どんなイメージを持たれているんだろう。
『あのね、ロイ。私、別に怖い話くらいでトイレに行けなくなったりしないからね?』
「…風呂は?」
『おふろ………ロイがお風呂のドア向こうで待っててくれれば平気!』
「待ってるなんて御免だなあ…そんなの生殺しと一緒だろ」
どうしてロイがドア向こうで待っててくれると生殺しになるのかは考えない事として、兎に角私は怖い話がしたいのだ。
『ねー!いいでしょ!』
「…そもそも、何でそんなに話したがるんだ」
『ロイが怖がる姿を見たい!!』
ふん!と胸を張ると、ロイのため息がワンテンポ遅れて聞こえた。
そう、ロイの怖がる姿が見たい。
ふとそう思ったのだ。
「あいにくだが、私は怪談くらいで驚いたりはしないぞ」
『私もそう思いましたよ、ええ!今日あれを聞くまではね……』
今日のお昼、司令部の中にある食堂でアームストロング少佐と同席した時に聞いた話がある。
それは身体中の毛の一本一本が逆立つような…そんな恐ろしい話だったのだ。
思わず食事も喉を通らなくなってしまうような、そんな話。
『私は思ったの!この話ならロイもきっと顔面蒼白になる……!』
「…」
何だかロイが呆れたような視線を送っているような気がするけど…無視しよう。
「つまりは聞いた話が怖いから、それを私と共有してトイレも風呂も共に行動しようと言うことか」
『ち、違うし!トイレもお風呂も、ドアの向こうで待っててくれれば良いの!』
「結局トイレも待つことになるのか…」
『と、とにかく!良いでしょ!ね?怖い話しようよー!』
ロイの体をゆさゆさと揺らせば、持っていた本を机に置いてまたため息を吐いて。
「一緒ならいいよ」
『え?一緒って?』
「風呂」
そう言ってにやりと笑うロイ。
私はと言うと、それがどういう意味かがすぐには理解できなくて。
でも回転していない頭でやっと理解すると、顔に熱が集まっていくのを感じた。
『や、やだ!』
「じゃあ怖い話はまた今度だな。さて、寝る前に風呂に入ろうか。先に行っておいで、ここで待ってるから」
『う…うー!!!』
ロイにしては珍しいくらいの意地悪に思わず唸る。
ポカポカとロイの体を殴ると、当の本人は面白そうに笑い始めた。
「どうする?二人で楽しく風呂に入るか、それとも一人で怯えて風呂に入るか」
『うぐぐ……』
そんな選択肢を出されたら、前者しか選べないじゃない!
そう思いながら睨めば、ロイは至極面白そうに笑って私を見つめていて。
『…いじわる』
「好きな子はいじめたくなるってよく言うだろ?」
『知らないし!!…絶対怖がらせてやる!!』
その余裕そうな表情を、不安と恐怖の表情に変えてやる!!
そう意気込み、なるべく低く…そしてゆっくりと話し始めた。
『…眠れない』
真っ暗な中ぼんやりと天井を見つめながらそう呟く。
横に居るロイは、私のそんな呟きを聞いてため息を小さく吐いた。
「結局、話す為に思い出して余計怖くなったみたいだな」
『…なんでロイは平気そうなの!』
「あまり怖くなかった。何だあの話は…なんで出てきた幽霊と一緒に食事をするんだ」
『知らないよー!それが怖いんじゃん!幽霊が隣に座って、食べてたご飯を横取りするんだよ!?怖くて眠れないよ!!!』
「それで怖がるのはななしくらいだと思うんだが」
この通り、結局ロイは怖がらせる事が出来ず。
思い出した私だけが震える羽目になったし、二人でお風呂に入る事になって軽くのぼせてしまったし。
お布団に入ったのは良いものの、ロイにピッタリくっついてないと怖くて無理だし。
『何でこんな時に限って雨が降るんだろう…』
いつもなら月明かりで淡く照らし出されている寝室も、雨雲のせいで真っ暗で殆ど何も見えない。
遠くの方でゴロゴロと雷の音も聞こえて、ちょっとだけ嫌な予感がする。
「ほら、こっちおいで」
握っていたロイの手に引かれて、ロイの腕の中へと入る。
温かくて、良い匂いのする体。
とくとくと一定の速度で動く心臓の音。
全てに安心して、ロイの胸にぐりぐりと頭を擦り付けた。
『うう〜…』
「まだ怖い?」
『さっきより怖くない…』
「それは良かった」
私の頭を撫でていたロイの大きな手が、私の背中に回ってきてトントンと優しく叩かれる。
言わば子供を寝かしつける時のアレだ。
『…私子供じゃない』
「でも安心するだろ?」
『まあ…と言うか、こういうの知ってるんだ』
「そりゃこれくらいの知識はあるよ」
『…もしかして、子供の時マダムにして貰ったことがあったり?』
「…ノーコメント」
暗くて顔は見えないけれど、声色からするにちょっと照れてるなこれは。
そうか、ロイにもそんな時代があったんだー…なんて考えたけど、想像は出来なくて。
あとでマダムに聞いてみよう!と意気込んだ。
「…マダムに聞くのは無しだからな」
『な、何で?』
「ななしなら聞きかねない」
『そ、そんなことしないし』
「…明日にでも電話しておくよ」
あーじゃあ明日はロイよりも先にマダムに連絡しておかなくちゃ…
そう言いたかったけど、急な眠気に襲われた私は途切れ途切れに言葉を繋いだ。
「おやすみ、ななし」
今にも寝そうな私に気づいたロイは、優しくて甘い声色でそう囁いてから私の額にキスを落とした。
一瞬目の前が明るくなったような気がして目を覚ます。
気のせいだったのか、未だに部屋は暗くて。
暫くぼーっとしていると、暗闇に慣れてきたのか抱きしめてくれているロイの寝顔がぼんやりと見えてきた。
耳を済ませて外を確認すると、未だに雨は降り続いているようだ。
雷の音も寝る前よりも近く感じる。
明日は傘必須だなぁ…雨が酷いようならタオルも持っていかなくちゃ。
そんな事をぼんやりと考えている間に脳が覚醒してきたらしく、完全に目が覚めてしまって。
おまけに水分を取りたくなってしまった私は、ロイを起こさないように起きた。
が、部屋の中は思っていたよりも暗くて…正直怖い。
こんな時に限って今日の話を鮮明に思い出してしまって、体が震えた。
…どうしよう、ロイを起こしちゃおうか。
そう思ったけれど、大の大人が怖いからという理由で恋人を起こすのも恥ずかしい。
私は、意を決して一人で行く事にした。
部屋を出て真っ先に電気を点ける。
明るい部屋は案外怖くなくて、ほっとした私は何を考える事なくキッチンへと向かった。
無事に水分も取った私は、近くの窓まで行って外を確認する。
が、思ったよりも酷いみたいで雨以外何も見えない。
所謂豪雨というやつで。
『やっぱり傘だけじゃ不安だし、レインコートも用意しておこうかな』
そう思い立った直後。
『う、わっ…!』
外が明るく照らし出されたと思ったら直ぐに小さな地響きと共に大きく雷が鳴り、明るかった部屋が真っ暗になって。
所謂停電だと気づくのに時間はかからなかった。
一切光の無い空間に一人。
なんだか、知らない所に一人で放り出された気分になって心臓が早くなる。
おまけに、こんな時にまたあの怖い話を思い出してしまって、ぶるりと体を震わせた。
『むりむりむり…』
ロイが居たから平気だったものの、一人となると怖いし…こう暗いと私の周りがどうなっているかも分からず、嫌な方向へと物事を進めてしまって。
後ろに居たらどうしよう、横に、下に、上に……ネガティブは更なるネガティブを呼ぶようで、嫌だと思いつつも想像してしまう。
もう何も考えずに早く寝室に戻ろう。
そう思って前を向いた時、遠くの方でゆらゆらと揺れる小さな炎が見えた。
それはどうやら、私の方へとゆっくりゆっくり向かってきているようで。
『えっ……』
サーっと血の気が引いていく感覚に陥る。
驚きのあまり、体が硬直してしまって動かない。
目を逸らした隙に隣まで来るんじゃないか、と不安になって目も逸らせずにただ炎を見つめていた。
大分炎が近くなった所で奥の方からぬるりと手が伸びてきて、それに驚いて後退りした挙げ句、足がもつれて尻餅をついてしまって。
痛さよりも何よりも恐怖が勝って、私は何も見えないようにと目を強く閉じた。
「ななし?」
ふとロイの声が聞こえて反射的に顔を上げると、驚いたような表情のロイが手燭を持って立っていた。
そのゆらゆらと揺れる小さな炎を見て、幽霊じゃなかったと思った途端に何だか力が抜けてしまって。
「盛大に尻餅をついたみたいだが…何処か痛めてないか?」
手燭を置いて私の背中に手を回してくれるロイ。
蝋燭の灯りで照らし出されているロイは、何だかいつもよりも暖かく感じて…気づいたら私の目から涙がポロポロと零れていた。
私もびっくりしたけれど、何よりもロイがびっくりした様子で。
でも何かを察したようで、優しく抱きしめられた。
「驚かせてしまったかな」
何度も何度も優しく頭を撫でてくれるから、それに酷く安心してロイの背中に手をまわす。
ふっと笑う声が耳元でしたけれど、聞こえないふりをした。
「可愛いなあ」
『…あのね、驚いてないからね、その、怪談とか幽霊とか…全然、』
「ふは、それ気にしてたって言ってるようなものだぞ……いたっ!」
泣くほど怖がってしまった事をどうにか隠そうと言い訳をしたけれど、ロイはそれをも見透かして笑って。
それが悔しくて、背中を叩いた。
『もう!もう!!…あ、』
痛がるロイを横目に、お構い無しで殴り続けていると電気が復旧した様で一気に周りが明るくなる。
それによって、今ロイと抱き合っているのがとてつもなく恥ずかしく感じてロイの胸を押した。
だけど、どんなに強く押してもロイが離れることは無くて。
『は、恥ずかしい!離して!』
「さっきは怖がって泣いてしがみついて来たのになあ」
『あれはアクシデント!だ、だれだって暗闇の中炎があったら驚く!』
「まあそれもそうだな」
『だから離して…!』
そう言って今一度力を入れるけど、やっぱり離れなくて。
何故か私の力じゃ少しも動かない悔しさでロイを睨むと、優しく笑っているロイに触れるだけのキスをされた。
「涙目で睨まれてもなあ」
『うー!!、わっ』
突如ふわりと体が浮いて、ロイの顔が目の前に来る。
背中と太ももを支えられていて、お姫様だっこをされているというのに気づくまで時間はかからなかった。
『や、な、なにして』
「ななしの事だ、恐らく腰が抜けて立てないだろう?押す力もそれほど無かったしな」
『なるほど、それで……じゃなくて!だったら担ぐのでもいいじゃん…!わざわざこんな、』
「女性を、ましてや可愛い恋人を担ぐなんて事するわけ無いだろ?」
そうだった、ロイはそういう性格だった。
どんなときでも女性扱いしてくれるのは凄く嬉しいけど、でもやっぱりお姫様だっこは何度されても慣れなくて。
でもまだ一人じゃ歩けそうにないし、選択肢はこれしか残ってない。
仕方なくロイの首に手をまわすとロイは満足そうに笑った。
「さ、寝室に行こうかお姫様?」
『寝室まで送り届ける王子様なんて聞いたこと無い!』
「そこは小さく頷く所だろ」
『そんなの分かんないし!』
「まあ、こういう所も可愛いんだけどな」
そういう事言うから、私はいつだってロイにドキドキしてしまうのだ。
「ふは、顔が真っ赤だ」
『う、うるさい!!』
「にゃにするんひゃ」
『あはは!』
楽しそうにからかってくるロイのほっぺを摘まんでびょいーんと引っ張る。
じと、と見てきたロイだけど全く言えていないその姿が可愛くて大笑いしてしまった。
そのあと小さな声で、寝室行ったら覚えてろ、と言ったような気がしたけど……私は聞こえないふりをして目を閉じた。
2019/08/13