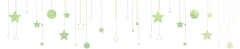何処か分からない、真っ暗な空間。
私の腕の中に居るななしは、いつものような笑顔は無く目を閉じていて。
その体には力が無く、彼女から滲み出ているのは赤い…
「……っ」
はっと目を覚まして飛び起きる。
ドクドクと動く心臓は、まるでそれが現実だと言うかの様に痛いほど音を立てていて。
布団に冷や汗か寝汗か分からないものが何度も落ちて染み込んでいく。
まさか…と恐る恐る隣を見てみると、目を閉じている彼女が規則正しく寝息を立てていて安堵のため息を吐いた。
だが一度うるさくなった心臓はなかなか静まることが無く。
落ち着く為にもと静かにベッドから出た私は、寝室を出てキッチンへと向かった。
「…はあ」
コップに入った水を見つめてもう一度ため息を漏らす。
ゆらゆらと揺れる水面を見つめれば、ぼんやりと情けない自分の顔が映って。
こんな夢は初めてだった。
私の夢に出てくる彼女はいつだって笑顔で私の手を取ってくれていたのに。
…夢だったのに、力無い彼女をこの腕に抱いた感覚がある気がして忘れられない。
カチカチと響く時計の音だけが響く、暗いキッチンに一人。
落ち着く為に自分から来たはずなのにななしが居ない事が酷く不安で、ぶるりと体を震わせた。
『…ロイ?』
彼女が恋しい。
そう思って戻ろうとコップの中の水を一気に飲み干すと、少しだけぼんやりとした声が聞こえて。
とろりとした表情の彼女は、寝ぼけ眼を擦りながらゆっくりと此方へ歩いてきた。
「すぐ戻るつもりだったんだ、すまない」
『それは別に……ロイ?』
「…ななし?」
『酷い汗だよ、表情も暗いし…何かあった?』
心配してくれている様子のななしは、私に駆け寄ってくると優しく頬に触れてくれて、その柔らかな手が余りにも暖かくて思わず手を重ねた。
「……嫌な、夢を見たんだ」
『うん』
「…ななしが、」
『うん』
「……、…」
『…ゆっくりでいいよ』
ふわりと微笑んでくれた彼女が、夢の中の彼女と余りにも違いすぎてホッとする。
そうだ、あれは夢なんだ。
「ななしが、私の腕の中で目を閉じていたんだ」
『うん』
「生死は分からなかった、ただ、血まみれで」
『うん』
「…情けないな、」
過去に何人も、何十人も何百人も命を奪ってきた人間がこんなにも滅入ってしまっているなんて。
『…ねえ、少し外行こっか!まだ夜中は肌寒いし、少しだけ着込んで!』
「ななし…」
『ね!ほら一緒に上着、取りに行こ!』
そう言って笑った彼女に手を優しく引かれて寝室まで上着を取りに行き、私たちは外へと歩き出した。
自宅から歩いてすぐ近くにある公共のベンチへ腰掛けて少し息を吸う。
冷たい空気が喉を通って、器官を通ってドロドロとした気持ちを消してくれている気がした。
『真っ暗だね!』
「まだ夜中だからな」
『でも見て、星がきらきらしてる!息も白い!』
空を見上げてはしゃぐ彼女を見ていると、夢の事など起こり得ないんだと思うことが出来て少しだけ気が楽になる。
だが、不安が完全に拭いきれたわけでは無いようで、私はそっとななしの手に触れた。
ななしはそれに気づくと指と指を絡めて、照れくさそうに笑って。
『情けなくなんて無いからね、誰だって不安になっちゃう様な夢を見ることはあるんだから』
「…そう、だな」
『うん!だから大丈夫!私はちゃんと隣にいるよ!ロイを残して居なくなったりなんて絶対しないから!』
寒さのせいか、鼻を赤くして笑うななしは少しだけ握っている手に力を込めた。
それに合わせてこちらも力を込めれば、彼女は嬉しそうに目を細める。
『ふふ、それに私が簡単に死んじゃうなんて有り得ないでしょ?』
「随分と強気だなあ」
『だって万が一私がピンチになったとしても、ロイが絶対助けてくれるでしょ?』
「勿論、命に代えても守るよ」
『あは、私だって!ロイがピンチの時は命に代えてでも守るよ!』
そうハッキリと言った彼女は力こぶを見せるようなポーズをとったのだが、力こぶなんて何処にも無くてくすりと笑ってしまった。
『あー!笑ったな!』
「相変わらず筋肉が無いなあ」
『人が気にしてることを!もう!明日からアームストロング少佐に鍛えてもらおうかな!』
「そ、それはちょっと」
『少佐みたいにムキムキになってやる!』
そう言ってアームストロング少佐の真似をしてポーズを取るななしが、余りにも真剣な表情をするので声を上げて笑うとななしもつられて笑って。
ひとしきり二人で笑った後に星空を見上げる。
『きっと私もロイも簡単に終わったりしないね!』
「そうだなあ」
『私はロイを残したりしないもの、勿論リザ達も!私の周りに居る私の大切な人達は絶対に一人にさせない、悲しませたりしない』
「ああ」
『絶対、この手を離さないから、ね!』
「…ああ」
それは確証の無い言葉。
だがその言葉が私をどれだけ救ってくれることか。
『ロイに悲しい顔なんて似合わないよ!女の人に良い顔してる方が似合う!』
「それは貶されてるのかな」
『一応褒めてる?』
「何で疑問系なんだ」
『あはは!』
楽しそうに笑う彼女を見ていると、こちらも自然と広角が上がるのを感じる。
私はこれまでこの子に一体どれだけ救われていたのだろう。
これから一体どれだけ救われるのだろう。
「…私はななしが居ないと駄目みたいだ」
不意に小さく出た本音はしっかりとななしの耳に届いていたようで、楽しそうに揺れていた体がピタリと止まり先程よりも急激に赤くなった頬を隠すように手で覆った。
その姿に小さく笑みが溢れて、その手を優しく退ければ困ったように眉を下げて赤くなる彼女と目があって。
小さく名前を呼ばれて、それに応えるようにそっとキスをした。
『…もう』
「ふは、真っ赤だな」
『変なこと言うから』
「本音がぽろっと」
『もう!もう!』
恥ずかしそうにポカポカと殴ってくる彼女がどうしようもなく愛しくて、手を掴んで引き寄せる。
腕の中にすっぽりと包まれたななしは、嫌がる素振りも恥ずかしがる素振りも無く背中に手を回した。
「恥ずかしがって暴れると思った」
『さ、寒いし、このままじゃ凍えちゃう、かも』
「それは困るな、どうしようか」
『…強く、』
抱きしめて、と呟いた彼女に応えるべく痛くない程度に強く抱きしめて首筋へと顔を埋める。
汗ばんでいるほどに熱いななしの首筋からかなり早い心臓の音が聞こえて、その素直で心優しい彼女の姿に小さく笑った。
「本当に、寒いな」
『…くっついて無いと凍えちゃうでしょ』
「そうだなあ」
彼女のお陰で、負の感情なんてものは消えていったようで。
恥ずかしいはずなのに、汗ばむほど暑いはずなのに私の為に抱きしめられている彼女が愛しくて堪らない。
「…ありがとう」
そう呟けば、私の背中へと回された手に力が入るのを感じた。
2019/04/11
私の腕の中に居るななしは、いつものような笑顔は無く目を閉じていて。
その体には力が無く、彼女から滲み出ているのは赤い…
「……っ」
はっと目を覚まして飛び起きる。
ドクドクと動く心臓は、まるでそれが現実だと言うかの様に痛いほど音を立てていて。
布団に冷や汗か寝汗か分からないものが何度も落ちて染み込んでいく。
まさか…と恐る恐る隣を見てみると、目を閉じている彼女が規則正しく寝息を立てていて安堵のため息を吐いた。
だが一度うるさくなった心臓はなかなか静まることが無く。
落ち着く為にもと静かにベッドから出た私は、寝室を出てキッチンへと向かった。
「…はあ」
コップに入った水を見つめてもう一度ため息を漏らす。
ゆらゆらと揺れる水面を見つめれば、ぼんやりと情けない自分の顔が映って。
こんな夢は初めてだった。
私の夢に出てくる彼女はいつだって笑顔で私の手を取ってくれていたのに。
…夢だったのに、力無い彼女をこの腕に抱いた感覚がある気がして忘れられない。
カチカチと響く時計の音だけが響く、暗いキッチンに一人。
落ち着く為に自分から来たはずなのにななしが居ない事が酷く不安で、ぶるりと体を震わせた。
『…ロイ?』
彼女が恋しい。
そう思って戻ろうとコップの中の水を一気に飲み干すと、少しだけぼんやりとした声が聞こえて。
とろりとした表情の彼女は、寝ぼけ眼を擦りながらゆっくりと此方へ歩いてきた。
「すぐ戻るつもりだったんだ、すまない」
『それは別に……ロイ?』
「…ななし?」
『酷い汗だよ、表情も暗いし…何かあった?』
心配してくれている様子のななしは、私に駆け寄ってくると優しく頬に触れてくれて、その柔らかな手が余りにも暖かくて思わず手を重ねた。
「……嫌な、夢を見たんだ」
『うん』
「…ななしが、」
『うん』
「……、…」
『…ゆっくりでいいよ』
ふわりと微笑んでくれた彼女が、夢の中の彼女と余りにも違いすぎてホッとする。
そうだ、あれは夢なんだ。
「ななしが、私の腕の中で目を閉じていたんだ」
『うん』
「生死は分からなかった、ただ、血まみれで」
『うん』
「…情けないな、」
過去に何人も、何十人も何百人も命を奪ってきた人間がこんなにも滅入ってしまっているなんて。
『…ねえ、少し外行こっか!まだ夜中は肌寒いし、少しだけ着込んで!』
「ななし…」
『ね!ほら一緒に上着、取りに行こ!』
そう言って笑った彼女に手を優しく引かれて寝室まで上着を取りに行き、私たちは外へと歩き出した。
自宅から歩いてすぐ近くにある公共のベンチへ腰掛けて少し息を吸う。
冷たい空気が喉を通って、器官を通ってドロドロとした気持ちを消してくれている気がした。
『真っ暗だね!』
「まだ夜中だからな」
『でも見て、星がきらきらしてる!息も白い!』
空を見上げてはしゃぐ彼女を見ていると、夢の事など起こり得ないんだと思うことが出来て少しだけ気が楽になる。
だが、不安が完全に拭いきれたわけでは無いようで、私はそっとななしの手に触れた。
ななしはそれに気づくと指と指を絡めて、照れくさそうに笑って。
『情けなくなんて無いからね、誰だって不安になっちゃう様な夢を見ることはあるんだから』
「…そう、だな」
『うん!だから大丈夫!私はちゃんと隣にいるよ!ロイを残して居なくなったりなんて絶対しないから!』
寒さのせいか、鼻を赤くして笑うななしは少しだけ握っている手に力を込めた。
それに合わせてこちらも力を込めれば、彼女は嬉しそうに目を細める。
『ふふ、それに私が簡単に死んじゃうなんて有り得ないでしょ?』
「随分と強気だなあ」
『だって万が一私がピンチになったとしても、ロイが絶対助けてくれるでしょ?』
「勿論、命に代えても守るよ」
『あは、私だって!ロイがピンチの時は命に代えてでも守るよ!』
そうハッキリと言った彼女は力こぶを見せるようなポーズをとったのだが、力こぶなんて何処にも無くてくすりと笑ってしまった。
『あー!笑ったな!』
「相変わらず筋肉が無いなあ」
『人が気にしてることを!もう!明日からアームストロング少佐に鍛えてもらおうかな!』
「そ、それはちょっと」
『少佐みたいにムキムキになってやる!』
そう言ってアームストロング少佐の真似をしてポーズを取るななしが、余りにも真剣な表情をするので声を上げて笑うとななしもつられて笑って。
ひとしきり二人で笑った後に星空を見上げる。
『きっと私もロイも簡単に終わったりしないね!』
「そうだなあ」
『私はロイを残したりしないもの、勿論リザ達も!私の周りに居る私の大切な人達は絶対に一人にさせない、悲しませたりしない』
「ああ」
『絶対、この手を離さないから、ね!』
「…ああ」
それは確証の無い言葉。
だがその言葉が私をどれだけ救ってくれることか。
『ロイに悲しい顔なんて似合わないよ!女の人に良い顔してる方が似合う!』
「それは貶されてるのかな」
『一応褒めてる?』
「何で疑問系なんだ」
『あはは!』
楽しそうに笑う彼女を見ていると、こちらも自然と広角が上がるのを感じる。
私はこれまでこの子に一体どれだけ救われていたのだろう。
これから一体どれだけ救われるのだろう。
「…私はななしが居ないと駄目みたいだ」
不意に小さく出た本音はしっかりとななしの耳に届いていたようで、楽しそうに揺れていた体がピタリと止まり先程よりも急激に赤くなった頬を隠すように手で覆った。
その姿に小さく笑みが溢れて、その手を優しく退ければ困ったように眉を下げて赤くなる彼女と目があって。
小さく名前を呼ばれて、それに応えるようにそっとキスをした。
『…もう』
「ふは、真っ赤だな」
『変なこと言うから』
「本音がぽろっと」
『もう!もう!』
恥ずかしそうにポカポカと殴ってくる彼女がどうしようもなく愛しくて、手を掴んで引き寄せる。
腕の中にすっぽりと包まれたななしは、嫌がる素振りも恥ずかしがる素振りも無く背中に手を回した。
「恥ずかしがって暴れると思った」
『さ、寒いし、このままじゃ凍えちゃう、かも』
「それは困るな、どうしようか」
『…強く、』
抱きしめて、と呟いた彼女に応えるべく痛くない程度に強く抱きしめて首筋へと顔を埋める。
汗ばんでいるほどに熱いななしの首筋からかなり早い心臓の音が聞こえて、その素直で心優しい彼女の姿に小さく笑った。
「本当に、寒いな」
『…くっついて無いと凍えちゃうでしょ』
「そうだなあ」
彼女のお陰で、負の感情なんてものは消えていったようで。
恥ずかしいはずなのに、汗ばむほど暑いはずなのに私の為に抱きしめられている彼女が愛しくて堪らない。
「…ありがとう」
そう呟けば、私の背中へと回された手に力が入るのを感じた。
2019/04/11