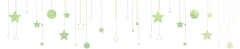"あの"バレンタインから数日が経った。
あの日以来、所謂マスタング組と呼ばれているオレ達は休憩になる度にある場所に集まっている。
ある場所とは、そう…大佐が専用で使っているあの部屋だ。
今日も今日とてその部屋に集まったオレ達は、大佐のデスクに山盛りに積まれているその甘い箱を漁っていた。
勿論、マスタング大佐も一緒に。
「あれから毎日食ってますけど、全然減る様子が無いっすね…」
「う、もう限界…気持ち悪い…」
「肌荒れが…」
「口の中甘すぎる……」
「手が止まっているぞ、動かせ」
げっそりとした様子のオレ達にそう言って箱から取った一粒を口に運ぶ大佐。
その動作すらも見ていて胃もたれがしそうで、思わず目を瞑る。
「動かせって簡単に言いますけどね、これ全部大佐宛のチョコレートっすからね?」
「食べきれないからって手伝ってるのに…」
そう、オレ達をここまで苦しめている箱の中身の正体は、チョコレートなのだ。
あの色々あったバレンタインの日に、"マスタング大佐へ"と各所から女性達が送ってきたもので。
あまりにも量が多すぎる為、一人では食べきれないと判断した大佐に頼まれて手伝っているのだが。
「それにしても、かなり甘いものが多いですね」
「今年は生クリームを使ったチョコが流行ってるんだとよ」
「だからこんなに胃もたれが……」
フュリーとブレダが青い顔をしてチョコレートを見つめる。
手作り系は殆ど食べきれているのだが、問題は市販品で。
「でも、生クリームを使ってるものって市販品でも消費期限が近いですからね、こんなにあると期限内に食べきれるかどうか……」
裏の消費期限を見つめてファルマンがそう言った途端に皆の空気が重くなったのを感じる。
オレも例外では無く、食べた分のチョコレートがずっしりと胃に響くのを感じた。
そんな中、大佐だけが涼しげな顔をしてチョコレートを口に運んでいて。
「かーっ、やっぱ毎年こんもりと貰う人はこの量じゃ胃もたれなんかしないっすよね」
そう皮肉めいた言葉をぶつけてみれば、大佐は顔色を変えずに一言。
「胃もたれする前に口に入れる。」
その発言の後も、休まずぱくぱくと口に入れる大佐へと視線が集まる。
「でも大佐、程々にしておかないと午後の仕事に響きますよ」
「……」
「ハボック少尉、恐らくその為に…」
「なるほど、胃もたれしてたら仕事なんて出来ないもんなあ…」
ブレダ達の視線に気づいて目を反らす大佐。
……チョコレートですら仕事放棄の為に使うか、と呆れを通り越して感心してしまう。
「…ていうか、何でこの場に中尉もななしも居ないんですか?」
「女性から貰った物を同じ女性や恋人に食べさせるわけにはいかないだろ」
「はー、なるほど……オレ達は男だから良いと」
「ま、そんな所だ」
今頃ななしと中尉は仲良く食堂で食事でもしているのだろう。
甘くない、塩気のある食事…
「オレもご飯食べたい…」
「こんなにチョコを食べたら胸焼け凄くて食べたくても食べられないだろうな」
「オレなんて最近チョコしか食ってない…」
「流石の大佐も、夕飯まで食う気力無いっすよね」
「毎日食べてる」
ポロリ、とフュリーの口からチョコレートが落ちた。
他の皆も度肝を抜かれたかのように目を丸くしていて。
「他の女性から貰ったものでお腹一杯ですなんて言うわけ無いだろ、ななしの作った食事なら意地でも食べるさ」
ならば何故未だそんなに口に運べるのか不思議でしょうが無い。
職場でも食べて自宅でも食べて、この人の胃袋はどうなっているのだろう。
まさか別腹なんていうものがこの人には本当に付いていたりするのだろうか。
「……大佐って本当にななしの事大好きっすよね」
「何だ急に」
「だって言ったそうじゃないっすか"チョコは貰ってない"って…本当はこんなに貰ってんのに」
「あの時は本当に一つも貰ってなかったからな」
「それでも、その後貰った事も言わずに隠してるじゃないすか」
「隠してはない、毎年の事だからななしも分かっているんだろう、聞いてすら来ない……聞いてくれて、その上嫉妬でもしてくれたら嬉しい事この上無いがな」
そう言ってため息を吐く大佐を見ていると何だか笑ってしまいそうになる。
直ぐに"減給だ!"と言われるから黙っておくけど。
「案外気付いて無いんじゃないすか?かなり天然だし、こういう事に疎そうだし」
「上司の恋人を馬鹿にしたか、今」
「や、別にそういうつもりじゃないっすけど」
やばい、口が滑った。
これはめんどくさい事になりそうだ……と、息を飲んだ時部屋の扉が小さくノックされた。
大佐の声を確認してから入ってきた人物は、今まさに話の中心に居る人物で。
『ども!』
「ななし、ご飯はキチンと食べてきたのかな」
『うん!もうそれはお腹いっぱいに……そうそう、それでね?皆にこれ淹れてきた!』
そう言って笑顔で運んできたのは、それぞれ専用のマグカップで。
一人一人の前に置かれたそれには温かい珈琲が淹れてあるようだ。
「ありがとうななし」
『いいえ!きっと口の中甘くてしょうがないんじゃないかなって!』
「助かるよ」
そう言って頭を撫でた大佐に向かって嬉しそうに笑うななし。
口の中が甘ければ、目の前も甘ったるい。
「大佐の言う通り、気付いてたんですね」
『え?何の事?』
フュリーの問い掛けに首をかしげたななしだが、先程の話題の件を伝えれば頬を膨らませてオレを睨んできた。
『そんなに鈍感じゃないし!ロイが人気なの知ってるし!』
「す、すんません…」
『もう、全く……それじゃあ私は一足先に執務室に行ってるから!』
「ん、私たちも時間になったら直ぐに戻るよ」
マグカップを乗せてきたトレイだけを胸に抱えて扉を開けるななしだが、何かを言い残したのか振り替えってにこりと笑った。
『皆に手伝って貰うのも良いけど、ちゃんと一箱一箱ロイが開けて最初に食べてね?』
「そうしてるよ」
『なら良かった!』
大佐の答えに満足したのか、飛びきりの笑顔を見せたななしはゆっくりと扉を閉めた。
とてとてと彼女らしい変わった足音が遠のいていく。
「……あの時みたいに嫉妬してくれてもいいのにな」
そう呟いた大佐はオレ達に見せないような何とも言い難い顔をしていて。
「ま、あの時はタイミングやら気持ちの整理やらがぐっちゃぐちゃでしたし」
一粒チョコレートを口に入れたオレは、それを溶かす様に珈琲を口に含んだ。
「あ、うま」
苦い珈琲と甘いチョコレートが混ざりあったこの味に、何て名前を付けようか。
未だ悩んでいるらしい大佐をチラリと一目して口の中のものを飲み込んだ。
これだからこの上司達は面白い。
2019/02/20
あの日以来、所謂マスタング組と呼ばれているオレ達は休憩になる度にある場所に集まっている。
ある場所とは、そう…大佐が専用で使っているあの部屋だ。
今日も今日とてその部屋に集まったオレ達は、大佐のデスクに山盛りに積まれているその甘い箱を漁っていた。
勿論、マスタング大佐も一緒に。
「あれから毎日食ってますけど、全然減る様子が無いっすね…」
「う、もう限界…気持ち悪い…」
「肌荒れが…」
「口の中甘すぎる……」
「手が止まっているぞ、動かせ」
げっそりとした様子のオレ達にそう言って箱から取った一粒を口に運ぶ大佐。
その動作すらも見ていて胃もたれがしそうで、思わず目を瞑る。
「動かせって簡単に言いますけどね、これ全部大佐宛のチョコレートっすからね?」
「食べきれないからって手伝ってるのに…」
そう、オレ達をここまで苦しめている箱の中身の正体は、チョコレートなのだ。
あの色々あったバレンタインの日に、"マスタング大佐へ"と各所から女性達が送ってきたもので。
あまりにも量が多すぎる為、一人では食べきれないと判断した大佐に頼まれて手伝っているのだが。
「それにしても、かなり甘いものが多いですね」
「今年は生クリームを使ったチョコが流行ってるんだとよ」
「だからこんなに胃もたれが……」
フュリーとブレダが青い顔をしてチョコレートを見つめる。
手作り系は殆ど食べきれているのだが、問題は市販品で。
「でも、生クリームを使ってるものって市販品でも消費期限が近いですからね、こんなにあると期限内に食べきれるかどうか……」
裏の消費期限を見つめてファルマンがそう言った途端に皆の空気が重くなったのを感じる。
オレも例外では無く、食べた分のチョコレートがずっしりと胃に響くのを感じた。
そんな中、大佐だけが涼しげな顔をしてチョコレートを口に運んでいて。
「かーっ、やっぱ毎年こんもりと貰う人はこの量じゃ胃もたれなんかしないっすよね」
そう皮肉めいた言葉をぶつけてみれば、大佐は顔色を変えずに一言。
「胃もたれする前に口に入れる。」
その発言の後も、休まずぱくぱくと口に入れる大佐へと視線が集まる。
「でも大佐、程々にしておかないと午後の仕事に響きますよ」
「……」
「ハボック少尉、恐らくその為に…」
「なるほど、胃もたれしてたら仕事なんて出来ないもんなあ…」
ブレダ達の視線に気づいて目を反らす大佐。
……チョコレートですら仕事放棄の為に使うか、と呆れを通り越して感心してしまう。
「…ていうか、何でこの場に中尉もななしも居ないんですか?」
「女性から貰った物を同じ女性や恋人に食べさせるわけにはいかないだろ」
「はー、なるほど……オレ達は男だから良いと」
「ま、そんな所だ」
今頃ななしと中尉は仲良く食堂で食事でもしているのだろう。
甘くない、塩気のある食事…
「オレもご飯食べたい…」
「こんなにチョコを食べたら胸焼け凄くて食べたくても食べられないだろうな」
「オレなんて最近チョコしか食ってない…」
「流石の大佐も、夕飯まで食う気力無いっすよね」
「毎日食べてる」
ポロリ、とフュリーの口からチョコレートが落ちた。
他の皆も度肝を抜かれたかのように目を丸くしていて。
「他の女性から貰ったものでお腹一杯ですなんて言うわけ無いだろ、ななしの作った食事なら意地でも食べるさ」
ならば何故未だそんなに口に運べるのか不思議でしょうが無い。
職場でも食べて自宅でも食べて、この人の胃袋はどうなっているのだろう。
まさか別腹なんていうものがこの人には本当に付いていたりするのだろうか。
「……大佐って本当にななしの事大好きっすよね」
「何だ急に」
「だって言ったそうじゃないっすか"チョコは貰ってない"って…本当はこんなに貰ってんのに」
「あの時は本当に一つも貰ってなかったからな」
「それでも、その後貰った事も言わずに隠してるじゃないすか」
「隠してはない、毎年の事だからななしも分かっているんだろう、聞いてすら来ない……聞いてくれて、その上嫉妬でもしてくれたら嬉しい事この上無いがな」
そう言ってため息を吐く大佐を見ていると何だか笑ってしまいそうになる。
直ぐに"減給だ!"と言われるから黙っておくけど。
「案外気付いて無いんじゃないすか?かなり天然だし、こういう事に疎そうだし」
「上司の恋人を馬鹿にしたか、今」
「や、別にそういうつもりじゃないっすけど」
やばい、口が滑った。
これはめんどくさい事になりそうだ……と、息を飲んだ時部屋の扉が小さくノックされた。
大佐の声を確認してから入ってきた人物は、今まさに話の中心に居る人物で。
『ども!』
「ななし、ご飯はキチンと食べてきたのかな」
『うん!もうそれはお腹いっぱいに……そうそう、それでね?皆にこれ淹れてきた!』
そう言って笑顔で運んできたのは、それぞれ専用のマグカップで。
一人一人の前に置かれたそれには温かい珈琲が淹れてあるようだ。
「ありがとうななし」
『いいえ!きっと口の中甘くてしょうがないんじゃないかなって!』
「助かるよ」
そう言って頭を撫でた大佐に向かって嬉しそうに笑うななし。
口の中が甘ければ、目の前も甘ったるい。
「大佐の言う通り、気付いてたんですね」
『え?何の事?』
フュリーの問い掛けに首をかしげたななしだが、先程の話題の件を伝えれば頬を膨らませてオレを睨んできた。
『そんなに鈍感じゃないし!ロイが人気なの知ってるし!』
「す、すんません…」
『もう、全く……それじゃあ私は一足先に執務室に行ってるから!』
「ん、私たちも時間になったら直ぐに戻るよ」
マグカップを乗せてきたトレイだけを胸に抱えて扉を開けるななしだが、何かを言い残したのか振り替えってにこりと笑った。
『皆に手伝って貰うのも良いけど、ちゃんと一箱一箱ロイが開けて最初に食べてね?』
「そうしてるよ」
『なら良かった!』
大佐の答えに満足したのか、飛びきりの笑顔を見せたななしはゆっくりと扉を閉めた。
とてとてと彼女らしい変わった足音が遠のいていく。
「……あの時みたいに嫉妬してくれてもいいのにな」
そう呟いた大佐はオレ達に見せないような何とも言い難い顔をしていて。
「ま、あの時はタイミングやら気持ちの整理やらがぐっちゃぐちゃでしたし」
一粒チョコレートを口に入れたオレは、それを溶かす様に珈琲を口に含んだ。
「あ、うま」
苦い珈琲と甘いチョコレートが混ざりあったこの味に、何て名前を付けようか。
未だ悩んでいるらしい大佐をチラリと一目して口の中のものを飲み込んだ。
これだからこの上司達は面白い。
2019/02/20