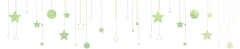最近ななしの機嫌が良い。
今もルンルンとした雰囲気を纏っている彼女だが、その理由は今の時期丸分かりな訳で。
『ロイ、これなんだけど…』
「ああ」
仕事モードの彼女が書類を持って此方へ歩み寄ってくる。
執務室に用意されている私のデスクと言うものはかなり大きくて、体の小さいななしは書類を見せるのにも身を乗り出さないといけない。
その為か、彼女が何かを聞きに来るときは大体私の横まで来るのだが、今回も例外無く横まで書類を持って来た。
『この事件の処理は…』
そう言って覗き込んでくる彼女からふわりと甘い香りが漂ってくる。
衣服の匂いでもななし自身の匂いでも無いそれの匂いが何なのかと言えば、答えは一つなのだ。
チョコレート。
そう、この鼻を擽るような甘い香りはななしの大好きなチョコレートの香り。
何故こんなにも彼女からチョコレートの香りがしているのか普段の私なら不思議でしょうがないが、今なら分かる。
そう、バレンタインだ。
「ここを記入して提出だよ」
『あー!なるほど!ありがとう!助かりました!』
笑顔を見せたななしは意気揚々と自分のデスクへと戻っていく。
そのデスクをまじまじと見つめてみれば、彼女に割り振られていた書類はもう微々たるものになっていた。
「今日も早めに帰るのかな」
『うん!ちょっと先に帰ってやることがあるから……仕事はちゃんと片付けていくからね!』
笑ってそう言ったななしは素早い手つきで書類を捌いていき、あっという間に自分の分が終わったようで他の連中の書類も手伝える範囲で手伝っていく。
『じゃあ、お先に帰ってるね!』
「ああ、お疲れ様」
他の連中の手伝える分の書類も終わり、定時も過ぎた頃にそう言ってななしは足早に執務室を出ていった。
「ななしさん最近早めに帰りますよね」
「あれだよ、バレンタイン」
「あー……なるほど」
部下のそんな会話を耳に入れつつ自分も仕事を進める。
とは言ってもそんなに早く仕事を終わらせてしまうとななし的にも困ると思うので、ゆっくりとペンを滑らせていく。
「あ、大佐随分とゆっくりっすね」
「急いで帰ってしまったらななしが驚くだろう」
「いつもなら中尉に怒られるところっすけど」
ちらりと中尉を見ると、書類を見つめながらも一言。
「たまには少しくらい遅くても大丈夫ですよ」
無表情で放たれたその言葉は、普段を考えれば随分と甘いもので。
「…中尉って案外ななしに甘いっすよね」
本当に全くもってその通りだ。
「ただいま、ななし」
ガチャリと扉を開けて声を掛ける。
いつもならパタパタと騒がしく出迎えに来てくれる筈のななしが来ない。
不思議に思ってリビングの方へと足を向ければ、何やら独り言のような話し声が。
『練習に夢中になりすぎて時間忘れてた……!』
ガチャガチャと音を立てて慌ただしく片付けをしている様子のななし。
何だかその生活音すらも愛しくて、気付かれないように足音を立てずに玄関まで戻る。
暫くしてガチャリとリビングのドアが開き、顔を覗かせた彼女は私が玄関に立っているのを見てたちまち笑顔になった。
きっと、気付かれずに済んだと喜んでいるのだろう。
『ずっとそこで待ってたの?』
「ああ、ななしからのお出迎えが欲しくて」
『何それ!』
クスクスと笑う彼女は、仕事の時よりも甘い香りを漂わせていて。
ふと彼女の口元に視線を送れば、そこにはチョコレートが。
味見で食べているときに付いたんだろうな、とその姿が容易に想像できて広角が上がる。
私は、ななしがそのチョコレートに気づかないうちにと自身の唇を寄せた。
『ん、……ロイ?』
「…キスしたかったんだが…駄目だったかな」
『そ、そんなことない!ちょっとびっくりしちゃっただけ!』
にこりと笑った彼女の顔が段々と赤くなっていく。
相変わらずこういった行為に慣れる気配もないななしは、恥ずかしそうに私の手を握る。
『お夕飯作ってあるから、食べよ!』
「ありがとう、楽しみだよ」
そう言ってまた一つキスを落とす。
彼女とのキスは、普段とは比べ物にならないくらい甘くて。
その甘さをもっと楽しみたくて、私はその行為を深めた。
『ロイが休憩中に外に出るなんて珍しいね』
「最近一緒に帰れないから寂しくて」
『ば、ばか!』
「何で今罵倒されたんだ」
賑わいを見せるセントラルシティの大通り。
時刻はまだまだ昼で、本来ならば司令部の食堂で食事でもしている頃だ。
ななしはと言うと、いつも昼休憩になると大通りまで出て買い物や食事を楽しんでいて、今回は私も付いてきたと言う訳で。
「それにしてもどこもかしこも甘い匂いだな」
『そりゃー明日は遂に!…あ、何でもない!』
「ななし?」
『な、何でも?』
焦ったように顔を反らせたななし。
きっと私がバレンタインと言う事に気づかないようにと気を利かせたのだろうけれど、流石にここまで来てそれに気づかないほど鈍い男じゃない。
だが、ななしが隠したがっている以上分かっているような態度を取るのは野暮と言うものなので黙っておくことにしよう。
『あ!見てロイ、あそこ!』
「ん?…いつもの店か?」
ななしが見ている方を見れば、そこにはいつの間にやらお得意様となった焼き菓子店の女性が外に箱を積んで立っていた。
ななしが手を振って走っていく。
女性もそれに気がついたようで手を振り返した。
「こんにちは!大佐さんとななしちゃん」
『こんにちは!寒いのに外に出て何を売り出してるの?』
「ほら、もうすぐイベントでしょ?それに合わせてチョコレートを使ったお菓子を売り出してるの!」
そう言って女性が見せてくれたのは、見本と書かれた小さい箱でその中にはチョコレートの焼き菓子が沢山と入っていた。
『わー!凄い!』
「イベントものには乗らなくちゃ損だもの!張り切って沢山作っちゃった!」
『全部美味しそう…』
「ななしちゃんチョコ好きだものね」
『うん、好き!』
そんな話をしていたななし達だが、ふと目の端に映る不審な人影に勢い良く顔を向ける。
そこには、焼き菓子店の売り出しされているお菓子の箱を持った男がそろりそろりと逃げようとしている所で。
『あの、それお会計しました?』
「!!」
咄嗟にななしが声を掛けたのだが、それに驚いた男は走って逃げていく。
思わず追いかけようと足を動かすと私よりも先にななしが走り出す。
「ななし、」
『泥棒くらい一人で大丈夫!二次被害が無いようにロイはそこに居て!』
そう言った彼女はあっという間に走り去って行き、ぽつんと私と女性だけが残った。
「…行っちゃいましたね」
「すぐに戻ってくるよ」
「頼もしい彼女さんだなあ」
「突っ走ることが多くて目が離せないかな」
「ふふ、確かに!」
しん、と静まり返り話題を探そうとした瞬間、遠くの方で声を掛けられた気がして振り向く。
ななしかと思ったが、声が違う事に気づいて声の主を探せば此方に駆け寄ってくる女性が一人。
「マスタング大佐!お久しぶり、覚えてるかしら!」
「君は…勿論覚えているよ」
昔、情報収集として一度食事をした女性だ。
私の事をかなり気に入ったようで帰り際に口説かれたのを良く覚えている。
暫くその女性と話をしていれば、今度は後ろから方を叩かれる。
「マスタングさん、こんにちは」
「おや、こんにちは。お昼からアルコールかい?」
「ふふ、まあそんなところ」
この女性はこの前帰宅途中に酔って絡んできた女性。
見過ごすわけにもいかないので、少しの間介抱した人だ。
そして、この女性達を筆頭に次から次へと女性が話しかけてくる。
好意を寄せていてくれた女性は勿論、ただの話仲間のような女性。
人間と言うものは不思議なもので、少しでも人だかりが出来るとそこからどんどんと囲まれるように知り合いが増えていく。
そしていつの間にか私の周りには知り合いの女性が大勢集まってきていて、先程まで話していた焼き菓子店の女性も心なしか顔がひきつっている。
「すまない、今日はちょっと話す余裕が無いんだ」
『ロイ!』
どき、と胸が鳴った。
いつから居たのだろうか、とか勘違いしていないだろうか、とか。
一瞬のうちにグルグルと頭を回転させたけれど答えなんて出ることはなく。
声のした方に振り向けば、ななしは笑顔でピースをしていて何だかその姿にホッとする。
犯人が居ない事を見るに、恐らく応援を呼んで連行させたのだろう。
私は、女性の波を抜けてななしの手を取った。
「これからまた仕事なんだ、それじゃあ」
そう言って笑いかけて歩き出す。
手は繋いだまま、ゆっくりと歩いているが会話が無い。
そりゃあそうだろう。
恋人としてはああいったシーンというのはあまり好まないものだ。
流石のななしも嫌な思いをしたのだろう。
「…気にしてる?」
『…っえ?何が?』
恐る恐る声を掛ければ、きょとんとしたななしと目が合って。
その瞳は、曇りなんて一つもなくて先程の事など一切気にしていない様子だった。
「いや、いいんだ」
『…?変なの』
不思議な様子で首をかしげるななしを横目に、少しだけ落ちた気分を隠して歩く。
…もう少し嫉妬とかしてくれても良いんだが。
ななしは変なところで嫉妬するのに、一般的に嫉妬するような所では殆どしない。
それが良いところでもあるのだが、私が彼女にベタ惚れな以上束縛されたいなんて気持ちもあって。
はあ、とため息を落とす。
ななしは、それにも気にする様子もなく鼻唄を歌いながら歩いていて。
そんな彼女を見て、まあいいか。なんて。
『……頑張らなくちゃね』
彼女のその言葉は、私に届くこと無く空へと溶けていった。
2019/02/13
今もルンルンとした雰囲気を纏っている彼女だが、その理由は今の時期丸分かりな訳で。
『ロイ、これなんだけど…』
「ああ」
仕事モードの彼女が書類を持って此方へ歩み寄ってくる。
執務室に用意されている私のデスクと言うものはかなり大きくて、体の小さいななしは書類を見せるのにも身を乗り出さないといけない。
その為か、彼女が何かを聞きに来るときは大体私の横まで来るのだが、今回も例外無く横まで書類を持って来た。
『この事件の処理は…』
そう言って覗き込んでくる彼女からふわりと甘い香りが漂ってくる。
衣服の匂いでもななし自身の匂いでも無いそれの匂いが何なのかと言えば、答えは一つなのだ。
チョコレート。
そう、この鼻を擽るような甘い香りはななしの大好きなチョコレートの香り。
何故こんなにも彼女からチョコレートの香りがしているのか普段の私なら不思議でしょうがないが、今なら分かる。
そう、バレンタインだ。
「ここを記入して提出だよ」
『あー!なるほど!ありがとう!助かりました!』
笑顔を見せたななしは意気揚々と自分のデスクへと戻っていく。
そのデスクをまじまじと見つめてみれば、彼女に割り振られていた書類はもう微々たるものになっていた。
「今日も早めに帰るのかな」
『うん!ちょっと先に帰ってやることがあるから……仕事はちゃんと片付けていくからね!』
笑ってそう言ったななしは素早い手つきで書類を捌いていき、あっという間に自分の分が終わったようで他の連中の書類も手伝える範囲で手伝っていく。
『じゃあ、お先に帰ってるね!』
「ああ、お疲れ様」
他の連中の手伝える分の書類も終わり、定時も過ぎた頃にそう言ってななしは足早に執務室を出ていった。
「ななしさん最近早めに帰りますよね」
「あれだよ、バレンタイン」
「あー……なるほど」
部下のそんな会話を耳に入れつつ自分も仕事を進める。
とは言ってもそんなに早く仕事を終わらせてしまうとななし的にも困ると思うので、ゆっくりとペンを滑らせていく。
「あ、大佐随分とゆっくりっすね」
「急いで帰ってしまったらななしが驚くだろう」
「いつもなら中尉に怒られるところっすけど」
ちらりと中尉を見ると、書類を見つめながらも一言。
「たまには少しくらい遅くても大丈夫ですよ」
無表情で放たれたその言葉は、普段を考えれば随分と甘いもので。
「…中尉って案外ななしに甘いっすよね」
本当に全くもってその通りだ。
「ただいま、ななし」
ガチャリと扉を開けて声を掛ける。
いつもならパタパタと騒がしく出迎えに来てくれる筈のななしが来ない。
不思議に思ってリビングの方へと足を向ければ、何やら独り言のような話し声が。
『練習に夢中になりすぎて時間忘れてた……!』
ガチャガチャと音を立てて慌ただしく片付けをしている様子のななし。
何だかその生活音すらも愛しくて、気付かれないように足音を立てずに玄関まで戻る。
暫くしてガチャリとリビングのドアが開き、顔を覗かせた彼女は私が玄関に立っているのを見てたちまち笑顔になった。
きっと、気付かれずに済んだと喜んでいるのだろう。
『ずっとそこで待ってたの?』
「ああ、ななしからのお出迎えが欲しくて」
『何それ!』
クスクスと笑う彼女は、仕事の時よりも甘い香りを漂わせていて。
ふと彼女の口元に視線を送れば、そこにはチョコレートが。
味見で食べているときに付いたんだろうな、とその姿が容易に想像できて広角が上がる。
私は、ななしがそのチョコレートに気づかないうちにと自身の唇を寄せた。
『ん、……ロイ?』
「…キスしたかったんだが…駄目だったかな」
『そ、そんなことない!ちょっとびっくりしちゃっただけ!』
にこりと笑った彼女の顔が段々と赤くなっていく。
相変わらずこういった行為に慣れる気配もないななしは、恥ずかしそうに私の手を握る。
『お夕飯作ってあるから、食べよ!』
「ありがとう、楽しみだよ」
そう言ってまた一つキスを落とす。
彼女とのキスは、普段とは比べ物にならないくらい甘くて。
その甘さをもっと楽しみたくて、私はその行為を深めた。
『ロイが休憩中に外に出るなんて珍しいね』
「最近一緒に帰れないから寂しくて」
『ば、ばか!』
「何で今罵倒されたんだ」
賑わいを見せるセントラルシティの大通り。
時刻はまだまだ昼で、本来ならば司令部の食堂で食事でもしている頃だ。
ななしはと言うと、いつも昼休憩になると大通りまで出て買い物や食事を楽しんでいて、今回は私も付いてきたと言う訳で。
「それにしてもどこもかしこも甘い匂いだな」
『そりゃー明日は遂に!…あ、何でもない!』
「ななし?」
『な、何でも?』
焦ったように顔を反らせたななし。
きっと私がバレンタインと言う事に気づかないようにと気を利かせたのだろうけれど、流石にここまで来てそれに気づかないほど鈍い男じゃない。
だが、ななしが隠したがっている以上分かっているような態度を取るのは野暮と言うものなので黙っておくことにしよう。
『あ!見てロイ、あそこ!』
「ん?…いつもの店か?」
ななしが見ている方を見れば、そこにはいつの間にやらお得意様となった焼き菓子店の女性が外に箱を積んで立っていた。
ななしが手を振って走っていく。
女性もそれに気がついたようで手を振り返した。
「こんにちは!大佐さんとななしちゃん」
『こんにちは!寒いのに外に出て何を売り出してるの?』
「ほら、もうすぐイベントでしょ?それに合わせてチョコレートを使ったお菓子を売り出してるの!」
そう言って女性が見せてくれたのは、見本と書かれた小さい箱でその中にはチョコレートの焼き菓子が沢山と入っていた。
『わー!凄い!』
「イベントものには乗らなくちゃ損だもの!張り切って沢山作っちゃった!」
『全部美味しそう…』
「ななしちゃんチョコ好きだものね」
『うん、好き!』
そんな話をしていたななし達だが、ふと目の端に映る不審な人影に勢い良く顔を向ける。
そこには、焼き菓子店の売り出しされているお菓子の箱を持った男がそろりそろりと逃げようとしている所で。
『あの、それお会計しました?』
「!!」
咄嗟にななしが声を掛けたのだが、それに驚いた男は走って逃げていく。
思わず追いかけようと足を動かすと私よりも先にななしが走り出す。
「ななし、」
『泥棒くらい一人で大丈夫!二次被害が無いようにロイはそこに居て!』
そう言った彼女はあっという間に走り去って行き、ぽつんと私と女性だけが残った。
「…行っちゃいましたね」
「すぐに戻ってくるよ」
「頼もしい彼女さんだなあ」
「突っ走ることが多くて目が離せないかな」
「ふふ、確かに!」
しん、と静まり返り話題を探そうとした瞬間、遠くの方で声を掛けられた気がして振り向く。
ななしかと思ったが、声が違う事に気づいて声の主を探せば此方に駆け寄ってくる女性が一人。
「マスタング大佐!お久しぶり、覚えてるかしら!」
「君は…勿論覚えているよ」
昔、情報収集として一度食事をした女性だ。
私の事をかなり気に入ったようで帰り際に口説かれたのを良く覚えている。
暫くその女性と話をしていれば、今度は後ろから方を叩かれる。
「マスタングさん、こんにちは」
「おや、こんにちは。お昼からアルコールかい?」
「ふふ、まあそんなところ」
この女性はこの前帰宅途中に酔って絡んできた女性。
見過ごすわけにもいかないので、少しの間介抱した人だ。
そして、この女性達を筆頭に次から次へと女性が話しかけてくる。
好意を寄せていてくれた女性は勿論、ただの話仲間のような女性。
人間と言うものは不思議なもので、少しでも人だかりが出来るとそこからどんどんと囲まれるように知り合いが増えていく。
そしていつの間にか私の周りには知り合いの女性が大勢集まってきていて、先程まで話していた焼き菓子店の女性も心なしか顔がひきつっている。
「すまない、今日はちょっと話す余裕が無いんだ」
『ロイ!』
どき、と胸が鳴った。
いつから居たのだろうか、とか勘違いしていないだろうか、とか。
一瞬のうちにグルグルと頭を回転させたけれど答えなんて出ることはなく。
声のした方に振り向けば、ななしは笑顔でピースをしていて何だかその姿にホッとする。
犯人が居ない事を見るに、恐らく応援を呼んで連行させたのだろう。
私は、女性の波を抜けてななしの手を取った。
「これからまた仕事なんだ、それじゃあ」
そう言って笑いかけて歩き出す。
手は繋いだまま、ゆっくりと歩いているが会話が無い。
そりゃあそうだろう。
恋人としてはああいったシーンというのはあまり好まないものだ。
流石のななしも嫌な思いをしたのだろう。
「…気にしてる?」
『…っえ?何が?』
恐る恐る声を掛ければ、きょとんとしたななしと目が合って。
その瞳は、曇りなんて一つもなくて先程の事など一切気にしていない様子だった。
「いや、いいんだ」
『…?変なの』
不思議な様子で首をかしげるななしを横目に、少しだけ落ちた気分を隠して歩く。
…もう少し嫉妬とかしてくれても良いんだが。
ななしは変なところで嫉妬するのに、一般的に嫉妬するような所では殆どしない。
それが良いところでもあるのだが、私が彼女にベタ惚れな以上束縛されたいなんて気持ちもあって。
はあ、とため息を落とす。
ななしは、それにも気にする様子もなく鼻唄を歌いながら歩いていて。
そんな彼女を見て、まあいいか。なんて。
『……頑張らなくちゃね』
彼女のその言葉は、私に届くこと無く空へと溶けていった。
2019/02/13