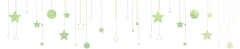「やっぱり恋人と手を繋ぐのって幸せな気分になるよね〜!」
お昼休憩中に買い物をしにセントラルの大通りへ出たのだが、二人組の女性とのすれ違い様に聞いたその言葉が何となく頭から離れず。
周りのカップルを見れば手を繋いでる人達が殆どで、繋いでいる人達は例外無く幸せそうに微笑んでて。
『…私もあんな顔するのかな』
頬を染めて恥ずかしそうに微笑む女性を見て、そこに私を重ねてみる。
果たして私はあんな風に可愛らしく笑うのだろうか。
『考えたこともなかったなあ…』
恋人であるロイと手を繋ぐという事は頻繁にあって、頻繁にあるからこそあまり考えた事も無くて。
ロイの手に自分の手を重ねる想像をして、何だか無性に恥ずかしくなった私は頭を大きく左右に振った。
『買い物買い物…』
先程の想像を忘れるようにと何度も目的を呟く。
すれ違う人が必ず振り返っている気がするけれどそれを気にする余裕もなく私は目的のお店へと足を進めた。
『も、戻りました…』
執務室に戻った頃には、お昼休憩も終わりに近くて。
げっそりとした様子でデスクに戻る私を見たブレダが不思議そうに此方を見る。
「何かやつれてないか?」
『そ、そう?』
「カップルの熱にでもやられたか!」
わははと笑うブレダのその発言にびくりと体を震わせた。
そうなのだ。
目的のお店へと行ったのは良いものの、何処もかしこもカップルだらけで。
普段ならそんなの全く気にしないのに今日は妙に気になってしまって、繋がれた手やら赤く染まった顔などを見てしまい。
ブレダの言う通り熱にやられた私はふらふらと帰ってきたのだ。
「お、正解っぽい?」
『ひ…人混みで酔っただけだよ!』
思わずつく嘘。
だって本当の事を言っても絶対に笑われる。
椅子に体を預けて此方を見ているロイだって、何を今さらそんな事でって笑うに決まってて。
いや、私だって今更?とか朝まで気にしてなかったのに?とか思うよ!
思うけれど、意識してしまったら最後。
だって良く考えてみたら、手を繋ぐって事は私の手をロイの手が包むわけで。
あの優しくて暖かくて大きい手が私の手を、と考えるだけで顔が熱くなってしまう。
「大丈夫か?」
『ん、え!?ろ、ロイ…!大丈夫…!』
「顔赤いぞ」
『こっこれは…!その、人混みの中居たから暑くて!』
いつの間にか側に来ていたロイに顔を覗かれてちょっとだけ舌を噛んだ。
顔が赤いのはどう考えても先程の事のせいなんだけど、それを隠したい私は嘘をまたついて。
怪訝な顔をしたロイと目が合ったけど、すいっと逸らす。
すると突然ロイが不気味に笑い始めて、思わず視線を向ける。
「そうか、そうか」
『え?な、なに怖い…』
「暑いなら少し外に出て冷まそうじゃないか」
『えっ』
「ななし一人だと心配だからな、私も着いていこう」
『えっえ!?』
何が何だか分からないまま、執務室の外へと連れ出される。
扉が閉まる直前に見えたのは、私達を気にすること無く仕事を始める部下達だった。
「で、何があったんだ」
『えっ、と……外じゃなかったの…』
「寒いから却下」
『……自分で言ったのに』
近くの使われていない会議室に入った私達は、向かい合うように椅子を並べて座る。
膝がぶつかってしまうくらい近い距離で顔がまた熱くなってしまう。
「人混みに酔ったとか暑いとか嘘だろ?」
『そ、そんな事分かるの』
「ななしは分かりやすいからな」
『分かりやすくない!』
「それはどうかな」
くすりと笑ったロイをじとりと見つめれば、可笑しそうに笑って私の頭を撫でた。
その撫でられる行為が気持ち良くて目を細めてしまうけど、先程までの事を思い出した途端にロイの手に意識が集中してしまう。
「…私が何かしたのか」
『えっ?』
「何かする度にななしが反応するから」
『あ、えっと……』
「顔真っ赤」
『うっ……』
鼻先にちょん、とロイの指が触れる。
自分の顔が真っ赤なんて分かりきってる事で、でもそれを人に指摘されるというのは分かっていても中々恥ずかしいもので。
「外で何かあったんだろ?」
『……』
「…」
『……』
「…言わないとここで襲うぞ」
『すっすれ違った女の子達が!』
爆弾発言と共に私の太ももをするりと撫でる手に思わず口から真実が漏れる。
言わなければ絶対に襲われてしまう。
そう確信した私は、一度大きく息を吐いてから下を向いた。
『…す、すれ違った女の子達が話してたの』
「何を」
『好きな人と手を繋ぐと幸せな気分になるって…私、そんな事考えた事も無かったから』
「…なるほど」
『考え出したら止まらないし、ロイの手を思い出して…わ、私の手をロイの手が…』
「……」
『…?ロイ………な、なに笑ってるの』
返事や相槌が無くて顔を上げれば、笑いを堪えた様子のロイと目があって。
ぷくりと頬を膨らませれば、ロイの手が頬に触れてびくりと体が揺れる。
「それでカップルにしか目が行かず熱にあてられたってわけか」
『う…はい…』
「ったく…今までそんなの気にせず自分から手を繋ぎに来てたのにな」
『だ、だから…それは何も考えずに…』
「じゃあ、今繋いでみるか?」
その言葉に目が丸くなる。
ん、と差し出されたロイの手はやっぱり大きくてゴツゴツしてて、私の手とは大違いで。
『ど、どうしてそうなるの』
「今まで何も考えずに繋いできたんだろ?」
『…うん…』
「考えられる状態で繋いだら、その女の子達の気持ちも分かったりしてな」
確かに分かるかもしれない。
でも意識したらドキドキは止まらないわけで、中々ロイの手に触れられず見つめるばかり。
じっと見つめる私をロイは面白そうに見ていて何だか不思議な光景だ。
「ほら」
『う…じゃ、じゃあ…繋いでも、いい、ですか…』
「何だそれ、いつもみたいに何も言わず繋いでいいよ」
『そうは言っても!…うう』
恐る恐るロイの手に自分の手を重ねる。
暖かいロイの手はやっぱり私の手よりも大きくて、まるで自分が子供になったような気分だ。
ドキドキする胸を押さえつつ、角度をつけてロイの手を握る。
するとロイも握り返してくれて、じんわりと暖かさが手に広がった。
「感想は?」
『…ロイの手おっきい』
「男だからな」
『改めて触ってみると硬い…』
「ななしはぷにぷにだ」
『ぷにぷにじゃない!』
「じゃあふにふに?」
からかうように笑ったロイに映る私は、きっと凄く真っ赤なんだろう。
この胸は未だドキドキと脈打っていてうるさい。
けれど、それは決して不快なものじゃなくて…
『…分かったかも』
「ん?」
『女の子達が幸せって思う気持ち…好きな人と手を繋げるのって凄いことだね』
「…そうだな」
『凄くドキドキするけど…ロイと手を繋げて幸せ』
「…」
『こんな気持ちになるんだったら、もっと前から意識してればよかったかも』
「……」
『…ロイ?』
またもや無言のロイに視線を向ければ空いている方の手で顔を覆っていて、手の隙間から見える頬はほんのりと赤く染まっている。
『え?え?な、なんでロイまで照れてるの?』
「ななしが変なこと言うから…」
『だって事実だし…』
「いつもは幸せとか滅多に言わないくせに」
『そうだっけ…?』
「さっきまで真っ赤な顔で照れてたのに今はもう平気そうだな」
『ロイが照れてるから?』
「何だそれ…」
小さく息を吐いたロイの頬はまだ染まったままで、見ていて少し面白い。
手を繋ぐ前は意識しすぎて痛いくらいドキドキしていたけれど、繋いでみたら幸せな気持ちの方が勝ってドキドキも心地がいい。
落ち着いてきた私は、からかうようにロイの頬を優しくつついた。
「…何だよ」
『ほっぺ、赤いなーって』
「ななしだって赤いだろ」
『ロイほどじゃないよ、わっ』
へらっと笑ってまたつつく。
それが気にくわなかったのか、ロイは私の手を掴んで自分の方へと強く引き寄せた。
自分が座っていたはずの椅子が視界の端に映る。
目の前にはロイが居て、手は繋がれたまま。
『あ、えっと…?こ、この体勢は一体…』
「私の膝の上にななしが乗ってる」
『そうじゃなくて!なんでこんな体勢に…!』
「随分と余裕そうだったもんで」
『えっ』
「その余裕無くしてしまおうか、なんてな」
ギラリとした目で見つめられて体が小さく震える。
離れようと繋がれた手に力を込めたけれど、びくともしなくて。
焦っているうちにどんどんロイの顔が近くなってきて、ドキドキが加速する。
その先の事を想像して無意識にギュッと目を閉じた瞬間、鼻先にちゅっと何かが触れた。
『…』
「何だよ、その間抜けな顔は」
『い、いや…てっきり』
「ここにされるかと思った?」
ロイの指が私の唇に触れる。
かあ、と赤くなったその顔を隠すためにロイの肩に顔を埋めれば、くすくすと笑う声が少し上から聞こえて。
「やっぱり私よりななしが照れている方がしっくり来る」
『…意味わかんない』
「ななしは可愛いなって事だよ」
ますます意味がわからない!とロイの胸を小さく叩けば、またくすくすと笑う声が聞こえた。
「…で、先程まで手を繋ぐことに大変照れていたななしさん」
『な、なに』
「これからはどうするのかな」
『どうするって』
「繋ぐ度に照れるのか、はたまた自分からは繋げないのか」
『つ、繋ぐよ!』
勢い良く顔をあげてロイの方へ向けば、優しい顔して微笑んでて。
てっきりからかうように笑ってると思ったのに、そんな顔されたら心臓に悪い。
『…照れるときもあると思うけど、それよりも幸せな気持ちが勝つから繋ぐ…』
「いつも通り、自分から?」
『う、うん…』
「ん、なら良かった。もう繋がないなんて言われたら悲しいからな」
ロイの唇が私の唇に重なる。
触れるだけの優しいそれはロイによって何度も何度も繰り返されて、蕩けてしまいそう。
ふわふわした気持ちの中、繋がれたロイの手を繋ぎ直して指を絡ませる。
ぎゅっと握れば、ぎゅっと握り返してくれて嬉しくなって。
唇が離れた時に小さく好きだよ、と呟けば私もだよ、と声が帰ってきて胸がきゅんと疼く。
その後も私達は何度も何度も重ねるだけのキスを繰り返した。
『結構時間経っちゃったね』
「ななしがキスに夢中だったからな」
『むっ…!』
会議室を出て執務室へ向かう途中、そんな事を言われてまた顔が熱くなる。
それをみたロイは面白そうに笑っていて、むっとした私は繋がれた手に全力で力を込めた。
「全く痛くない」
『うう…私がもっとゴリゴリマッチョだったら…』
「それは勘弁してくれ…」
『手だけでも鍛えようかな』
「今のままが良いんだが…」
ふにふにと何かを確かめるように触るロイを横目に、鍛えることを考えつつ歩く。
リザに聞いてみようかな、アームストロング少佐にも聞いてみよう。
「…頼むから中尉やアームストロング少佐に鍛えてもらわないように」
『なっ何で分かったの!?』
「はあ…ななしは分かりやすいって言ったろ?考えていることなんてお見通しだよ」
『ぐっ……』
「このままの手が好きだから、このままでいてほしいな」
ロイが微笑んでそう言うから、やっぱりこのままでいいか、なんて思ってしまう。
なんて分かりやすいんだろう、私は。
そんな自分に恥ずかしさを感じて手に力を込めれば、ロイも優しく力を込めてくれて。
『…手を繋ぐの好きだな』
「それは良かった」
繋いだ手から溢れる幸せに心がいっぱいになるのを感じて顔が緩む。
今の私は、きっとあの時見た女の子みたいに幸せそうに微笑んでいるんだろうな。
なんて、そんな事を思いながら執務室の扉を叩いた。
2019/01/28
お昼休憩中に買い物をしにセントラルの大通りへ出たのだが、二人組の女性とのすれ違い様に聞いたその言葉が何となく頭から離れず。
周りのカップルを見れば手を繋いでる人達が殆どで、繋いでいる人達は例外無く幸せそうに微笑んでて。
『…私もあんな顔するのかな』
頬を染めて恥ずかしそうに微笑む女性を見て、そこに私を重ねてみる。
果たして私はあんな風に可愛らしく笑うのだろうか。
『考えたこともなかったなあ…』
恋人であるロイと手を繋ぐという事は頻繁にあって、頻繁にあるからこそあまり考えた事も無くて。
ロイの手に自分の手を重ねる想像をして、何だか無性に恥ずかしくなった私は頭を大きく左右に振った。
『買い物買い物…』
先程の想像を忘れるようにと何度も目的を呟く。
すれ違う人が必ず振り返っている気がするけれどそれを気にする余裕もなく私は目的のお店へと足を進めた。
『も、戻りました…』
執務室に戻った頃には、お昼休憩も終わりに近くて。
げっそりとした様子でデスクに戻る私を見たブレダが不思議そうに此方を見る。
「何かやつれてないか?」
『そ、そう?』
「カップルの熱にでもやられたか!」
わははと笑うブレダのその発言にびくりと体を震わせた。
そうなのだ。
目的のお店へと行ったのは良いものの、何処もかしこもカップルだらけで。
普段ならそんなの全く気にしないのに今日は妙に気になってしまって、繋がれた手やら赤く染まった顔などを見てしまい。
ブレダの言う通り熱にやられた私はふらふらと帰ってきたのだ。
「お、正解っぽい?」
『ひ…人混みで酔っただけだよ!』
思わずつく嘘。
だって本当の事を言っても絶対に笑われる。
椅子に体を預けて此方を見ているロイだって、何を今さらそんな事でって笑うに決まってて。
いや、私だって今更?とか朝まで気にしてなかったのに?とか思うよ!
思うけれど、意識してしまったら最後。
だって良く考えてみたら、手を繋ぐって事は私の手をロイの手が包むわけで。
あの優しくて暖かくて大きい手が私の手を、と考えるだけで顔が熱くなってしまう。
「大丈夫か?」
『ん、え!?ろ、ロイ…!大丈夫…!』
「顔赤いぞ」
『こっこれは…!その、人混みの中居たから暑くて!』
いつの間にか側に来ていたロイに顔を覗かれてちょっとだけ舌を噛んだ。
顔が赤いのはどう考えても先程の事のせいなんだけど、それを隠したい私は嘘をまたついて。
怪訝な顔をしたロイと目が合ったけど、すいっと逸らす。
すると突然ロイが不気味に笑い始めて、思わず視線を向ける。
「そうか、そうか」
『え?な、なに怖い…』
「暑いなら少し外に出て冷まそうじゃないか」
『えっ』
「ななし一人だと心配だからな、私も着いていこう」
『えっえ!?』
何が何だか分からないまま、執務室の外へと連れ出される。
扉が閉まる直前に見えたのは、私達を気にすること無く仕事を始める部下達だった。
「で、何があったんだ」
『えっ、と……外じゃなかったの…』
「寒いから却下」
『……自分で言ったのに』
近くの使われていない会議室に入った私達は、向かい合うように椅子を並べて座る。
膝がぶつかってしまうくらい近い距離で顔がまた熱くなってしまう。
「人混みに酔ったとか暑いとか嘘だろ?」
『そ、そんな事分かるの』
「ななしは分かりやすいからな」
『分かりやすくない!』
「それはどうかな」
くすりと笑ったロイをじとりと見つめれば、可笑しそうに笑って私の頭を撫でた。
その撫でられる行為が気持ち良くて目を細めてしまうけど、先程までの事を思い出した途端にロイの手に意識が集中してしまう。
「…私が何かしたのか」
『えっ?』
「何かする度にななしが反応するから」
『あ、えっと……』
「顔真っ赤」
『うっ……』
鼻先にちょん、とロイの指が触れる。
自分の顔が真っ赤なんて分かりきってる事で、でもそれを人に指摘されるというのは分かっていても中々恥ずかしいもので。
「外で何かあったんだろ?」
『……』
「…」
『……』
「…言わないとここで襲うぞ」
『すっすれ違った女の子達が!』
爆弾発言と共に私の太ももをするりと撫でる手に思わず口から真実が漏れる。
言わなければ絶対に襲われてしまう。
そう確信した私は、一度大きく息を吐いてから下を向いた。
『…す、すれ違った女の子達が話してたの』
「何を」
『好きな人と手を繋ぐと幸せな気分になるって…私、そんな事考えた事も無かったから』
「…なるほど」
『考え出したら止まらないし、ロイの手を思い出して…わ、私の手をロイの手が…』
「……」
『…?ロイ………な、なに笑ってるの』
返事や相槌が無くて顔を上げれば、笑いを堪えた様子のロイと目があって。
ぷくりと頬を膨らませれば、ロイの手が頬に触れてびくりと体が揺れる。
「それでカップルにしか目が行かず熱にあてられたってわけか」
『う…はい…』
「ったく…今までそんなの気にせず自分から手を繋ぎに来てたのにな」
『だ、だから…それは何も考えずに…』
「じゃあ、今繋いでみるか?」
その言葉に目が丸くなる。
ん、と差し出されたロイの手はやっぱり大きくてゴツゴツしてて、私の手とは大違いで。
『ど、どうしてそうなるの』
「今まで何も考えずに繋いできたんだろ?」
『…うん…』
「考えられる状態で繋いだら、その女の子達の気持ちも分かったりしてな」
確かに分かるかもしれない。
でも意識したらドキドキは止まらないわけで、中々ロイの手に触れられず見つめるばかり。
じっと見つめる私をロイは面白そうに見ていて何だか不思議な光景だ。
「ほら」
『う…じゃ、じゃあ…繋いでも、いい、ですか…』
「何だそれ、いつもみたいに何も言わず繋いでいいよ」
『そうは言っても!…うう』
恐る恐るロイの手に自分の手を重ねる。
暖かいロイの手はやっぱり私の手よりも大きくて、まるで自分が子供になったような気分だ。
ドキドキする胸を押さえつつ、角度をつけてロイの手を握る。
するとロイも握り返してくれて、じんわりと暖かさが手に広がった。
「感想は?」
『…ロイの手おっきい』
「男だからな」
『改めて触ってみると硬い…』
「ななしはぷにぷにだ」
『ぷにぷにじゃない!』
「じゃあふにふに?」
からかうように笑ったロイに映る私は、きっと凄く真っ赤なんだろう。
この胸は未だドキドキと脈打っていてうるさい。
けれど、それは決して不快なものじゃなくて…
『…分かったかも』
「ん?」
『女の子達が幸せって思う気持ち…好きな人と手を繋げるのって凄いことだね』
「…そうだな」
『凄くドキドキするけど…ロイと手を繋げて幸せ』
「…」
『こんな気持ちになるんだったら、もっと前から意識してればよかったかも』
「……」
『…ロイ?』
またもや無言のロイに視線を向ければ空いている方の手で顔を覆っていて、手の隙間から見える頬はほんのりと赤く染まっている。
『え?え?な、なんでロイまで照れてるの?』
「ななしが変なこと言うから…」
『だって事実だし…』
「いつもは幸せとか滅多に言わないくせに」
『そうだっけ…?』
「さっきまで真っ赤な顔で照れてたのに今はもう平気そうだな」
『ロイが照れてるから?』
「何だそれ…」
小さく息を吐いたロイの頬はまだ染まったままで、見ていて少し面白い。
手を繋ぐ前は意識しすぎて痛いくらいドキドキしていたけれど、繋いでみたら幸せな気持ちの方が勝ってドキドキも心地がいい。
落ち着いてきた私は、からかうようにロイの頬を優しくつついた。
「…何だよ」
『ほっぺ、赤いなーって』
「ななしだって赤いだろ」
『ロイほどじゃないよ、わっ』
へらっと笑ってまたつつく。
それが気にくわなかったのか、ロイは私の手を掴んで自分の方へと強く引き寄せた。
自分が座っていたはずの椅子が視界の端に映る。
目の前にはロイが居て、手は繋がれたまま。
『あ、えっと…?こ、この体勢は一体…』
「私の膝の上にななしが乗ってる」
『そうじゃなくて!なんでこんな体勢に…!』
「随分と余裕そうだったもんで」
『えっ』
「その余裕無くしてしまおうか、なんてな」
ギラリとした目で見つめられて体が小さく震える。
離れようと繋がれた手に力を込めたけれど、びくともしなくて。
焦っているうちにどんどんロイの顔が近くなってきて、ドキドキが加速する。
その先の事を想像して無意識にギュッと目を閉じた瞬間、鼻先にちゅっと何かが触れた。
『…』
「何だよ、その間抜けな顔は」
『い、いや…てっきり』
「ここにされるかと思った?」
ロイの指が私の唇に触れる。
かあ、と赤くなったその顔を隠すためにロイの肩に顔を埋めれば、くすくすと笑う声が少し上から聞こえて。
「やっぱり私よりななしが照れている方がしっくり来る」
『…意味わかんない』
「ななしは可愛いなって事だよ」
ますます意味がわからない!とロイの胸を小さく叩けば、またくすくすと笑う声が聞こえた。
「…で、先程まで手を繋ぐことに大変照れていたななしさん」
『な、なに』
「これからはどうするのかな」
『どうするって』
「繋ぐ度に照れるのか、はたまた自分からは繋げないのか」
『つ、繋ぐよ!』
勢い良く顔をあげてロイの方へ向けば、優しい顔して微笑んでて。
てっきりからかうように笑ってると思ったのに、そんな顔されたら心臓に悪い。
『…照れるときもあると思うけど、それよりも幸せな気持ちが勝つから繋ぐ…』
「いつも通り、自分から?」
『う、うん…』
「ん、なら良かった。もう繋がないなんて言われたら悲しいからな」
ロイの唇が私の唇に重なる。
触れるだけの優しいそれはロイによって何度も何度も繰り返されて、蕩けてしまいそう。
ふわふわした気持ちの中、繋がれたロイの手を繋ぎ直して指を絡ませる。
ぎゅっと握れば、ぎゅっと握り返してくれて嬉しくなって。
唇が離れた時に小さく好きだよ、と呟けば私もだよ、と声が帰ってきて胸がきゅんと疼く。
その後も私達は何度も何度も重ねるだけのキスを繰り返した。
『結構時間経っちゃったね』
「ななしがキスに夢中だったからな」
『むっ…!』
会議室を出て執務室へ向かう途中、そんな事を言われてまた顔が熱くなる。
それをみたロイは面白そうに笑っていて、むっとした私は繋がれた手に全力で力を込めた。
「全く痛くない」
『うう…私がもっとゴリゴリマッチョだったら…』
「それは勘弁してくれ…」
『手だけでも鍛えようかな』
「今のままが良いんだが…」
ふにふにと何かを確かめるように触るロイを横目に、鍛えることを考えつつ歩く。
リザに聞いてみようかな、アームストロング少佐にも聞いてみよう。
「…頼むから中尉やアームストロング少佐に鍛えてもらわないように」
『なっ何で分かったの!?』
「はあ…ななしは分かりやすいって言ったろ?考えていることなんてお見通しだよ」
『ぐっ……』
「このままの手が好きだから、このままでいてほしいな」
ロイが微笑んでそう言うから、やっぱりこのままでいいか、なんて思ってしまう。
なんて分かりやすいんだろう、私は。
そんな自分に恥ずかしさを感じて手に力を込めれば、ロイも優しく力を込めてくれて。
『…手を繋ぐの好きだな』
「それは良かった」
繋いだ手から溢れる幸せに心がいっぱいになるのを感じて顔が緩む。
今の私は、きっとあの時見た女の子みたいに幸せそうに微笑んでいるんだろうな。
なんて、そんな事を思いながら執務室の扉を叩いた。
2019/01/28