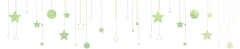今日は最高の日の筈だった。
ロイと私が同じ日にお休みで、それだけで堪らなく嬉しいのにロイは私をデートに誘ってくれて。
昨日の夜には服も選んでおいたのに。
『まさか風邪を引くなんて…』
げほ、と咳き込んで頭に手を当てる。
平熱だったらな…なんて淡い希望を寄せるけど、掌から感じる温かさは熱そのもので。
はあ、とため息をついて天井を見つめた。
「起きてるか?」
『うん…』
突然のノックの後、開いたドアの先には洗面器を持ったロイが心配げに立っていて。
その姿が妙に面白くて、つい笑いそうになってしまう。
「…なに笑いを堪えてるんだ」
『ご、ごめん…』
少し顔をしかめたロイは私の側に来て、額の上に乗っていたタオルを取る。
それを洗面器に入っている水に浸け、固く絞って再度私の額へと優しく置いてくれた。
「熱は?」
『下がってない…』
「そうか…今日中に下がれば良いんだが」
私の頬に優しく触れたロイの手はとても冷たくて、それが妙に気持ち良くて私は目を閉じて掌に頬を擦り付けた。
『冷たい…』
「水触ったからな」
『ごめんね、折角のお休みなのに』
「いいよ」
『……デートしたかったな』
そう呟くとロイは困ったように笑って、しょうがない子だな。と私の頭を撫でてくれる。
「たまにはこういうのも良いものだよ」
『でも…』
「また風邪が治ったらデートすれば良いさ。」
『うーん……』
「寧ろこれはデートじゃないか?所謂…」
『"おうちデート"?』
そうだ、それだと頷くロイに思わず笑みがこぼれる。
本当に優しくて素敵な人。
「…さ、少し寝るといい」
『うん、ありがとう…』
「寝るまで側にいるから」
そう言ってずっと頭を撫でてくれているロイに胸がいっぱいになって、幸福感のまま目を閉じる。
直ぐに睡魔が襲ってきて、私はそれに逆らうことをせずに眠りへと落ちていった。
ガタン!と遠くで何かが落ちる音がして目を覚ます。
横を見ればロイは居なくて、目を覚ました事にも納得で。
ロイが居ないと満足に寝られないこの体は、風邪の時でもそうらしく…完全に目が覚めてしまった。
『…ひとりだ』
ぽつりと呟いた声も誰の耳に届くでもなく消えていく。
遠くから何やらドタバタと何かの音がするけど、それもどこか遠い遠い届かないものの様に感じてしまう。
寂しい、なんて久しく感じたことも無い感情に自然と笑いが込み上げてきて。
ひとしきり小さく笑った後には虚しさのようなものしか残らなくて。
『一人は寂しいな…』
「ななし、」
『…ロイ?』
開けるぞ、と言う声と共にガチャリと扉が開く。
そこには何か器のような物を持ったロイが居て、先程の洗面器を思い出してまた笑ってしまった。
「笑う元気はあるみたいだな」
『ご、ごめん…』
「いや、大丈夫だよ。それよりも、これを」
何だかいつもより優しいロイがベッドサイドテーブルに置いてくれたそれは、ほかほかと湯気が立つ具沢山なスープで。
『…これ、ロイが作ったの?』
「ああ。普段料理をしないからな、ななしの手料理には到底敵わないが…」
『そっそんな事無い!食べて良い?』
「勿論」
木のスプーンで掬って、ぱくりと口に運び、程よく味がついている野菜を噛み締めて飲み込む。
スープと食材が喉を通るのを感じた後、お腹がじんわりと温かくなる。
その感覚に、私は自然と口角が上がるのを感じた。
『美味しい…!すっごく美味しいよ!』
「それは良かった」
あまりの美味しさに食べる手が止まらず、どんどんと食べ進める。
その間ロイは私の頭にあったタオルを水に浸けてくれていた。
量が少ないこともあって、すぐに食べ終わった私はロイに渡された薬を飲んでからまた横になる。
ロイは絞ったタオルを私の額にそっと乗せて、そのまま私の頬に手を添えた。
「先程よりも下がってるみたいだな」
『ロイのご飯美味しかったから?』
「それは光栄な事だな」
ちょっとだけ嬉しそうに笑ったロイは、食べ終わった食器を持って立ち上がって。
また一人になっちゃうなあ、なんて考えていたらロイが私に優しい顔で微笑んだ。
「片付けてくるから、少しだけ起きてていられるかな」
『?うん』
その言葉に頭を傾げたけど、どうせロイが居なければろくに寝られない身体。
私は素直に頷いて寝室を出たロイを待つことにした。
暫くしてカチャカチャとお皿を洗う音が聞こえる。
私は目を閉じてそれを聞いていて。
ただの音でも、それがロイの行動によって奏でられている音だと思うと心が温かくなる。
その音は何分もしないうちに止んで、直ぐに歩く音が聞こえた。
ガチャリと扉を開けて入ってきたロイは、私を見てにこりと微笑み躊躇無くベッドに入ってくる。
『えっ?ろ、ロイ?』
「なんだ」
『私、風邪引いて……』
「そうだな」
『そうだな、じゃなくて!移っちゃう…』
驚く私をよそに抱きしめてくるロイは、変わらず微笑んでいて。
ふと小さく名前を呼ばれて頭を撫でられた。
「良く寝れるように傍にいるよ」
『ベッドに入る意味は…!』
「こうした方が暖かいだろ?」
『そ、そうだけど…』
「食事を作ってる時は寂しい思いをさせたからなあ」
ロイは私の気持ちなんて見透かしたようにしていて、何だか悔しい。
でもそれ以上に嬉しくて、ロイの身体を抱きしめ返した。
『…気づいてたの』
「ななしの事なら何でも」
『何それ』
「嬉しいだろ?」
自信満々な声が耳に届いて、ロイの背中を叩く。
その間も頭を撫でる手は止まらなくて、ふたりの体温でベッドも暖かくて。
ロイの胸に耳を当てると、規則正しい鼓動が聞こえる。
『落ち着く』
「それは嬉しいな」
『……移っちゃったらどうしよう』
「ななしに看病してもらえるし、仕事も休める。最高だな」
『ふふ、何それ!ロイらしい!』
クスクスと笑えば、ロイも小さく笑った。
先程までの寂しい気持ちなんて吹っ飛んで、今は幸せな気持ちでいっぱいだ。
「起きるまでずっと居るから、少し寝よう」
『ん……ありがとう』
ウトウトし始めた私は、その言葉に頷いて抱きしめる力を少し強める。
目を瞑るとロイの匂いが鼻を掠めて、その心地良い匂いに顔が緩む。
『……私はロイが居ないと駄目だからなあ…』
ロイがピクリと動いた気がする。
心臓の音も早くなっているけど、気にすること無く。
私は幸せな気持ちを抱えて意識を手放した。
その日見た夢はロイと笑い合う夢で。
夢の中でおでこにキスをされて、抱きしめられて…夢なのに体温も感じたような気がする。
「好きだよ」
そう囁かれた言葉も耳元から聞こえるロイの心拍音も、全部がリアルで夢とは思えないくらいで。
夢の中の私は笑ってその言葉に答えたのだ。
2019/01/10
ロイと私が同じ日にお休みで、それだけで堪らなく嬉しいのにロイは私をデートに誘ってくれて。
昨日の夜には服も選んでおいたのに。
『まさか風邪を引くなんて…』
げほ、と咳き込んで頭に手を当てる。
平熱だったらな…なんて淡い希望を寄せるけど、掌から感じる温かさは熱そのもので。
はあ、とため息をついて天井を見つめた。
「起きてるか?」
『うん…』
突然のノックの後、開いたドアの先には洗面器を持ったロイが心配げに立っていて。
その姿が妙に面白くて、つい笑いそうになってしまう。
「…なに笑いを堪えてるんだ」
『ご、ごめん…』
少し顔をしかめたロイは私の側に来て、額の上に乗っていたタオルを取る。
それを洗面器に入っている水に浸け、固く絞って再度私の額へと優しく置いてくれた。
「熱は?」
『下がってない…』
「そうか…今日中に下がれば良いんだが」
私の頬に優しく触れたロイの手はとても冷たくて、それが妙に気持ち良くて私は目を閉じて掌に頬を擦り付けた。
『冷たい…』
「水触ったからな」
『ごめんね、折角のお休みなのに』
「いいよ」
『……デートしたかったな』
そう呟くとロイは困ったように笑って、しょうがない子だな。と私の頭を撫でてくれる。
「たまにはこういうのも良いものだよ」
『でも…』
「また風邪が治ったらデートすれば良いさ。」
『うーん……』
「寧ろこれはデートじゃないか?所謂…」
『"おうちデート"?』
そうだ、それだと頷くロイに思わず笑みがこぼれる。
本当に優しくて素敵な人。
「…さ、少し寝るといい」
『うん、ありがとう…』
「寝るまで側にいるから」
そう言ってずっと頭を撫でてくれているロイに胸がいっぱいになって、幸福感のまま目を閉じる。
直ぐに睡魔が襲ってきて、私はそれに逆らうことをせずに眠りへと落ちていった。
ガタン!と遠くで何かが落ちる音がして目を覚ます。
横を見ればロイは居なくて、目を覚ました事にも納得で。
ロイが居ないと満足に寝られないこの体は、風邪の時でもそうらしく…完全に目が覚めてしまった。
『…ひとりだ』
ぽつりと呟いた声も誰の耳に届くでもなく消えていく。
遠くから何やらドタバタと何かの音がするけど、それもどこか遠い遠い届かないものの様に感じてしまう。
寂しい、なんて久しく感じたことも無い感情に自然と笑いが込み上げてきて。
ひとしきり小さく笑った後には虚しさのようなものしか残らなくて。
『一人は寂しいな…』
「ななし、」
『…ロイ?』
開けるぞ、と言う声と共にガチャリと扉が開く。
そこには何か器のような物を持ったロイが居て、先程の洗面器を思い出してまた笑ってしまった。
「笑う元気はあるみたいだな」
『ご、ごめん…』
「いや、大丈夫だよ。それよりも、これを」
何だかいつもより優しいロイがベッドサイドテーブルに置いてくれたそれは、ほかほかと湯気が立つ具沢山なスープで。
『…これ、ロイが作ったの?』
「ああ。普段料理をしないからな、ななしの手料理には到底敵わないが…」
『そっそんな事無い!食べて良い?』
「勿論」
木のスプーンで掬って、ぱくりと口に運び、程よく味がついている野菜を噛み締めて飲み込む。
スープと食材が喉を通るのを感じた後、お腹がじんわりと温かくなる。
その感覚に、私は自然と口角が上がるのを感じた。
『美味しい…!すっごく美味しいよ!』
「それは良かった」
あまりの美味しさに食べる手が止まらず、どんどんと食べ進める。
その間ロイは私の頭にあったタオルを水に浸けてくれていた。
量が少ないこともあって、すぐに食べ終わった私はロイに渡された薬を飲んでからまた横になる。
ロイは絞ったタオルを私の額にそっと乗せて、そのまま私の頬に手を添えた。
「先程よりも下がってるみたいだな」
『ロイのご飯美味しかったから?』
「それは光栄な事だな」
ちょっとだけ嬉しそうに笑ったロイは、食べ終わった食器を持って立ち上がって。
また一人になっちゃうなあ、なんて考えていたらロイが私に優しい顔で微笑んだ。
「片付けてくるから、少しだけ起きてていられるかな」
『?うん』
その言葉に頭を傾げたけど、どうせロイが居なければろくに寝られない身体。
私は素直に頷いて寝室を出たロイを待つことにした。
暫くしてカチャカチャとお皿を洗う音が聞こえる。
私は目を閉じてそれを聞いていて。
ただの音でも、それがロイの行動によって奏でられている音だと思うと心が温かくなる。
その音は何分もしないうちに止んで、直ぐに歩く音が聞こえた。
ガチャリと扉を開けて入ってきたロイは、私を見てにこりと微笑み躊躇無くベッドに入ってくる。
『えっ?ろ、ロイ?』
「なんだ」
『私、風邪引いて……』
「そうだな」
『そうだな、じゃなくて!移っちゃう…』
驚く私をよそに抱きしめてくるロイは、変わらず微笑んでいて。
ふと小さく名前を呼ばれて頭を撫でられた。
「良く寝れるように傍にいるよ」
『ベッドに入る意味は…!』
「こうした方が暖かいだろ?」
『そ、そうだけど…』
「食事を作ってる時は寂しい思いをさせたからなあ」
ロイは私の気持ちなんて見透かしたようにしていて、何だか悔しい。
でもそれ以上に嬉しくて、ロイの身体を抱きしめ返した。
『…気づいてたの』
「ななしの事なら何でも」
『何それ』
「嬉しいだろ?」
自信満々な声が耳に届いて、ロイの背中を叩く。
その間も頭を撫でる手は止まらなくて、ふたりの体温でベッドも暖かくて。
ロイの胸に耳を当てると、規則正しい鼓動が聞こえる。
『落ち着く』
「それは嬉しいな」
『……移っちゃったらどうしよう』
「ななしに看病してもらえるし、仕事も休める。最高だな」
『ふふ、何それ!ロイらしい!』
クスクスと笑えば、ロイも小さく笑った。
先程までの寂しい気持ちなんて吹っ飛んで、今は幸せな気持ちでいっぱいだ。
「起きるまでずっと居るから、少し寝よう」
『ん……ありがとう』
ウトウトし始めた私は、その言葉に頷いて抱きしめる力を少し強める。
目を瞑るとロイの匂いが鼻を掠めて、その心地良い匂いに顔が緩む。
『……私はロイが居ないと駄目だからなあ…』
ロイがピクリと動いた気がする。
心臓の音も早くなっているけど、気にすること無く。
私は幸せな気持ちを抱えて意識を手放した。
その日見た夢はロイと笑い合う夢で。
夢の中でおでこにキスをされて、抱きしめられて…夢なのに体温も感じたような気がする。
「好きだよ」
そう囁かれた言葉も耳元から聞こえるロイの心拍音も、全部がリアルで夢とは思えないくらいで。
夢の中の私は笑ってその言葉に答えたのだ。
2019/01/10