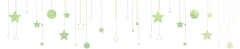今年最後の日。
それはまるでプレゼントの様に降ってきた。
『わー!ね、ロイ!雪が降ってきてる!』
「んん……騒がしいな…」
いつものように二人で寝ていた朝方、顔に当たる空気が冷たくて目を覚ました私は何となく体を起こした。
ベッドから覗ける窓にはハラハラと降る雪が見えて、寝ぼけて見つめていた私はそれが雪だと分かると思わずベッドから飛び出す。
私が居なくなった事によって寒くなったのか、起きてしまった様子のロイは少しだけ丸まって私の方をチラリと見た。
「…雪なんてそう珍しくもないだろ」
『そうだけど…』
「それに雪が降る度に興奮して遊んでるし」
『楽しいから!』
「……」
呆れたような表情のロイが私を見つめて来るけどそんなのお構いなしで。
早く積もらないかな!とルンルンでいれば、気だるそうなロイがベッドをポンポンと叩いた。
「おいで」
『えー、雪が……』
「降りだしたばかりだろう?まだ積もるには時間がかかる……まだ四時だぞ、遊ぶには体力が必要だろ」
『!遊んでくれるの!』
「今日だけだぞ」
だからもう一度寝よう。
そう言われた私は笑顔でまたベッドに戻る。
すかさずロイが抱きしめて来るけど私の体は既に冷たくて。
それでも離そうとしないロイの体温によって、じんわりと体が暖められていく。
『ね、起きたら覚えてなかったは無しだからね』
「約束するよ」
普段なら遊んでる私を見てるだけのロイが、まさか一緒に遊んでくれるなんて!
興奮して眠れなくなってしまった私をよそに、ロイは既に夢の中に行ってしまったようで小さく寝息が聞こえた。
『早く積もります様に…』
そう願って目を閉じれば段々と睡魔がやって来て私は夢の中へ溶けていった。
『さてさて!やっと積もりました!』
時刻は変わってお昼の一時。
あれから起きて朝ご飯を食べてゆっくりして、お昼ご飯を食べて。
外を見れば綺麗に積もっていて、私はゆっくりと読書をしていたロイの前に立つ。
ロイはチラリと外を見てからソファから立ってコートとマフラーを私に着せた。
「じゃ、行くか」
『覚えてた!』
「当たり前だろ」
そう言って笑いながら私に手袋をはめるロイ。
『…厳重装備だね』
「霜焼けになったら凄く凄く困るからな」
『そんなに!?』
その後ロイもコートを着て、さて行きますか!と意気込んで勢いよく玄関を開ける。
目の前に広がるのは銀世界ってやつで、やっぱり何度見ても心が踊ってしまう。
『ひゃー!ゆきー!!』
「…この光景も見慣れたものだな」
『ゆきー!ゆきー!』
興奮のあまり同じ言葉ばかり発する私を見てロイが笑っていて、それが何だか楽しくて。
『ロイ!一緒に雪だるま作ろう!』
「良いだろう、大きいのを作ってやる」
『やった!』
ロイと小さな雪を転がして大きくしていく。
たまに私が転んで、大笑いして。
やっと完成した雪だるまは私の身長位あるもので思わず歓声をあげる。
『凄い!』
「ま、私にかかればこのくらい」
『ロイ凄い!凄いよ!』
「そこまで誉められると流石に照れそうだ」
『じゃあ…次は雪うさぎ!』
そう言うとロイは任せろと雪をかき集めた。
『雪だるまに、雪うさぎ…雪ハヤテ号に雪アルフォンスくん!沢山作ったね!』
「腰が痛い……」
腰を曲げて辛そうにするロイの横には作ったものが沢山並べられている。
雪うさぎや雪ハヤテ号は小さいけど、雪アルフォンスくんは等身大レベルで大きくてまるで本物みたいだ。
『顔は微妙だけど体の大きさはそっくりー!』
「微妙ってなんだ!頑張ったんだぞ、大の大人が!!」
『大の大人…そっか、ロイって三十路だった……』
「三十路とか言うな!」
『ごめんごめん!そこに座ろっか!腰辛いでしょ!』
「急に労らないでくれ……」
玄関の近くの腰を掛けられる所に積もっている雪を退けて、持っていた厚めの大きなハンカチを敷いてそこに二人で座った。
『…今年ももう終わりだね』
「そうだな」
『……ありがとうね、ロイ』
「何だ急に」
思いがけない言葉だったのかロイが此方を見る。
私はそれに気付いたけど、何だか目を合わせるのが恥ずかしくて雪うさぎ達をじっと見つめていた。
『私、ロイが居なければきっと今生きていないから…ロイが私に手を差し伸べてくれたから、今生きていられてると思うんだ』
「ななし…」
『だから、ありがとう!大好き!来年も大好きだよ!』
そう言って笑えば、ロイに小さくキスをされて。
外だよ、なんて言ったけどそれに笑って返された。
「再来年は好きじゃない?」
『え!?も、勿論好きだよ!』
「はは、私も好きだよ。愛してる、ずっと」
『あ、ありがとう……』
ロイからの突然な言葉にドキリとして下を向く。
自分の膝の上でぎゅっと握った手にロイの手が重なって、手袋をしているのに体温が伝わりそう。
「…ななし」
ふと小さく名前で呼ばれて、素直に顔を上げればロイの顔が近くて。
外なのに、とまた考えたけど、もう周りも薄暗くなってきたから…と自分に言い聞かせて目を閉じた。
「あんりゃまー、お二人さんお熱いねえ」
唇が重なる瞬間、近くから聞こえたその声に勢いよく離れる。
声の先には知らないおじさんが犬を散歩させていて、私達を見てにんまりと笑って去っていった。
『…』
「……」
何が起こったのか分からなくて二人して固まっていたけど、ロイと顔を見合わせて笑った。
『…もう日も落ちてきたし戻ろっか』
「そうだな……ななし」
『?わっ』
立ち上がった瞬間ロイに呼び止められて小さくキスをされる。驚いて固まっていれば、ロイはいたずらっ子みたいに笑って立ち上がった。
「行こうか」
『う…うん』
ドキドキと胸が高鳴るのを感じながらロイの後ろをついていく。
私よりも大きい背中にまた胸が高鳴って、私は思わず抱きついた。
瞬間。
「ぐっ……!」
『へ?わあ!』
ドアを開けたロイが玄関に向かって倒れてしまい、私も一緒になって倒れる。
勢いよく退けば、ロイは腰を押さえて震えていて。
「こ、腰……」
『あっ…ごめん!忘れてた……』
「大丈夫だ…」
ロイは倒れたままにこやかに笑ったけれど、顔は顔面蒼白ってやつで、何度も何度も謝った。
『…大の大人だもんね、すぐに治らないよね』
「……」
『ご、ごめん』
じと、と睨まれたのは言うまでもなく。
そのまま動けないロイをリビングに連れていくために私は気合いを入れた。
2018/12/31
それはまるでプレゼントの様に降ってきた。
『わー!ね、ロイ!雪が降ってきてる!』
「んん……騒がしいな…」
いつものように二人で寝ていた朝方、顔に当たる空気が冷たくて目を覚ました私は何となく体を起こした。
ベッドから覗ける窓にはハラハラと降る雪が見えて、寝ぼけて見つめていた私はそれが雪だと分かると思わずベッドから飛び出す。
私が居なくなった事によって寒くなったのか、起きてしまった様子のロイは少しだけ丸まって私の方をチラリと見た。
「…雪なんてそう珍しくもないだろ」
『そうだけど…』
「それに雪が降る度に興奮して遊んでるし」
『楽しいから!』
「……」
呆れたような表情のロイが私を見つめて来るけどそんなのお構いなしで。
早く積もらないかな!とルンルンでいれば、気だるそうなロイがベッドをポンポンと叩いた。
「おいで」
『えー、雪が……』
「降りだしたばかりだろう?まだ積もるには時間がかかる……まだ四時だぞ、遊ぶには体力が必要だろ」
『!遊んでくれるの!』
「今日だけだぞ」
だからもう一度寝よう。
そう言われた私は笑顔でまたベッドに戻る。
すかさずロイが抱きしめて来るけど私の体は既に冷たくて。
それでも離そうとしないロイの体温によって、じんわりと体が暖められていく。
『ね、起きたら覚えてなかったは無しだからね』
「約束するよ」
普段なら遊んでる私を見てるだけのロイが、まさか一緒に遊んでくれるなんて!
興奮して眠れなくなってしまった私をよそに、ロイは既に夢の中に行ってしまったようで小さく寝息が聞こえた。
『早く積もります様に…』
そう願って目を閉じれば段々と睡魔がやって来て私は夢の中へ溶けていった。
『さてさて!やっと積もりました!』
時刻は変わってお昼の一時。
あれから起きて朝ご飯を食べてゆっくりして、お昼ご飯を食べて。
外を見れば綺麗に積もっていて、私はゆっくりと読書をしていたロイの前に立つ。
ロイはチラリと外を見てからソファから立ってコートとマフラーを私に着せた。
「じゃ、行くか」
『覚えてた!』
「当たり前だろ」
そう言って笑いながら私に手袋をはめるロイ。
『…厳重装備だね』
「霜焼けになったら凄く凄く困るからな」
『そんなに!?』
その後ロイもコートを着て、さて行きますか!と意気込んで勢いよく玄関を開ける。
目の前に広がるのは銀世界ってやつで、やっぱり何度見ても心が踊ってしまう。
『ひゃー!ゆきー!!』
「…この光景も見慣れたものだな」
『ゆきー!ゆきー!』
興奮のあまり同じ言葉ばかり発する私を見てロイが笑っていて、それが何だか楽しくて。
『ロイ!一緒に雪だるま作ろう!』
「良いだろう、大きいのを作ってやる」
『やった!』
ロイと小さな雪を転がして大きくしていく。
たまに私が転んで、大笑いして。
やっと完成した雪だるまは私の身長位あるもので思わず歓声をあげる。
『凄い!』
「ま、私にかかればこのくらい」
『ロイ凄い!凄いよ!』
「そこまで誉められると流石に照れそうだ」
『じゃあ…次は雪うさぎ!』
そう言うとロイは任せろと雪をかき集めた。
『雪だるまに、雪うさぎ…雪ハヤテ号に雪アルフォンスくん!沢山作ったね!』
「腰が痛い……」
腰を曲げて辛そうにするロイの横には作ったものが沢山並べられている。
雪うさぎや雪ハヤテ号は小さいけど、雪アルフォンスくんは等身大レベルで大きくてまるで本物みたいだ。
『顔は微妙だけど体の大きさはそっくりー!』
「微妙ってなんだ!頑張ったんだぞ、大の大人が!!」
『大の大人…そっか、ロイって三十路だった……』
「三十路とか言うな!」
『ごめんごめん!そこに座ろっか!腰辛いでしょ!』
「急に労らないでくれ……」
玄関の近くの腰を掛けられる所に積もっている雪を退けて、持っていた厚めの大きなハンカチを敷いてそこに二人で座った。
『…今年ももう終わりだね』
「そうだな」
『……ありがとうね、ロイ』
「何だ急に」
思いがけない言葉だったのかロイが此方を見る。
私はそれに気付いたけど、何だか目を合わせるのが恥ずかしくて雪うさぎ達をじっと見つめていた。
『私、ロイが居なければきっと今生きていないから…ロイが私に手を差し伸べてくれたから、今生きていられてると思うんだ』
「ななし…」
『だから、ありがとう!大好き!来年も大好きだよ!』
そう言って笑えば、ロイに小さくキスをされて。
外だよ、なんて言ったけどそれに笑って返された。
「再来年は好きじゃない?」
『え!?も、勿論好きだよ!』
「はは、私も好きだよ。愛してる、ずっと」
『あ、ありがとう……』
ロイからの突然な言葉にドキリとして下を向く。
自分の膝の上でぎゅっと握った手にロイの手が重なって、手袋をしているのに体温が伝わりそう。
「…ななし」
ふと小さく名前で呼ばれて、素直に顔を上げればロイの顔が近くて。
外なのに、とまた考えたけど、もう周りも薄暗くなってきたから…と自分に言い聞かせて目を閉じた。
「あんりゃまー、お二人さんお熱いねえ」
唇が重なる瞬間、近くから聞こえたその声に勢いよく離れる。
声の先には知らないおじさんが犬を散歩させていて、私達を見てにんまりと笑って去っていった。
『…』
「……」
何が起こったのか分からなくて二人して固まっていたけど、ロイと顔を見合わせて笑った。
『…もう日も落ちてきたし戻ろっか』
「そうだな……ななし」
『?わっ』
立ち上がった瞬間ロイに呼び止められて小さくキスをされる。驚いて固まっていれば、ロイはいたずらっ子みたいに笑って立ち上がった。
「行こうか」
『う…うん』
ドキドキと胸が高鳴るのを感じながらロイの後ろをついていく。
私よりも大きい背中にまた胸が高鳴って、私は思わず抱きついた。
瞬間。
「ぐっ……!」
『へ?わあ!』
ドアを開けたロイが玄関に向かって倒れてしまい、私も一緒になって倒れる。
勢いよく退けば、ロイは腰を押さえて震えていて。
「こ、腰……」
『あっ…ごめん!忘れてた……』
「大丈夫だ…」
ロイは倒れたままにこやかに笑ったけれど、顔は顔面蒼白ってやつで、何度も何度も謝った。
『…大の大人だもんね、すぐに治らないよね』
「……」
『ご、ごめん』
じと、と睨まれたのは言うまでもなく。
そのまま動けないロイをリビングに連れていくために私は気合いを入れた。
2018/12/31