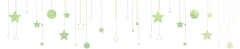カチコチと時計の針の進む音が響く。
私は一人でソファに座っていて、何をするわけでもなくボーッと窓の外を見ていた。
もう夜も遅いのに窓の外は明るくて、雪が降っているんだなと頭の隅で考える。
一人でこの家に居るなんて珍しいことで。
なんでも、今日までの仕事を溜め込んでいたせいでまだ帰れないとか。
手伝うよと声を掛けたけど、大佐相当の人じゃないと記入してはいけない書類らしく、先に帰ることとなってしまった。
初めは寝てしまおうかと寝室に行ったけど、なんだか一人では寝れなくて。
結局リビングで待つ事にしたのだけど……
『大丈夫かな…』
しんしんと降り積もっていく雪を見て、少し心配になる。
きっと執務室にはロイ一人だけしか居なくて、静かな中やっているんだろうな。
『…よし!』
私は勢い良く立ち上がって、お気に入りのコートに手を伸ばした。
『うあ〜…さっぶい…』
外に出てみればもう道路が白くて、まるで粉砂糖が振り掛けられたみたいで。
大きめの傘ひとつをさして歩けば、まだ独特の音はしないけれど足跡が残った。
一つ、二つ、三つと足跡を残してから振り返ってそれを見る。
私の足跡しかないその道路は、まるで私だけに許された道みたいで何だか優越感。
『ふふ』
一人で不気味に笑っても見ている人など居るわけもなく。
はあ、と空に息を漏らせばそれは白く色づいて消えていった。
『帰ったら、先ずはお風呂かな〜、その後珈琲入れてあげよう!』
帰った後の事を想像しながら口に出して歩く。
ふと立ち止まって傘を下へ向ければたくさんの雪が落ちてきて、それすらも何だか楽しくて。
通り道の街へ行けば、雪のお陰で明るくて思わず感動の声が口から漏れる。
足跡はやっぱり1つもなくて、私は足跡をたくさんつけるように歩き回った。
『あちゃ、遊んでると帰りにロイに怒られちゃう』
ただでさえ、こんな夜遅くに一人で出歩いて怒られるだろうに、ここで遊んでいたことが足跡で分かってしまったらもっと怒られてしまう。
早々に止めて、また目的地へ向かって歩き出す。
『ふんふーん』
子供の頃に好きだったオルゴールの曲を口ずさむ。
通りすぎるお店を全部見るようにゆっくり歩いて、思い出を思い返す。
『このお店はロイと良く食べに来るお店!ここは行きつけのお菓子屋さん!ここは、ロイと…』
そのどれもがロイとの幸せな思い出ばかり。
いつの間にか沢山の思い出を貰っていて、胸がいっぱいになる。
『ふふ、ロイが居ないのにロイの事ばっかり!』
そう笑った私の頬は、寒さも感じないほど暖かくて。
ロイに早く会いたいな、なんて思って歩くスピードを早めた。
「…ふう、やっと終わったか」
処理済みの書類の山を見ながらため息をひとつ。
外を見ればいつの間にか雪が降っていたようで、辺り一面が真っ白だった。
「ななしは暖かくしているだろうか」
もう日付も変わる時刻。
ベッドでほかほかと眠るななしを想像して、一人にやけてしまう。
一人きりの執務室も何だか違和感があるもので、片付けを早々に済ませて立ち上がる。
片付けた書類は記入こそ今日までだったものの提出は明日の朝でも間に合うので、デスクの引き出しに閉まった。
自分の足音だけが響く廊下を歩く。
窓を見ればまだ雪は降り続いていて、傘を持っていない事に気付いた。
この降り具合だと、帰る頃には自分は真っ白になっているかもしれない。
「…そうなったらななしに吃驚されるな」
くすりと笑う。
ななしは、私が側に居れば何をしても起きないものの、私が居ないと少しの物音でも起きる。
きっと帰った音で起きて出迎えてくれるのだろう。
驚いたように慌ててタオルを持ってくる姿が安易に想像できた。
だけれどこんな夜遅くに一人で帰るなんてとても久しぶりで、少しだけ寂しく感じてしまう自分が居て。
「…いつだって側にはななしが居るからなあ」
彼女が自分の側に居ることが当たり前になっているのだ。
他の女性には感じたことの無い特別感で胸がいっぱいになる。
…早く会いたいな
素直なその気持ちは、自分でも気持ち悪いなと笑ってしまうほどで。
だけれどななしへの気持ちに嘘など無く、私は足早に外へと向かった。
「結構降ってるな」
さあ後一歩で外だ、という所で立ち止まる。
はらはらと降り止まない雪を見て、さてどうしようか。と考えていた時。
『ロイ!』
「……ななし?」
小さな体に似合わぬ大きめの傘をさしてこちらへ手を振るななし。
それに自然と振り返せば、嬉しそうに駆け寄ってくる。
「こら、滑るぞ」
『へへ…ごめん!』
おでこにコツンと手をやれば、真っ赤な頬をして微笑むななしがすぐ側に居て、思わず抱きしめた。
傘がポトリと落ちたがそんなの関係ない。
『ロイの体冷たい!』
「ななしも冷たい……と言うかどうして」
『一人だと寂しくて…迎えに来ちゃった!』
自分の胸の中でクスクス笑う彼女がとても愛しくて、思わず抱きしめている力を強めれば痛い!と苦情が来て。
渋々離すと、ななしは落ちた傘を拾って笑った。
『一緒に帰ろ!』
雪景色の中、そう言って笑うななしは一段と綺麗に見えて、思わず胸が鳴る。
ななしは傘を上に持ち上げて私が入るスペースを作ってくれて、その姿だけでも可愛くて。
私は少しだけ笑って傘の下に入った。
『…怒らないの?出歩くな!って』
「まあいつもなら怒るが…」
『…?』
「会いたかった」
そう言って微笑めば、真っ赤なななしの顔が更に赤くなって慌てたように俯く。
俯いた彼女が小さな声で私も、と呟いたのを聞き逃さず、私はななしの名前を呼んだ。
「ななし」
『…なに?…ん』
「ふ…真っ赤だな」
『っもう!』
顔をあげたななしにキスを一つ落とせば、困ったように怒る。
それが照れているときの行為だと知っている私は、ななしの持っている傘を取って彼女の腰に手を添えた。
「行こうか」
『…うん』
歩き出した時には既にななしの足跡は無くなっていて、雪特有の音が鳴る。
『家を出たときは鳴らなかったの!』
「転ばないようにな」
嬉しそうに跳ねるななしにそう注意すると笑顔で頷かれた。
ななしと傘一つで帰るというのも中々良いもので、今の私は顔が緩んでいるだろう。
そう考えながらななしに合わせて歩いていると、雪が首筋に落ちて身震いを一つ。
それに気づいたななしは、少し笑って私の腕に自分の手を絡ませた。
『帰ったらね、お風呂入って…その後珈琲飲もうね!』
「一緒に?」
『おっ、お風呂は駄目!』
「えー」
『えー、じゃなくて…!』
からかうように言えば困ったように顔を赤くしていて更ににやけてしまう。
帰ったら一緒に風呂に入って、珈琲を飲んで…その後は……
すぐに体が暖まりそうな事を想像しつつ、不気味に笑えば驚いたななしが覗き込んできて、その可愛らしい頬に唇を寄せれば、何だか物足りなさそうな顔をしていて。
「帰ったらな」
そう言ってななしの唇を指でなぞると、照れたように笑うから此方まで照れてしまった。
『照れた!』
「うるさい」
家に帰ったら覚えてろ、必ず一緒に風呂に入ってやる。
未だ楽しそうにからかってくるななしに、笑ってられるのは今だけだぞと心の中で呟いた。
2018/12/28
私は一人でソファに座っていて、何をするわけでもなくボーッと窓の外を見ていた。
もう夜も遅いのに窓の外は明るくて、雪が降っているんだなと頭の隅で考える。
一人でこの家に居るなんて珍しいことで。
なんでも、今日までの仕事を溜め込んでいたせいでまだ帰れないとか。
手伝うよと声を掛けたけど、大佐相当の人じゃないと記入してはいけない書類らしく、先に帰ることとなってしまった。
初めは寝てしまおうかと寝室に行ったけど、なんだか一人では寝れなくて。
結局リビングで待つ事にしたのだけど……
『大丈夫かな…』
しんしんと降り積もっていく雪を見て、少し心配になる。
きっと執務室にはロイ一人だけしか居なくて、静かな中やっているんだろうな。
『…よし!』
私は勢い良く立ち上がって、お気に入りのコートに手を伸ばした。
『うあ〜…さっぶい…』
外に出てみればもう道路が白くて、まるで粉砂糖が振り掛けられたみたいで。
大きめの傘ひとつをさして歩けば、まだ独特の音はしないけれど足跡が残った。
一つ、二つ、三つと足跡を残してから振り返ってそれを見る。
私の足跡しかないその道路は、まるで私だけに許された道みたいで何だか優越感。
『ふふ』
一人で不気味に笑っても見ている人など居るわけもなく。
はあ、と空に息を漏らせばそれは白く色づいて消えていった。
『帰ったら、先ずはお風呂かな〜、その後珈琲入れてあげよう!』
帰った後の事を想像しながら口に出して歩く。
ふと立ち止まって傘を下へ向ければたくさんの雪が落ちてきて、それすらも何だか楽しくて。
通り道の街へ行けば、雪のお陰で明るくて思わず感動の声が口から漏れる。
足跡はやっぱり1つもなくて、私は足跡をたくさんつけるように歩き回った。
『あちゃ、遊んでると帰りにロイに怒られちゃう』
ただでさえ、こんな夜遅くに一人で出歩いて怒られるだろうに、ここで遊んでいたことが足跡で分かってしまったらもっと怒られてしまう。
早々に止めて、また目的地へ向かって歩き出す。
『ふんふーん』
子供の頃に好きだったオルゴールの曲を口ずさむ。
通りすぎるお店を全部見るようにゆっくり歩いて、思い出を思い返す。
『このお店はロイと良く食べに来るお店!ここは行きつけのお菓子屋さん!ここは、ロイと…』
そのどれもがロイとの幸せな思い出ばかり。
いつの間にか沢山の思い出を貰っていて、胸がいっぱいになる。
『ふふ、ロイが居ないのにロイの事ばっかり!』
そう笑った私の頬は、寒さも感じないほど暖かくて。
ロイに早く会いたいな、なんて思って歩くスピードを早めた。
「…ふう、やっと終わったか」
処理済みの書類の山を見ながらため息をひとつ。
外を見ればいつの間にか雪が降っていたようで、辺り一面が真っ白だった。
「ななしは暖かくしているだろうか」
もう日付も変わる時刻。
ベッドでほかほかと眠るななしを想像して、一人にやけてしまう。
一人きりの執務室も何だか違和感があるもので、片付けを早々に済ませて立ち上がる。
片付けた書類は記入こそ今日までだったものの提出は明日の朝でも間に合うので、デスクの引き出しに閉まった。
自分の足音だけが響く廊下を歩く。
窓を見ればまだ雪は降り続いていて、傘を持っていない事に気付いた。
この降り具合だと、帰る頃には自分は真っ白になっているかもしれない。
「…そうなったらななしに吃驚されるな」
くすりと笑う。
ななしは、私が側に居れば何をしても起きないものの、私が居ないと少しの物音でも起きる。
きっと帰った音で起きて出迎えてくれるのだろう。
驚いたように慌ててタオルを持ってくる姿が安易に想像できた。
だけれどこんな夜遅くに一人で帰るなんてとても久しぶりで、少しだけ寂しく感じてしまう自分が居て。
「…いつだって側にはななしが居るからなあ」
彼女が自分の側に居ることが当たり前になっているのだ。
他の女性には感じたことの無い特別感で胸がいっぱいになる。
…早く会いたいな
素直なその気持ちは、自分でも気持ち悪いなと笑ってしまうほどで。
だけれどななしへの気持ちに嘘など無く、私は足早に外へと向かった。
「結構降ってるな」
さあ後一歩で外だ、という所で立ち止まる。
はらはらと降り止まない雪を見て、さてどうしようか。と考えていた時。
『ロイ!』
「……ななし?」
小さな体に似合わぬ大きめの傘をさしてこちらへ手を振るななし。
それに自然と振り返せば、嬉しそうに駆け寄ってくる。
「こら、滑るぞ」
『へへ…ごめん!』
おでこにコツンと手をやれば、真っ赤な頬をして微笑むななしがすぐ側に居て、思わず抱きしめた。
傘がポトリと落ちたがそんなの関係ない。
『ロイの体冷たい!』
「ななしも冷たい……と言うかどうして」
『一人だと寂しくて…迎えに来ちゃった!』
自分の胸の中でクスクス笑う彼女がとても愛しくて、思わず抱きしめている力を強めれば痛い!と苦情が来て。
渋々離すと、ななしは落ちた傘を拾って笑った。
『一緒に帰ろ!』
雪景色の中、そう言って笑うななしは一段と綺麗に見えて、思わず胸が鳴る。
ななしは傘を上に持ち上げて私が入るスペースを作ってくれて、その姿だけでも可愛くて。
私は少しだけ笑って傘の下に入った。
『…怒らないの?出歩くな!って』
「まあいつもなら怒るが…」
『…?』
「会いたかった」
そう言って微笑めば、真っ赤なななしの顔が更に赤くなって慌てたように俯く。
俯いた彼女が小さな声で私も、と呟いたのを聞き逃さず、私はななしの名前を呼んだ。
「ななし」
『…なに?…ん』
「ふ…真っ赤だな」
『っもう!』
顔をあげたななしにキスを一つ落とせば、困ったように怒る。
それが照れているときの行為だと知っている私は、ななしの持っている傘を取って彼女の腰に手を添えた。
「行こうか」
『…うん』
歩き出した時には既にななしの足跡は無くなっていて、雪特有の音が鳴る。
『家を出たときは鳴らなかったの!』
「転ばないようにな」
嬉しそうに跳ねるななしにそう注意すると笑顔で頷かれた。
ななしと傘一つで帰るというのも中々良いもので、今の私は顔が緩んでいるだろう。
そう考えながらななしに合わせて歩いていると、雪が首筋に落ちて身震いを一つ。
それに気づいたななしは、少し笑って私の腕に自分の手を絡ませた。
『帰ったらね、お風呂入って…その後珈琲飲もうね!』
「一緒に?」
『おっ、お風呂は駄目!』
「えー」
『えー、じゃなくて…!』
からかうように言えば困ったように顔を赤くしていて更ににやけてしまう。
帰ったら一緒に風呂に入って、珈琲を飲んで…その後は……
すぐに体が暖まりそうな事を想像しつつ、不気味に笑えば驚いたななしが覗き込んできて、その可愛らしい頬に唇を寄せれば、何だか物足りなさそうな顔をしていて。
「帰ったらな」
そう言ってななしの唇を指でなぞると、照れたように笑うから此方まで照れてしまった。
『照れた!』
「うるさい」
家に帰ったら覚えてろ、必ず一緒に風呂に入ってやる。
未だ楽しそうにからかってくるななしに、笑ってられるのは今だけだぞと心の中で呟いた。
2018/12/28