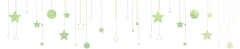『むむむむむ……』
綺麗な夜空の下。
私は、ロイと二人で棲んでいる家を前にして唸っていた。
手元にある少し大きな箱を見つめて。
事の発端は、今日の夕方なのである。
今日も今日とて仕事が山積みだったのだけれど、とても大切な用事があると皆に告げたロイが、見たことの無い速さで仕事を片付けたのだ。
そして、夕日が完全に落ちる前に仕事終了……解散となった。
『ハボック、感動のあまり夕日みて泣いてたな…』
帰り道である街の中を歩く。
…ロイの用事とは何なのだろうか。
大切な用事………女性関係なのかな、なんて考えてしまうけれど…
先に帰っててくれ、なんて言われて珍しく一人で歩いてるわけで。
少しだけ落ち込んだ気分で歩いていると、ふと目に入る小さなお店。
『焼き菓子…専門店?』
はて、こんなところにお店なんてあっただろうか?
思わず足を止めて、お店をじろじろと見てしまう。
そこで店内に居た女性と目が合い、会釈される。
『…入ってみようかな』
こちらも会釈して、扉を開けた。
ふんわりと甘い香りが鼻を擽って、つい頬が緩んでしまう。
「いらっしゃいませ、何かお探しでしたか?」
『あ!いえ…ここにこんな良いお店あったかな、なんて考えてて…』
「あら、嬉しいことを…開店してまだ日が浅くて」
なるほど、だから気づかなかったのか
なんて考えつつ店内を見渡す。
折角だし何か買っていこう
「見たところ、軍人さんかしら?こんなに可愛らしい方もいらっしゃるのね」
『そんな…お世辞でも照れちゃいます』
店員さんは、綺麗に微笑んだ後何かを嗅ぐような仕草をした。
咄嗟に自分の服の臭いを確認する。
『ご、ごめんなさい、汗臭かったですか?』
「いいえ、違うの。この匂い………もしかして、恋人とかいらっしゃる?」
『えっ!?』
どきり、と胸が鳴って同時に自分の顔が熱くなるのを感じた。
「やっぱり!」
『な、なんで…』
「ふふ…私って鼻が良くて…あなたから、恋をしている甘い香りがしたから」
『ど、どういう…!?』
慌てている私を横目に、店員さんは目の前のショーケースにあるバウムクーヘンを指差す。
「これ、恋をしている方にぴったりなケーキなんです」
『恋をしている人に…?』
バウムクーヘンに意味などあったのだろうか…
そう首を傾げると、それが店員さんに伝わったようだ。
「バウムクーヘンには、凄く素敵な言葉が込められているんですよ。それは……」
『……!』
耳打ちで教えられたその言葉に、思わずごくりと喉が鳴った。
「素敵だと思いませんか?」
『たしかに素敵です…でも、意味がばれちゃったら少し恥ずかしいですね…』
「でも、確実にあなたの気持ちは届きますわ。きっと意味を知ったら、恋人の方は大喜びするんじゃないかしら」
ロイが大喜び…!?
「もしかしたら、顔を真っ赤にしてしまうかも」
ロイが顔を真っ赤に……!
「それとも、嬉しくて泣いてしまうかしら?」
ロイが……泣く…!?
『それ、買います!!』
と言うわけで現在に至るのだが。
『ロイの反応見たさに買ってしまった……』
絶賛後悔中の私は、中々家に帰れずにいた。
ロイならきっと、こういう贈り物は他の女性から沢山受け取ってきた筈だし…からかわれるに決まってるのだ。
バウムクーヘンが入った綺麗な箱を見つめて、ため息を溢す。
美味しそうだったし、一人で食べちゃおうかな…
ロイに見つかる前に食べてしまえば証拠隠滅になる!
『……よし!』
「ななし?」
『…!』
箱に手を掛けたその時、家のドアが開くと同時に声を掛けられた。
それは勿論、私の恋人なわけで。
ケーキの箱を持ってダラダラと汗を流す私は、端から見たらかなり変な人なのだろう。
「人の気配がしたから来てみたら……中に入らないのか?」
『えっと、入ります……』
ケーキの箱を隠すように持ってゆっくりと家に入ると、扉を閉めてくれたロイが後ろから私を覗き込んだ。
「ななし、何か変だぞ…………その箱」
『うっ……』
隠そうにも中々隠せない大きさの箱は、直ぐに見つかってしまった。
『…っあー!もうヤケだ!これ!あげる!!』
ロイの前に箱を突き出す。
半ば反射的にそれを受け取ったロイは、少しポカンとしたように私を見つめていた。
「これは」
『かっ帰り道!新しいお菓子屋さん!買ってきた!』
箇条書きのような言葉を紡いで下を向く。
上の方から開けて良い?と声が聞こえて、ここで?と思ったけど頷いた。
「バウムクーヘン…」
『いっ意味…分かっちゃったり、する…?』
「…ななしは分かっているのか?」
『う、うん…』
うるさいほど鳴る胸を押さえながら顔を上げる。
ロイは私を真剣な眼差しで見つめていて、思わず肩を下げてしまった。
『お、大喜びしてない……』
「は?」
『顔真っ赤にしてない……泣いてない…』
「急になんだ」
『やっぱり、貰いなれてるんだ……からかわれるんだ…』
「…なるほど?大体理解した」
ロイはバウムクーヘンを箱に戻して、私の肩を優しく包むように抱いた。
「これは、ななしの素直な気持ちとして受け取って良いのかな?」
『そ、それは、まあ……そ、そうだけど…』
思わず赤くなる私を見たロイに連れられて、リビングへと行く。
待っててと言われソファで待っていると、ロイはキッチンから少し小さな箱を持ってきた。
『あれ…その箱…』
「やっぱり、同じ店だな」
同じロゴの箱。
いつの間にロイも行っていたんだろう。
「開けてごらん」
そう言われて箱をゆっくりと開ける。
『これは……?』
中に入っていたのは、キラキラと輝く粒。
「マロングラッセだよ」
『マロングラッセ……?』
「ななしへのプレゼントとして、今日買いに行ったんだ」
『じゃあ、大切な用事って……』
女性関係だと思っていた数時間前の私を殴りたい。
この人は、いつだって私の事を大切にしてくれていたのだ。
「この前新しくオープンしていた店を見つけたんだが、時間が無くてな…日を改めた今日行ってきたんだ」
『でも、何でマロングラッセを…?』
「意味があるんだよ」
『意味…?』
「その前に」
ロイは私の目の前に先程渡した箱を置いて、私の横へと詰めて座った。
「バウムクーヘンの意味を教えてくれ」
『えっ!知ってるんじゃ……!』
「ななしの口から聞きたい」
ぐっと顔を近付けられて、顔が熱くなる。
恥ずかしくて下を向こうとした私の頬をロイの手が優しく包んで上へ向かせる。
「ななし」
ロイの熱い眼差しに胸が高鳴る。
『……永遠の、愛』
小さくぽつりと呟けば、それを合図かのようにロイに抱きしめられる。
驚く暇もなくキスをされて、また抱きしめられた。
腕の中で目を閉じればロイの鼓動が聞こえて。
『…ロイ、ドキドキしてる』
「愛してる女性から永遠の愛なんて貰えたんだから、そりゃドキドキくらいするさ」
ゆっくりと離れて、最後にまたキスをされる。
「マロングラッセの意味は、永遠の愛を誓う証。私も君に永遠の愛を贈るよ。そしてそれを絶やさない事をここに誓おう。」
少しだけ照れ臭そうに笑ったロイを見て、全身から火が出るんじゃないかってくらい熱くなってしまった。
『わ、私なんかに永遠の愛を誓っていいの』
「ななしだから誓ったんだ」
『…まるでプロポーズみたい』
「ななしだってそうだろう?」
…たしかに、そうかも
深く意味を考えていなかった私は、思わずロイに抱きつく。
「その反応…深く考えてなかったな?」
『う…で、でも、意味はそのままだよ!私はこの先ロイしか愛せないから……あっ!』
しまった、と言わんばかりに手で口元を覆うけれど一歩遅かったようで。
両手を掴まれて口元から離され、そのまま少し強引にキスをされた。
「私もこの先ななししか愛せない」
『…っ!!』
耳元囁かれたその声は、聞いたことがないくらい重くて甘くて…私の身体中に電気が走ったような感覚に陥らせる。
「愛してる」
そう呟いてロイは私の額にキスを落とした。
ふと目が合った時、お返しだと今度は私から唇を寄せる。
『わ、私だって愛してる』
恥ずかしいけれど同じ言葉を言えば、ロイは顔を赤くして私の首筋に顔を埋めた。
『…赤くなったね』
「……うるさい」
『バウムクーヘンの意味伝えたとき、喜んでたよね』
「…」
『あとは、泣いたら完璧…』
突然腰と頭に手を添えられ、身体を押されてそのままソファに倒れ込む。
本当に突然の事で驚いていると、着ていた軍服の上着を器用に脱がされ、キャミソール一枚になる。
『えっ』
今度は下も…と言わんばかりに手を伸ばすロイの腕を掴む。
『な、なにして』
「啼くのはななしだろう?」
にっこりとした笑顔を向けられて、ぶるっと身体が震えた。
『それ、絶対意味が違う……!』
最初は少し抵抗したけれど、キスをされたら力が抜けてしまうもので。
深いキスをされてるうちに脱がされたようだった。
…ま、いっか
なんて頭の片隅でぼんやり考えながら、ロイの愛を全身で受け止める様に私は目を閉じた。
2018/12/04
綺麗な夜空の下。
私は、ロイと二人で棲んでいる家を前にして唸っていた。
手元にある少し大きな箱を見つめて。
事の発端は、今日の夕方なのである。
今日も今日とて仕事が山積みだったのだけれど、とても大切な用事があると皆に告げたロイが、見たことの無い速さで仕事を片付けたのだ。
そして、夕日が完全に落ちる前に仕事終了……解散となった。
『ハボック、感動のあまり夕日みて泣いてたな…』
帰り道である街の中を歩く。
…ロイの用事とは何なのだろうか。
大切な用事………女性関係なのかな、なんて考えてしまうけれど…
先に帰っててくれ、なんて言われて珍しく一人で歩いてるわけで。
少しだけ落ち込んだ気分で歩いていると、ふと目に入る小さなお店。
『焼き菓子…専門店?』
はて、こんなところにお店なんてあっただろうか?
思わず足を止めて、お店をじろじろと見てしまう。
そこで店内に居た女性と目が合い、会釈される。
『…入ってみようかな』
こちらも会釈して、扉を開けた。
ふんわりと甘い香りが鼻を擽って、つい頬が緩んでしまう。
「いらっしゃいませ、何かお探しでしたか?」
『あ!いえ…ここにこんな良いお店あったかな、なんて考えてて…』
「あら、嬉しいことを…開店してまだ日が浅くて」
なるほど、だから気づかなかったのか
なんて考えつつ店内を見渡す。
折角だし何か買っていこう
「見たところ、軍人さんかしら?こんなに可愛らしい方もいらっしゃるのね」
『そんな…お世辞でも照れちゃいます』
店員さんは、綺麗に微笑んだ後何かを嗅ぐような仕草をした。
咄嗟に自分の服の臭いを確認する。
『ご、ごめんなさい、汗臭かったですか?』
「いいえ、違うの。この匂い………もしかして、恋人とかいらっしゃる?」
『えっ!?』
どきり、と胸が鳴って同時に自分の顔が熱くなるのを感じた。
「やっぱり!」
『な、なんで…』
「ふふ…私って鼻が良くて…あなたから、恋をしている甘い香りがしたから」
『ど、どういう…!?』
慌てている私を横目に、店員さんは目の前のショーケースにあるバウムクーヘンを指差す。
「これ、恋をしている方にぴったりなケーキなんです」
『恋をしている人に…?』
バウムクーヘンに意味などあったのだろうか…
そう首を傾げると、それが店員さんに伝わったようだ。
「バウムクーヘンには、凄く素敵な言葉が込められているんですよ。それは……」
『……!』
耳打ちで教えられたその言葉に、思わずごくりと喉が鳴った。
「素敵だと思いませんか?」
『たしかに素敵です…でも、意味がばれちゃったら少し恥ずかしいですね…』
「でも、確実にあなたの気持ちは届きますわ。きっと意味を知ったら、恋人の方は大喜びするんじゃないかしら」
ロイが大喜び…!?
「もしかしたら、顔を真っ赤にしてしまうかも」
ロイが顔を真っ赤に……!
「それとも、嬉しくて泣いてしまうかしら?」
ロイが……泣く…!?
『それ、買います!!』
と言うわけで現在に至るのだが。
『ロイの反応見たさに買ってしまった……』
絶賛後悔中の私は、中々家に帰れずにいた。
ロイならきっと、こういう贈り物は他の女性から沢山受け取ってきた筈だし…からかわれるに決まってるのだ。
バウムクーヘンが入った綺麗な箱を見つめて、ため息を溢す。
美味しそうだったし、一人で食べちゃおうかな…
ロイに見つかる前に食べてしまえば証拠隠滅になる!
『……よし!』
「ななし?」
『…!』
箱に手を掛けたその時、家のドアが開くと同時に声を掛けられた。
それは勿論、私の恋人なわけで。
ケーキの箱を持ってダラダラと汗を流す私は、端から見たらかなり変な人なのだろう。
「人の気配がしたから来てみたら……中に入らないのか?」
『えっと、入ります……』
ケーキの箱を隠すように持ってゆっくりと家に入ると、扉を閉めてくれたロイが後ろから私を覗き込んだ。
「ななし、何か変だぞ…………その箱」
『うっ……』
隠そうにも中々隠せない大きさの箱は、直ぐに見つかってしまった。
『…っあー!もうヤケだ!これ!あげる!!』
ロイの前に箱を突き出す。
半ば反射的にそれを受け取ったロイは、少しポカンとしたように私を見つめていた。
「これは」
『かっ帰り道!新しいお菓子屋さん!買ってきた!』
箇条書きのような言葉を紡いで下を向く。
上の方から開けて良い?と声が聞こえて、ここで?と思ったけど頷いた。
「バウムクーヘン…」
『いっ意味…分かっちゃったり、する…?』
「…ななしは分かっているのか?」
『う、うん…』
うるさいほど鳴る胸を押さえながら顔を上げる。
ロイは私を真剣な眼差しで見つめていて、思わず肩を下げてしまった。
『お、大喜びしてない……』
「は?」
『顔真っ赤にしてない……泣いてない…』
「急になんだ」
『やっぱり、貰いなれてるんだ……からかわれるんだ…』
「…なるほど?大体理解した」
ロイはバウムクーヘンを箱に戻して、私の肩を優しく包むように抱いた。
「これは、ななしの素直な気持ちとして受け取って良いのかな?」
『そ、それは、まあ……そ、そうだけど…』
思わず赤くなる私を見たロイに連れられて、リビングへと行く。
待っててと言われソファで待っていると、ロイはキッチンから少し小さな箱を持ってきた。
『あれ…その箱…』
「やっぱり、同じ店だな」
同じロゴの箱。
いつの間にロイも行っていたんだろう。
「開けてごらん」
そう言われて箱をゆっくりと開ける。
『これは……?』
中に入っていたのは、キラキラと輝く粒。
「マロングラッセだよ」
『マロングラッセ……?』
「ななしへのプレゼントとして、今日買いに行ったんだ」
『じゃあ、大切な用事って……』
女性関係だと思っていた数時間前の私を殴りたい。
この人は、いつだって私の事を大切にしてくれていたのだ。
「この前新しくオープンしていた店を見つけたんだが、時間が無くてな…日を改めた今日行ってきたんだ」
『でも、何でマロングラッセを…?』
「意味があるんだよ」
『意味…?』
「その前に」
ロイは私の目の前に先程渡した箱を置いて、私の横へと詰めて座った。
「バウムクーヘンの意味を教えてくれ」
『えっ!知ってるんじゃ……!』
「ななしの口から聞きたい」
ぐっと顔を近付けられて、顔が熱くなる。
恥ずかしくて下を向こうとした私の頬をロイの手が優しく包んで上へ向かせる。
「ななし」
ロイの熱い眼差しに胸が高鳴る。
『……永遠の、愛』
小さくぽつりと呟けば、それを合図かのようにロイに抱きしめられる。
驚く暇もなくキスをされて、また抱きしめられた。
腕の中で目を閉じればロイの鼓動が聞こえて。
『…ロイ、ドキドキしてる』
「愛してる女性から永遠の愛なんて貰えたんだから、そりゃドキドキくらいするさ」
ゆっくりと離れて、最後にまたキスをされる。
「マロングラッセの意味は、永遠の愛を誓う証。私も君に永遠の愛を贈るよ。そしてそれを絶やさない事をここに誓おう。」
少しだけ照れ臭そうに笑ったロイを見て、全身から火が出るんじゃないかってくらい熱くなってしまった。
『わ、私なんかに永遠の愛を誓っていいの』
「ななしだから誓ったんだ」
『…まるでプロポーズみたい』
「ななしだってそうだろう?」
…たしかに、そうかも
深く意味を考えていなかった私は、思わずロイに抱きつく。
「その反応…深く考えてなかったな?」
『う…で、でも、意味はそのままだよ!私はこの先ロイしか愛せないから……あっ!』
しまった、と言わんばかりに手で口元を覆うけれど一歩遅かったようで。
両手を掴まれて口元から離され、そのまま少し強引にキスをされた。
「私もこの先ななししか愛せない」
『…っ!!』
耳元囁かれたその声は、聞いたことがないくらい重くて甘くて…私の身体中に電気が走ったような感覚に陥らせる。
「愛してる」
そう呟いてロイは私の額にキスを落とした。
ふと目が合った時、お返しだと今度は私から唇を寄せる。
『わ、私だって愛してる』
恥ずかしいけれど同じ言葉を言えば、ロイは顔を赤くして私の首筋に顔を埋めた。
『…赤くなったね』
「……うるさい」
『バウムクーヘンの意味伝えたとき、喜んでたよね』
「…」
『あとは、泣いたら完璧…』
突然腰と頭に手を添えられ、身体を押されてそのままソファに倒れ込む。
本当に突然の事で驚いていると、着ていた軍服の上着を器用に脱がされ、キャミソール一枚になる。
『えっ』
今度は下も…と言わんばかりに手を伸ばすロイの腕を掴む。
『な、なにして』
「啼くのはななしだろう?」
にっこりとした笑顔を向けられて、ぶるっと身体が震えた。
『それ、絶対意味が違う……!』
最初は少し抵抗したけれど、キスをされたら力が抜けてしまうもので。
深いキスをされてるうちに脱がされたようだった。
…ま、いっか
なんて頭の片隅でぼんやり考えながら、ロイの愛を全身で受け止める様に私は目を閉じた。
2018/12/04