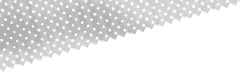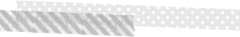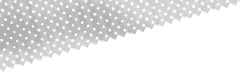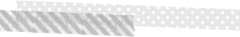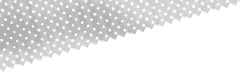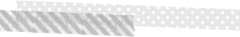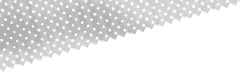
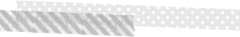
※書きたい所だけを書くSS詰め合わせ落書きシリーズ。
窓際の席で、お客様が外を眺めるその光景を不思議に思うようになったのは何時からだろう。
あのお客様は何時から乗車されていたのか、
(もう何日も揺られている‥)
頬杖をつきながら何をする訳でもなくただ外を見続けているだけ。この列車に乗り込んだという事は何処か向かいたい目的地がある筈なのに、あのお客様は。彼は、乗り込んで以来ずっと同じ場所から外を見ている
「失礼しますお客様。乗車券はお持ちですか?」
「‥‥」
「お客様?」
「‥え?」
「突然声をかけてしまって申し訳ありません。記憶違いでなければ何日も此方に乗っていらっしゃるので、一度目的地の確認をさせて頂いた方が宜しいかと思いまして」
「‥目的、地?」
「はい。乗車されているという事は何処かへ向かう途中だったのですよね?」
「‥‥俺は、‥いや待て。此処、は‥何処だ?」
ー ー ー ー ー
「なるほど。記憶が曖昧で自分が誰か、何故此処に居るのかが分からないと‥」
「ああ、」
「ふむ‥それは、困りましたね」
本人が目的地を忘れている以上、送り届ける先が分からない。かと言って、乗客として乗り込んで来ている彼を追い出す事も出来ず。
何より、
行き先が分からない。進むべき道を見失っているという状況下に置かれ困惑している気持ちは自分も知っている。痛い位に良く分かる。だから、彼が行き先を思い出すまでは一緒にいよう
そう思った。
「貴方の事は、必ず‥自分がきちんと“正しい場所”まで送り届けますと約束します。ご安心下さい」
ー ー ー ー ー
(どの位ホテルの方へ戻っていないのだろう)
兄弟達に会えなくなってかなりの時間が経って、皮肉な事に体調の面ではかなり楽になった。
何をしていても酷く眠いという一番悩まされていたあの症状がめっきり落ち着いている。今では一週間程度であれば寝ずに行動が出来る程にまで回復した。それでも、
(‥スピードマウス‥赤、青‥)
自分の体調が改善されてきている嬉しさよりも、大事に思っていた兄弟達に会えなくなった寂しさの方がうんと強い。
迷界に帰らずに向こうと連絡を取り合う手段が自分にはないのだ。だから、弟達が元気にしているのかも分からない。自分の仕事が長引いているだけだと、暫く帰れていないが心配しないで欲しいと。たったそれだけ伝える事さえ叶わない
「‥はぁ‥」
「何溜め息なんて吐いてるんだ車掌さん」
「‥お客様‥いえ。何でもありませんよ。それよりも、自分に何か用事でしょうか」
「いや。ただ、最近のあんたは元気がなさそうだと思ってな。ちょっと気になってたんだ」
彼に悟られたのは少しばかり長く一緒に居たからなのだろうか、それとも。そんなにも自分の気持ちが分かりやすく表に出ていたのだろうか。
ー ー ー ー ー
ふーっ、と。此方に向けて口から吐き出された煙に思わず咳き込んだ。
「っ、‥お客様。この列車は全車両禁煙です」
「‥怠い」
「体調不良ですか?であれば尚の事煙草は控えるべきかと」
「いや、此処から移動するのが怠い」
「‥お客様‥」
何時の間にやらすっかり定位置になってしまった特定車両の座席の窓側。そこから窓の外を眺める乗客の彼と、声をかける車掌の自分
「‥せめて窓を開けて下さい‥今は他のお客様がいないので許可しますが。次は車内での喫煙は控えて下さいね」
「‥‥んー‥」
ー ー ー ー ー
「車掌さん、これ。こないだのお詫び」
「え」
「あんた時々部屋でペン立て‥っつーか、これ見てるから好きなのかと思って」
それは以前、まだ幼い妹の赤と弟の青が整備士達の手伝いをして貯めたお小遣いで買ってくれた物で。中身が無くなってからも捨てることが出来ず、洗った後にペン立てとして使う為机の上に置いてある物。だが、それよりも。
「勝手に車掌室を覗かないで下さい」
「え、あそこ車掌室なのか?俺の知ってるのと随分違っていかにも普通の部屋っぽいのに」
「そうですよ。貴方がいつの間にか覗いていたその普通っぽい部屋が車掌室ですよ。と言いますか、次回からヒトの部屋を開ける時はノックをして下さいね」
「はいはい。分かったよ車掌さんごめんね」
「全く‥それよりお客様、これを何処で?貴方はこの列車から一度も降りていませんよね。何故この缶詰を持っているのですか?」
「何故って、丸い耳の付いたキャスケットを被ってる車内販売のガキから買ったんだよ」
「この列車で働いているのは、仕事をしているのは自分ただ一人です。他の方は誰も“労働”をしていません。勿論、車内販売員もおりません。‥ましてや、子供を働かせるなんて‥そんな事は‥」
「え、じゃあの、顔がツギハギの‥」
「か、顔が‥ツギハギ、の‥?」
「‥‥‥俺、何か変なものを見たのかも知れない。‥車掌さんソレ、その桃の缶詰食べない方が良いよ」
ー ー ー ー ー
本日の業務も無事に終了。“トラブル”が多く何時もより疲れが出ている
(そういえば、)
一週間程前に渡された桃の缶詰があった事を思い出したので夜食の意味合いも兼ねて食べさせて貰う事にした。
机の上にあった缶詰を手に取り、プルタブに手をかける。すると部屋のドアをノックする音が。
「車掌さん。入るぞ」
「おや。どうされましたかお客様」
「今夜は少し冷えるから毛布があれば貸して欲しいと思って‥って、それ、食べたら呪われる缶詰」
「こちら何時から曰くつきの缶詰になったんですか」
「俺が変なものを見た日から」
「そうでしたか。今から開けようと思っていた所なのですが、もし宜しければ御一緒に‥あ」
まだ開けていない缶詰を、開ける前に取り上げられた。危ないかも知れないと言って。
「大丈夫です。見た所普通の缶詰ですよ」
「けど、もしかしたら呪われ、」
「ないです。大丈夫です」
変なモノにはそれなりに敏感な方だ。けれども缶詰からは特におかしな感じはしない。寧ろ、これは絶対に大丈夫だという確信が不思議とある位。
「なので、今から開けようと思うのですが御一緒にいかがですかお客様」
気を取り直してもう一度誘ってみると、お客様は少し悩むように。困ったように眉を寄せた後。缶詰を手元に返してくれた。
「まぁ、俺も小腹、空いてきたし。何かあっても二人で食べてたら呪いも半減するだろうし」
何やらいらぬ心配をしてくれているお客様。その雰囲気が、不器用なのに妙に過保護な気遣いの仕方が何処となく。明るい寒色をした一番年の近い弟を思い出させるもので
「何笑ってんだ」
「いえ何でも」
缶詰を食べる前から何だか仕事の疲れが緩和されたような。そんな気がした。
ー ー ー ー ー
「車掌さんって若く見えるけど幾つ位のヒト?」
「自分ですか?二十六です」
「じゃあ俺より年下か年上、若しくは同い年か」
「はい?」
「俺、自分が幾つなのか思い出せてないからあんたの年齢を参考にある程度の目安をと思ったんだけど。正直全然参考にならなかった」
「はぁ」
何時もの窓際の席に、今日も一人で座るお客様。どうやら相変わらず何も思い出せてはいないらしい
「ある程度の目安で良いのなら恐らく二十代半ば‥から、いってても三十代前半辺りだと思いますよ」
「そう見える?」
「自分から見ての感想になりますが十代ではなさそうですね」
「ふぅん。そっか。‥そう見えるのか」
それきり黙り込んでしまったお客様。
「‥俺は、自分の年齢すら分からない」
一体何処の誰なんだろう。
聞こえるか聞こえないか程度の大きさで、独り言のように呟かれた言葉に
「‥分かりません」
それ以外返す言葉を、かけられる言葉を、持ち合わせてはいなかった。
ー ー ー ー ー
「なぁあんた、名前は?家族は?恋人はいるか?」
「名前はトレインです。誰とも血縁ではありませんが父と母。それと弟が二人、妹が一人います。恋人はいません」
「へぇ、複雑な家庭の長男か。恋人、は‥まぁ‥そうか。アレだ。あんたの場合性格でカバー出来る程度の見た目では、‥いや‥うん‥‥良くも悪くも“普通”だし、多分‥」
された質問に答えると、見た目の評価をお客様が口にする。その評価は、時折誰かに言われるものと全く同じで
他人の目から見た自分の容姿は、平均以上の評価をつけるにはかなり難しいもののようだ。
「それより長男。あんた俺に付き合ってるせいでかなり長い事帰れてないだろ。家族は良いのか?」
「‥それは、」
「自分が何処の誰で、行き先も分からない俺なんか放っておいてくれて良いんだぞ」
とは言うものの、彼は間違いなく自分の列車に乗り込んで来た乗客であり。この列車に乗った以上は彼を送り届けるのが車掌である自分の役目であり。更に言えば記憶の欠落の仕方が何処か似ている彼を放っておく事は自分には出来なくて。
「約束したじゃないですか。貴方の事は、きちんと送り届けると」
あの時の自分のように、行き先の分からぬ不安の中。貴方を一人放り出すような事は、決して───。
ー ー ー ー ー
「車掌さん暇。相手してくれ」
「すいませんお客様、自分は只今業務の最中でして‥」
トランプのカードを此方に見えるように持ったお客様から声をかけられる
だが生憎とまだ仕事の真っ最中なので相手をする事は出来ない。
「乗客が車掌さんに構ってもらえなかった結果、暇過ぎて死んでも良いのか?暇な乗客の相手をするっていう項目を業務内容に追加してくれ今すぐ」
「‥また随分と無茶なクレーマーのような事を‥」
「さっきの駅で降りた客が忘れてったみたいでさ。せっかくなら使ってみたいだろ」
「おや。他のお客様の忘れ物ですか?ではそれは此方でお預かりして‥」
「いいだろ別にトランプ位。こんなのいくらでも代わりは買えるって」
「ですが」
「良いって良いって、ほら。あっちあっち、あっちに行こう」
何時もの席、何時もの窓際に座っていたお客様はトランプを片手に座席から立ち上がると、
「あんたの部屋で遊ぼうぜ」
そのまま強引に、車掌室である自分の部屋に連れて行かれた。
「トランプやるならテーブルが必要だと思ってな」
「そうですか」
「だからいい感じのテーブルがある部屋に来た」
「テーブルではありません。これは机です。引き出しが付いているでしょう?」
「うん、ついてる。けどどっちだって良いよ。結局は似たような物だ」
「分かりました。確かにどちらも似たような物です。ですが‥まさかそれを許可もなく勝手に移動させられるとは思いませんでしたよ。しかも部屋の真ん中に」
「壁際に置いてあったら向かい合えないだろ」
「それはそうですが」
「負けた方が勝った方の言う事を何でも一つ聞くこと」
「嫌です」
「何でだよトランプのルールだと常識だろ」
「え‥そう、なのですか‥?」
「‥‥‥そうなんだよ」
返答までに妙な間があったので恐らく嘘なのだろう。けれど、部屋まで強引に連れてこられ物の配置まで変えられた事を考えると
彼の提案した条件を飲まないと、この遊びを終わらせてはくれないような気がしたので
「‥わかりました。一回だけですよ」
仕方なくおかしなルール付きでのトランプ勝負を一度だけ。そして、決着の方はわりと早めについた
「‥弱すぎか?」
「すいません。あまりトランプで遊んだ事がなかったので‥」
「あー‥それ何となく分かる。あんた、遊び全般殆どやった事がないタイプだろ。真面目に仕事だけして生きてる感じがする」
「良くわかりましたね」
「つまらないだろ、そんなの。もっと遊んだ方が良いぞ。という訳で。俺の言う事を一つ聞くって話しだけど」
「はい」
一体どんな事を言われるのか検討もつかないけれど、あまり変な事ではないと良いのだが。そう覚悟を決めて聞いた言葉に
「俺と友達になってよ車掌さん」
理解が追いつかなかったので返事をし損ねてしまった。
「家族も恋人も居なくて自分の事も良く分からないんだ。せめて友達位は欲しいだろ‥って、話し聞いてるか?」
「あ。はい聞いてます」
「俺とあんたと、多分そんなに年も離れてないっぽいし」
嗚呼、あの時年齢を聞かれたのには彼自身の見た目確認以外にも意味があったようだ。
「ですが友達というものは、こういう風に強制をして作るものではないと思います」
「だってこうでもしないと、あんたは俺を“そういう”目線で見てくれないだろ。仕事馬鹿なんだから」
「‥成る程」
「ほら。な?だから、友達になってくれよ。俺と」
「わかりました。では貴方とは今日から友達です」
「ありがと。宜しくなトレイン」
「此方こそ宜しくお願いしますお客様」
そう返せば『あー‥』と言葉を漏らし頭を抱え、お客様は項垂れた
「そうだ‥今の俺、名前がないんだった。‥せっかく友達になったのにお客様はあんまりだろ‥この際あだ名でも何でも良いから別の名前で呼んでくれ」
「かしこまりました。それでは、そのあだ名を教えて頂いても?」
「ある訳ないだろ。何も覚えてないし、この車内では俺、あんた以外とは話さないんだから」
「では何と呼べば良いでしょう」
「そうだなぁ‥せっかく友達になったんだし。あんたが決めてくれないか」
「‥!」
それは少し、いや、かなりの難題だ。他人の呼び方を一から決めないといけない日が来るとは思わなかった
そもそも、何かに名前をつけた事がない。こんな事なら、日頃から手持ちの品物に愛称でもつけておくべきだったのだろうか。
初めての名前決めでいきなりお客様に名前をつけるのは、それは。自分にはとても、
(荷が重すぎる)
ー ー ー ー ー
「それ、何で明かりがついてる所でも消さないんだ?」
すっかりお客様の『何時もの場所』になってしまった座席シートのある車両の通路を歩いていると、指差されたのは何時も腰から下げているこの列車に似せて作られたランタンだ。
中にあるのは自分の割れたタマシイ。所謂半身。これは好きで明るく光っている訳ではなくて、自分が生きている限り勝手に明かりを灯してしまう物で
「消さないのではなく、消せないんですよ」
「何で?」
「それは‥」
「それは?」
「‥どうしても消すとなれば、命と引き換えになってしまいますので」
真面目に返したけれど、冗談だと受け取られたらしくお客様は珍しく笑っていた。
「あんたの命で灯ってる、か。綺麗だな、その明かり」
「ありがとうございます」
彼には、この中に入っているタマシイは見えていない。ランタンが明るいという認識は出来ても中にあるのが割れたタマシイだと、“人間”である彼には分からないだろう。
仮にもし中身のタマシイが見えたとして、そのタマシイが“割れている”と判断出来るヒトは今までほんの数人しか出会った事がない。タマシイを“きちんと視る”というのは、とても難しい事なのだ。
この先彼がランタンの中身を視る事はきっと一生ないけれど。それでも何時か本当にタマシイが、命が入っているという事が冗談ではないと彼に伝われば良いのに。
そんな風に、思ってしまった。
「仕事の邪魔したな。俺、今から寝るから。おやすみトレイン」
「おやすみなさいお客様。良い夢を」
今は自分以外には彼一人きりしか乗っていない車両の明かりを消して、自分は引き続き何時もの業務に戻る事にした。
ー ー ー ー ー
今日、お客様から思いがけない事を言われた。
「トレインってネズミ好きなのか?」
「ネズミ‥?え、何故」
「何故、って。ぼーっとしながらこの間呟いてたから」
業務中にぼんやりしていた事の指摘より、ネズミと呟いた記憶がない事に困ってしまった
無意識に呟く程好きな物ではない。それに、ネズミと聞いて一番はじめにピンとくるのは“雇い主である彼”で。寧ろ、狂気の大元とも呼べる彼は少し苦手な部類であり
「ネズミに対して‥普通以外の感情は特にありませんが」
「そうなんだ。何かちょっと変わったネズミの名前だったから、どんなネズミか気になってたんだけどな」
「変わった?」
「何だっけな‥ネズミっつーか、何とかマウス?」
「それは‥」
ネズミと言われてピンとは来ないが、そちらの呼び方に変えられると途端に思い当たる節が出て来た。
「多分、兄弟の事かと」
「兄弟?誰の」
「自分の」
「じゃあまさか、あんたもネズミなのか?」
「いえ。いいえ、以前話したじゃないですか。血縁ではない兄弟がいると」
「ああ、確かに何か言ってたかも」
「弟達の名前に『マウス』が入っているので恐らくそれではないでしょうか」
「‥トレインとネズミが、兄弟‥」
じと、と。訝しむように見られてしまう。はてさて、一体何を、どこからどうやって説明していくべきだろうか。
ー ー ー ー ー
「あのさ、前から思ってたんだけど」
「はい何でしょうか」
「何ていうか似合わないよ、これ」
そう言いながら伸ばされた手は、耳についている装飾品を軽く触れてくる。
「似合いませんか」
「見た目の問題じゃなくてさ。ガラじゃないっていうの?トレインは、こういうの興味なさそうだから」
「嗚呼‥成る程、そういう事ですか」
興味があるか、ないか、その二択しか与えられていないのであれば答えは確かに後者である。
けれど、
「右と左と。二つあるなら一つ俺に、」
「駄目ですよお客様」
だからと言ってこれを手放す事が出来るかと言われれば、答えはノーだ。
軽く触れていた指が耳から装飾品を外そうとする動きに変わったので、緩く押し返して拒否を示す。
「貴方の言う通り自分は装飾品にそれほど興味はありません。ですがこれは大切な方からの頂き物なので、あげられません」
「大切な‥誰、」
「弟です」
「弟‥また弟‥あんた思いの外ブラコンの気が強い」
「そう、でしょうか」
「うん」
「‥あの。今つけている物はあげられませんが似たようなので良ければ弟に頼、」
「ホラまた弟。別にいらないよ。あんたがつけてる物で、耳のやつが二つあったから一つなくなっても困んないかと思っただけだから」
「それはつまり。これが欲しい訳ではなく“自分”の持ち物が欲しい、と?」
「え、あー‥まぁ。そんな所」
スピードマウスに貰ったイヤーカフは渡せないが、他の物でも良いのなら何かなかっただろうか。
ポケットの中に手を入れて、チャリ、と。鎖の擦れる音が聞こえて取り出した
「‥此方でも構いませんか?」
「こちら、って、何。この高そうな懐中時計」
「時計の価値は分かりませんが貴方が先程の物ではなく、これでも良いと言うのなら差し上げられますが‥どうします?」
何時から持っていたかはあまり覚えていないが、今日までずっと使ってきた物ではある。
壊れていないのを知っているからこそ、これでも良いのならと取り出したのだが
「や、いや待て。こんな‥いかにも大事そうな‥」
「何を大切に思うかは人それぞれですよ。自分は、この時計なら差し上げても良いと思えたのでこうして出しているんです」
「‥‥あんたが良いって言うなら、じゃあ‥」
少し悩んだ様子を見せた後、此方の手に乗っていた懐中時計を受け取るお客様
「‥大切にする」
「ええ、そうして頂けると自分も嬉しく思います」
きっと彼はあの時計を大切にしてくれるだろう。何故かは分からないが強くそう思えた。そうして、少しばかり軽くなったポケットを擦る。
物自体は渡しても良いと思っての事なので、今のやり取りに後悔はないけれど。やはり時間が分からないという点に関しては車掌としてかなりの問題だ。
(次の駅で停まった時にでも、新しい時計を探さなくてはいけませんね)
ー ー ー ー ー
そろそろ候補とか位は出来たのか。そう問いかけられて、動きが止まった
「候補というのは、」
「俺の名前」
「‥申し訳ありませんお客様、どうにもかなりの苦手分野でして」
名前、もしくは愛称。それを考えて欲しいと言われてからそれなりの日数が経っている
そして自分は、未だに目の前のその課題をクリア出来てはいなかった。
「そんな難しいもんかね」
「とても難しいですよ。自分の名前を思い出して貰う方がよっぽど簡単な気がします」
「いや無理、何も思い出せない。此処にどうやって乗り込んだかすら思い出せない」
「では相変わらず行き先の方は」
「駄目、どこに行きたくてコレに乗り込んだのかもさっぱり分からない」
「そうですか」
性別以外何も判明していないと言っても過言ではない彼をこの列車に乗せてからもうどの位か。行き先が分からないまま降ろしてしまっては直ぐに“消えてしまう”だろうから、きちんとした目的地が判明するまでと思い乗せ続けてはいるものの、彼は一向に行き先が分からないとの一点張り。
「困りましたね」
「困ってんの?」
「ええ、はい。とても。貴方を送り届けないと自分の仕事は何時まで経っても終わりを迎えられません」
「あー‥ごめん。それに関しては本当に悪いと思ってる‥けど、」
「思い出せない事を責めている訳ではありませんよ」
自分だって、相も変わらず何も思い出せていないのだ。そんなヒトが他人にどうこう言える訳がない。
自分の事が分からない。何処から来て、何処に行きたかったのか。
自分も、彼も、ずっとずっと。迷子なのだ。
「もし、もしも貴方がこの先今と同じように何も思い出せないのであれば」
「ん?」
「この列車の乗務員にでもなってもらいましょうかね」
この列車には自分以外の働き手はいない。だからと言って人手が足りないと感じた事はないが、この先状況が変わらないようなら。
名前を持たない彼を迎え入れても良いと、そう思うようになっていた。
ー ー ー ー ー
(おや?)
何時ものお客様が、何時もの席から居なくなっている事に気がついて首を傾げる。
彼は何処に行ったのだろうか。
目を閉じて、意識を集中する。
(彼は‥ああ、居た。最後尾、展望デッキ‥)
つまるところ、外である。気分転換でもしているのだろうか。
それとも、もしかしたら具合が悪く風に当たっているのかも知れないので、念のため様子を確認しに行くと。見つけたお客様は手摺部分に片方の手を置いて、もう片方の手には煙草を一本。
「喫煙中ですか」
「トレイン。ああ、どっかの車掌が中で吸うと煩くてな」
「それ、“自分”の事ですよね」
「あえて濁してんのに名乗り出るなよ」
ふ、と。小さく笑みを浮かべている所を見る限りただの一服のようだ。
「ここにはあまり長く居ない事をオススメします」
「なんで?」
「何故って、今夜は特に寒いですから。直ぐに体が冷えきってしまいますよ」
「けど、寒いと星も良く見えるんだぜ?知ってたか?」
「‥星?」
あまり気にした事はなかったが、言われて上を見れば成る程確かに夜空に幾つもの星がハッキリと輝いている
「もう少し見てたいんだ」
「分かりました。それでは、また後、でっ?!‥な、何を‥?!」
「“貸してくれ”」
グイグイと、半ば無理やり引き剥がされたのは羽織っていた外套。
「後で返す」
少し意地悪そうに口角を上げて、自分から取り上げた外套を羽織り煙草に口をつけている
「お客様っ」
「あんたが言ったんだろ。ここに居たら体が冷えるって。ほら、あんたはさっさと中に戻りな」
しっし、と。さも、邪魔だと言わんばかりにお客様の手が払い除けるような動作で動く。
「‥必ず後で返して下さいね。それがないとランタンの明かりが隠せないので」
「わかったわかった」
全くこのお客様は何故、何時もこうなのだろう。元々他人の気持ちは良く分からないが、彼の気持ちや行動を読むのは尚のこと自分にとっては難しい。
「トレイン」
「はい‥っ、つ?!」
「あんた、煙草の煙。ものすごーく苦手だよな」
そう思うのならどうして直接紫煙を吹きかけようと思うのか
本当に。
「‥貴方の行動は理解するのが難しいです‥」
それでも、これがこの人、このお客様なのだと納得して諦めてしまう位には。
他のお客様よりも彼の方が“分かりやすい”と思う所まで来てしまった。
「あー、流れ星。仕事ばっかのトレインがゆっくり休めますように」
「‥なら、先ずは貴方の問題行動をどうにかして頂けると此方としては非常に有り難いのですが」
「ん?それはそれ、これはこれ」
「‥‥貴方って人は‥」
ー ー ー ー ー
「トレイン、トレインちょっとこっちに来い」
「どうしました?」
「どうしましたじゃないだろう。あんた、顔が赤いぞ‥ああほら、やっぱり熱がある」
呼ばれて近くに寄れば手を額に当てられる。
「こないだ俺が外であんたの外套取ったからか?」
「まさか。そんな事位では発熱しませんよ」
「でも現に熱出してるだろ。ずっと見てて思ったけど、あんた間違いなく働きすぎだぞ」
働きすぎ、と。言われても自分にとってはこれが普通で。仕事がなかったら何をすればいいか分からない
「とりあえず今日は部屋で寝てろ」
促されるまま自室に押し込まれ、『ちゃんと温かくしておけよ』と念を押される。それに対して分かっていますよと返事をすれば、分かってるなら良いんだ。と。
「‥なぁトレイン。あんたが前に言ってた乗務員の件。あれ、そろそろ前向きに検討してくれても良いから」
「‥え」
「そしたらさ、こういう時。俺もちょっとは手伝えるだろ?」
そう言ったお客様が何処か少し寂しげに見えたのは気のせいだろうか。
「じゃあ、良い子にしてゆっくり寝てろよ」
おやすみ、という言葉と共に部屋のドアが締められる。
既に部屋から居なくなってしまった相手に届かない事を分かりきったうえで、
「‥子供では、ないのですが‥」
そう呟いた。
ー ー ー ー ー
「おはようトレイン」
「夜ですよ?」
「けど、お前が起きたのは今なんだろう?なら、おはようであってる。違うか?」
「‥違い‥ませんね。おはようございます」
「ん。それで、少しは熱下がったか?」
前回同様、手を額にあてられ体温を確認される。
「うん、下がってそうだな。良かった。あんまり無理すんなよ」
「‥‥はい」
心配させてしまい申し訳ないと思う気持ちと、体調不良の原因がわかっているだけに素直に返事が出来ない事と。
複雑な気持ちが自分の中でいっぱいになりつつ、今日も今日とて。こなさなければならない仕事があるのだった。
ー ー ー ー ー
マズイかも知れない。そう思ったのは、目が覚めた後に感じた酷い怠さから。
もう長い事出しっぱなしにしている列車。行き先を思い出せないお客様を乗せている為、自分の中へとソレを戻せなくなっているせいでどうにも『列車であり車掌でもある自分』という概念が『車掌』の部分にのみ傾き始めているらしく
最近、列車その物との連携が非常に取りにくい。今の自分は、列車ではなく『車掌をしているただのヒト』という状態に限りなく近い。
(自分は、ヒトであると同時に機械の一部でもある‥のに‥駄目だ、制御が、利きにくい‥)
一度何処かの駅に停まって車両を取り込み、列車としての概念を取り戻すべきか。いや、けれどあのお客様を列車の外に出す訳にはいかない。かと言って、お客様が残っている状態では車体をナカに戻せない。
行き先が、進むべき道が決まっていないあやふやな状態であのお客様を外に出してしまったら、その場で消えてなくなってしまう可能性がかなり高い。それ程までに、現在の彼は弱々しい存在だ。
だからずっと“囲っていた”のに。
「トレイン、今大丈夫か?」
「どうかしましたか?」
「あのさ、向こうなんだけど‥変な扉が‥」
「扉?」
言われた場所までついていくと車両と車両の連結部に、普段とは違う見覚えのない赤黒くて不気味な扉が佇んでいた。
この先の車両に何時もお客様が座っている席がある。どうやら少し席を離れた間に戻れなくなったらしい。それで仕方なく車掌である自分を呼びに来てくれたらしいのだが
(‥入り込まれている事に気がつけなかった‥)
目の前の異質な扉に軽く目眩を感じた。これは『お客様』ではなく別の『ナニカ』だ。何処からか入り込んで根付いてしまったらしい
何時もなら直ぐに気づいてこうなる前に対処出来ていただろうに。こんな事にも気が付けない程自分の概念が狂い始めている。車掌であり、列車でもある事を前提として定義されたこの身体はどちらか片方に傾くだけでおかしくなる。段々と正常では無くなってきている。
自分が、このカラダが。ヒトとして弱り始めているのはこの間の体調不良で痛感済みだ。それに加えて様々な感覚も鈍くなっているせいで、
(これが害のあるものかどうかも分からない)
扉の周囲に張り巡らされた不気味で奇妙な太い根が、ドクン、ドクンと脈を打っている。恐らくコレは生物なのだろうが自我のあるものか、此処に在るだけのナニカなのか
「なぁこれ、根っこがドクドク動いてるし凄く気持悪いんだけどどうするんだ?」
「どうしましょうか‥見た限りではそれなりに侵食されてしまっていますし」
「それなりに?」
「この扉の向こうから全ての車両が」
「俺の指定席、あっち側」
「貴方が普段座っている座席は自由席ですよ。勝手に指定席にしないで下さい」
はぁ、と。息をついてとりあえず扉に触れてみる。
特に何も感じないけれど。自分ではない、受け入れてもいないナニカが“内側”にあるのは嫌な不快感がある。
不快感、と言っても。体調に直結するような感覚ではないので視覚から入ってくる情報。この根のグロテスクなビジュアルのせいだろうか。
とにかく見た目が“少しばかり”宜しくない。これはあくまでも個人的な感想だが、見ていて気分が良いものではない事はお客様の発言からしても明らかだろう。
明確な駆除方法は分かりかねるが、この扉より前に乗っているお客様達を一つの車両に集め待機してもらい、その間にどうにか引き剥がしていくしかなさそうだ。
「お客様、すいませんが少し離れて‥」
べちゃり、
言葉をかけながら後ろを向くと、顔に生温かいものが飛んできた。
扉から生えていた根の数本が蠢きながら物凄い速さで伸び始め、前の車両へと侵入していく。止めなければこの列車ごと根に覆われ完全に侵食されてしまう。でも、だけど、
動けなかった。
数本の内一本がお客様の体を貫通している。先程飛んできた生温かいものがお客様の。彼の血だという事は直ぐに分かった
何かに進行を邪魔されたと気づいたのか、突き刺さった根は直ぐに引き抜かれ他の根と同じように勢い良く前進していく
刺さった根が抜かれた事で空いた穴を塞ぐものがなくなり、ボタボタと勢い良く床に血が落ちていく。
ぐらりと傾き倒れそうになるお客様を抱きとめ、そのまま膝をつくように座り込んだ
「お客様‥ッ」
出血が酷い。空いた穴が大き過ぎる。彼の血が、辺りに広がっていく。
住人の身ならまだしも人間にとってのこれは一目で分かる程に致命的なモノだ。
助からない。
それはきっと誰よりお客様本人が一番良く分かっていて、
「‥あんた‥最後まで、な、まえ‥くれなかっ、た‥な」
どうしてこの人はこんな時に、今までで一番穏やかに笑って見せるのか。何故、よりにもよって今、そんな事を言うのか
「‥お客様‥」
最後、という言葉に酷く胸が軋む。彼はわざと。今だからこそ言ったのだろうか。この胸の痛みを、傷跡を、残していこうとでもしたのだろうか。
「‥貴方を送り届けると、約束‥したのに‥」
まただ。“また”約束を守れなかった。どうして何時も約束を守れないのか。何故約束を守れないまま別れる形になってしまうのか
(‥また、って‥前回の約束は‥何時、誰と‥?)
頭が痛い。
ズキズキと痛いのは本当に頭だけだろうか。息が苦しい、全部が、全部、どうして、何で、
嫌だ
嫌だ、嫌だ、嫌だ、いやだ、イヤだ。自分は彼に
『死んでほしくない』
「‥痛い、‥苦しい、‥‥嫌‥だ‥ッ」
分からない。何も分からない。思い出せない、何時も何も分からない。だけど、それでも、分からないなりにも。自分が大切にしたいモノ位は、
「‥死なせません、貴方を、‥自分は‥、っ」
今、何をするべきか位は、分かるから
「“ラストトレイン”の名において、貴方の最期に寄り添うと、最後まで送り届けると誓ったから‥!」
だから自分は、彼を───
ー ー ー ー ー
「本当に大丈夫ですか?」
「ああ、まぁ何とかなるだろ」
とある駅で、二人の車掌が会話をしている。どうやら片方の車掌の見送りらしい。
制帽を深めに被り、濃紺の長いコートを纏った人物がポケットから取り出した時計で時刻の確認をしている。
「そろそろ時間だ。じゃあな。長い間世話になった」
「いえ‥あの、もし。もしも貴方がこの先きちんとした行き先を、目的地を見つけた時には‥。“思い出した”時にはどうか自分に送らせて下さい」
「俺はまた、あんたの『お客様』に戻っても良いのかトレイン?」
「また、ではなく、貴方はずっと自分にとってのお客様ですよソウル」
「‥そ。じゃあ、何時の日か目的地が見つかった時には宜しくな。“車掌さん”」
ぽん、と。帽子の上から頭を軽く撫でられる。
お客様は、ソウルは、短めの黒い髪で。性格的に大人しい訳ではないが自分と同じく表情にあまり大きな変化の見られないヒト。そして自分よりも少しばかり背が高い男性。オマケに彼はハッキリとした年齢が分からずずっと自分よりも年上だと言い張っている為、時折今みたいに年下のように扱われてしまう
そして、
「けほ、っ、‥吸うなとは言いませんが、今後お客様の前では控えるように」
「んー」
煙草は相変わらず。彼は恐らく悪戯好きだ。
今でも煙草を吸っている場面に遭遇すると煙を吹きかけられてしまうので、非喫煙者にも関わらず自分もお客様の前に出る時には匂いに気をつけなければいけなくなっていた
けれどそれも今日で終わり。彼は、本日この瞬間から自分の列車を降りる事になった
目的地が思い出せた訳でも、新しく行き先を見つけた訳でもないが、迷界側に生きる住人となった事でこの列車から降りても行動出来るようになったから。彼はこれから色々な所へ出向き、沢山のものを見てくるのだろう。
お客様。改め、彼。『ソウルトレイン』は自分の元から旅立っていく。
根を張る不思議な扉によって列車を侵食されたあの日。彼は一度死にかけた。もう手遅れという段階ではあったものの、人間でさえなければまだ十分に助かる可能性がある状態だった
だから自分は彼を、自らのエゴによって人間から人ならざる別のモノへと押し上げてしまった。本人の同意も得ずに、だ。
人間を人間でなくならせるには本人の強い意志、または他者からの力の影響があってはじめて成立する現象で。成功するかどうか自体は分からなかったけれど。あの時“今の自分ならやれる”と、そう感じた。
迷界に戻らなくなっていた事により、以前もより能力的な面での力が強くなっていた自覚があったからかも知れない。
あの根を張る扉も“気づいた時には”列車から跡形も無く消えてしまっていた。知らず知らずの内に引き離す事に成功していたらしいが、何をどうしたのかはあまり思い出せない。
覚えているのは、彼を生かすため元々割れていたタマシイを自らの意思で『更に砕いた』という事。
とはいえほんの少しだけ。その、ほんの少しのタマシイを彼に使った。
タマシイを分け与えて、名前もつけた。自分達のような存在にとって名前はとても、とても大切な物。
ヒトではないモノに名前をつけるのはそう簡単な事ではない。己の力が弱ければ自分自身に名前をつける事さえ叶わないような世界の中で。自分ではない他のモノに名前をつけるのは想像以上に難しい事。
名前をつけられる側よりも、つける側がある程度上位のモノである事は大前提である。そして下位のモノが名前を直接握られた段階で取り返しのつかない自体に発展する事も珍しくはないのだ。が、勿論自分は名前をつけたからと言ってソレを使い捨てのコマのように扱ったりはしないのだけれど。
ただ、ずっと悩んでいた通り何かに名前をつけるという行為そのものがあまりにも苦手で
自らのタマシイを分け与えた彼に、タマシイの別名であるソウルという名前を付ける形になってしまったのだが彼は案外気に入ってくれたようで。その後、自分の力の影響か元々そうなる運命だったのか、彼の理はヒトから列車へと切りかわっていった。そうして最終的には自分と同じく列車兼車掌として生きていく事を決め、彼は『ソウルトレイン』と名乗るようになった。
「よし、それじゃあ行くか。ついてこい“ベンダー”」
「うん!バイバイ、赤毛の車掌さん。あ、黒髪の車掌さん待ってよー!」
車掌となった彼ソウルの背中を、丸い耳が付いたキャスケットを被った小さな子供がパタパタと追いかけて行く。あの子は以前、車内でソウルに桃の缶詰を売った少年。ストリートベンダー。
どうやら、ソウルが乗ってきた際隠れて一緒に乗り込んで来ていたらしいのだが。気配がとても小さく、少年がソウルの気配に隠れてしまっている内に少しずつ列車との繋がりが薄くなっていった自分は車内に隠れ続ける物売りの少年に気がつけないでいたのだ。
根を張る扉の一件後、列車を一旦ナカに戻す前に見つけた彼は、その後随分とソウルに懐いて。自分の列車から降りるソウルについていくと決めたらしい。
彼等はこの先二人で共に生きていくとの事で、ソウルも、物売りの少年も。一人ではないというだけで安心出来た。
(‥汽笛が鳴っている)
自分の列車のものではないソレに耳を傾け、動き出す車両を見送った。友人であり、同業者であり、この先も大切なお客様である彼の列車が見えなくなるまでずっと、ずっと。
「さようなら。また会いましょう」
何時の日か、貴方が向かう先が見つかった時には再びあの窓際の席で、貴方を乗せて、目的地まで。