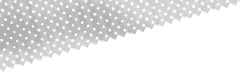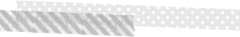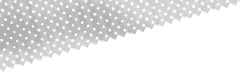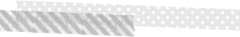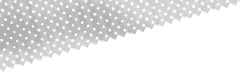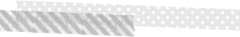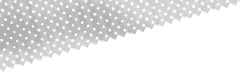
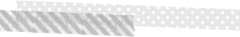
《硝子玉(2)》
ジッ、っと。何か言葉を発する訳でもなく、黙って顔を覗き込む。
この場合、見つめているのは本人ではなく。瞳の色だ。吸い込まれそうな程の深い青に、思わず洩らしたのは、まるで宝石のようだと。そんな素直な感想だった。
「サファイア、タンザナイト、ブルースピネル‥」
「あの、‥どうしたのミラー‥さん」
ぶつぶつと何か呟いて、ぼんやりと、それでいてどこかうっとりと。親友の瞳の中にある青い色を眺めているのはミラーマン。そんな親友に、ビクビクとして思わず名前に『さん』をつけてしまっているのは地獄のタクシー
普段のタクシーは、ミラーマンの事をミラーと呼ぶ。
が、時々『さん』をつけてしまうのはミラーマンがタクシーより七つも年上だからか、あるいは仕事の癖か。もしくは単に怯えているのか。これが選択問題ならば、恐らく今回の件では第三の選択肢で間違いないであろう。
とにもかくにも、タクシーの瞳の中を覗き込むミラーマンはどこか異様な雰囲気を醸し出していた。
「お前の瞳の色は綺麗だ‥見ていて飽きない」
「‥だからって、ただひたすらお前と目を合わせてなきゃならない俺の気持ちも考えろよ‥」
両頬に手を添えられ、ミラーマンから逃げ出す事が出来ずにいるタクシーが。困ったように眉尻を下げて訴えている。
「俺の目の色、好きって言ってもらえるのは嬉しいけど。ここまで真剣に見られると‥」
逸らすに逸らせない。けれど、直視するのも何だか違う気がして。目線がちらちらと別の方向に向いてしまう。
ミラーマンは、そんなに宝石が好きだっただろうか。タクシーの記憶にある限り、そんな話しは聞いたことがないはずだが。そもそも自分の記憶が宛てになるものではないと、仕方がないので、本人に聞いてみる事にした。お前、そんなに宝石が好きだったか。と
するとミラーマンは言う
「綺麗なモノは、嫌いじゃねぇ」
「‥え」
意外だ。てっきり、そんなことはないと返されると思っていたのに。
「じゃあ、俺、金貯めてお前に青い宝石買ってやろうか‥?」
「はっ、その日暮らしがやっとのくせに、何偉そうな事ほざいてやがる」
「これから土産とか減らしていけば、少しずつは貯まるよ」
「‥嗚呼、そうか、そういやお前。そういう面で金使う所あるよな」
今まで、現実世界に行くとタクシーが何かしらの手土産を持って来ていた事を思い出すミラーマン。
タクシーの給料は一人分と考えればそれなりに妥当な方かも知れないが。如何せん彼は人より遥かに食費がかさむ。加えて、一人では仕事をする事が出来ず。タイヤという仕事仲間と働いているのだが、
二人で働いているという事を、雇い主に報告していない為。もらえるお金は一人分。こちらはタクシーと違い、かかってくるのは食費ではなく治療費だ。タクシーの方も定期的に病院にかかっているが、タイヤの怪我の頻度の方がずっとずっと多いと思われる。
タイヤの治療費は仕方がないとしても。他人に対する浪費癖は今後の為に直させた方が良いかもしれない。と、思うと同時に。
その浪費癖のおかげで、ミラーマンがタクシーに救われた事があるのもまた事実
「まぁ、なんだ。その‥ほどほどに、な?」
「そうだなぁ。お前に宝石やるなら、あれは直さないといけないよなぁ」
「別に宝石なんか欲しくねぇよ」
「でも、今、綺麗なモノは嫌いじゃないって」
「だが、それが欲しいと俺は言ったか?」
「‥言ってない」
何やら残念そうに肩を落としているタクシーは、ミラーマンが喜ぶのなら、と。宝石を買ってあげたかったのだろうが
それをきっぱりと断られ、彼の喜ぶ顔が見られないと。残念がっているのだろう
そんなタクシーを見たミラーマンが、ニッっと笑って言う
「宝石なんかより、ずっと良いモノ。持ってるんだ‥見たいか?」
楽しそうに笑うミラーマンが漸くタクシーから目線を逸らしたかと思えば、ひょいと身軽にソファーの上から床へと着地して。部屋に置かれたアンティークのキャビネットから。小さな小箱を取り出すと
それをそのままタクシーへと手渡した。
「‥開けて良いのか?」
「勿論」
こちらもキャビネットと同じくアンティークの、綺麗な小箱。それを傷付けないようそっと開けば。切ない位に優しい音色が鳴り響く
「わぁ‥これ、オルゴールなんだな」
「まぁな。小物も入れられるような作りになってるんだが‥」
「あ。何か入ってる。えっと‥ん?何これビー玉‥」
「綺麗だろう」
「へ?あ、ああ。うん、綺麗だけど‥もしかして宝石より良いモノって‥」
「このビー玉だ」
オルゴールの底の部分に、ころん。と、小さな硝子玉が二つ
それを手にとりシャンデリアの明かりにかざして見れば、成る程うっすらとではあるが青く色づいている
「本当だ、凄く綺麗」
「‥とても大切なモノなんだ」
「これが?」
「‥嗚呼」
そう言って、タクシーを見ながら何処か寂しそうな笑みを浮かべるミラーマン。
大切だと言っていた小さな二つの硝子玉にもう一度視線を向けて、大切なモノならば、傷つけてはいけないな、と。元の場所へとビー玉を戻すと
静かな部屋の中を、柔らかく包み込むように流れている旋律をそっと遮るように。タクシーは手の中にあるオルゴールの蓋を、ゆっくりと閉じた
「はい」
音が鳴り止み、再び木箱へと戻ったそれをミラーマンへと差し出すタクシー
オルゴールがミラーマンの手に渡る直前に、木箱が傾き音を立てて床へと落ちると。その拍子に蓋が開いて再びあの優しいメロディーが鳴り。中にしまい込んだ大切な硝子玉がころころと床の上を転がっていく
「ご、ごめんわざとじゃ‥」
「わかってる。良いさ、落ちたならば拾えば良いだけの事だから」
「‥壊れてないか」
「多分、大丈夫だろう」
転がっていく硝子玉を、ミラーマンの綺麗な指が遮って。そのまま拾い上げると先程タクシーがやったように明かりへかざす
「ん、傷は付いてねぇな」
「このオルゴールは?」
「そっちはどうだって良い。只の入れ物だから」
「でもこれ、高価なモノじゃないのか」
「値段はそれなりかもな。けど、モノの価値を決めるのは金額じゃなくて持ち主の気持ちだろう‥だからな、俺にとってこの硝子玉は、そこら辺の宝石なんかより、ずっとずっと価値のある大切なモノなんだ」
手にしたビー玉を、両手握り込むと。目を瞑って自らの胸にそっとあてる
(硝子‥玉‥)
タクシーは、ふと、あの小さな硝子玉に見覚えがあるような気がしてきた。ミラーマンが、彼が、大切だと言った二つのビー玉。
あれを見るのは、本当に今回が始めてなのだろうか
「‥み、らー‥それ、」
「どうした?」
「俺、‥これ、見た事がある気がするんだけど‥」
「‥え‥」
見た事がある。タクシーのその言葉に、ミラーマンがバッと顔を上げてタクシーを見る
(ああ、やっぱり初めて見たモノじゃないのか‥)
ミラーマンの反応を見る限り、どうやら以前にもこれを見ているらしい。
何故、こんな硝子玉を彼は大事にしているのか。どうして、宝石なんかよりも価値があると言ったのか。
もしかしたら、この透き通った硝子玉が大切だと思わせる何かを、自分がやったのではないだろうか。だから、ミラーマンは、こうしてわざわざ自分にビー玉を見せてくれたのでは
と、タクシーは思った。
「‥喉、乾いてないか」
「え?あー‥、何か飲ませてくれるならもらおうかな」
「ん。今、用意するからまたそこ座っとけ」
「はぁい」
言われるがままに再度ソファーに腰を下ろして。ミラーマンが飲み物を持ってきてくれるのを待っていれば、数分ほどで目の前にシュワシュワ、パチパチ、なんだかとても心地好い音がする飲み物が用意された
それはミラーマンが出してくれるにしては、珍しい飲み物。
「ソーダ水だ」
「たまには良いだろ」
「うん。俺、ソーダ水好き」
正確には、タクシーに嫌いな物などないのだけれど。それでも、そうか、と笑ってその言葉を受け入れてくれる
いただきます。と、出されたソーダ水の入ったグラスを持ち上げて。こくこくと飲み込んだ
久しぶりに飲んだ炭酸水は、喉の奥でもパチパチと弾けて。飲みほされるその瞬間まで、自らの存在を主張し続けていた
「‥美味いな。なんか、懐かしい味がする」
「‥そうか」
「前にも、こうしてお前と‥‥あ、」
そこでタクシーはハッっとし、漸く思い出した
「‥そうだ‥俺、約束したんだ」
──‥俺がお前を外に連れ出してやる‥
ラムネの瓶を割ってそんな話しをしたのは、何時の夏だっただろう
確か、人間界に行った時。夏祭りの夜店で懐かしさのあまり購入して。それをそのまま土産に持ち帰った事があった
あの時、瓶の中に閉じこめられたビー玉を見てミラーマンが言った台詞は、まるで自分の様だ、と。
だからタクシーは言ったのだ。割れた硝子片で怪我をしてまで中身のビー玉を取り出して。ビー玉だって外に出られる。お前が望むなら、俺が必ず外に連れ出してやる
間違いなく、彼はミラーマンにそう約束をしていた
「お前が自分から外に出たいって言うまで、何年でも、何十年でも。ずっとずっと、‥待っててやるって‥」
「‥タクシー‥」
「みら‥うわぁ?!ど、どうして泣いてるんだ?!」
「お、お前が‥そんな下らねぇ事、思い出すなんて‥思い出して、くれるなんて‥思ってなか、っ‥」
ぽたぽたと、ミラーマンの右目の赤から。透明な雫が零れ落ちる
それはまるで、透き通ったビー玉そのもの
「下らなくないだろう‥お前だって、俺の言った事、覚えててくれたから‥このビー玉、大事にしてくれてたんだもんな‥?」
ミラーマンの右目から、後から後から沸き上がる小さな小さなビー玉の雫は、頬を伝って流れては消えた。
確かに、このタイミングでソーダ水を出したのは。もしかしたら、あの時の事を思い出してくれるのでは、
と。心の何処がでそんな風に思っていたからこそだろう。けれど、良いではないだろうか
自分の中にある大切な二人の思い出を。また、同じように分かち合いたいと思っても。
「ミラー?」
「‥ん‥」
「覚えててくれてありがとう」
「‥タクシー」
「何?」
「思い出してくれて‥ありがとう」
互いの台詞に、ふふ、と。声を洩らして笑い合い
こつんと額を合わせて。一緒に言った
「どういたしまして」
あの日、俺達は大切な約束を二人でしたんだ。