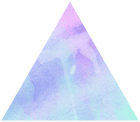「それじゃ……先生ちょっと用事があるから席外すけど、横になってゆっくりしてなさいね」
「うう、はい……」
わたしの返事を聞いた先生は上品に微笑んでそのまま保健室を後にした。
ずしりと痛む腹部を両手で抑えながらベッドに向けて足を運ぶ。2つ並ぶベッドのうち、どうやら片方には先客がいるらしい。白いカーテンが囲うように閉められていた。
空いている窓側のベッドに腰を下ろすとスプリングが軋み、わたしは静かに横になった。
いやはや、生理というのは全く苦痛でしかない。
月に1度、しかも約1週間も頭痛や腹痛、吐き気なんかに襲われる意味がわからない。毎月この時期になると女をやめてしまいたいなんて考えるものだ。
「ハア…………」
ごろんと軽く寝返りをうって天井を見上げた。横になっていれば腹痛も少しはマシになるものの、完全に治るわけじゃない。あー、女やめたい。
「大丈夫?」
溜息ばかり吐いていると、突然カーテン越しに声が聞こえてきた。
驚いたわたしは思わず肩を揺らしたけれど、カーテンのせいでその姿は見えなかった。
「いきなり堪忍なあ、さっき保健室入ってきはった時に先生との話が聞こえてもうて」
京なまりで話すその声に聞き覚えはない……というかそもそもわたしはクラスの男子とも用がない限りほとんど話をしないのだ。きっと知り合いではないだろう。
「いえ……」
「お腹痛いんやろ?話しとったらもしかしたらしんどいん忘れられるかもしれへんし、どうかなー思て」
どこの誰かは知らないが、正直ありがたい提案だ。彼の言うとおり、何もせず横になって腹痛に集中するよりは、話をして気を紛らわせる方が気持ちは楽になると思う。だけど……
「えと……でも、あなたの体調が……」
「あ〜、俺はええんですわ!そもそも次の日本史めんどい思てサボりにきただけやもんで……」
「……え?!さ、サボり?!」
咄嗟につい大きな声を出してしまい、はっと片手で口を噤んだ。
正十字学園に通う生徒はお金持ちがほとんどだから、そういった行動を見せる人は稀なのだ。まさか、わたしが現行を目撃してしまうなんて。
「めんどい授業受けるより保健室来てキレーなせんせーに会おう思たんですわ〜。そしたら、君に会えた。これって、ひょっとして運命やったりして」
「……っ!」
身体中の熱が顔に集中したのかってくらい、熱く火照っていくのが自分でもわかる。少しでも冷まそうと両手でぱたぱたと扇いでみるが、全く効果は見られない。
こんなキザなセリフを吐く人がいるなんて。
こんなキザなセリフを自分が吐かれるなんて。
考えれば考えるほど顔が火照るから何か別のことを想像しようとしても、胸の鼓動が邪魔をする。言葉だけでこんな風にさせるなんて、彼はある種の天才なんじゃないだろうか。
ふと、彼はどうしてカーテンを開けないのかが気になった。授業をサボって綺麗な保健の先生に会いに来ただとか、わたしに会えたのが運命だとか、そんな口説き文句を次々吐き出す彼はきっとプレイボーイなのだ。それならカーテンの1枚や2枚、すぐにでも取っ払ってしまいそう……なんて、偏見だけど。
「……あ、もしかしてなんで俺がカーテン開けへんのかな〜思てはる?」
「へっ?!」
彼はエスパーなんじゃないだろうか。
「あっははは!開けへんよぉ。開けたいのは山々ですけど、女の子って体調悪い時に顔見られるん嫌がるやん」
それはきっと、コンデションが悪ければ肌の調子が整わなかったりするからだ。現にわたしもカーテンを開けられなくてよかったなんて思ってしまっている。
女子じゃないとわからないようなこんな点を気遣ってくれるなんて──先程の熱が尾を引いているのか、ドコドコと心臓が細かく跳ね上がる。
「や、優しいんですね」
「えっほんま?!嬉しいわぁ〜」
わかりやすく明るくなった声色に、微かにカーテンが揺れた。
それから2人は他愛もない、いろんな話をして過ごした。
学食は何が美味しいとか、学校近くによく可愛らしい黒猫がウロついているとか。わたしが休日によくやる趣味の話もしたし、彼の友達の話もした。時間が経つことなんて忘れて、声を潜めて笑いあった。
「それでその時になあ……」
ふと、カララとドアが開く音が聞こえた。話の途中で途端押し黙った彼が小さく息を吐いたのが耳に届いた。
「おひらきやなあ」
ほんの僅かな声量で囁かれた次の瞬間、カーテンが開く音がした。こちら側のどのカーテンも動いていないことから、きっと隣のベッドのカーテンが開けられたのだろう。
「調子はどうかしら?」
「いや〜、寝たら完全復活ですわ!」
どうやら保健の先生が用事から帰ってきたらしい、体調を窺う声の後に彼は陽気に答えた。
「寝たら」なんて嘘のくせに。体調が悪いのなんて嘘のくせに。けれどその嘘を知っているのがわたしだけなことに気がついて、なんだかとても嬉しく感じた。
「苗字さん」
「わっ!……は、はい」
不意に名前を呼ばれて驚きながら返事をすれば、今度はこちら側のカーテンが開けられた。
「どうかしら。落ち着いた?」
「は……はい、だいぶ楽になりました」
「そう、よかったわ」
薄く微笑んだ先生をよそに保健室を見渡したけれど、もうわたしと先生以外誰もいないようだった。
「ありがとうございました。教室に戻ります」
「お大事にね」
そう挨拶をして保健室から踏み出たものの、廊下にももう彼は見当たらなかった。
結局顔も名前もわからず終いだった。
彼と過ごした時間はとても楽しかったのだけれど、もう会うことは叶わないのだろうか。彼の言うとおりわたし達の出会いが運命ならば、きっと会えるのかもしれないけれど。
耳に残るのは彼の優しく囁く甘いテナー。
未だ脈打つ心臓とは裏腹に、教室へと向かう足取りはひどく重たいものだった。
あれから2週間ほど経っただろうか。
顔も名前もわからないなんてもちろん探しようがあるはずもなく、ただいたずらに時間が過ぎていった。
もう諦めよう。そんな風に思っていたら、ふと廊下ですれ違いざまに聞き覚えのある声が耳に届いた。
「ほんなら今日の放課後、久しぶりにぽんちゃんでも行きます?」
思わず勢いよく振り返った。真ん中だけを金髪に染めたガタイのいい男子を挟むように、小柄な坊主の男子とピンク頭の男子が並んで歩いていた。
お金持ちが多く通う正十字学園の生徒には似つかない、ブレザーの下に自前のパーカーを着込んだスタイル。ピンク色に染められた頭髪。
頭の中でこの2週間何度も思い出した声がこだまする。彼だ。
顔も名前もわからないけれど、きっと彼があの時の声の主だと確信を持てた。
もしも再会できたらどう声をかけようとか、何を話そうとか、いろいろ考えたのにそれら全てが抜け落ちてしまったかのように頭の中が真っ白だ。心臓がひどく跳ね上げて、呼吸もままならない。
だけど、それでもわたしは、どうしてもまた彼と話がしたくて。
声が裏返るのも、周りの視線が集まるのも気に留めず、わたしはただがむしゃらに声をかけた。
「……あ……あの……っ!!」
---------------
お題配布サイト「確かに恋だった」様より
わたしと保健室と彼5題
「うう、はい……」
わたしの返事を聞いた先生は上品に微笑んでそのまま保健室を後にした。
ずしりと痛む腹部を両手で抑えながらベッドに向けて足を運ぶ。2つ並ぶベッドのうち、どうやら片方には先客がいるらしい。白いカーテンが囲うように閉められていた。
空いている窓側のベッドに腰を下ろすとスプリングが軋み、わたしは静かに横になった。
いやはや、生理というのは全く苦痛でしかない。
月に1度、しかも約1週間も頭痛や腹痛、吐き気なんかに襲われる意味がわからない。毎月この時期になると女をやめてしまいたいなんて考えるものだ。
「ハア…………」
ごろんと軽く寝返りをうって天井を見上げた。横になっていれば腹痛も少しはマシになるものの、完全に治るわけじゃない。あー、女やめたい。
「大丈夫?」
溜息ばかり吐いていると、突然カーテン越しに声が聞こえてきた。
驚いたわたしは思わず肩を揺らしたけれど、カーテンのせいでその姿は見えなかった。
「いきなり堪忍なあ、さっき保健室入ってきはった時に先生との話が聞こえてもうて」
京なまりで話すその声に聞き覚えはない……というかそもそもわたしはクラスの男子とも用がない限りほとんど話をしないのだ。きっと知り合いではないだろう。
「いえ……」
「お腹痛いんやろ?話しとったらもしかしたらしんどいん忘れられるかもしれへんし、どうかなー思て」
どこの誰かは知らないが、正直ありがたい提案だ。彼の言うとおり、何もせず横になって腹痛に集中するよりは、話をして気を紛らわせる方が気持ちは楽になると思う。だけど……
「えと……でも、あなたの体調が……」
「あ〜、俺はええんですわ!そもそも次の日本史めんどい思てサボりにきただけやもんで……」
「……え?!さ、サボり?!」
咄嗟につい大きな声を出してしまい、はっと片手で口を噤んだ。
正十字学園に通う生徒はお金持ちがほとんどだから、そういった行動を見せる人は稀なのだ。まさか、わたしが現行を目撃してしまうなんて。
「めんどい授業受けるより保健室来てキレーなせんせーに会おう思たんですわ〜。そしたら、君に会えた。これって、ひょっとして運命やったりして」
「……っ!」
身体中の熱が顔に集中したのかってくらい、熱く火照っていくのが自分でもわかる。少しでも冷まそうと両手でぱたぱたと扇いでみるが、全く効果は見られない。
こんなキザなセリフを吐く人がいるなんて。
こんなキザなセリフを自分が吐かれるなんて。
考えれば考えるほど顔が火照るから何か別のことを想像しようとしても、胸の鼓動が邪魔をする。言葉だけでこんな風にさせるなんて、彼はある種の天才なんじゃないだろうか。
ふと、彼はどうしてカーテンを開けないのかが気になった。授業をサボって綺麗な保健の先生に会いに来ただとか、わたしに会えたのが運命だとか、そんな口説き文句を次々吐き出す彼はきっとプレイボーイなのだ。それならカーテンの1枚や2枚、すぐにでも取っ払ってしまいそう……なんて、偏見だけど。
「……あ、もしかしてなんで俺がカーテン開けへんのかな〜思てはる?」
「へっ?!」
彼はエスパーなんじゃないだろうか。
「あっははは!開けへんよぉ。開けたいのは山々ですけど、女の子って体調悪い時に顔見られるん嫌がるやん」
それはきっと、コンデションが悪ければ肌の調子が整わなかったりするからだ。現にわたしもカーテンを開けられなくてよかったなんて思ってしまっている。
女子じゃないとわからないようなこんな点を気遣ってくれるなんて──先程の熱が尾を引いているのか、ドコドコと心臓が細かく跳ね上がる。
「や、優しいんですね」
「えっほんま?!嬉しいわぁ〜」
わかりやすく明るくなった声色に、微かにカーテンが揺れた。
それから2人は他愛もない、いろんな話をして過ごした。
学食は何が美味しいとか、学校近くによく可愛らしい黒猫がウロついているとか。わたしが休日によくやる趣味の話もしたし、彼の友達の話もした。時間が経つことなんて忘れて、声を潜めて笑いあった。
「それでその時になあ……」
ふと、カララとドアが開く音が聞こえた。話の途中で途端押し黙った彼が小さく息を吐いたのが耳に届いた。
「おひらきやなあ」
ほんの僅かな声量で囁かれた次の瞬間、カーテンが開く音がした。こちら側のどのカーテンも動いていないことから、きっと隣のベッドのカーテンが開けられたのだろう。
「調子はどうかしら?」
「いや〜、寝たら完全復活ですわ!」
どうやら保健の先生が用事から帰ってきたらしい、体調を窺う声の後に彼は陽気に答えた。
「寝たら」なんて嘘のくせに。体調が悪いのなんて嘘のくせに。けれどその嘘を知っているのがわたしだけなことに気がついて、なんだかとても嬉しく感じた。
「苗字さん」
「わっ!……は、はい」
不意に名前を呼ばれて驚きながら返事をすれば、今度はこちら側のカーテンが開けられた。
「どうかしら。落ち着いた?」
「は……はい、だいぶ楽になりました」
「そう、よかったわ」
薄く微笑んだ先生をよそに保健室を見渡したけれど、もうわたしと先生以外誰もいないようだった。
「ありがとうございました。教室に戻ります」
「お大事にね」
そう挨拶をして保健室から踏み出たものの、廊下にももう彼は見当たらなかった。
結局顔も名前もわからず終いだった。
彼と過ごした時間はとても楽しかったのだけれど、もう会うことは叶わないのだろうか。彼の言うとおりわたし達の出会いが運命ならば、きっと会えるのかもしれないけれど。
耳に残るのは彼の優しく囁く甘いテナー。
未だ脈打つ心臓とは裏腹に、教室へと向かう足取りはひどく重たいものだった。
あれから2週間ほど経っただろうか。
顔も名前もわからないなんてもちろん探しようがあるはずもなく、ただいたずらに時間が過ぎていった。
もう諦めよう。そんな風に思っていたら、ふと廊下ですれ違いざまに聞き覚えのある声が耳に届いた。
「ほんなら今日の放課後、久しぶりにぽんちゃんでも行きます?」
思わず勢いよく振り返った。真ん中だけを金髪に染めたガタイのいい男子を挟むように、小柄な坊主の男子とピンク頭の男子が並んで歩いていた。
お金持ちが多く通う正十字学園の生徒には似つかない、ブレザーの下に自前のパーカーを着込んだスタイル。ピンク色に染められた頭髪。
頭の中でこの2週間何度も思い出した声がこだまする。彼だ。
顔も名前もわからないけれど、きっと彼があの時の声の主だと確信を持てた。
もしも再会できたらどう声をかけようとか、何を話そうとか、いろいろ考えたのにそれら全てが抜け落ちてしまったかのように頭の中が真っ白だ。心臓がひどく跳ね上げて、呼吸もままならない。
だけど、それでもわたしは、どうしてもまた彼と話がしたくて。
声が裏返るのも、周りの視線が集まるのも気に留めず、わたしはただがむしゃらに声をかけた。
「……あ……あの……っ!!」
---------------
お題配布サイト「確かに恋だった」様より
わたしと保健室と彼5題