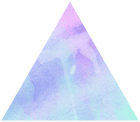※ 死ネタです。
あの男と出会ったのは、ちょうど今日みたいに雨のひどい日だった。
その日、わたしは山に生る木の実が料理にどうしても必要だった。
まだ晴れていた昼間に山に入ったのだけれど、今年は不作なのか不思議なことにどこにも見当たらない。雲行きが怪しくなる中山奥に進む足は止めずにいたが、やはりどこにも見当たらない。
気がつけば足を踏み入れたこともないほどに随分と奥まったところまで来てしまったようで、さすがに引き返そうと思った時には既に遅く、降る雨は次第に強くなる一方だった。
慣れない山場、しかも大雨でぬかるんだ土地を行くほど馬鹿ではない。どこかで雨宿りをすることにしたのだ。
するとふと小さな山小屋を見つけたのだが、それと同時にマキノさんの言葉を思い出した。
先日、赤髪の船長さん率いる海賊さんたちやルフィくんが遊びに来ていた日に、お店に山賊がお酒を求めてやって来たらしい。しかしその時は海賊さんたちに全て出してしまった後で、腹を立てた山賊の頭が船長さんに怒り散らしたのだという。一先ずその場は収まったらしいのだが、「ナマエちゃんもくれぐれも気をつけてね」と教えてくれたのだ。
わたしはもう一度山小屋を見て、寒さか恐怖か、身震いをした。
いつ止むかわからない雨を待ちながらこのままここで立ち尽くしていては、最悪冷えて死んでしまうかもしれない。だけど、もしかすると山賊の根城かもしれない場所に身一つで突入するのも危険だ。
寒さで回らなくなっていく頭を抱えながら、次々に血の気が引いていくのを感じる。焦りからか眩暈までしてきた。ああ、だめだ、このままじゃ。
すると不意に、山小屋の扉がキィと開いたのだ。
朦朧とする意識の最中驚いてそれを見れば、中から顔をのぞかせたのは額に大きな傷のある長身の男だった。
「なんだ嬢ちゃん、そんなところで何してやがる」
風貌からしてやはり山賊なのだろうその男がわたしに問うたけれど、凍えて呂律の回らない舌では質問に答えることはおろか、叫ぶことすら不可能だった。
「そんなとこいたら死んじまうぞ。オラ、こっちに来い」
山賊に呼び寄せられたわたしは恐怖よりもこの寒さから逃れたい気持ちが勝って、ガクガクと震える足を押し出して言われるままに小屋の中へ入った。
「おいおい、びしょ濡れじゃねェか……」
「あ……りがと、ござ、ます」
小屋に入るや否や、眉間に皺を寄せる男がわたしをガシガシと雑に拭いてくれたけれど、麻布だったから正直擦れて痛かった。
しかし浸潤していたわたしの身体はみるみる乾いていき、男の掌からじわじわと体温を受け取っているのがわかった。
山賊……かと思ったのだけれど、違ったのだろうか。
「あの……あなたは」
「あァ?おれァ山賊だ」
「え、」
つい、聞き間違いかと思ってしまった。
じゃあきっとこの人がマキノさんが話していた山賊───だけど、なぜこんなにも親切にしてくれるのだろう。
恐る恐る透けた麻布越しに男を見上げれば、不満げにチ、と小さく舌を打たれた。
「別におめェみたいなガキを取って食おうなんざ思わねェし、アジトの目の前で死なれりゃァ後で処理が面倒だろうが」
「な、なるほど……」
ガキなどと言われ内心かなり複雑ではあるが、この行為が男の親切心だということがわかった以上それについて抗議する必要はない。
アジトなのだというこの小屋をぐるりと見回してみると、どうやら今はわたしとこの男の2人だけしかいないようだ。マキノさんは10、20人ほどはいたと言っていたが、他の人たちはどうしたのだろう。
するとそれを察してか否か、男は「子分共はみんな町へ行ってんだ」と教えてくれた。
「町ですか?」
「あァ、この山で採れる木の実がどうやら絶品だと評判らしくてな。昼間のうちに根こそぎ回収して町へ売りに出ていたんだが、この雨で足止めを食らっちまってるみてェだな」
「あ……だからどこにも木の実がなかったんですね」
「なんだ嬢ちゃん、木の実目当てだったか?」
「はい、そうなんです。今日の献立に使おうと思いまして。わたし料理が好きでお店のお手伝いもしたりするんですけど、あの実を使うか使わないかでかなりコクが違って……」
得意の料理のこととなると思わず溌剌と語ってしまい、は、と我に帰った。
「あは…………すみません」
「はっはっはっ!面白い嬢ちゃんだ」
そう言って男は麻布を乱雑に取っ払ったかと思えば、ゴツゴツとした大きな掌がわたしの頭部を包み込む。今度は素手でわたしの頭をやはり雑にこねくり回した。力強く、それはわたしの首までぐねぐねと動かすものだから酔ってしまいそうで心配になるけれど、温かなその体温はやけに心地よかったのだ───。
いつも穏やかな海も、今日は雨のせいで荒れている。丘の上にあるわたしの家からは海がよく見える。
あの後、雨が上がったものだからあの男に礼を告げてから山を降りると、心配して探してくれていたらしい村長やマキノさん、村の皆にひどく叱られた。あの大雨の中あまり濡れていないわたしの姿に驚いていたが、怪我がなくてよかったと安心した様子だった。余計な心配を増やしたくはないから、山でのことは皆には黙っておいた。
……わたしが今あの雨の日のことを思い出したのには理由がある。
風の噂で、あの男の訃報を聞いたのだ。
海賊さん達と争った末、ルフィくんを攫って海へ逃げた際に近海の主に襲われたのだという。幼い子供を巻き添えにするだなんて、まったく自業自得である。
話を聞けば聞くほど、あの男は卑怯で、狡猾で、酷い人なのだと思う。
だけどどうしても思い出してしまうのはあの掌の温もりばかりなのだ。
あの男がわたしに優しくしてくれたのは気まぐれだったかもしれないけれど、間違いなく真実だった。わたしはあの雨の日の親切な山賊さんに恋をしてしまったのかもしれない。
ふと窓の外を覗いてみれば、空は黒く曇り激しく雨が地面を打ち付けていながら、遠くの西には微かに光が見える。
きっと晴れる明日、名前も聞けなかったあの男に、花を手向けに行こうと思う。一輪のシオンと、あの木の実を使って焼いたクッキーを持って。
あの男と出会ったのは、ちょうど今日みたいに雨のひどい日だった。
その日、わたしは山に生る木の実が料理にどうしても必要だった。
まだ晴れていた昼間に山に入ったのだけれど、今年は不作なのか不思議なことにどこにも見当たらない。雲行きが怪しくなる中山奥に進む足は止めずにいたが、やはりどこにも見当たらない。
気がつけば足を踏み入れたこともないほどに随分と奥まったところまで来てしまったようで、さすがに引き返そうと思った時には既に遅く、降る雨は次第に強くなる一方だった。
慣れない山場、しかも大雨でぬかるんだ土地を行くほど馬鹿ではない。どこかで雨宿りをすることにしたのだ。
するとふと小さな山小屋を見つけたのだが、それと同時にマキノさんの言葉を思い出した。
先日、赤髪の船長さん率いる海賊さんたちやルフィくんが遊びに来ていた日に、お店に山賊がお酒を求めてやって来たらしい。しかしその時は海賊さんたちに全て出してしまった後で、腹を立てた山賊の頭が船長さんに怒り散らしたのだという。一先ずその場は収まったらしいのだが、「ナマエちゃんもくれぐれも気をつけてね」と教えてくれたのだ。
わたしはもう一度山小屋を見て、寒さか恐怖か、身震いをした。
いつ止むかわからない雨を待ちながらこのままここで立ち尽くしていては、最悪冷えて死んでしまうかもしれない。だけど、もしかすると山賊の根城かもしれない場所に身一つで突入するのも危険だ。
寒さで回らなくなっていく頭を抱えながら、次々に血の気が引いていくのを感じる。焦りからか眩暈までしてきた。ああ、だめだ、このままじゃ。
すると不意に、山小屋の扉がキィと開いたのだ。
朦朧とする意識の最中驚いてそれを見れば、中から顔をのぞかせたのは額に大きな傷のある長身の男だった。
「なんだ嬢ちゃん、そんなところで何してやがる」
風貌からしてやはり山賊なのだろうその男がわたしに問うたけれど、凍えて呂律の回らない舌では質問に答えることはおろか、叫ぶことすら不可能だった。
「そんなとこいたら死んじまうぞ。オラ、こっちに来い」
山賊に呼び寄せられたわたしは恐怖よりもこの寒さから逃れたい気持ちが勝って、ガクガクと震える足を押し出して言われるままに小屋の中へ入った。
「おいおい、びしょ濡れじゃねェか……」
「あ……りがと、ござ、ます」
小屋に入るや否や、眉間に皺を寄せる男がわたしをガシガシと雑に拭いてくれたけれど、麻布だったから正直擦れて痛かった。
しかし浸潤していたわたしの身体はみるみる乾いていき、男の掌からじわじわと体温を受け取っているのがわかった。
山賊……かと思ったのだけれど、違ったのだろうか。
「あの……あなたは」
「あァ?おれァ山賊だ」
「え、」
つい、聞き間違いかと思ってしまった。
じゃあきっとこの人がマキノさんが話していた山賊───だけど、なぜこんなにも親切にしてくれるのだろう。
恐る恐る透けた麻布越しに男を見上げれば、不満げにチ、と小さく舌を打たれた。
「別におめェみたいなガキを取って食おうなんざ思わねェし、アジトの目の前で死なれりゃァ後で処理が面倒だろうが」
「な、なるほど……」
ガキなどと言われ内心かなり複雑ではあるが、この行為が男の親切心だということがわかった以上それについて抗議する必要はない。
アジトなのだというこの小屋をぐるりと見回してみると、どうやら今はわたしとこの男の2人だけしかいないようだ。マキノさんは10、20人ほどはいたと言っていたが、他の人たちはどうしたのだろう。
するとそれを察してか否か、男は「子分共はみんな町へ行ってんだ」と教えてくれた。
「町ですか?」
「あァ、この山で採れる木の実がどうやら絶品だと評判らしくてな。昼間のうちに根こそぎ回収して町へ売りに出ていたんだが、この雨で足止めを食らっちまってるみてェだな」
「あ……だからどこにも木の実がなかったんですね」
「なんだ嬢ちゃん、木の実目当てだったか?」
「はい、そうなんです。今日の献立に使おうと思いまして。わたし料理が好きでお店のお手伝いもしたりするんですけど、あの実を使うか使わないかでかなりコクが違って……」
得意の料理のこととなると思わず溌剌と語ってしまい、は、と我に帰った。
「あは…………すみません」
「はっはっはっ!面白い嬢ちゃんだ」
そう言って男は麻布を乱雑に取っ払ったかと思えば、ゴツゴツとした大きな掌がわたしの頭部を包み込む。今度は素手でわたしの頭をやはり雑にこねくり回した。力強く、それはわたしの首までぐねぐねと動かすものだから酔ってしまいそうで心配になるけれど、温かなその体温はやけに心地よかったのだ───。
いつも穏やかな海も、今日は雨のせいで荒れている。丘の上にあるわたしの家からは海がよく見える。
あの後、雨が上がったものだからあの男に礼を告げてから山を降りると、心配して探してくれていたらしい村長やマキノさん、村の皆にひどく叱られた。あの大雨の中あまり濡れていないわたしの姿に驚いていたが、怪我がなくてよかったと安心した様子だった。余計な心配を増やしたくはないから、山でのことは皆には黙っておいた。
……わたしが今あの雨の日のことを思い出したのには理由がある。
風の噂で、あの男の訃報を聞いたのだ。
海賊さん達と争った末、ルフィくんを攫って海へ逃げた際に近海の主に襲われたのだという。幼い子供を巻き添えにするだなんて、まったく自業自得である。
話を聞けば聞くほど、あの男は卑怯で、狡猾で、酷い人なのだと思う。
だけどどうしても思い出してしまうのはあの掌の温もりばかりなのだ。
あの男がわたしに優しくしてくれたのは気まぐれだったかもしれないけれど、間違いなく真実だった。わたしはあの雨の日の親切な山賊さんに恋をしてしまったのかもしれない。
ふと窓の外を覗いてみれば、空は黒く曇り激しく雨が地面を打ち付けていながら、遠くの西には微かに光が見える。
きっと晴れる明日、名前も聞けなかったあの男に、花を手向けに行こうと思う。一輪のシオンと、あの木の実を使って焼いたクッキーを持って。