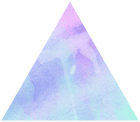「てめェ!!ハレンチだ!!」
至る所から漂う木材の良い香りとリズム良く鼓膜を叩く工具の音。突然轟いたのは街一番の造船工場には似合わない、そんな怒声だった。
その場の誰もが一度は視線を向けるけれど、すぐに「またか」とでも言うように自らの作業に戻っていく。
この街でハレンチだなんて叫ぶのは、誰に問うてもあの男の名前しか上がらない。
皆が憧れるガレーラカンパニー1番ドックの職長が1人、いつも借金取りに追われていて葉巻を咥えずにはいられないニコチン中毒ーーーついでに言えばなんとわたしの恋人、パウリーさんだ。
そんな彼の言葉の飛ぶ先にいるのはカリファさん。わたしの先輩にあたる方で市長アイスバーグさんのスーパー秘書、おまけにスーパー美人ときた。とにかくスーパーな彼女は、いつもそのスーパーに美しい御御足を短いスカートから覗かせている。
男だらけの世界で仕事をしてきたものだから女性の露出に耐性がないなんて話すパウリーさんは、そんな彼女を見かける度に先程のような怒声を浴びせているのだ。
「カリファ、てめェは何度言やァわかる!ここは男の職場だぞ!」
「落ち着いてパウリー」
「うるせェ!少しはナマエを見習え!」
顔を真っ赤にさせながらビシと差した指は間違いなくわたしに向いていて、いきなり話を振られたものだからびっくりして身を縮こまらせてしまった。
わたしは彼の言うような所謂"ハレンチ"な格好はしていない。いつも着ているのは、第1ボタンまでしっかり留めた装飾の少ないブラウスにハイウエストのジーンズ。だけどそれは別に彼が破廉恥だとか言うからではなくて、単にラフな服装が好きなのだ、わたしは。
「いやァ、わたしは……」
「パウリー、前から言おうと思っていたけどあなたナマエを縛りすぎじゃないかしら?恋人だからといって好きな服装も着させてあげないのは可哀想よ」
「ハァ?!なんでおれだよ!んなこと縛っちゃいねェし……」
「あら、そろそろ時間ね。行きましょうナマエ」
「あっおい!」
ドック内に設置された時計を一瞥した彼女はそっとわたしの肩を支え、カンパニーの本社へ向けて歩き始めた。背後から未だ騒がしいパウリーさんの声が聞こえていたが、仕方がないので放っておくことにした。
「最近はどうなの?」
本社へ向かう途中、不意にカリファさんから声をかけられた。パウリーさんとのことだ。
彼女はいつもわたしと彼のことを気にかけてくれて、よく相談にも乗ってくれる。
「ウーン、相変わらずですね」
「相変わらずって……まだキスしてないの?」
「うう……まあ」
彼女の発言にハハと乾いた笑いを送れば、カリファさんは困ったように眉尻を下げた。
ガレーラカンパニーの事務員として仕事をするうちにパウリーさんに惹かれていったわたしは少しでもお近づきになりたくて会うたびに声をかけ続けていた。そしたらなんと彼の方から顔を真っ赤にして交際を申し出てくれたのが、つい1ヶ月半前の話。ハレンチだハレンチだと日々喚いている彼からまさか告白されるなんて思ってもいなかったわたしは大喜びで、翌日発熱したことも記憶に新しい。
そう、交際を始めてそろそろ2ヶ月が経とうとしている今、わたしとパウリーさんはキスはおろか実は手を繋いだことさえ僅か3回だけだ。少ないからどんな場面だったかもばっちり覚えている。
……と言っても彼の性質はわかっているつもりだし、無理強いとかをする気はさらさらないのだけど……
「さすがに2ヶ月何もないのは、ほんとに付き合ってるのか不思議になってきちゃいますね……」
「ナマエ……」
ポロと溢れた本音に思わず自分で肩を落とした。
告白されたのは実は夢だったんじゃないか、なんて考えが過ることもあるけど、交際を始めてからと言うものの毎日事務仕事で帰りが遅くなるわたしを彼は家まで送ってくれているのだ。これが夢なわけがない。
「なんじゃ、お前さんらまだキスもしとらんのか」
どこかから聞き慣れた声がしたと思って辺りを見渡せば、突然目の前へ降りてきたのはパウリーさんの職長仲間であるカクさんだった。「山風」の異名を持つ彼はまたどこかから飛んできたのだろうか。
「き、聞いてたんですか!」
「聞こえたんじゃ。しかしあのパウリーに恋人ができたなんて聞いたときはたまげたもんじゃったが、結局あいつは何もできとらんのか……わしがパウリーにガツンと言ってやろうか?」
「え!!いいですよ!やめてください!」
冗談じゃない!と言わんばかりにブンブンと手と頭を振り回せば、カクさんは「そうか」と言って存外すぐに引き下がった。
「……そもそもあのパウリーさんと恋人どうしってだけで奇跡みたいなもんですし、さっき話したのはちょっとしたワガママみたいなやつです。忘れてください!」
割と本心でそう話したのに、2人揃って可哀想なものを見るみたいな目つきをされた。やめて!そんな目で見ないで!!
そろそろ日付が変わる時間だろうか。
今日は政府の役人がアイスバーグさんを訪ねたり海賊が暴れたりと問題が重なって、それらの処分に手間取っていたらいつもより随分遅い時間になってしまった。基本は定時で帰れる職場だが、今日みたいに帰りが遅くなる日が多々ある。しかしこんなに遅くなったのは初めてだった。
他の事務職の人たちはとっくに仕事を切り上げて帰っていったし、比較的遅くまで付き合ってくれたカリファさんも予定があるからと言って退社してしまった。
本社が自宅であるアイスバーグさんからの声援を受けつつようやく仕事を終わらせたのはついさっきで、この後の帰路はいつもならパウリーさんと一緒だけれど、さすがに今日はもう帰ってしまっただろうか。
なんて思いながらトボトボと本社を後にすれば、こんな誰もいないような夜中の造船所に人影が見えた。
「ヒッ…………泥棒……!?」
「ハァ?何言ってんだナマエ、おれだおれ!」
呆れるような声と共にこちらへ近づいてきたその人の顔が月明かりに照らされて露わになった。なんと珍しいことに、今は葉巻を咥えていないようだ。
「パウリーさ……。……えっなんで」
「なんでもなにもいつも帰りは一緒だろうがよ。こんな遅くまで仕事してたのか?オラ、帰るぞ」
そう言って少し乱暴にわたしから鞄を奪い取った彼は照れくさそうに反対側の手を差し出した。少し驚いたけれど、わたしは飛びつくみたいにしてすぐにその手を取った。これで、手を繋ぐのは4回目だ。わたしは思わず口元を緩ませた。
「……昼間カクによ」
「え?」
少しの街灯に照らされただけの暗い夜道を2人歩く途中、不意に口を開いたのはパウリーさんだった。
「カクに言われたんだ、おめェにもう少し恋人らしくしてやれって」
言うなって言ったのに結局言ったのかあの木人形め。だけどそのおかげでこうして手を繋げたわけだし、次会ったら一言くらいお礼を言っておこう。
「言われてみれば確かにもうそろそろ2ヶ月経つんだよな。恋人らしいこと何もしてやれてねェで、その……悪かったな」
「え!いや…………いいんです。そりゃあそういうのに憧れたりはしますけど……パウリーさん、ハレンチなの苦手でしょ?だからそんな無理してもらわないで……」
わたしより断然身長の高い彼を見上げれば、至極真面目そうな表情のパウリーさんと視線がかち合った。その眼差しから何故か逃げられなくて、気がつけばお互い歩くのを止めていた。
水路のせせらぎだけが静かに響き渡っている。ふと繋いでいた手が離されたものだから切なさに少しだけ胸が締め付けられたと思ったのも束の間、離れた彼の右手はわたしの頬へ移っていた。ひどく優しく頬に触れる掌から彼の温度とほんの少しの震えを感じる。
緊張のあまりドコドコと波打つわたしの鼓動が煩くて、それを誤魔化すみたいに行き場のなくなった手をぎゅっと握りしめた。
「……目ェ閉じてろ」
掠れた彼の声に心地いい擽ったさを感じながら、言われるままに瞼を下ろした。
すると数秒の間をあけて、不器用に押しつけられた柔らかなものがわたしのそれと重なった。
いつの間にか鞄を持つ彼の左手はわたしの肩に置かれていて、わたしもそれに応えるように彼の背中へ両手を回し、ジャケットを小さく掴んだ。
ああ、わたしとパウリーさんは今、キスしているんだ。 わたしは幸福感に満ち溢れて、嬉しくて思わず涙が溢れてしまうかと思ったけれど必死でそれを堪えた。
初めての距離に心臓の音はやっぱりうるさくて、だけどそれがどちらのものなのかははっきりしなかった。
永遠だったような一瞬だったような時が過ぎて、2人の顔は離れた。目をあけてみれば笑ってしまいそうなほど赤く火照らせたパウリーさんの顔が目の前にあったけれど、それはきっとわたしも同じなのだろう。
頬に置かれたままだった彼の右手が離されたかと思えば、わたしの身体は勢いよく抱き寄せられた。
「わっ?!」
突然上半身を引かれたものだからわたしはよろめいて、全体重を預ける形で彼に向かって倒れ込んだ。転げてしまわないように彼の背中をぎゅっと抱きしめる。
……なんだか次々と幸せなことばかり起こっているが、一体なんなのだろう。そろそろ脳がキャパオーバーを起こしてショートしてしまいそうだ。
「あ、あの、パウリーさん……?」
「…………こうやっておめェを抱き締めてみてェと随分考えてた」
静かに話し始めた彼のトーンは真面目そのもので、わたしは口を挟むことなく言葉の続きを待った。
「けどおめェはハレンチな服とか着ねェし、そんなおめェにこんな不埒なこと言っていいもんなのかと……」
「な、なんですかそれえ」
彼があまりにばつが悪そうに言うものだから、拍子抜けしたわたしはそれがおかしくてクスクスと笑ってしまった。
パウリーさんの中ではわたしも所謂"ハレンチが苦手なひと"になっていたということだろうか。それは普段の服装も原因のひとつだとは思うけれど、どうやらわたしたちは遠慮しすぎてお互いのことをちゃんとわかっていなかったみたいだ。
仮にも2ヶ月弱もの間を恋人として過ごしてきたというのになんて今更な話だろうと、2人して静かな夜道で声をあげて笑いあった。
「わたしだって、ずっとパウリーさんと同じこと思ってたんですよ!」
とりあえず、明日はスカートを履いてみよう。
至る所から漂う木材の良い香りとリズム良く鼓膜を叩く工具の音。突然轟いたのは街一番の造船工場には似合わない、そんな怒声だった。
その場の誰もが一度は視線を向けるけれど、すぐに「またか」とでも言うように自らの作業に戻っていく。
この街でハレンチだなんて叫ぶのは、誰に問うてもあの男の名前しか上がらない。
皆が憧れるガレーラカンパニー1番ドックの職長が1人、いつも借金取りに追われていて葉巻を咥えずにはいられないニコチン中毒ーーーついでに言えばなんとわたしの恋人、パウリーさんだ。
そんな彼の言葉の飛ぶ先にいるのはカリファさん。わたしの先輩にあたる方で市長アイスバーグさんのスーパー秘書、おまけにスーパー美人ときた。とにかくスーパーな彼女は、いつもそのスーパーに美しい御御足を短いスカートから覗かせている。
男だらけの世界で仕事をしてきたものだから女性の露出に耐性がないなんて話すパウリーさんは、そんな彼女を見かける度に先程のような怒声を浴びせているのだ。
「カリファ、てめェは何度言やァわかる!ここは男の職場だぞ!」
「落ち着いてパウリー」
「うるせェ!少しはナマエを見習え!」
顔を真っ赤にさせながらビシと差した指は間違いなくわたしに向いていて、いきなり話を振られたものだからびっくりして身を縮こまらせてしまった。
わたしは彼の言うような所謂"ハレンチ"な格好はしていない。いつも着ているのは、第1ボタンまでしっかり留めた装飾の少ないブラウスにハイウエストのジーンズ。だけどそれは別に彼が破廉恥だとか言うからではなくて、単にラフな服装が好きなのだ、わたしは。
「いやァ、わたしは……」
「パウリー、前から言おうと思っていたけどあなたナマエを縛りすぎじゃないかしら?恋人だからといって好きな服装も着させてあげないのは可哀想よ」
「ハァ?!なんでおれだよ!んなこと縛っちゃいねェし……」
「あら、そろそろ時間ね。行きましょうナマエ」
「あっおい!」
ドック内に設置された時計を一瞥した彼女はそっとわたしの肩を支え、カンパニーの本社へ向けて歩き始めた。背後から未だ騒がしいパウリーさんの声が聞こえていたが、仕方がないので放っておくことにした。
「最近はどうなの?」
本社へ向かう途中、不意にカリファさんから声をかけられた。パウリーさんとのことだ。
彼女はいつもわたしと彼のことを気にかけてくれて、よく相談にも乗ってくれる。
「ウーン、相変わらずですね」
「相変わらずって……まだキスしてないの?」
「うう……まあ」
彼女の発言にハハと乾いた笑いを送れば、カリファさんは困ったように眉尻を下げた。
ガレーラカンパニーの事務員として仕事をするうちにパウリーさんに惹かれていったわたしは少しでもお近づきになりたくて会うたびに声をかけ続けていた。そしたらなんと彼の方から顔を真っ赤にして交際を申し出てくれたのが、つい1ヶ月半前の話。ハレンチだハレンチだと日々喚いている彼からまさか告白されるなんて思ってもいなかったわたしは大喜びで、翌日発熱したことも記憶に新しい。
そう、交際を始めてそろそろ2ヶ月が経とうとしている今、わたしとパウリーさんはキスはおろか実は手を繋いだことさえ僅か3回だけだ。少ないからどんな場面だったかもばっちり覚えている。
……と言っても彼の性質はわかっているつもりだし、無理強いとかをする気はさらさらないのだけど……
「さすがに2ヶ月何もないのは、ほんとに付き合ってるのか不思議になってきちゃいますね……」
「ナマエ……」
ポロと溢れた本音に思わず自分で肩を落とした。
告白されたのは実は夢だったんじゃないか、なんて考えが過ることもあるけど、交際を始めてからと言うものの毎日事務仕事で帰りが遅くなるわたしを彼は家まで送ってくれているのだ。これが夢なわけがない。
「なんじゃ、お前さんらまだキスもしとらんのか」
どこかから聞き慣れた声がしたと思って辺りを見渡せば、突然目の前へ降りてきたのはパウリーさんの職長仲間であるカクさんだった。「山風」の異名を持つ彼はまたどこかから飛んできたのだろうか。
「き、聞いてたんですか!」
「聞こえたんじゃ。しかしあのパウリーに恋人ができたなんて聞いたときはたまげたもんじゃったが、結局あいつは何もできとらんのか……わしがパウリーにガツンと言ってやろうか?」
「え!!いいですよ!やめてください!」
冗談じゃない!と言わんばかりにブンブンと手と頭を振り回せば、カクさんは「そうか」と言って存外すぐに引き下がった。
「……そもそもあのパウリーさんと恋人どうしってだけで奇跡みたいなもんですし、さっき話したのはちょっとしたワガママみたいなやつです。忘れてください!」
割と本心でそう話したのに、2人揃って可哀想なものを見るみたいな目つきをされた。やめて!そんな目で見ないで!!
そろそろ日付が変わる時間だろうか。
今日は政府の役人がアイスバーグさんを訪ねたり海賊が暴れたりと問題が重なって、それらの処分に手間取っていたらいつもより随分遅い時間になってしまった。基本は定時で帰れる職場だが、今日みたいに帰りが遅くなる日が多々ある。しかしこんなに遅くなったのは初めてだった。
他の事務職の人たちはとっくに仕事を切り上げて帰っていったし、比較的遅くまで付き合ってくれたカリファさんも予定があるからと言って退社してしまった。
本社が自宅であるアイスバーグさんからの声援を受けつつようやく仕事を終わらせたのはついさっきで、この後の帰路はいつもならパウリーさんと一緒だけれど、さすがに今日はもう帰ってしまっただろうか。
なんて思いながらトボトボと本社を後にすれば、こんな誰もいないような夜中の造船所に人影が見えた。
「ヒッ…………泥棒……!?」
「ハァ?何言ってんだナマエ、おれだおれ!」
呆れるような声と共にこちらへ近づいてきたその人の顔が月明かりに照らされて露わになった。なんと珍しいことに、今は葉巻を咥えていないようだ。
「パウリーさ……。……えっなんで」
「なんでもなにもいつも帰りは一緒だろうがよ。こんな遅くまで仕事してたのか?オラ、帰るぞ」
そう言って少し乱暴にわたしから鞄を奪い取った彼は照れくさそうに反対側の手を差し出した。少し驚いたけれど、わたしは飛びつくみたいにしてすぐにその手を取った。これで、手を繋ぐのは4回目だ。わたしは思わず口元を緩ませた。
「……昼間カクによ」
「え?」
少しの街灯に照らされただけの暗い夜道を2人歩く途中、不意に口を開いたのはパウリーさんだった。
「カクに言われたんだ、おめェにもう少し恋人らしくしてやれって」
言うなって言ったのに結局言ったのかあの木人形め。だけどそのおかげでこうして手を繋げたわけだし、次会ったら一言くらいお礼を言っておこう。
「言われてみれば確かにもうそろそろ2ヶ月経つんだよな。恋人らしいこと何もしてやれてねェで、その……悪かったな」
「え!いや…………いいんです。そりゃあそういうのに憧れたりはしますけど……パウリーさん、ハレンチなの苦手でしょ?だからそんな無理してもらわないで……」
わたしより断然身長の高い彼を見上げれば、至極真面目そうな表情のパウリーさんと視線がかち合った。その眼差しから何故か逃げられなくて、気がつけばお互い歩くのを止めていた。
水路のせせらぎだけが静かに響き渡っている。ふと繋いでいた手が離されたものだから切なさに少しだけ胸が締め付けられたと思ったのも束の間、離れた彼の右手はわたしの頬へ移っていた。ひどく優しく頬に触れる掌から彼の温度とほんの少しの震えを感じる。
緊張のあまりドコドコと波打つわたしの鼓動が煩くて、それを誤魔化すみたいに行き場のなくなった手をぎゅっと握りしめた。
「……目ェ閉じてろ」
掠れた彼の声に心地いい擽ったさを感じながら、言われるままに瞼を下ろした。
すると数秒の間をあけて、不器用に押しつけられた柔らかなものがわたしのそれと重なった。
いつの間にか鞄を持つ彼の左手はわたしの肩に置かれていて、わたしもそれに応えるように彼の背中へ両手を回し、ジャケットを小さく掴んだ。
ああ、わたしとパウリーさんは今、キスしているんだ。 わたしは幸福感に満ち溢れて、嬉しくて思わず涙が溢れてしまうかと思ったけれど必死でそれを堪えた。
初めての距離に心臓の音はやっぱりうるさくて、だけどそれがどちらのものなのかははっきりしなかった。
永遠だったような一瞬だったような時が過ぎて、2人の顔は離れた。目をあけてみれば笑ってしまいそうなほど赤く火照らせたパウリーさんの顔が目の前にあったけれど、それはきっとわたしも同じなのだろう。
頬に置かれたままだった彼の右手が離されたかと思えば、わたしの身体は勢いよく抱き寄せられた。
「わっ?!」
突然上半身を引かれたものだからわたしはよろめいて、全体重を預ける形で彼に向かって倒れ込んだ。転げてしまわないように彼の背中をぎゅっと抱きしめる。
……なんだか次々と幸せなことばかり起こっているが、一体なんなのだろう。そろそろ脳がキャパオーバーを起こしてショートしてしまいそうだ。
「あ、あの、パウリーさん……?」
「…………こうやっておめェを抱き締めてみてェと随分考えてた」
静かに話し始めた彼のトーンは真面目そのもので、わたしは口を挟むことなく言葉の続きを待った。
「けどおめェはハレンチな服とか着ねェし、そんなおめェにこんな不埒なこと言っていいもんなのかと……」
「な、なんですかそれえ」
彼があまりにばつが悪そうに言うものだから、拍子抜けしたわたしはそれがおかしくてクスクスと笑ってしまった。
パウリーさんの中ではわたしも所謂"ハレンチが苦手なひと"になっていたということだろうか。それは普段の服装も原因のひとつだとは思うけれど、どうやらわたしたちは遠慮しすぎてお互いのことをちゃんとわかっていなかったみたいだ。
仮にも2ヶ月弱もの間を恋人として過ごしてきたというのになんて今更な話だろうと、2人して静かな夜道で声をあげて笑いあった。
「わたしだって、ずっとパウリーさんと同じこと思ってたんですよ!」
とりあえず、明日はスカートを履いてみよう。