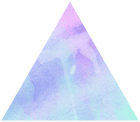※眠れる森の美女主題歌“いつか夢で”をイメージソングとして書いています。
※夢主≠監督生
「……それで、アンタが例の新入生ね」
「ふふっ、よろしくお願いしますわ。えーっと、ヴィル?」
にこりと上品に笑う彼女はここへ来る以前から学園中で話題だった。なんせ男子校であるこのナイトレイブンカレッジに、女子が入学してくると言うのだから当然だ。
どこだかの国の公爵令嬢だという彼女は父親の多額の寄付金によってこの学園への入学を認められたらしい。相変わらず後ろ暗い学園……。どこぞの砂漠の寮長様みたいね。
「そう、アタシが寮長のヴィル・シェーンハイト。それと世間知らずのアンタにひとつ教えてあげる。歳上には敬称を付けなさい」
「敬称……ヴィル様?」
「まあそれでもいいけれど……。とにかくアンタがどれだけ偉かろうがここではアタシがルールなの。それをわかっておきなさいね」
「そうなのね。わかったわ」
「…………」
はあ、と小さくため息を吐いた。
学園長からの話によると、彼女は3歳の時に社交パーティーに参加して以来一度も外の世界へ出されなかった「ド」の付く箱入り娘らしい。そのパーティーで誘拐されかけたせいでそんなことになったそうなのだけど、それにしても一度もっていうのは少しやりすぎじゃないかしら。
本で見た学園生活というものを送ってみたい、と駄々をこねたこの子に折れた父親が「自分の出身校なら」ということで学園に掛け合い、こうして入学が叶ったのだとか。長年家の中に閉じ込めていたくせに一転して男子校へ放り込むだなんて、父親は過保護なのか考えなしなのか。よくわからない。
「入学式にも出ていなかったようだけれど」
「たくさんの人が集まるお式に出るのはいけないって、お父様に止められていますの。式典服だって、着るの楽しみにしてたのに……」
そう言ってつまらなそうにオーダーメイドの制服のスカートの裾をいじる。当然ナイトレイブンカレッジには男子の制服しかないので、彼女のために新しく女子制服がデザインされたのだという。
「それはアンタのお父様がアンタを想ってのことでしょう。ついでに言っておいてあげるけど、この学園で過ごすのならくれぐれも男には気をつけなさいよ」
「あら、心配してくださるんですか?」
「自分の寮生が何かトラブルに巻き込まれたんじゃ寝覚めが悪いだけよ。オオカミの大群に小さなお花ちゃんが一輪飛び込むようなものなんだから」
「? オオカミはお花を愛でないわ」
「そういうところよ」
またひとつ息を吐いた。こんなふうに何も知らない彼女が、この学園で生き抜いていけるのだろうか。
しかし彼女はというと、爛々と瞳を輝かせながら細く小さな手指を口元できゅっと組んでみせた。
「それにもしもオオカミが襲ってきてもきっと大丈夫だわ。だってわたしには王子様がいるんですもの」
「……へぇ、王子様との婚約でも決まっているの?」
「いいえ、正式には。だけどいつか絶対迎えに来てくださるのよ」
「…………ちなみにその人に会ったことは?」
「毎日会ってるわ、夢の中で!」
────言葉が出ないってこういうことを言うのね。
満面の笑みで彼女が夢で会った王子様の話をしてくれているけれどアタシの頭には何ひとつ入ってきやしなかった。やっぱり10年以上も家の中に閉じ込められていたんじゃ頭もおかしくなってしまうらしい。かわいそうに。
「とにかく、その“王子様”がいるのだとしても、最低限自分の身は守れるように気をつけておきなさいよ」
「ええ、わかったわヴィル様」
目を細め笑い素直に返事をする彼女だけれど、きっと何もわかっていないのだろう。アタシはもう一度深くため息を吐いた。
* * *
入学初日にヴィル様はああ言っていたけれど、きっと心配のしすぎだ。遠い記憶の中にある3歳の社交パーティーではなにかよくないことが起こったそうだけれど、それ以来そんなことは一度もなかったのだから。
だからきっと、今こうして3人の大柄な男性に囲まれているのも皆わたしとお友達になりたいと思っているに違いないのよ。
「へえ、今年は女が入学してきたってのはホントだったんだな」
「男子校に入ってくるってことは、やっぱ痴女なの? ヤられ願望あり??」
「……? チジョ……って、なんですの?」
「え? あ、もしかして何も知らない系? じゃあ俺らが手取り足取り教えてあげるしさ、あっち行こうぜ」
そう言った男性に手首を強く握り引っ張られた。もげるかと思った。
「いっ……! いた、や、やめてください……!」
「ええ? んな強くしてねーじゃん、大袈裟〜」
ヘラヘラ笑っているけれど、絶対大袈裟なんかじゃない。こんなに強い力で腕を掴まれるのは初めてだもの。まあ、そもそも男性に腕を掴まれること自体が初めてなのだけれど。
じわりと、目頭に涙が滲んだ。もし何か起きてもわたしならきっとどうにか対処できる、なんとかなる、大丈夫、と思っていたのに、いざこうして男女の力の差を思い知ると途端に怖くなってきてしまった。抵抗できない。不安だ。
助けて、誰か、王子様……!
「るっせーなぁ……」
恐怖できゅっと瞑っていた目蓋をはっと見開いた。背後から聞こえてきたその声は、なんだかどこかで聞いたことがあるような、ないような。
わたしを囲んでいた男性達を見上げてみると怖気付くみたいに顔を硬らせていて、腕を掴む力も少し弱まった。咄嗟に腕を引き男性から一歩退いて声のした方を振り向くと、わたしははっと息を飲むことになった。
「てめぇら……俺の睡眠を妨げるとはいい度胸じゃねぇか」
「レ……っ! レオナさん!」
「いや違うんスよ、偶然というか、俺たちレオナさんがここで昼寝してるなんて知らなくて……」
「だがその昼寝の邪魔をしたことは確かだよなぁ?」
「ヒッ……!」
先程まであんなに怖かった男性達が情けなく身を縮こまらせている。だけどそんなことは微塵も気にならなかった。気にしている場合ではなかった。
だって、だって目の前に────。
「す、すみませんでしたァ!!」
慌ただしい声にはっと気がついて振り返れば、3人組がドタドタと駆け出し逃げていくところだった。
すごい。あんなに恐ろしい男性たちを、あっという間に1人で追っ払ってしまった。感動で胸が躍るようだわ。
走る鼓動が鳴り止まない。ああ、さすがわたしの、
「王子様……!」
「………………は?」
* * *
「あーっはっはっは! アンタが“夢で会った王子様”……!!」
「おいヴィルどういうことだ、笑ってねぇで説明しろ」
アタシが中庭で優雅にお茶をしていたところに野良猫が飛び込んできたかと思いきや、なんとそれはうちのお花ちゃんを連れたレオナ・キングスカラーだった。
ナマエが早速どんなことをしでかしたのかと話を聞けば、この野蛮男があの例の王子様だとか抜かすものだから笑うしかないじゃない。
「この子は毎晩夢でアンタに会ってるそうよ」
「ああ? んなわけねーだろ、初対面だぞ。人違いじゃねぇのか」
「間違うはずありませんわ!!」
不意に、先程まで惚けて大人しかったナマエがやや興奮気味に声を上げてレオナに詰め寄る。レオナが引いているだなんて珍しい……と思ったけれど、コイツは故郷の慣しで女性に強く出られないとかってたしかラギーが言ってたかしら。
「あなたをいつも夢に見ているんですもの。その新緑のように透き通った翡翠の瞳さえとても懐かしい…………。だから、絶対に間違うはずがないんですわ」
そう言って恍惚としながら己を見つめるナマエに、レオナは難しい顔をした。満更でもないなんて言い方をすればさすがに嘘になるけれど、心底不満ではない、拒絶はしない、といった感じだ。まさかあの自己中心俺様ひねくれ男のこんな表情を見る時がくるなんて、驚きね。
「まあたしかに、アンタ仮にも第二王子なわけだし。案外ナマエが3歳の時に行ったっていう社交パーティーで会ってたりするんじゃない?」
「んな昔のこと覚えてるわけねぇだろ……」
「あら、そう? まあなんにせよ、これで安心して学園生活を送れるわね、ナマエ」
ふと声をかけられたナマエはわたしと視線を合わせると、そうですわね、とゆるりと目を細めて嬉しそうに微笑んだ。
それにしても、あれだけ気を付けろと言ったはずなのに入学早々迫られるとは。偶然近くにレオナがいて、偶然レオナの気が向いて口を挟んでくれたからよかったものの、もしそうでなかったらと考えるとゾッとする。不覚にもアタシはこの男に感謝してしまうのだった。本意じゃないけれど。
----------
『キングスカラー殿! まさか貴方もこのパーティに参加されているとは。お久しぶりだ』
『ああ、ミョウジ殿か。随分と久しいな……ん? そちらの少女は……』
『おっと、紹介が遅くなって申し訳ない。娘のナマエだ』
『は、はじめまして……』
『この子が……! 貴方に娘ができたと噂には聞いていたよ。ようやくお目にかかれて光栄だ。そうだ、今日は私の息子達もいるんだ。彼女に紹介しよう……っと、レオナ、兄さんはどうした?』
『知り合いがいたって、向こうに』
『そうか、仕方ない。ではレオナ、お前だけでも挨拶なさい』
『……レオナ・キングスカラーです』
『ナマエともうします。レオナさま、お会いできてうれしいわ』
※夢主≠監督生
「……それで、アンタが例の新入生ね」
「ふふっ、よろしくお願いしますわ。えーっと、ヴィル?」
にこりと上品に笑う彼女はここへ来る以前から学園中で話題だった。なんせ男子校であるこのナイトレイブンカレッジに、女子が入学してくると言うのだから当然だ。
どこだかの国の公爵令嬢だという彼女は父親の多額の寄付金によってこの学園への入学を認められたらしい。相変わらず後ろ暗い学園……。どこぞの砂漠の寮長様みたいね。
「そう、アタシが寮長のヴィル・シェーンハイト。それと世間知らずのアンタにひとつ教えてあげる。歳上には敬称を付けなさい」
「敬称……ヴィル様?」
「まあそれでもいいけれど……。とにかくアンタがどれだけ偉かろうがここではアタシがルールなの。それをわかっておきなさいね」
「そうなのね。わかったわ」
「…………」
はあ、と小さくため息を吐いた。
学園長からの話によると、彼女は3歳の時に社交パーティーに参加して以来一度も外の世界へ出されなかった「ド」の付く箱入り娘らしい。そのパーティーで誘拐されかけたせいでそんなことになったそうなのだけど、それにしても一度もっていうのは少しやりすぎじゃないかしら。
本で見た学園生活というものを送ってみたい、と駄々をこねたこの子に折れた父親が「自分の出身校なら」ということで学園に掛け合い、こうして入学が叶ったのだとか。長年家の中に閉じ込めていたくせに一転して男子校へ放り込むだなんて、父親は過保護なのか考えなしなのか。よくわからない。
「入学式にも出ていなかったようだけれど」
「たくさんの人が集まるお式に出るのはいけないって、お父様に止められていますの。式典服だって、着るの楽しみにしてたのに……」
そう言ってつまらなそうにオーダーメイドの制服のスカートの裾をいじる。当然ナイトレイブンカレッジには男子の制服しかないので、彼女のために新しく女子制服がデザインされたのだという。
「それはアンタのお父様がアンタを想ってのことでしょう。ついでに言っておいてあげるけど、この学園で過ごすのならくれぐれも男には気をつけなさいよ」
「あら、心配してくださるんですか?」
「自分の寮生が何かトラブルに巻き込まれたんじゃ寝覚めが悪いだけよ。オオカミの大群に小さなお花ちゃんが一輪飛び込むようなものなんだから」
「? オオカミはお花を愛でないわ」
「そういうところよ」
またひとつ息を吐いた。こんなふうに何も知らない彼女が、この学園で生き抜いていけるのだろうか。
しかし彼女はというと、爛々と瞳を輝かせながら細く小さな手指を口元できゅっと組んでみせた。
「それにもしもオオカミが襲ってきてもきっと大丈夫だわ。だってわたしには王子様がいるんですもの」
「……へぇ、王子様との婚約でも決まっているの?」
「いいえ、正式には。だけどいつか絶対迎えに来てくださるのよ」
「…………ちなみにその人に会ったことは?」
「毎日会ってるわ、夢の中で!」
────言葉が出ないってこういうことを言うのね。
満面の笑みで彼女が夢で会った王子様の話をしてくれているけれどアタシの頭には何ひとつ入ってきやしなかった。やっぱり10年以上も家の中に閉じ込められていたんじゃ頭もおかしくなってしまうらしい。かわいそうに。
「とにかく、その“王子様”がいるのだとしても、最低限自分の身は守れるように気をつけておきなさいよ」
「ええ、わかったわヴィル様」
目を細め笑い素直に返事をする彼女だけれど、きっと何もわかっていないのだろう。アタシはもう一度深くため息を吐いた。
* * *
入学初日にヴィル様はああ言っていたけれど、きっと心配のしすぎだ。遠い記憶の中にある3歳の社交パーティーではなにかよくないことが起こったそうだけれど、それ以来そんなことは一度もなかったのだから。
だからきっと、今こうして3人の大柄な男性に囲まれているのも皆わたしとお友達になりたいと思っているに違いないのよ。
「へえ、今年は女が入学してきたってのはホントだったんだな」
「男子校に入ってくるってことは、やっぱ痴女なの? ヤられ願望あり??」
「……? チジョ……って、なんですの?」
「え? あ、もしかして何も知らない系? じゃあ俺らが手取り足取り教えてあげるしさ、あっち行こうぜ」
そう言った男性に手首を強く握り引っ張られた。もげるかと思った。
「いっ……! いた、や、やめてください……!」
「ええ? んな強くしてねーじゃん、大袈裟〜」
ヘラヘラ笑っているけれど、絶対大袈裟なんかじゃない。こんなに強い力で腕を掴まれるのは初めてだもの。まあ、そもそも男性に腕を掴まれること自体が初めてなのだけれど。
じわりと、目頭に涙が滲んだ。もし何か起きてもわたしならきっとどうにか対処できる、なんとかなる、大丈夫、と思っていたのに、いざこうして男女の力の差を思い知ると途端に怖くなってきてしまった。抵抗できない。不安だ。
助けて、誰か、王子様……!
「るっせーなぁ……」
恐怖できゅっと瞑っていた目蓋をはっと見開いた。背後から聞こえてきたその声は、なんだかどこかで聞いたことがあるような、ないような。
わたしを囲んでいた男性達を見上げてみると怖気付くみたいに顔を硬らせていて、腕を掴む力も少し弱まった。咄嗟に腕を引き男性から一歩退いて声のした方を振り向くと、わたしははっと息を飲むことになった。
「てめぇら……俺の睡眠を妨げるとはいい度胸じゃねぇか」
「レ……っ! レオナさん!」
「いや違うんスよ、偶然というか、俺たちレオナさんがここで昼寝してるなんて知らなくて……」
「だがその昼寝の邪魔をしたことは確かだよなぁ?」
「ヒッ……!」
先程まであんなに怖かった男性達が情けなく身を縮こまらせている。だけどそんなことは微塵も気にならなかった。気にしている場合ではなかった。
だって、だって目の前に────。
「す、すみませんでしたァ!!」
慌ただしい声にはっと気がついて振り返れば、3人組がドタドタと駆け出し逃げていくところだった。
すごい。あんなに恐ろしい男性たちを、あっという間に1人で追っ払ってしまった。感動で胸が躍るようだわ。
走る鼓動が鳴り止まない。ああ、さすがわたしの、
「王子様……!」
「………………は?」
* * *
「あーっはっはっは! アンタが“夢で会った王子様”……!!」
「おいヴィルどういうことだ、笑ってねぇで説明しろ」
アタシが中庭で優雅にお茶をしていたところに野良猫が飛び込んできたかと思いきや、なんとそれはうちのお花ちゃんを連れたレオナ・キングスカラーだった。
ナマエが早速どんなことをしでかしたのかと話を聞けば、この野蛮男があの例の王子様だとか抜かすものだから笑うしかないじゃない。
「この子は毎晩夢でアンタに会ってるそうよ」
「ああ? んなわけねーだろ、初対面だぞ。人違いじゃねぇのか」
「間違うはずありませんわ!!」
不意に、先程まで惚けて大人しかったナマエがやや興奮気味に声を上げてレオナに詰め寄る。レオナが引いているだなんて珍しい……と思ったけれど、コイツは故郷の慣しで女性に強く出られないとかってたしかラギーが言ってたかしら。
「あなたをいつも夢に見ているんですもの。その新緑のように透き通った翡翠の瞳さえとても懐かしい…………。だから、絶対に間違うはずがないんですわ」
そう言って恍惚としながら己を見つめるナマエに、レオナは難しい顔をした。満更でもないなんて言い方をすればさすがに嘘になるけれど、心底不満ではない、拒絶はしない、といった感じだ。まさかあの自己中心俺様ひねくれ男のこんな表情を見る時がくるなんて、驚きね。
「まあたしかに、アンタ仮にも第二王子なわけだし。案外ナマエが3歳の時に行ったっていう社交パーティーで会ってたりするんじゃない?」
「んな昔のこと覚えてるわけねぇだろ……」
「あら、そう? まあなんにせよ、これで安心して学園生活を送れるわね、ナマエ」
ふと声をかけられたナマエはわたしと視線を合わせると、そうですわね、とゆるりと目を細めて嬉しそうに微笑んだ。
それにしても、あれだけ気を付けろと言ったはずなのに入学早々迫られるとは。偶然近くにレオナがいて、偶然レオナの気が向いて口を挟んでくれたからよかったものの、もしそうでなかったらと考えるとゾッとする。不覚にもアタシはこの男に感謝してしまうのだった。本意じゃないけれど。
----------
『キングスカラー殿! まさか貴方もこのパーティに参加されているとは。お久しぶりだ』
『ああ、ミョウジ殿か。随分と久しいな……ん? そちらの少女は……』
『おっと、紹介が遅くなって申し訳ない。娘のナマエだ』
『は、はじめまして……』
『この子が……! 貴方に娘ができたと噂には聞いていたよ。ようやくお目にかかれて光栄だ。そうだ、今日は私の息子達もいるんだ。彼女に紹介しよう……っと、レオナ、兄さんはどうした?』
『知り合いがいたって、向こうに』
『そうか、仕方ない。ではレオナ、お前だけでも挨拶なさい』
『……レオナ・キングスカラーです』
『ナマエともうします。レオナさま、お会いできてうれしいわ』