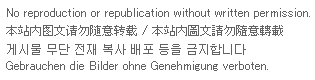- さめない夢の中で眠ろう -
低級悪魔 × 魔女
今年も私の大嫌いなハロウィンがやってくる。ゴーストたちの歌声にのってパンプキン・ホプキンスが冥界から人間界へとやってくるのだ。鼻歌交じりに大きなカボチャのマスクを被って、今頃は薄暗い夜道を歩き、その先に佇む丘の上の小さな私のお家を目指しているに違いない。現在の時刻は11:59だ。ああ、もうすぐ日付が変わりそう。……サン、ニ、イチ。
「ハッピーハロウィーン!元気だったかい?リリー」
「……ノックくらいしてよ」
「君とボクの間柄じゃないか。いいだろ、別に」
「どんな関係よ、全くもう」
期待を裏切らずにドンッという扉の開く音と共にスーツ姿で現れたのはやっぱりあの人だった。毎年この時期になるとふらりとやってくる。個性的な被り物の素顔は今まで1度たりとも見たことがない。そもそもこの男の素顔はこのカボチャじゃないんだろうか、とすら思える。易々と私にハグを交わして視界の悪いそれを感じさせないのだから。
「リリー会いたかったよォー」
「相変わらず暑苦しい人ね。今日は何日か知ってる?まだ1日よ、ハロウィンには気が早すぎるんじゃない?」
「いいのいいの。10月になったらハロウィンなんて目前なんだからサ」
そう言って更にギュッと抱き締める力を込めた。私は何を考えているのか分からない、おどけたこのピエロが嫌いだ。毎年この季節に現れるから必然とハロウィンも大嫌いになった。まあ、それ以外にもいくつか理由はあるのだけど。
「どうして、あなたは毎年此処へ?」
「リリーも知ってるでしょ?この時期は都合がいいからネ。この神無月の貴重な月は死者の霊が家族を訪ねたり、精霊や異刑のモノが出てくると信じる人間が多いんだ。それが要因となって冥界と人間界の時空に歪みが生じるってワケ」
「私は魔女として生きるのをやめた。人間として生きることを決めたの。もう、此処にはこないで」
「それは魔女狩りが流行ったから?リリーが魔女だという事実は変わらないよ。君はコッチ側の人間ってこと、忘れちゃイヤ」
「そんな理由じゃないわ。私、もう何年も魔法は使ってないのよ。呪文だって、もう…。そんな出来損ないの魔女を魔女と呼べる?」
半ば八つ当たりのように発してしまったことに後悔はなかった。ただ、私の気持ちを無視して綽々と話すこの人に苛立ちを隠せなかった。魔女狩りを行われて尚、この人間界に留まる理由。それは、
「ボク、知ってるよ。リリーはハロウィンの日に死んじゃった、好きだった人間の男が忘れられないんでしょ。名前はラルフ、だっけ?でも、そいつはこの世にいない。冥界にも、ね。何故か分かる?」
それはゆっくりと静かに、けれども怒気を含んでいるようにも感じた。淡々と彼の紡ぐ言葉1つ1つに疑問を投げつけたい。どうして私の彼の名前を?彼はどこへ行ってしまったの?あなたは何を、知っているの?
「……分からない、わ」
大好きだった彼が亡くなる前日、1つだけ約束を交わした。冥界で会おう、と。今度は冥界で共に暮らそう、って。それなのに、いざ冥界へ行ってみると彼の姿は既になかった。それは何故なんだろう、私に愛想が尽きてしまったんだろうか、あの言葉は嘘だったんだろうか、ずっとそう思っていた。その理由を私の目の前にいるこの人は知っている。
◇
◇
◇
もともとハロウィンは大好きだった。ハロウィンの日は狼男や吸血鬼に仮装した人間に混じってお菓子を貰いに町中を走ったし、手品という名目で魔法を使ってお金を稼ぎ、その日の遊楽に利用したこともあった。そんな中、だ。まだ肌寒さのない10月の始めにラルフと出逢ったのは。
「トリック・オア・トリート」
「はい?」
「お菓子を下さいな、お嬢さん」
にっこり笑いながら大の大人が手の平を出す姿に私はあからさまに怪訝な表情をしていたと思う。変な客に捕まってしまった、ってね。でも、そうじゃなかった。
「なんてね、それは冗談」
「あの、私に何か…?」
「もうこんな時間だし、夜に女の子1人なんて危ないでしょ?だから声をかけたんだ」
彼は私の身を案じて声をかけたらしい。心配性な人、それが第一印象だった。けれど、それ以来この人は私の名ばかりの手品を見にくるようになった。魔女の歪(いびつ)な形をした帽子から飛び出すキャンディー。魔法の杖で叩けば軽快に踊りだすドール。呪文を唱えて指をパチンと鳴らせばカボチャは甘ーいスイートポテトに。私は魔法を私利私欲の為に使い続けた。
◇
◇
◇
彼と親しくなるのに時間はかからなかった。ラルフの名前を知ったのはそれから間もなくのこと。彼は足繁く通い続け、私にこんな話をした。
「やあ、今日もお疲れ様」
「いつも見に来てくれるのね。ありがとう、ラルフ」
「リリーのマジックは本当に凄いよ。まるで本物の魔法みたいだ!」
「魔法だなんて…。大袈裟よ、私は手品師だもの。ちゃんとタネだってあるわ」
そう、そのタネはタネであってタネじゃない。魔女の魔法だけど。彼にこのタネ明かしは絶対にしてはいけないと思った。話してしまったら彼はきっと、私から離れて行ってしまうから。
「え、そうなの?」
「そうよ。誰にも話してない秘密の中の秘密のタネなの」
「うわぁ、凄く気になるー」
彼に嘘をつくのは何回目だろう。私は彼に何度、嘘を重ねるんだろう。少し、罪悪感で胸が痛んだ。
◇
◇
◇
彼に淡い恋心を抱くのに時間は必要なかった。ラルフの病気を知ったのはそれから間もなくしてからだった。最初は体調が悪いと言い、次に頭が痛いと言い、そして私の名ばかりの手品に顔を出すことはなくなった。嫌な予感が脳裏を過(よ)ぎり、丘の上にあるラルフの家まで走った。しかし、チャイムを鳴らせどラルフは出てこない。ドアノブを回せばドアが、開いた。
「ラルフ…?いないの?」
他人様の家に勝手にあがるのは気が引ける。けれど、もしものことがあったら…。そう思ったら無意識に身体が動いていた。
「いるんでしょ、ラルフ!」
叫び声に反応したかのように薄暗い部屋の中からゴトッと音が聞こえた。その音のする方へ近寄ってみると、そこにはベッドから床へ倒れ込んでいる弱りきったラルフの姿だった。
「ラルフ……?!」
「リリー、わざわざ僕に会いに来てくれたのかい…?」
「だって、あなたが顔を見せないから…。心配したのよ、ほんとに……」
駆け寄って彼の身体を起こし、涙ながらに私の思いを伝えるとラルフは困ったような顔をして私の頭をポンポンと撫でる。まるで小さな子をあやすように。私は彼よりも何倍も長く生きているのに不思議な感覚だった。
「子供の頃からこの身体は硝子のようで、とてもデリケートだった…。やっと落ち着いたかと思えば、この様さ」
人生は何が起こるか分からないね、そう弱々しく話すラルフに以前までの元気な姿はなかった。けれど、人間の患う病だ。こんな病くらい、私の魔法ですぐに治ってしまうに違いない。そう安堵する自分がいた。ラルフが生きてくれるなら魔女だとばれてしまっても構わなかった。
「……私ね、ずっとあなたに嘘をついていることがあるの」
「それは君が、魔女ということ…?」
「え、なんで…!知っていたのっ?」
「分かるさ。僕は人間と魔女のハーフ。君のように魔法は使えないけど、母さんの魔法とリリーの魔法は形(かた)が似ていたから…。それに、ね。君のマジックは、見る者たち皆を笑顔にさせた。まるで魔法のように。僕もその1人なんだよ、リリー…?」
ラルフが魔女とのハーフ?じゃあラルフは最初から私の正体を知っていたということ…?知っていながら私に会いに来てくれたんだ。それなら、もっと早く彼に伝えてしまえばよかった。そうすればこうしてラルフが病に苦しむこともなかったのだから。
「待ってて。今、私の魔法であなたの病を治してあげるわ」
「ありがとう、リリー。でも、その必要は、ないよ…。気持ちだけで、充分だから」
「なッ…どうして!この病が完治すればもっと長く生きられるのよ?やりたいことだって、まだあるでしょう?」
私はあなたに長生きしてほしいし、病なんかに負けてほしくない。私ならラルフを救えるし、その力もあるのに。どうして?今にも死んでしまいそうなのに…!そんな思いを察してか、彼は力なくゆっくりと話し始めた。
「僕は人間としての人生を真っ当に生きたいんだ。魔法で治ってしまったら、僕の人生は人生じゃなくなる。この病を抱えたからこそ、僕の生きた証があるのに。それがいきなり消えてしまったら、その僕の生きた意味が分からなくなってしまう…。だから、これでいいんだ。このままで、いい。その代わり、冥界でまた会おう。会って、君と一緒に暮らせたらいいなぁ…」
その晩、私はラルフが眠るベッドの横でわんわん泣いた。何もできない自分が不甲斐なくて、悔しくて。無理矢理に魔法を使ってラルフの病を治してしまうこともできるけど、彼の話を聞いてしまってはそうすることはできなかった。
「……わかった。魔法は、使わない。もう2度と、使ったりしないわ。誰も救えない魔法なんて、必要ないもの…っ。あなたを救えない魔法なんて、もう要らない。こんな力、要らないわ!」
涙でぐちゃぐちゃになった顔で自分への戒めとして彼に誓った。次の日のハロウィン。大好きなハロウィンは大嫌いなハロウィンになった。彼は眠るように亡くなってしまったのだ。彼はもう目覚めない。あの笑顔を見ることも、ない。たった1ヶ月の短く淡い恋はこうして終わった。けれど、冥界に行けば彼に会える。そう、信じていた。
◇
◇
◇
葬式はしめやかに行われた。あれから1年が経ち、彼に誓ったとおり私は魔法を使うことなく日々を過ごした。そうして人間界と冥界に歪みを生じるハロウィンの日に冥界に行ってみれば彼の姿はどこにもいない。一体彼はどこへ?ずっと気掛かりだった。その理由を目の前の男は知っている。


...next page →
×