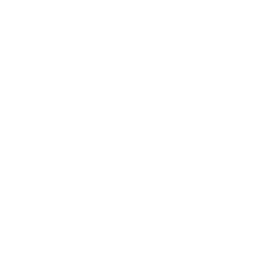
寂しげな背中
日用品コーナーで買い物を済ませると、私は店を出る前、もう一度スマートフォンのメモ帳アプリに入力したリストを確認した。家族を除いて男性と一緒に生活するというのは初めてのことだ。必要なものがいまいちぴんと来ないのだが、必要最低限の物は揃えただろう。足りないものはまた買い足せばいいだけだ。
「煉獄さん。取りあえずこれで大方生活必需品は揃ったと思います。特に必要なものが無ければ、一旦帰りましょうか」
隣の煉獄さんを見れば、彼は奇妙な物を見るように私の手首に巻き付けられたウェアラブルウォッチを眺めていた。
「…これ、気になります?」
「俺は、こちらの世界の通貨や支払いの仕組みがよく分からないのだが、名前は支払いの度にそれを機械に翳していただろう?…それが、通貨の代わりなのか」
「ああ、すみません、ちゃんとこっちの世界のお金の話をしてなくて。大正時代とは貨幣価値が違いますが、勿論この時代にも貨幣はあります。ただ、今はこういう電子マネー…電子通貨?みたいなもので決済することが多いんです」
ウェアラブルウォッチを煉獄さんの目の前に掲げ、端的に説明する。
「よもや…驚いた」
「あ、でも、全部がこれで支払えるわけじゃないです。勿論、基本は紙幣なんですけどね」
驚き入る煉獄さんに慌てて補足すれば、彼は何やら難しそうな表情を作って私を見た。
「これは、名前が働いて得た賃金だろう」
「へ?」
「俺はこんなに君に世話になりっぱなしでいいのだうか。…やはり、心苦しいな」
きっと煉獄さんは、私に食事の世話をされたり、私のお金で彼に必要な物を購入することを申し訳なく思っているのだろう。今の時代には「ひも」と呼ばれる男性も多く居るというのに、本当に真面目で律儀な人だ。
「それは気にしないでください。別に贅沢しなければ煉獄さん一人くらい私のお給料でどうにでもなります。むしろ、食事とかは余らせなくていいかもしれないですし。…確かに、男性の煉獄さんからしたら心苦しいかもしれないですけど…。あ、じゃあ家事とか沢山手伝ってください!それだけでも、私は助かるので」
「名前がそう言うのなら、いいのだが」
どこか腑に落ちない様子だったが、最後は納得してくれたのか彼は短く頷いた。煉獄さんの気持ちを考えれば、何か職を探してあげたい気持ちはやまやまだが、住民票もなければ身分証明書もない彼を、働きに出すことは難しいだろう。それに、煉獄さんはいつ居なくなってしまうかも分からない人なのだから。
出口に向かって肩を並べて歩いていると、季節の催し物のコーナーの一画で、浴衣フェアが行われているのが目に入り思わず足を止める。ブース内では、男女が楽しそうに互いの浴衣を選んでいる姿も見受けられる。
「先ほど名前が言っていた男性物の浴衣もあるな」
「あ、ごめんなさい。そうなんです。この季節は結構取り扱ってることが多いんですよ。…煉獄さん、本当に浴衣買わなくても大丈夫ですか?」
「ああ、本当に気にしないでくれ。それより、名前は浴衣を着ることはないのか?君は和服も似合いそうだが」
ブースに所狭しと並べられた商品を眺めた後、煉獄さんは何食わぬ顔で言って微笑んだ。天然ジゴロは末恐ろしい。これで女を口説いているわけではないのだから心底驚いてしまう。そして彼はきっと、全ての女性に同じことを言うのだろうなと思うと、少しだけ寂しい気持ちになった。
「私は…もう浴衣を着る機会は大分少なくなりましたね。それこそ昔は花火大会に行く時は着て出かけましたけど。…あんまりいい思い出がないんですよ」
「いい思い出?」
「あはは、はい。お恥ずかしいんですけど、花火大会で修羅場になったことがあって」
「修羅場?」
「当時お付き合い…あー煉獄さんの時代の言葉でいうと、所謂恋仲にあった男性ですね。その方と悲惨な別れ方をしたんです。…まぁ、原因は向こうの不倫だったんですけどね。ようは…私が遊ばれてたってだけなんですけど」
そこまで言ってはっとする。煉獄さんに何て情けない話をしているのだろう。それに恐らく、彼の生きている時代は恋仲の異性は生涯の伴侶なのではないか。住む時代が違うとはいえ、尻軽な女に見えてしまっただろうかと不安になって、恐る恐る煉獄さんを見れば、彼は渋面を作っていた。
「そういう不届き者は、悲しいことだがいつの世も存在するのだな。なに、気にする必要はない。君は優しくて魅力的な女性だ。いつか、名前に相応しい男性が必ず現れる」
「っ…」
不憫に思ったのか、煉獄さんはまるで子供をあやすように私の頭を撫でた。たちまち自分の顔が赤くなっていくのが分かる。煉獄さんには何の意図もないだろうが、私の心を掻っ攫うには十分過ぎる言動。顔から火が出そうなほど恥ずかしくて彼を直視出来ず堪らず顔を背ける。すると、見知った老女を視界の端に捉えた。彼女は、自分の身長よりもずっと高い位置にある商品を取ろうと悪戦苦闘していた。
「あ…初枝さん!ご、ごめんなさい煉獄さん。ちょっと私、あのおばあちゃん知り合いなので助けてきます」
私はきょとんとする煉獄さんを置いて老女の元に走る。
「初枝さん、危ないですよ!こんな高い所の物とるなら、ちゃんと店員さんに声かけないと」
「あら、名前ちゃん。偶然ね、こんなところで」
「もう、怪我したら大変じゃないですか。私が代わりに取るので、教えてください」
この老女は、私の住むマンションの近くにある剣道場の奥様で、初枝さんといった。スーパーや近所の公園で何度も遭遇するうちに、次第に顔見知りになり仲良くなったのだ。時々頼まれて買い物を手伝うこともある。
「あのね、男性物のあの帯を取りたいのよ。おじいさんに買って行きたいんだけど」
「あの黄土色の帯ですね。…それにしても初枝さん珍しいですね。いつも買い物は絶対旦那さんと一緒なのに」
私はキョロキョロと周囲を見回し、いつも初枝さんと一緒にいるご主人の姿を探すが、彼の姿は見あたらない。ご主人は未だに現役で剣道場の師範をしているから、その運営で忙しいのだろうか。
「それがねぇ…あの人、腰をやってしまって。今道場はお休みしているのよ」
「え?」
初枝さんの言葉に目を丸くして、私は目当ての商品を取ろうと伸ばしていた爪先を一旦元の位置に戻す。
「困っちゃうわよねぇ。うちは子供もいないから、こういう時に頼れる人がいなくて。お弟子さん達にも申し訳ないし。全治三ヵ月ですって。早く良くなってくれればいんだけど」
初枝さんが伏し目がちに言う。
「そうだったんですか…それは心配ですね」
初枝さんだって若くはないし、ご主人が動けないとなれば色々と大変だろう。何か力になれないだろうかと考えながら、今一度初枝さんお目当ての商品を取ろうと背伸びをして手を伸ばせば、「これでいいのか?」という低い声が耳元で響いて、背後から逞しい腕が伸びてくる。
慌てて背後を振り返れば、身体が触れてしまいそうなほどの近距離に煉獄さんの姿があって、彼は小首を傾げながら、手にしていた帯を差し出した。
「れ、煉獄さん!そうです。すみません、手伝って貰っちゃって」
「いや、構わない。こんなに高い位置にあっては、御婦人には不便だろう」
「助かりました、ありがとうございます。…あ、初枝さん。これで大丈夫でしたか?」
煉獄さんから受け取った帯を初枝さんに手渡せば、彼女は好奇心でいっぱいのような視線で私達を見つめていた。
「やだ、名前ちゃん。この素敵な殿方、名前ちゃんのこれ?」
そう言って、初枝さんは右手の親指をピンと上げた。
「ち、違います!煉獄さんは」
「いいのよ隠さなくて。いいわねぇ、若い人は。それにしても男前なこと」
「初枝さん…違うのに」
私の恋人だなんて、煉獄さんにも申し訳ない。ちらりと隣に立つ煉獄さんを盗み見れば、彼は特段気にした様子もなく「そういう御婦人も美しい!」と爽やかな笑顔を満面に浮かべ初枝さんとの会話に興じているので、まぁいいかという気持ちになってくる。
「あら、貴方も剣をやられるの?」
初枝さんが、煉獄さんの大きな掌を見て声を弾ませる。どうやら、剣道や居合といった武道を極める人達は、手を見るだけでその人が剣に携わる人間か分かってしまうようだ。
「凄いな御婦人、貴方にも分かるのですか。確かに、俺は日常的に剣を握っていました」
「勿論、貴方の手を見れば分かります。ずっと剣をやってこられた方の手ですもの。こんなおばあちゃんでも、夫と一緒に長年道場を経営してきたのよ。それにしても、立派な手ね。さぞ高い技術をお持ちなんでしょうね。…はぁ、貴方みたいな方がうちの道場に教えに来てもらえたら、助かるんだけどねぇ」
初枝さんは悩まし気に溜息を吐いた。私と煉獄さんは顔を見合わせる。
「なんて、ごめんなさいね。年寄りの戯言だと思って聞き流してちょうだい。あ、これ、ありがとうね」
お目当ての帯が入った透明なプラスチックの箱を顔の前で何度か振ってみせ、初枝さんはそのままカートを押して人混みへと紛れていった。私達は、小さな背中が見えなくなるまで、その後ろ姿を眺めていた。