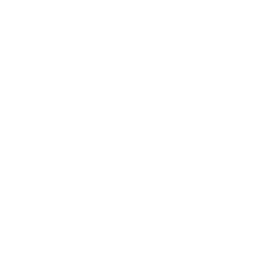
秘めた熱視線
「煉獄さんー、問題なく着られましたか?」
「うむ。問題はなさそうだ」
ショッピングモールに入る大手ファストファッションストア。その試着室の一つに向かって声を掛けると、その直後に扉が開き、こちらの世界の衣類に身を包んだ煉獄さんが姿を現し、「どうだろうか?」と伺うように問うてきた。
「はい…とっても似合っていると思います」
煉獄さんを頭頂部から爪先までまじまじと眺め、私は感心したような息を吐く。着る人が着れば、どんなに安い服だって素敵に見えるのだと、しみじみと感じる。
「そうか、ありがとう!俺の居た時代では洋服を着る機会など殆どなかったが…こちらでは皆こういう衣類を身に着けるのだな」
「煉獄さんの元居た場所は…やっぱり時代的には浴衣や着物が多いんですかね?だったら…洋服ってちょっと慣れないですよね。一応浴衣も見ていきましょうか?今の時季なら花火の季節なので、男性物の浴衣なら取り扱っていると思いますけど」
「いや、心配は不要だ。郷に入っては郷に従えと言うだろう」
そう言うと、煉獄さんは目を眇めたくなるような眩しい笑顔を見せた。零れる白い歯にどきりと心臓が大げさな音を立てて、なんだか落ち着かなかった。
「じゃ、じゃあ、私はこれを買ってきますので、煉獄さんはお店の前で待っていてくれますか」
衣類や下着が何着か入った買い物かごを持ち上げながら言えば、煉獄さんはそれをすることが仕事のように、私の手からかごを奪う。
「俺も一緒に行く。至れり尽くせりなのはどうも落ち着かんのだ。それに、俺に出来ることはさせて欲しいと先ほども言っただろう」
煉獄さんは申し訳なさそうに眉尻を下げ、私の肩をぽんぽんと叩いた。唐突に触れた手に、頬が熱くなる。恐らく煉獄さんは、こういうことを無意識にやってしまう人なのだろう。彼女や奥さんになる人はきっともやもやして仕方がないはずだ。
「名前、大丈夫か?」
「は、はい!ごめんなさい、すぐ行きます」
試着室の前でフリーズしたように立ち止まっていた私を振り返った煉獄さんに追いつくと、私達は長い行列の最後尾に並ぶ。流石この辺りでは一番大きなショッピングモールであり、店は老若男女で溢れていた。
「名前が住む時代は、随分と人が多いように思う」
店内や周囲の人々を興味深そうに眺めながら、煉獄さんはふむと顎に手をあてる。
「仰る通りです。…煉獄さんにとって未来の話をするのもどうかと思うんですけど、大正時代以降、日本は長らく海外と戦争をしてきた過去があります。人口が爆発的に増えたのは、戦後…今から約八十年くらい前の話ですかね」
「なるほど、そうなのか」
大学受験で勉強した今にも消えてしまいそうな歴史の知識を引っ張り出して説明すれば、煉獄さんは納得したように頷いてくれた。
そんな彼の端正な横顔を盗み見ながら、煉獄さんは本当に頭の良い人だと舌を巻く。先ほどのシャワーも、茶を淹れるウォーターサーバーも、移動に使った電車も、スマートフォンも、近代的な街の風景も、きっと煉獄さんの目に映るこの世界は、信じられないことばかりだろう。
しかし彼は、一度説明したことは決して忘れないし、私の拙い説明でもすぐに理解を示し、この世界に柔軟に対応してくれた。とても、昨日別の場所からやってきた人とは思えない。鬼殺隊という場所で、幹部をしていたというだけのことはある。
「…俺は…何か、おかしな行動をとってしまっているだろうか」
「へ?」
突然、煉獄さんが前方から私に視線を移し少し照れ臭そうに言う。質問の意図が分からずすぐに聞き返せば、彼は頬を指で掻きながら少し声のトーンを落とした。
「先ほどから…突き刺さるような視線を感じるのだが」
「え?視線…」
煉獄さんの言葉に慌てて店内を見渡せば、なるほど、確かに女性達の熱視線が彼に集まっているのが分かる。人目を引く少し派手な見た目もあるが、煉獄さんの顔は端正に整っているし、体格にも恵まれている。彼が女性の興味を惹くのは自明の理だろう。かくいう私も、昨日から何度煉獄さんを恰好いいと思ったか分からない。
「煉獄さん。突き刺さる視線というのは勘違いだと思います。少なくとも悪意のある視線じゃないですから、安心してください」
「むぅ、そうだろうか」
腕を組み、少し考え込む煉獄さんの鈍感さに内心苦笑していると、「お客様、こちらにどうぞ」という店員の明るい声が一番奥のレジから聞こえてくる。
「いらっしゃいませ。商品お預かりしますね」
「はい、お願いします」
「……あれ、ひょっとして…名前?」
赤の他人だと思い込んでいた店員の口から紡がれた自分の名前に、一瞬耳を疑う。確認するように店員の女性を凝視すれば、なんと職場の元同僚ではないか。確か彼女は地元に帰ると仕事を辞めたはずだったが。
「倫子!…え…なんでこんな所に。確か地元に帰ったって…」
「そうなの。でも、やっぱり実家だと両親が居るから窮屈になっちゃって、こっちに戻って来たんだ」
「そうだったんだ。はー、こんなところで本当にびっくりだね」
突然の再会に驚いていると、倫子の視線が私の右斜め上に移動したのが分かり、煉獄さんが居たことを思い出す。
「…このイケメン、名前の彼氏?」
倫子は遠慮なく問うて、煉獄さんに興味深そうな視線を注いでいる。
「あ、あの、えっと…この人は…実は従兄弟で…」
昨晩絢斗にも煉獄さんの存在を従兄弟と言って誤魔化したことを思い出し、私は話を合わせて欲しいと言わんばかりの視線を彼に向ける。すると、煉獄さんはこちらの意図を汲み取ったように、ゆっくり頷いてくれた。
「名前の親戚の煉獄杏寿郎だ。いつも名前が世話になっている。宜しく頼む」
春風のように爽やかな挨拶を済ますと、煉獄さんは服を畳む倫子の手に視線を走らせ、どこか嬉しそうに言葉を続けた。
「君は、居合をやっているのか」
「え、な、なんで分かるんですか!そうなんです。学生の頃からずっと剣道をしていて。今は居合をやっているんです」
「君の手の傷は、納刀する時にできるものだろう」
目の前で楽しそうに繰り広げられる会話に呆気にとられる。煉獄さんは、この世界だけでなく、私の友人にも柔軟に対応してしまうようだ。そして、惚れっぽい倫子の頬は、ほんのり赤く染まっている。どういうわけか、心が薄い雲に覆われるようにモヤモヤして、私は唐突に二人の会話に割って入った。
「あ、あの!倫子、大丈夫?ほら、お客さん結構並んでるし、あんまりレジで話込んでたらいけないんじゃないかな」
「あ、うん、そうだね。そろそろ怒られるかも。名前、また連絡するから飲みに行こうよ!煉獄さんも一緒に」
「そ、そうだね。また連絡して!」
そそくさと会計を済ますと、私は思わず隣の煉獄さんの手を掴んで、逃げるように店を後にする。
「ご、ごめんなさい。突然…」
店を出て数メートル歩いたところで、私はぱっと煉獄さんの手を離し謝罪を口にする。「いや、俺は構わない。…どうした?何か心配なことでもあったか」
顔に出しているつもりは微塵もないのに、煉獄さんは私の微細な変化を敏感に察知してくれたようだ。倫子が煉獄さんと楽しそうに話そうが私には関係ないはずなのに、まるでおもちゃを取られてしまった子供のように駄々を捏ねたくなった。
煉獄さんは昨日会ったばかりの人だというのに、一体どうしてこんなことを思うのだろうか。注意深く自分の心を点検してみるも、その答えは分からずじまいだった。
「な…何でもないんです。ごめんなさい。あ、次は日用品を見に一階へ――」
意味もなく前髪を撫で付けながら苦笑混じりに言えば、その手を今度は煉獄さんが掴んだ。
「え…あの」
予想もしなかった彼の行動に、私は目を瞬かせる。
「先ほど風呂場で転倒した件もそうだが…名前はなんだか危なっかしくて心配だ」
煉獄さんは悪戯っぽく笑い、柔らかな声で言った。そして、まるで彼氏が彼女にするみたいに、優しく私の手を引き歩き出す。
どくどくと激しく打ち始めた鼓動が頭の中で木霊した。
私は真っ赤に染まった顔を見られないよう、自分の爪先を凝視しながら、煉獄さんの隣を歩いた。こんなに胸が鳴るのは、久しぶりに異性に触れられたせいだと、自分に言い聞かせながら。