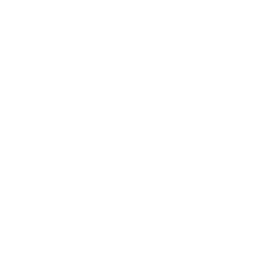
奇跡の痕跡
決まった時間に鳴るようセットされたスマートフォンのアラームで目が覚める。おもむろにそれを止めると、ホーム画面に並ぶいくつかのニュースが目に入る。そのトップが「昨晩のオリオン座流星群は過去最高数を観測」という見出しが視界に飛び込んできて、眠気がこびりついていた頭が一気に覚醒する。どくどくと不穏な鼓動が打って、全身の毛穴から汗が噴き出してくる気がした。
慌ててベッドから体を起こせば、ルームウェアが着せられている。隣に、杏寿郎さんの姿はない。
心臓の音はさらに激しく大きくなり、しんと静まり返った寝室に響いてしまうようだった。この家はこんなに静かだっただろうか。震える足でベッドから降りると、浅くなる呼吸を抑えるように胸に手をあて、おそるおそる寝室の扉を開ける。
リビングのソファには、丁寧に畳まれた杏寿郎さんの衣類が一式置かれている。私が彼に買ったものだ。一方で、壁に立てかけてあった刀や、隊服や、炎柱の羽織はなくなっていた。
ぶわりと涙が溢れてきて、視界が歪んでいく。
昨日が流星群であったことは、スマートフォンに流れてきたニュースで先ほど知ったばかりだ。そういえば、昨晩は驚くほど星が流れていたことを思い出す。
彼は、帰ってしまったのだ。元居た世界に。私が居ない世界に。星の輝きとともに。
今にも崩れ落ちそうになる足を必死に叱咤してソファに近づくと、その前に置かれたテーブルに、スマートフォンと薄いピンク色の小ぶりの箱が並べて置かれていることに気が付く。スマートフォンは私が杏寿郎さんに持たせたものだ。まるで指輪を入れるようなツイード生地に包まれた小さなケースは、あの日銀座で、杏寿郎さんとショーウインドウ越しに見たものだった。
ぼろぼろと瞳から零れ落ちて服を濡らす涙を懸命に拭って、震える手で、ゆっくりとそのケースを開ける。そこには、ウェーブラインにダイヤモンドが煌めく指輪が輝いていた。
――今の時代は、婚約指輪を渡して男性が女性に求婚するんです
自分の言葉が脳裏に蘇り、ダムが崩壊したように更なる涙が溢れてくる。胸が咽せ、浅くなる呼吸がさらに促拍して上手く息が出来ない。小さな嗚咽を漏らしながら、涙のせいでたまぼけのように光る指輪をそっと持ち上げると、その内部には、杏寿郎さんのイニシャルと私のイニシャルが刻まれていた。
私は、箍が外れたように泣き叫ぶ。それはまるで赤ん坊のように、火がついたように、隣の部屋の住人にまで聞こえてしまうのではないかと思うほどの大きな声で。
一体杏寿郎さんは、いつこんなものを準備していたのだろう。安いものではなかったはずだ。私が頑なに受け取らなかったお金を、彼は思いもよらぬ形で私に贈ってくれたのだ。
こんな風に受け取りたくなかった。出来れば直接渡して欲しかった。ずっとずっと、一緒にいて欲しかった。不思議なくらいぴたりと薬指にはまった指輪ごと手を握りしめると、昨晩の杏寿郎さんの体温が舞い戻ってくるようだった。体はこんなにも杏寿郎さんを覚えているというのに、彼はもう居ない。私を抱き締めてくれることもない。
記憶は別れることはない。理屈としては勿論そうなのだけれど、突きつけられた現実はあまりにも残酷で、切なくて、悲しかった。
涙を止められぬまま、何やらぴこぴこと光るスマートフォンに手を伸ばす。まるで杏寿郎さんの痕跡を探すように操作すると、殆ど初期状態のままのそれに、一つの録音データを見つける。
どくんと、心臓が跳ねた。まるで何かの病にかかってしまったかのように震え痺れる指先で再生ボタンを押し、スマートフォンを耳に宛がった。
『名前』
まるですぐ隣に居るかのように、耳元で囁かれているように、杏寿郎さんの声が聞こえてくる。
『君がこれを聞いているということは、やはり俺は、もう名前の隣には居ないのだろうな。どういう運命の悪戯で、君と俺が巡り合ったのかは分からない。もし一緒の世に、時代に、生まれることが出来ていたなら、名前と一生を共に過ごしたかった。
名前に謝らなければいけないことが、いくつかある。
昨晩…君は俺を忘れないと言ってくれた。だが、本当は怖いのだろうな。名前の中から、俺の記憶が薄れてしまうことが。なくなってしまうことが。…だからこうして、煉獄杏寿郎の痕跡を…君を愛しているという証を残すことを、どうか許して欲しい。
以前名前は、大正時代は求婚にどんなものを贈るのかと聞いたな。俺の生きている時代は、簪を贈ることが習慣だった。…覚えているか、あの夏祭りの日、君と一緒にとった簪を。名前にとても良く似合っていた。光る飾りの星が美しくて、君の笑顔のようだと思った。本来であれば、あの簪は置いていくべきなのだろう。
己の命が尽きても、名前を忘れることはないと言った言葉に嘘はない。だが俺も、君とともにあった証が欲しい。だから、一度は君に贈った簪は持っていく。…といっても、名前の金銭で取ったものだ。…それは、大目に見てもらえるだろうか。
俺は今、星を見上げながら自分の声を吹き込んでいる。名前と出会った時も、こんな風に星が流れていたな。場所こそ違ったかもしれないが、俺達はきっと、同じ空を見ていたのではないだろうか。
肉体は離れてしまっても、心はずっと名前の傍にある。君が俺を覚えてくれている限り、俺は君と別れることはない。だから、泣かないで欲しい。きっと名前は今、泣いているのだろうな。君が泣くと、俺は心配で堪らなくなるから。名前の笑顔が何よりも好きだ。だからずっと笑っていて欲しい。誰よりも幸せになって欲しい。それだけを俺は今、願っている。…愛してる、名前。…ありがとう』
全てを聞き終えた私は、スマートフォンを握り締め嗚咽を漏らす。
「っ…これで笑っていて欲しいなんて…無茶です…杏寿郎さん」
枯れるほど泣いたにも関わらず溢れてくれる涙を擦って立ち上がり、ふらふらとした足取りで洗面所へ向かう。抽斗を開ければ、奥の方でケースに入れて大切に保管していた簪は、杏寿郎さんの言葉通り姿を消していた。
その事実が、何故だか嬉しかった。彼の記憶意外にも、私という人間を証明するものがあると思えたから。
杏寿郎さんも私を忘れない。私も杏寿郎さんを忘れない。
一人納得するよう静かに頷くと、洗面台の脇に置かれたケースから何枚もティッシュを取り出して、顔全体を擦るように涙を拭い、ちんと勢いよく鼻をかむ。
笑っていて欲しい。杏寿郎さんはそう言ってくれた。いつでも私と誠実に向き合ってくれた彼に、私も答えたい。
一生泣かない、なんてことはきっと出来ないだろう。辛くて、悲しくて、どうしよもなくなることもあるだろう。でも、心の中に、記憶の中に、杏寿郎さんが居てくれる。だから私も、前を向いていかなければ。
「…よし、仕事行こ!」
杏寿郎さんまでとはいかないが、自分を激励するように大きな声で言った私は、洗面所の蛇口をひねり、冷たい水でびちゃびちゃと顔を洗い始めた。
また、今まで通りの日常が始まるだけ。以前と違うのは、杏寿郎さんという存在が、私自身に刻み込まれたということ。
「あら、おちびちゃん寝ちゃったの?流れ星見るんだって、楽しみにしてたのに」
微笑を浮かべた絢斗が、芝生の上に敷いたビニールシートの上で寝転ぶ子の髪を優しく撫でながら言う。
「うん、ちょっとはしゃぎすぎちゃったのかもね。ふふ…可愛いなぁ。本当、パパそっくり」
まるで杏寿郎さんが生まれ変わったのではないかと思うほど彼にそっくりな我が子の、大福のような頬をつつき目尻を緩める。
「まったく…その肝心な『パパ』は一体どこにいるって言うのよ」
皮肉混じりに呟くと、絢斗はしゃがんだシートに手をつき体を逸らして、プラネタリウムのように隙間なく星が瞬く空を見上げた。
ここは、日本で一番星が綺麗に見える場所だった。山々が複雑に入り組む地形によって街の明かりが遮られ、美しい星がくっきりと見えるのだ。今日はペルセウス座流星群が観測できるとあって、山の頂にある広場では、そこかしこで恋人や家族連れが芝生に敷いた レジャーシートの上に寝転んで、満点の星空を仰いでいた。
それに倣ってシートに寝転ぶと、晴れ渡った夜空が視界を覆う。ミルクを流したような天の川を中心に散らばった星屑が、宝石のようにきらきらと煌めいている様子は、筆舌に尽くしがたい絶景だ。
「さぁねぇ。宇宙や銀河はこの星空みたいにはてしないから」
感嘆の息を混ぜてのんびりとした口調で言えば、絢斗は呆れたような息を吐く。
「こんなに可愛い子を残して、まったく」
「そうしたくてした訳じゃないの…杏寿郎さんは」
「それはあんたから何度も聞いたから分かってるわよ。そんないい加減な男にも見えなかったし…でも、嫌味の一つでも言いたくなるでしょう」
杏寿郎さんが帰ってしまった数か月後、私の妊娠が発覚した。本当に彼は、最後の最後まで奇跡のような人だった。いや、杏寿郎さんと私が、奇跡を引き起こしたのかもしれないが。
一人で我が子を育てていく決意などあの夜から疾うに出来ていた私は、躊躇なく子を産んだ。そして、杏寿郎さんとの愛の証をこの手に抱いたのだ。
絢斗には全てを打ち明けた訳ではなかったが、勘の良い彼は事情を察し、追及せずにいてくれた。そしていつも私達親子を気にかけ、傍で見守ってくれている。私達の関係は、このままきっと変わらない。「ありがとう」と絢斗に笑みを向けぽつりと呟いたとほぼ同時くらいに、広場がライトダウンする。
全ての光が消え闇に包まれた瞬間、先ほどよりもさらにくっきりと、頭上に散りばめられた星達の姿が浮かび上がる。この時まで身を隠していた小さな星の光も、余すところなくこちらに届いてくるようだ。周囲からは歓声があがり、ぱらぱらと拍手が起こる。
刹那、視界を星が横切る。今まで見た中で、一番綺麗で、くっきりと見える流れ星だった。その一つを皮切りに、まるであの夜みたいに、星達が降り注いだ。
ねぇ、杏寿郎さん。あの日のみたいに、貴方もこの夥しい数の星の光を、この広い宇宙の、銀河の何処かで、見ていますか?
(完)