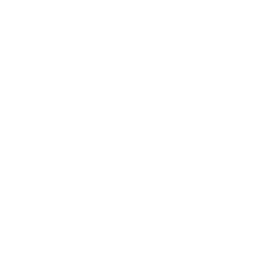
あの日の願いごと
中々捕まらないタクシーを諦めて、私は夜の街を自宅に向かって全力疾走する。煉獄さんにメールを返す時間も、電話で一報入れる時間すらも惜しくて、ここ数年で一番走ったのではないかと思うほど、私はひたすらに足を動かし続けた。
絢斗の家から私のマンションまでは歩いて三十分ほどだ。自宅近くの公園まで来たところで身体が限界を迎え、足を止めて肩で息をしながらウェアラブルウォッチの画面を確認すれば、絢斗の家を出てから、まだ十五分ほどしか経っていなかった。自分がこんなに速く走れることに驚きつつ、煉獄さんの待つ自宅に戻るため公園を横切…ろうとした。
「やだっ、誰か、誰か助けてっ!」
もう日付を跨ごうという時間帯の暗くて不気味な公園に、怯えた悲鳴のような声が響く。次の瞬間には、背後からどたどたと荒っぽい足音が聞こえてきて咄嗟に振り返れば、恐怖に顔を歪ませ涙を頬に貼り付けた女子高生が、私に縋るように飛びついてきた。
「ど、どうしたの?大丈夫」
衝撃でよろけそうになる身体を、足に力を入れることでぐっと踏みとどまり、胸に飛び来んできた女子高生に訳も分からぬまま問えば、彼女は震える声で息も絶え絶えに言った。
「た、助けて…包丁…もった…男がっ…」
「えっ?」
刃物で背筋を撫でられたような戦慄が走る。女子高生を追うようにゆっくりと近づいてきた足音が、私達の数メートル前方でぴたりと止まった。
静かな光を放つ街灯に照らされ姿を現したのは、全身黒い衣装に身を包んだ男性だった。その手には、刃渡り三十センチはありそうな包丁が握られており、鋭い刃先が、街灯の光を反射してキラリと光った。
全力疾走後で、ただでさえ慌ただしく動いていた心臓の鼓動が一層速くなり、不吉な脈動を刻み始める。
――刃物を所持した男は現場から逃走し、現在警察はその行方を追っています。
先日の通り魔事件の男が捕まったというニュースは、まだ見聞きした記憶がない。
「に、逃げるよ!」
こんな夜中に出歩いている人がいるか疑問だが、私は周囲に危機を知らせるよう精一杯大きな声で叫んで、女子高生の腕を掴んで走りだす。男の手にあるのは、刃渡り三十センチの包丁だ。刺されたらまず命はないだろう。生まれて初めて晒される命の危険に、全身の血がどくどくと激しい音を立てて身体を巡る。
しかし、懸命に足を動かしていた私の体は、叩きつけられるように地面に崩れ落ちる。後ろから追いかけてきた男が、コートの裾を引っ張ったのだ。最近の流行だからと、丈が足首ほどあるコートを羽織っていたことを、心底後悔する。膝がひりひりして、ストッキングが破れ流血しているのだとすぐに分かったが、当然そんなことを気にする余裕もない。もたもたしていたら、擦り傷どころか、血飛沫を見る可能性もある。
「逃げて、早く!」
「で、でも」
「いいから早く!向こうに交番があるからっ」
当惑した様子で私を見下ろす女子高生に向かって叫ぶ。彼女はごくりと唾を飲むと、踵を返して走り出す。「逃がすか」と低い声で呟き舌打ちし、後を追おうとした男の足を、私は必死に掴んだ。
「…っ、何すんだ!」
激しい怒りの声が、鞭のように私を打つ。深く被ったニット帽から覗く目が、刃物のように鋭い光を湛えて私を見る。
「た、助けてっ!誰かっ!煉獄さんっ!」
ぎゅっと目を瞑り、喉の奥から絞り出すように必死になって声を上げる。煉獄さんの名を呼んだのは、彼なら、私のピンチに駆け付けてくれるような気がしたから。
――俺も、名前を全力で守る
あの日の言葉を、彼が反故にすることなどないと思ったから。
カンと、金属が地面を叩く音が聞こえ、その直後、男のうめき声が鼓膜に流れ込んでくる。恐る恐る目を開けると、地面に転がる刃渡り三十センチ刃物が目に入る。視線をゆっくり上に向ければ、そこには、眉で八の字を描く煉獄さんの姿があった。彼の腕には、気を失った男が抱えられている。煉獄さんが手刀でも喰らわせたのかもしれない。
「や…やっぱり来てくれた」
煉獄さんの顔を見た途端、体が安堵に身震いする。息を吐くような小さな声が漏れ、目からは涙が零れ落ちる。
「…名前…」
ゆっくり名前を紡がれたかと思えば、男を地面に横たえた煉獄さんがしゃがみ込み、今度はその胸の中に私を迎え入れた。
「頼む…これ以上心配させないでくれ」
背中に回された腕に、強い力が込められる。耳に滲む声は、張り詰めていた精神が解放されたような、そんな声だった。物凄く心配をかけてしまったことを心苦しく思いながら、おずおずと彼の大きな背中に手を回す。
「やっぱり煉獄さんは…流れ星が連れて来てくれた、勇者なんですね」
「…名前?」
唐突な私の発言に、怪訝そうな声で煉獄さんは問うた。
「ペルセウス座流星群…煉獄さんが私の元に来てくれた日に観測された流星群です。…古代ギリシャ神話では、ペルセウスは姫を救助して大活躍する勇者なんですよ。…ね、煉獄さんみたいでしょ?」
涙で潤む目で彼を見上げれば、雄々しい瞳と視線が絡む。遠くでパトカーのサイレン音が聞こえ、徐々にそれが大きくなる。構わず私は続けた。
「あの日…流星群にお願いしたんです。勿論ダメもとで。素敵な彼氏が欲しいって。王子様に会いたいって」
「…俺は…名前にとってそういう存在に…なれたということか?」
「…煉獄さんは、私の王子様です。きっと、最初から…ずっと」
「名前…」
「煉獄さん、あの、私」
貴方のことが好き。そう想いを形作ろうとした唇は、煉獄さんのそれによってやんわりと塞がれる。驚きに目を見開けば、ゆっくりと唇が離れた。
「…もし、名前が同じ気持ちでいてくれるなら…俺から言わせてくれないか。君に話したいことがあると言っただろう」
「煉獄さ…」
「自分がいつ元居た世に戻る身かも分からない…そんな男が、名前を幸せに出来るはずもない。…君が、医師である友人を選ぶことも…なんら不思議はない。だが俺は…名前を彼の元に行かせたくないと思ってしまった」
「っ…ぅん」
止まることなく溢れてくる涙を指で拭いながら、こくこくと首を縦に振る。煉獄さんは、そんな私の額に優しく口付けて、大きな手を涙で濡れた頬に這わせる。
「名前…君のことが好きだ。だれよりも愛しく思う。…こんな手前勝手なことを言って…名前を困らせることは分かっている。…だが」
「っ…困らないです…ちっとも…困らない。…私も…好きです。煉獄さん…貴方が、好きで、好きで、どうしようもないんです。私の幸せは…貴方です」
震えを帯び濡れた声で、精一杯自分の想いをぶつける。すると、目の前の煉獄さんが幸せそうに目尻を下げた。
けたたましいサイレンの音がぴたりと止んだ。同時に、公園の入り口の方が騒々しくなる。私の叫びを耳にした住人が通報したのか、はたまた先ほどの女子高生が交番に駆け込んだのか、いずれにせよ、警察が到着したのだろう。
しかし私達はまるでこの世界にたった二人だけになってしまったかのように、到着した警察官に声をかけられるまで、骨が折れてしまいそうなくらい、互いの体をぎゅっと強く抱き締め合っていた。息も出来ないくらいに、強く、強く。
頭上に散らばる星達が、幾筋も幾筋も、静かに流れていった。
先程の刃物を所持した男は、やはり先日の通り魔事件の犯人で、煉獄さんのお陰で逮捕に至った。時間も遅いからということで、簡単な事情聴取で解放された私達はマンションへと戻った訳だが、膝小僧の傷にいち早く気づいた煉獄さんは、少し強引に私をソファに座らせた。以前煉獄さんを手当した時に使用した救急箱を納戸から取り出すと、彼は私の足元にしゃがみ込み、慣れた手つきで手当てを施してくれたところだった。
「刃物を持った男に掴みかかるとは…君も大概無鉄砲だな」
「お恥ずかしいです…」
「いや…名前のお陰で少女も無事だったのだろう。恥ずべきことなど何もない。…君は困っている人を放っておけないのだな。…こちらの世に来た俺を、助けてくれたように」
「それは…そうかもしれません。この性格で損してるなって思うことも多いですけどね」
頬を掻き苦笑を浮かべながら言えば、煉獄さんは手当を終えた私の膝に唇を寄せ、優しいキスを落とした後、ぽつりと呟く。
「そんな君だから…愛しくて堪らないのだろうな」
恥ずかしげもなく言う彼に、こちらが恥ずかしくなって、頬が火照る、
「ほ、本当は…煉獄さんのこと好きって認めるの…嫌だったんです」
照れ臭さを誤魔化したくて少し上擦った声で言うと、煉獄さんが先を促すように私の膝から顔へ端正な眉目を向けてくるので、そのまま言葉を続けた。
「煉獄さんが…突然私の元に来た時みたいに、いつか帰っちゃう人だって…分かっていたから。勿論確証があるわけじゃないけど…でも…煉獄さんとずっと一緒にいる未来が…どうしても私には想像出来なくて。だって煉獄さんは…私にとって…奇跡みたいな人だったから。…だから…辛いから…いつか来る別れが辛くなってしまうから、それなら最初から煉獄さんへの気持ちなんて気づかなければいい…認めなければいいって…そう思ってました」
煉獄さんは静かに頷いて、私の瞳をじっと見つめ言葉に耳を傾けてくれる。一度小さな息を吐いた私は、決意を漲らせるように目に力を入れ、おもむろに口を開く。
「でも…絢斗が教えてくれたんです。…一度巡り合った人とは、どんなに別れたくても別れることは出来ないんだって。それは…私達に記憶があるから。良くも悪くも記憶と共に私達は自分の人生を生きていかなきゃいけないんだって。…そう考えたら…煉獄さんとはずっと別れることはないんだって…そう思えて…」
そこまで言って煉獄さんの様子を窺えば、彼は静かに頷く。私をひたむきに見つめる、真っ直ぐな瞳。
「名前の友人の言う通りだな。確かに記憶というものは、生涯、別れることが出来ない。…本当に辛いことは…別れることでも、会えないことでもない」
煉獄さんの言葉に小首を傾げる。そんな私の表情を見て口許に小さな笑みを浮かべた彼は、腿の辺りで重ねていた私の両手を、自身のそれで大切そうに包んだ。
「煉獄さん…あの」
「一番辛いのは…相手の心から自分がいなくなってしまうことだと、俺は思う。名前が俺を覚えていてくれるなら、こんなに幸せなことはないな」
形の良い唇から紡がれた言葉に、止まった涙が再び溢れ出してくる。
「っ…煉獄さんは…私のこと……ずっと、ずっと、覚えていてくれますかっ…」
煉獄さんの掌に自身の手を重ね、震える声で言えば、次の瞬間には、私は彼の胸の中にいた。
「たとえこの命が尽きても…君を忘れることなどない」
力強い声が鼓膜を震わす。愛しい人の速い心音が、熱い体温が、触れ合った部分から伝わってくる。
「私も…忘れない。…忘れさせないで…煉獄さん…お願いっ」
懇願するような声で言って、彼の首に手を回し、涙で濡れた唇を彼のそれに押し付ける。一瞬、虚を突かれたような表情を浮かべた煉獄さんだったが、すぐに長い睫毛を大きな瞳に被せて目を瞑ると、私のキスを受け止めてくれた。
「…今日は私の寝室で…寝てくれますか」
舌先を触れ合せるキスの合間、熱い吐息に混ぜて言えば、煉獄さんは少し困ったような息を漏らして、私の体をふわりと抱きかかえた。そして、その答えをくれるように、もう一度私の唇を優しく吸った。