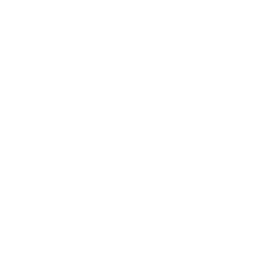
腐れ縁
「もしもし、名前?」
スピーカーを通して聞こえてきた倫子の声にごくりと唾を飲み、恐る恐る口を開く。
「も…もしもし」
「あ、良かった。出てくれて」
電話の向こう側で安堵する倫子の表情が想像出来るような声音だった。耳の中で自分の鼓動を聞きながら、私は彼女の言葉の続きを待った。
「……名前…ごめんね」
数秒の深い沈黙のあと、倫子の声が鼓膜に流れ込んでくる。その声は、本当にすまなそうに聞こえた。謝罪の真意が分からない私は直ぐに聞き返す。
「ごめんねって…どういうこと?」
「私、気付いてたんだよね。名前が煉獄さんに特別な感情を持ってるんだろうなって」
「え…」
倫子の予想外の発言に息をのむ。彼女はゆっくりと続けた。
「でも、従兄弟って言ってたから、そりゃあ名前とは血も繋がってるし、流石に名前も本気で彼とどうこうなりたいとは思ってないだろうって勝手に自己解釈したの。それで、煉獄さんが素敵な人で武道に携わってるっていう共通点も嬉しくて、ついついでしゃばった真似しちゃったんだけど」
そこまで一気に言って一旦言葉を切ったあと、倫子はまるで私が煉獄さんへ抱く気持ちを確認するかのように問うた。
「…従兄弟じゃないんでしょ?」
「それ…なんで」
「うん。実は、煉獄さんの口からきっぱり聞いたの。彼の…名前への気持ちってやつ」
「煉獄さんが…私のこと」
声が震え、心臓の鼓動がさらに速さを増していく。煉獄さんは、倫子にどんな胸の内を語ったというのだろう。
「恩人で、心から感謝してるって。大切なんだって」
倫子の口から紡がれる煉獄さんの言葉に胸が詰まり、目頭が熱くなってくる。
「どんな事情があるか分からないけど、従兄弟って私に偽らなきゃいけない何かがあったんだよね」
「っ…ごめん。倫子を騙すつもりはなくて」
「いいよ。私も、名前に嫌な思いさせてたなって自覚あるし。…この間の元彼のことも、よくよく考えたら名前に変な男を紹介されたみたいな言い方になってたし、それで煉獄さんの興味引こうとして…性格悪いなぁ自分…って、さっき反省してたとこ」
倫子の心苦しそうな声が聞こえてくる。私も、煉獄さんの真実を話すわけにはいかず咄嗟に彼との関係を従兄弟と言ってしまったことを、今一度謝罪する。
「そんなに謝んないで。今回はお互い様ってことで。じゃ、煉獄さんによろしくね。あ、道場も、家の近くで良いところ見つけたんだ。だから、初枝さんだっけ?…には悪いけど、そっちでお世話になることにしたから。また、時間合う時にご飯でも行こう」
「あ、あの、倫子」
「じゃあね、名前」
目的は果たしたというように、倫子は私の返事も聞かずに電話を切った。ツーツーという無機質な機械音を数回聞いた後、私はゆっくりとスマートフォンを耳から外す。
――恩人で、心から感謝してるって。大切なんだって
先ほどの倫子の言葉を頭の中で反芻し、否定するようにかぶりを振る。大切だからなんだというのだ。言うなれば雲をつかむような煉獄さんの存在より、確かなものがある。それが絢斗の存在であり、彼の言葉だった。先刻私は、彼の手をとったのだ。何を今更。
そう思った矢先、手中のスマートフォンが控えめに震えた。メッセージを受診した合図だ。恐る恐る画面に視線を落とせば、煉獄さんの名前が表示されている。ここ数日、ずっと待ち侘びていた彼からのメッセージだった。私は、震える指先で画面をタップする。
『逢いたい』
そのメッセージはたったの四文字。拍子抜けするくらいシンプルなもの。でも、煉獄さんの気持ちを知るには、私の心を揺らすには、十分すぎる四文字だった。画面の文字が涙で滲んでいき、その間合いで、頭上から唐突に声が降ってくる。
「さっき、一緒にいることが出来ない人を好きになっちゃいけないって言ったのは…どうして?」
弾かれるように顔を上げれば、いつの間に戻ってきたのか、腕組をした絢斗が背後に立っていた。私は呆気にとられたように口をぽかんと開けて彼を見る。
「…絢斗…そ、それは…」
「いいから答えなさい」
絢斗は有無を言わさぬような口調でぴしゃりと言って、切れ長の目で私をじっと見つめた。圧倒され、思わず首肯し慌てて口を衝いて出た言葉は、あまりにも単純な本音だった。
「わ、別れるのが……嫌だから。…いつか来る別れが…辛いから…。家族みたいに…いつでも連絡が出来る人じゃない…会おうと思えば会える距離にいる人でもない…もっとずっと…ずっと遠くて…二度と会えないところに…帰ってしまう人かもしれないから…っ…」
言い終えぬうちに、瞳から熱い雫がぽろぽろと零れてくる。涙に胸が咽せて、上手く言葉を紡ぐことが出来ない。
「…なーんだ。そんなことなのね」
ほんの少しの間を挟んで、絢斗が再び口を開いた。悲観的な私の考えを全面から否定するような、力強い口調だった。
「そ、そんなことって」
「名前、あんたにいいこと教えてあげる。人間っていうのはね、残念ながら一度巡り合った人と、別れることは出来ないのよ」
「…え?」
「ここ」
ぽかんと口を開ける私の額を、絢斗は自身の長い指でとんとんと二度叩いた。
「ここ?」
意味が分からず小首を傾げると、彼は口角を持ち上げて首肯する。
「私達には記憶があるでしょ。忘れたくても忘れられない記憶があるように、一度出会った人間のことを、忘れることは出来ない。一生付き合って生きていかなきゃならないの。自分の記憶と別れることなんて、残念ながら出来ないのよ」
絢斗の言葉に、目から鱗が落ちるような気分だった。迷い、苦しみ、悲しみ、蟠っていた気持ちが、頭の中からしゅわしゅわと蒸発していく。
気がついた時には、私は勢いよく立ち上がり、足元のバックを引っ掴んでいた。
「絢斗…ありがとう。なんか…上手く言えないけど…吹っ切れた気がする」
自分の気持ちを再確認するよう絢斗に向かって言えば、彼は口元に刻んだ笑い皺を満足そうに深めた。
「ほら、さっさと行きなさい。従兄弟が首を長くしてあんたの帰り、待ってるんじゃないの?」
「う、うん。あのね…あのね絢斗。私、絢斗に謝らなきゃ。…実は、煉獄さんは本当は従兄弟じゃないんだ。私の……私の好きな人」
「そんなの、改まって言われなくても最初から分かってるわよ」
「ひぇ?」
「まさか…ばれてないとでも思ったの?」
呆れたように言うと、絢斗は私の頭頂部をぺしりと叩く。ちっとも痛くないそこをさすりながら、彼を見上げもう一度謝罪の言葉を口にする。
「絢斗の気持ち…嬉しかった。…答えられなくてごめんね」
糸のように細い声で言うと、絢斗は形のよい眉の間にうっすらと皺を寄せ、怪訝そうな表情を向けてくる。そして、私の両肩を掴んでくるりと向きを変え、家から追い出すように玄関に向かって背中を押した。
「まるで私があんたのこと好きみたいな言い方ね、それ」
「へっ?」
予想外の彼の言葉に、思わず振り返る。
「私、名前のこと好きだなんて、一言でも言ったかしら」
「え……嘘?」
「そんなんだから、すぐ男に騙されるのよ。…今度の男は、きっと大丈夫なんでしょうけど。まぁ、またあんたが泣きついてきた時には話くらいは聞いてあげる」
絢斗はこちらに器用にウインクをしてみせ、呆然としながらヒールに足を通した私にひらひらと手を振った。
「なんだ…そうだよね。あはは、絢斗が私を好きなんて…ある訳ないか」
いつものことだが、また絢斗に一泡吹かされた。ないない、と顔の前で否定するように手を振る彼に苦笑を浮かべると、バイバイと手を振って、私はマンションの玄関を飛び出す。
「――名前!」
エントランスを出たところで、数メートル上の方から声が降ってくる。
「暗いから気をつけなさいよ!」
私を見送ろうとしてくれたのか、ベランダに出て柵に凭れかかった絢斗が少し声を張ってこちらに呼びかける。見上げた空に、一筋の星が光った。
「うん!ありがとう、絢斗!」
もう一度彼に手を大きく振ってから、私は強く地面を蹴って走り出す。
「あ…流れ星。…珍しい、流星群でもあるまいし」
微かな光が横切った藍色の空を仰いだ絢斗がぽつりと呟いた声は、当然、私には届かない。