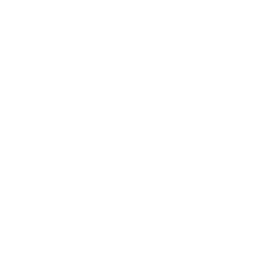
「好き」、だから
あの夜は、結局煉獄さんと鍋をすることも出来なければ、彼からの話を改めて聞くことも出来なかった。出来なかった、というと語弊があるかもしれない。煉獄さんに倫子を送るように頼んだのは私で、自分が煉獄さんと話す勇気がなかっただけだ。
運がいいのか悪いのか、翌日から地方へ泊りの出張だった私は、結局煉獄さんと会うこともなく数日が経過してしまった。
出張中、煉獄さんからスマートフォンに連絡はなかった。元々煉獄さんは私や初枝さんとの遣り取りなど必要最低限でしかスマートフォンを使用しないから、それ自体は不思議なことではない。仕事だと言って逃げるように出張に出た私に気を遣っているのかもしれない。自分で蒔いた種なのに、連絡がないことに不安になった私は、一生分スマートフォンを見たのではないかというくらい彼からの電話やメッセージを確認してしまった。
「採血結果を見るとちょっと炎症データが上がってるわね」
診察室のプリンターから印刷された私の血液検査の結果を、絢斗はひそめた眉で見つめた。
出張帰り、私は駅から絢斗が勤めるクリニックに直行した。その理由は、原因不明の微熱。そして、自宅に帰ってから煉獄さんと会うための心の準備だ。
煉獄さんは、今日倫子と会っているはずだった。それは煉獄さん経由ではなく、倫子経由で知った情報だ。スマートフォンのメッセージを見れば、彼女の嬉しそうな顔が目に浮かんだ。そして私の胸はまた、軋むように痛むのだ。
「もしかして、なんか悪い病気かな?」
恐る恐る絢斗にたずねれば、彼は呆れたように息を吐いて首をゆっくり左右に振った。
「多分知恵熱みたいなもんでしょ」
「知恵熱…」
「ストレスとか疲れよ。…いつにも増して辛気臭い顔して、一体何があったのよ。この間銀座で会った時は、楽しそうにしてたじゃない」
頬杖をついて、絢斗は心の中を見透かすようにじっとこちらを見つめてくる。私はすうっと一つ深呼吸をして、喉に閊えていた言葉を、逡巡の末絞り出す。
「…絢斗は…もし、好きになっちゃいけない人を好きになったら…どうする」
「はぁ?」
唐突な私の発言に、絢斗は怪訝そうな顔をし、視線で詳しく説明しろと促してくる。
「好きになっちゃいけないの。…その人と自分は…ずっと一緒にいることが出来ないから」
「それって、不倫とか浮気とか、つまりそういうこと?」
「ち、違う!そういうわけじゃないけど…でも…とにかく…好きになっちゃいけない人なの…」
眉間の皺を深め少しだけ咎めるような口調で聞き返してくる絢斗の言葉を慌てて否定するも、私の言葉は尻すぼみになってしまう。肺の中の空気を全て吐き出すように盛大な溜息を吐いた彼は、私の額を長い指でぴんと叩いた。
「この世に好きになっちゃいけない人なんて、いる訳ないでしょ」
「え…」
「それはあんたのエゴよ。勝手にそう思ってるだけ。別にいいじゃない、好きならそれで。誰かを好きになっても報われないことなんて、今までも山ほどあったでしょ?それと一緒だし、それでいいのよ。人を好きになるってそれだけで価値があることなんだから」
「…絢斗…」
絢斗の言葉に思わず生唾を飲み込む。まるで息を潜めるように、診察室の空気が張り詰めていくような気がした。
「…確かに、自分が愛する人が自分を同じように愛してくれて、一緒にいることが出来たらそんなに嬉しいことはないわね。でも、それが正解じゃない」
そう言った絢斗の顔に、どこか物憂げな表情がよぎる。
「絢斗…自分も同じ経験をしたような言い方…するんだね」
「はぁ?私に限ってそんなことはまずないわ。ま、名前は色々考えすぎよ。だからこんな熱なんて出すの。今日は帰って早く寝なさい」
言葉の意味を咀嚼するように何度か頷き、ぽつりと率直な感想を述べた私に、絢斗は心外だという顔をしてぴしゃりと言ってのける。そして、くるりと椅子を回してパソコンへと向き直り、キーボードを素早く叩き始める。私のカルテを入力しているのだろう。
「絢斗…あの」
「ほら、さっさと帰りなさい。…あの従兄弟も待っててくれるんでしょ?」
「え…」
「ねえ…あんた達って…」
「――先生!次の患者さんがお待ちですけど、まだかかりますか?」
絢斗が何か言おうと口を開きかけた時、バックヤードから看護師が顔を出し急かすように言った。迷惑そうな視線で一瞥された私は、慌てて目を伏せ席を立つ。
「ご、ごめんね絢斗。仕事中に余計なこと。また連絡するね」
「…薬は特に出さないわよ。どうせ寝たら治るでしょ」
「うん、ありがとう。…じゃぁ、また」
二人分の視線を背中で受け止めながら、私は足早に診察室を後にする。会計を待っている最中スマートフォンを確認したが、煉獄さんからの連絡は相変わらず皆無だった。一瞬考えた後、「そろそろ帰ります」とだけ画面に打ち込み、送信ボタンを押した。
都会であっても、目を凝らし暫く夜空を見つめていれば、次第に星が見えてくることに改めて気がつく。まるでこの世界で目を覚ましているのは自分だけかと思うほど静かな夜の公園で、ブランコに座った私は、出し惜しみするようにぽつりぽつりと姿を見せて輝き出す星を見上げていた。
少し冷たくて緩やかな秋の夜風が、囁きかけるようにひゅうっと吹きつけてくる。燃えるような赤や黄色に色づいた葉が木々の枝から落ちて、ひらひらと風に舞っていた。
煉獄さんに、そろそろ帰ると連絡をしてから既に一時間が経過した。あと数メートルというところで、自宅に帰る勇気を削がれた私は、いつもの公園で何度目か分からない溜息を吐く。
――この世に好きになっちゃいけない人なんて、いる訳ないでしょ
先程の絢斗の言葉が、壊れたカセットテープのように何度も頭の中で再生される。確かに、絢斗の言うことは尤もなのだ。私は結局自分が傷つくのが怖くて、自分の煉獄さんを想う「好き」という気持ちから逃げている。好きになればなるほど、彼と別れるその瞬間が、辛くて悲しくてどうしようもなくなってしまうから。
「人を好きになるだけで…価値がある…か」
耳を澄まさなければ聞こえないくらいの小さな声で、ぽつりと呟く。絢斗のように割り切って考えることが出来たら、どれだけいいだろうか。最後は自分の問題なのだと分かっている。歴代の恋人達のように、自分の「好き」の気持ちを思い出にしてしまえばいいだけ。でも、煉獄さんへの想いはそう簡単にいかない気がした。「好き」が大きすぎるのだ。無限に広がる宇宙のように。
「…名前、こんなところにいたのか。連絡があったきり帰ってくる様子がないから心配した」
視界に流れ星が二つ流れ、珍しいと目をしばたたいた時、前方で声が揺らぐ。夜空から地上に視線をゆっくり戻せば、そこには安堵の表情を浮かべた煉獄さんが立っていた。珍しく少しだけ息が乱れている。帰りが遅い私を探して走り回ってくれていたのは明らかだった。
「ご、ごめんなさい。その、気持ち良い夜だったので、少し風にあたりたくなって。星も綺麗だったので、つい…」
心臓がばくばくと身体を内側から叩き始める。突然の煉獄さんの登場に心も頭もついていかない私は、逃げるように彼から地面へと視線を移動させ、努めて明るい声を出し誤魔化すように言う。
「…名前…」
煉獄さんの足を、視界の端に捉える。彼が私と距離を詰めたのが分かり、ブランコのチェーンを持つ手に力が入る。
「れ、煉獄さん、そう言えば今日は…倫子と会ってたんですよね。倫子から連絡を貰ったんです。どうでしたか、二人でどこに行ったんですか?」
一層大きく速くなる鼓動を無視し、平静を装って言いながら顔を上げる。辛うじて笑顔と呼べるような表情を作ることは出来ていたかもしれないが、唇の端が震えていることは自分でも気づいていた。しかしそのタイミングで、煉獄さんが、私の手の上からブランコのチェーンを左右の手でそれぞれ掴んだ。視界が、彼の真剣な顔でいっぱいになる。
「そんなに悲しそうな顔をするなら、なぜ俺を友人と行かせたのだ?」
「え…」
「名前…君は今にも泣き出しそうだ」
「ち、違います!私は、そんなことない――」
ぎいぎいと、チェーンの鈍く軋む音がする。私の口は反論を述べる隙も与えられず、煉獄さんの唇によって塞がれた。炎のように揺らめく雄々しい瞳が、射抜くようにこちらを見つめている。私の手を包み込んだ彼の手に、一層強く力が込められたのが分かった。