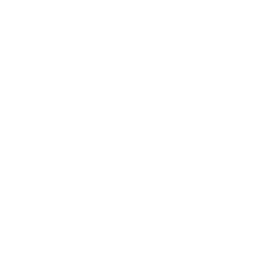
素直になれない
煉獄さんへの気持ちをはっきりと自覚したあの日から、数日が経過した。最近の私の心臓は辟易するほど鳴り響いて煉獄さんを好きだと教えてくるのに、彼の私に対する気持ちは分からなかった。
――俺はこの先も…名前が一人で泣いているのではないかと…きっと気が気でなくなってしまうのだろうな
そう言って、煉獄さんは私を抱きしめてくれた。あの言葉にはどんな意味が込められていたのだろうか。単に、危なっかしい子供から目が離せない親のような気持ちだったのだろうか。
きっと答えは後者だ。仕事終わりの帰り道、自問を繰り返しては心の中で諫めるように言い聞かせ、自宅までの道を急ぐ。
まだ、先日女性を刺したという通り魔事件の犯人は捕まっていなかった。平日で人通りはあるとはいえ女性の一人歩きは褒められたものではない。
それに、今日は煉獄さんと約束をしていたから。約束といっても、彼から「帰ってきたら、話したいことがある」と言われただけなのだけれど。真剣な面持ちで改まって言う煉獄さんがする話とは、一体なんなのだろうか。
途中スーパーに立ち寄り鍋用の食材を買って家に帰る。あまり好ましくないことを、聞きたくないことを告げられるのではないかという不安から、彼に「鍋でもしながら話しましょうか」と提案したのは私だ。
「ただいま帰りました……煉獄さん?」
靴を履いたまま、玄関から伺うように問う。時刻は夜二十一時を回っており、普段であれば煉獄さんは帰宅している時間だ。しかし、部屋の中は真っ暗で、秒を刻む時間を感じさせないほどにしんとしていた。
ドクン、と心臓が嫌な音を立てる。全身を冷や汗が伝い落ちたような気がした。
私はスーパーの袋を放りだし、すぐに踵を返して自宅を飛び出すと、初枝さんの道場へと走る。途中、鞄からスマートフォンを取り出して煉獄さんの電話番号をタップするも、数回虚しくコールが鳴った後に、留守番電話サービスのアナウンス音に切り替わってします。
早鐘を打っていた動悸が、益々激しくなる。まさか、煉獄さんが、帰ってしまった?
立派な門扉の前まで来ると、胸に手をあて乱れた呼吸を整える。重量感のあるずっしりとした木製の扉は開かれており、その先にある道場からは、まだ黄色い光が零れている。この時間に道場の電気が点いているということは、煉獄さんがまだ生徒を教えているのかもしれない。
庭に埋め込まれた飛び石を渡って道場まで近づいて、その足を止める。悲鳴に似た女性の声が聞こえてきたからだ。
「ちょっ、何なの、こんなところまで来て」
慌てて声の方へ駆けよれば、そこには四人の人影があった。それは、今にも飛び掛かりそうな勢いで苛立ちを露わにする男性に、ことの成り行きを不安そうに見つめる初枝さん。そして、袴姿の倫子に、男から倫子を庇うように立つ煉獄さんだった。
煉獄さんがまだこの世界にいる。そう安堵したのは一瞬のことで、私は咄嗟に近くの壁に身を隠しそっと様子を伺い、耳をそばだてる。
どうやら男は倫子の知り合いのようだ。怒りに歪められた顔は赤く、こちらまでアルコールの匂いが漂ってくるのを考えると、相当酒に酔っているのかもしれない。
「誰だ、お前?俺は倫子に話があるんだよ!そこどけよ」
「それは聞けない願いだ。君がまともに彼女と会話をするようには、到底見えんからな」
「はぁ、なんだとこら!ふざけんなよ」
煉獄さんにけんもほろろに突っぱねられた男は、額に青筋を浮かべ手を振り上げる。しかしそれは容易く煉獄さんに掴まれ捻りあげられる。男が、呻くような声を出し、今度は苦しそうに顔を歪める
「っ…痛ぇっ…おい、何すんだ!おい、倫子!コイツが誰だか説明しろ。勝手に音信不通になりやがって」
「もう貴方とは別れたかったの!こんな所まで来て…一体なんなの?もう構わないで」
煉獄さんの後ろに隠れた倫子が金切り声を上げ、彼の服を掴んで縋るように体を寄せた。すると私の胸も、掴まれたようにぎゅっと苦しくなる。
「…こいつが新しい男なのか?俺が嫌になったらもう次ってか」
「そうよ、悪い?分かったら、さっさと帰って。もう貴方と一緒にいるのなんて無理。少しも好きじゃない!」
「ちっ、もう知らねぇよお前みたいな女」
煉獄さんの腕を懸命に振りほどいた男は、悔しそうな表情を浮かべ、唾を撒き散らしながら吐き捨てるように言ってこの場を後にする。庭に敷き詰められた砕石がじゃりじゃりと音を立て、やがて静寂がおとずれる。
「はぁっ…びっくりした。二人とも怪我はない?」
男の姿が見えなくなると、まず口を開いたのは初枝さんだった。彼女は安堵の息を吐くと、煉獄さんと倫子に駆け寄り、心配そうに二人を交互に見た。
「俺は問題ない。君は大丈夫だったか?」
煉獄さんは初枝さんを安心させるように小さく笑みを作って言ってから、倫子に憂慮の視線を向ける。また、心臓に直接触れられたような痛みが走った。
「はい、私も大丈夫です。煉獄さんのおかげで怪我もなかったです。助けていただいてありがとうございました。…すみません、咄嗟に煉獄さんのことを彼氏みたいに言ってしまって…」
倫子は肩を竦め、申し訳なさそうに煉獄さんを上目遣いで見た。心なしか彼女の頬は赤く染まっている。
「いや…あの場合はしょうがないだろう。…それより、あの男は」
「あの人…私の以前の恋人なんです。実は、名前に紹介してもらった人なんですけど…」
倫子の口から唐突に紡がれた自分の名前に、思わずびくりとする。すると微かに跳ねた体が、壁に立てかけられていた竹箒に運悪くあたってしまう。名前は此処に隠れているぞと教えるように、箒は小さな音を立てて地面に倒れた。
「やだ、名前ちゃん!いつからそこに?」
壁に身を顰める私の存在にいち早く気づいた初枝さんが、直ぐに駆け寄ってきて私の手を引き、煉獄さんと倫子の前に引き摺りだす。
「…名前」
煉獄さんが大きな双眸を見開き、私の名を呟いた。
「ごめんなさい。ちょっと寄ってみたら、あんなことになってて…出ていきにくくて。…倫子、道場の見学って今日だったんだね。あ…大丈夫だった?…その、ごめん。さっきの男って…」
驚いた表情を浮かべる三人へ順番に視線を巡らせ、最後は倫子に伺うように問う。すると彼女は慌ててかぶりを振る。
「さっきの話、聞いてたよね。ごめんね、違うの、名前のせいじゃないから。ほら、あの人、名前が数年前に誘ってくれた合コンで知り合った人。…私のこと凄く好きって言ってくれてた人、いたじゃない?大手商社の」
数年前の記憶など曖昧だったが、「大手商社」でぴんとくる。確かに先ほどここで喚いていた男は、私がセッティングした飲み会に来ていた男だったかもしれない。
「付き合ったのは私だし、名前は何も悪くないから」
気圧されるように頷いた私に笑みを浮かべた倫子は、煉獄さんに向き直り、先ほどの話の続きを始めた。
「それで、あの人に付き纏われていて、困ってたんです。でも、きっともう大丈夫だと思います。私にこんな素敵な彼氏がいるって分かったら、流石に諦めると思うから」
煉獄さんは倫子の彼氏じゃないでしょう?口から迸りそうになった言葉を、唇を噛むことで必死に飲み込む。
煉獄さんは、あの場をやり過ごすために彼氏であることを否定しなかっただけだ。それなのに、どうして彼女はまるで煉獄さんが本当の彼氏のように言うのだろう。胸を掻き毟られたような気持ちになって、自然と眉間に皺が寄る。しかし倫子はそんな私の様子に気づくこともなく、無邪気に言葉を続けた。
「あの、是非今日のお礼をさせてください。今度一緒に食事でも」
「いや、本当に気にしないでくれ」
「でも、それじゃ私の気が済みません。ね、名前からも何とか言ってよ、従兄弟なんでしょ」
倫子がちらりと私を見、同時に煉獄さんも当惑したような視線を向けてくる。初枝さんも首を傾げて何か言いたそうに口をパクパク動かしていた。
私は、自分がどうしたいのか分からなかった。煉獄さんのことが好き。その気持ちは疑いようがなくて、倫子が彼との距離を縮めることも、胸が苦しくて仕方がなかった。
しかし、私が設定した場で出会った男性に苦しめられていた倫子のことを思うと心が痛み申し訳ない気持ちになったし、何より、自分がこれ以上煉獄さんに深入りしてしまうことが、怖かった。
万が一自分が彼と離れることになった時、死よりも辛い悲しみや苦しみに襲われることが、容易に想像出来たから。今は苦しいかもしれない。でも、傷は浅い方がいい。
そして、それは倫子にも言えることだったかもしれない。彼女は間違いなく煉獄さんに惹かれているし、彼女にも深入りさせるのはきっと良くないことだ。かといって、煉獄さんのことを話すことも出来ない私は、倫子の背中を後押しするという選択肢に辿り着いてしまう。
「折角のお誘いなんですから、行ってきたらいいじゃないですか。女性からの誘いを断るなんて失礼ですよ、煉獄さん。あ、それと、倫子のこと送ってあげてください。さっきの男が逆上して襲ってきたら大変ですから」
無理やり頬に笑みを貼り付けた中途半端な笑顔で、私は言った。倫子は、花が咲いたように顔を綻ばす。
彼女の笑顔とは対照的に、いつになく深く考えるような表情でこちらを見つめる煉獄さんの顔を、私は直視することが出来なかった。