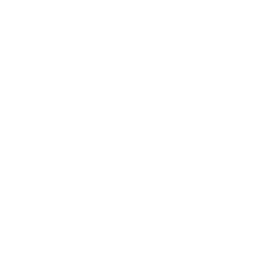
寒くて熱い帰り道
ウェアラブルウォッチを確認すれば、時刻は二十一時を回ったところであった。プラネタリウムの観賞を終えた私達は、駅から自宅までの道を肩を揃えて歩いていた。休日の今日は、この時間になると駅前も殆ど人がいない。首筋を撫でる夜気の冷たさにぶるりと身を震わす。世の中の人を暑がりと寒がりに分けるとしたら、私は間違いなく前者だった。故に、今日も長袖のブラウスとツイードスカートのドッキングワンピースという装いだったが、上着を持参しなかったことを後悔する。
自分の体を抱きしめるように肩を竦めれば、途端に背中が仄かな温もりに包まれる。
「こ、これ…」
その温もりの正体が、煉獄さんが着ていた上着なのだとすぐに分かって、私は反射的に隣を歩く彼を見上げる。
「昼間は暖かくとも、夜になると一気に冷えるな。俺のもので良ければ着るといい。…と言っても、これは名前が俺に買い与えてくれたものだが」
煉獄さんは少し困ったように微笑みながら言う。どくりと心臓が跳ね、一気に頭に血が昇るような感覚があった。先ほど、彼と超近距離でプラネタリウムを見た緊張と高揚が抜けきっていないのかもしれない。
「で、でも…煉獄さんは寒くないんですか?」
「俺のことは気にするな。名前が風邪を引いてしまっては大変だ。昨夜も何も着せずに寝かせるのは忍びなかったのだが…」
そこまで言って、煉獄さんははっとしたように口を噤む。よく見ると、薄っすらと耳朶が染まっている。そんな彼の表情を見て、私も釣られるように頬を染める。どうしてそんな表情をするのだろうかと心の中で首を傾げる。まさか、そんな大層なものでもない自分の体を彼の目に晒してしまったのだろうか。
「昨日は本当にすみませんでした!あんな素っ裸のまま寝てしまって…煉獄さんも困りましたよね。それなのに、私が風邪をひかないようにと気を遣って沢山バスタオルをかけて下さったのは分かってます。あ、あの、もし煉獄さんに私の汚い体を見せてしまっていたら本当に申し訳ないです…」
早口で言いながら、どんどん墓穴を掘っているような気になってくる。私は何を言っているのだろうか。軽いパニックを起こし、「あー」や「えっと」を繰り返していると、煉獄さんは困ったように眉尻を下げて、ゆっくりと首を左右に振った。
「そんなに自分を卑下する必要はないだろう。人の価値は見た目で判断するものではない。それに…心配せずとも名前は優しくて魅力的な女性だと、前にも言ったと思うが」
ただでさえ煩かった心臓が、今にも爆発しそうに烈しく脈打ち始める。顔が燃えるように熱くなって、私は堪らず煉獄さんから視線を逸らし「ありがとうございます」と絹糸のような細い声で呟いた。
煉獄さんはこういう人だ。別に相手の女性に特別な感情がなくともこういう芝居がかった台詞を言ってしまえる人だということは、もうこのひと月とちょっとで分かったではないか。鳴りやまない鼓動を落ち着かせようと何度も心の中で自分に言い聞かせ、掛けてもらった上着をぎゅっと握り締めた。
「…あっ、そういえば!」
ぷつりと煉獄さんとの会話が途切れてしまい、どこか浮足立った気持ちで足を前へ前へと動かしていると、ふと、まだ灯りのついたクリーニング店が目に入り思わず声を上げる。
「…名前?」
煉獄さんが不思議そうな声を出して首を傾げた。
「煉獄さん、あの、クリーニングを取ってきてもいいでしょうか?あ…クリーニングっていうのは、家で洗濯が難しい衣類などを、お金を払えば代行して洗濯してくれるお店なんですけど。煉獄さんがこちらの世界に来た時に着ていた衣類と羽織を預けていたのを失念してました」
「そうだったのか。それは余計な気遣いをさせてしまい申し訳なかった」
「い、いえ!自宅で洗濯するには難しそうだったので。あ、じゃあ取ってきますね。ここで少し待っていてください」
申し訳なさそうな表情を浮かべる煉獄さんにかぶりを振ってクリーニング店に入れば、すぐに来訪に気づいた顔馴染みの店主がバックヤードから顔を出す。
「苗字です。もうひと月くらい前に出したクリーニングなんですけど、引き取りに伺いました。遅くなってしまってすみません」
「はい、苗字さんね。ちょっと待ってて。えーっと」
財布から引換券を引っ張り出し店主に差し出しながら言う。店主は老眼の人がやるように引換券を目から遠ざけて見ると、再びバックヤードへと戻っていった。
待ちながらふと視線を店内に漂わせれば、天井に取り付けられたテレビが目に入る。小さな画面には真剣な面持ちのニュースキャスターが、重々しい声で原稿を読み上げていた。
――先ほど、路上で、自転車に乗っていた三十代女性を後ろから突き飛ばし顔面を切りつけるという事件が発生しました。病院に搬送された女性は軽傷で命に別状はありませんが、刃物を所持した男は現場から逃走し、現在警察はその行方を追っています。
「怖いわよねぇ。さっきから繰り返しこのニュースが流れてて。犯人、まだ捕まってないみたいだから気を付けてね。あ、お預かりしていたものこれで全部かしら?」
いつの間にか戻って来た店主が案じるような口調で言ってから、クリーニングの品を掲げてちらりと視線を向けてくる。
「あ、ありがとうございます。上着とズボンとシャツと…羽織。はい!これで全部です」
自分の物ならまだしも他人様の物を無くしてしまったら大変だ。私は二度、ビニールに包まれた衣類達に間違いがないかを確認してから会計を済ませる。
「はい、重いから気をつけてね。それと、帰り道も」
「お気遣いありがとうございます」
店主からクリーニングの品が入った袋を受け取りながら礼を述べる。ふと、煉獄さんが、こちらに来た時のように軍服に身を包んで羽織を纏った姿で、いつか元の世界に帰ってしまうことを想像してしまい、胸が絞られたように切なくなった。
嫌なことは考えないようにするに限る。考えたって時間の無駄なのだから。心の中で自分に言い聞かせて店を出れば、直ぐにこちら気づいた煉獄さんが、すっと私の手から袋を攫っていく。
「あ…ありがとうございます」
「いや、礼を言うのは俺の方だろう。何から何までありがとう。名前は気が利くし、良妻になるのだろうな。…それにしても、随分重いな」
物凄く照れ臭いことを言われていると気づくのに、一瞬だけ時間を要してしまった。「良妻」なんて言葉は聞き慣れなかったから。
「そっ、そんなことないです!煉獄さんは…私のことを褒めすぎです。…そんなに褒めても…何も出ませんよ」
「謙遜することはないだろう。勿論俺も、何か見返りを求めて言っているわけではない。…名前のそのような顔を見られるのは愉快だが」
恐らく赤く染まった顔で狼狽する私に、煉獄さんは可笑しそうに言った。きゅんと心臓が音をたてる。
「じゃあ…煉獄さんは、こんな私が妻だったらいいなって思ってくれるってことですか?」
どうして自分がこんな発言をしたのか分からなかった。無意識に口から言葉がするすると出て来てしまったのだ。煉獄さんの表情は、笑顔から意表を衝かれたようなものに変わっており、自分の失言に思わず下唇を噛む。
「…それは」
「なんて、冗談ですから!ごめんなさい、変なこと言って」
目尻を少し上げ表情を引き締めた煉獄さんの口から紡がれる答えを聞く勇気がなかった私は、努めて明るい声で言って彼の言葉を遮った。そして誤魔化すように笑って、煉獄さんの数メートル先に躍り出る。
「なんか今日は食べすぎちゃったから、まだお腹が苦しいです。煉獄さん、良ければ家の前の公園まで競争しませんか。煉獄さんはきっと速いから、十秒遅れてからスタートしてくださいね」
呆気に取られた様子の煉獄さんを振り返りながら言って、アスファルトの地面を蹴った。後先考えずに余計なことを口走った自分の口を恨めしく思いながら、火照った頬には丁度良い秋の夜風を受け公園までの道を走る。
煉獄さんだって、もっとさらりと受け流してくれたらいいのに。あんなに真剣な顔をして、一体何と答えようとしてくれていたのだろうか。