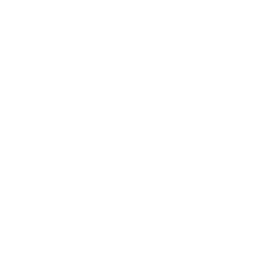
今と昔
スイッチを点けたように、ぱっと目が覚めた。寝室は既に明るく、もう朝であることに気がつく。昨日のこと全て夢であればいいのにと、恐る恐る上体を起こして自分の体を見れば、冷えて風邪をひかぬようにという配慮なのか、何枚もバスタオルがかけられていた。どうりで、もう季節は涼秋だというのに、全身にはじっとりと汗が滲んでいた。
ゆっくりベッドから降りると、私は直ぐに寝室に備え付けてあるクローゼットに走って衣類を身につける。顔から火が出そうな程恥ずかしくて、煉獄さんに申し訳なかった。
彼は、風呂場で倒れ運ばれたベッドで結局気を失うように眠ってしまった私の介抱をしてくれたのだろう。そして、流石に女性に服を着せるのは忍びない――間違いなく、私の裸を見ることになってしまうから――と思い、こうしてバスタオルで包んでくれたに違いない。
嘆きのような溜息が漏れる。昨日の自分の行動を鑑みても、煉獄さんに非など一ミリもない。悪いのは全て私で、独りで勝手に怒ったあげく、彼に迷惑をかけた。一体私はどんな顔をして煉獄さんに朝の挨拶をすればいいのだろう。謝罪の言葉を述べればいいのだろう。
ドアノブに手をかけて数分、唸り声を上げながら頭を捻っていると、コンコンと寝室の扉を叩く軽い音がする。そしてその直後に、秋の気持ちのよい太陽のような煉獄さんの声が聞こえてくる。
「名前?起きたのか」
「あっ、はっ、はいっ!起きました!」
反射的にドアを開けてしまう。そして、開けた瞬間に後悔する。昨日は髪も濡れたままで、肌の手入れもせずに眠ってしまったのだ。さぞぼさぼさの頭、酷い顔をしていることだろう。面食らった様子の煉獄さんがそれを証明している気がした。みるみる顔が熱くなる。しかし、続いた彼の言葉に、今度は私がまごついてしまう。
「良かった、顔色が戻っているな。昨夜は、体は熱いのに顔は死人のように真っ白で心配したが」
煉獄さんは愁眉を開く。物凄く心配してくれていたことが分かり、申し訳なさに頭を垂れる。
「煉獄さん、昨日は本当にごめんなさい。私、なんだかイライラして煉獄さんに一方的にあたってしまって。…挙句の果てに逆上せて倒れてご迷惑をおかけして…本当になんと謝罪したらいいのか」
「迷惑などではない。俺の方が、名前に余程迷惑をかけているだろう」
今にも消え入りそうな情けない声で謝罪すれば、煉獄さんは深く頭を下げる私の頬に手を添え、謝罪は不要だというように顔を持ち上げた。唐突に触れた手が、私の顔に朱を注ぐ。
「れ…ごくさ…」
「君が元気になってくれて良かった」
目を三日月型に細めて笑う煉獄さんに、熱い塊のようなものが胸にこみあげてきて上手く息が出来なくなってしまう。異常なまでに早鐘を打つ心臓が憎たらしい。
「もう八時を回っているが、大丈夫だったか?今日は週末だから、仕事は休みかと思い起こさなかったが…」
煉獄さんは言葉を切って、心配そうに私を見ると、そっと顔から手を離す。離れていく熱に後ろ髪を引かれながら、私は勢いよく首を縦に振り、慌てて口を開く。
「私は仰る通りお休みです!お気遣いありがとうございます。…あ、あのっ…煉獄さんは、今日はお休みではないんですか?」
「ん、俺か?ああ、今日は午前中は初枝殿の道場に行くことになっていて」
「じゃあ、お稽古が終わったらでいいので…午後は一緒にお出かけしませんか。あ、あのっ、えっと…昨日のお詫びがしたくて……銀座で、お芋のスイーツフェア…あ、甘味祭り?っていうのかな…がやってるんですけど、一緒に行きませんか。あれ…確か煉獄さん、薩摩芋がお好きだって言ってました…よね?」
勢いよく切り出した言葉が、最後は吐息のように弱々しくなるも、煉獄さんは嬉しそうに笑ったあと、大きく首肯した。
「ああ、そうだ。覚えていてくれてありがとう!薩摩芋の甘味祭りか。それは何より楽しみだ」
銀座のカフェで、たっぷりお芋スイーツを堪能した私達は、腹ごなしも兼ね街をぶらぶらと散策していた。真夏の焼けつくような陽射しの下であれば、一刻も早く室内に避難するところだが、爽秋の心地よい気候の今は、散歩にも打って付けだ。
普段はオフィスワーカーが多い銀座は、週末の今日は、老若男女で賑わいを見せていた。銀座という土地柄のせいか、すれ違う人々は、皆小綺麗に着飾っているようにも見えた。
「こちらの時代の銀座は、随分大正とは様変わりしているのだな」
興味津々といった様子で周囲の建物を見回す煉獄さんは、感心したように言う。
「煉獄さんの住んでいた時代でも、銀座はこんな風に賑わっていたんですか?」
「ああ、勿論だ。俺の住んでいた時代では、道路の真中に路面電車が走り、多くの馬車も行き交っていた。だが、当時と外観が変わらない建物もあるようだ。実に面白いな」
「へー、路面電車や馬車か。なんだかロマンチックですね。…私も乗ってみたい」
ぽつりと感想を述べれば、煉獄さんは少し驚いたように目を張って私を見ていた。何か変なことを言ってしまっただろうかと慌てて口を押えれば、煉獄さんは眉尻を少しだけ下げ、どこか物悲しい表情を浮かべた。
「…名前を俺の住む時代に連れていくことが出来れば、いくらでも乗せてやることが出来るのだが」
「…っ…」
胸が締め付けられるような気持ちになって、私は思わず言葉に詰まる。そんなつもりはなかったかもしれないが、煉獄さんの言葉は、私達の未来が永劫交わることはないのだと、言っているように感じてしまったから。そして、彼の遣る瀬無い表情が、それを残念に思ってくれているように見えたから。煉獄さんは、私と離れることを、少しは悲しいと思ってくれているのだろうか。
周囲の人々の会話がはっきりと耳に入ってくるほど、私達の間に沈黙が流れた。どう切り返せばいいのか分からない。煉獄さんは、私のどんな答えを期待してあんなことを言ったのだろうか。
互いに何となく口を閉ざしたまま、肩を揃えて歩道を歩いていると、ふと、可愛らしいジュエリーショップが目に入る。老舗の高級ブティックが軒を連ねる中、その店はまるで構える場所を間違えてしまったような違和感があった。しかし、閑古鳥が鳴いている高級ブティックやジュエリーショップと違い、店内は若い恋人達で賑わっていた。
気まずい空気を霧散したい気持ちもあったが、目を惹くディスプレイに、私は吸い込まれるようにショーウインドウに近づいていく。そこには、玩具のように小さな純白のアイアンゲートがあり、薄いピンク色の箱が、まるで海外のクリスマスプレゼントのように積み上げられていた。そして、箱の一番上には、プリザーブドフラワーをあしらったお花畑のようなジュエリーケースが乗せられており、そこには、なめらかなウェーブラインにダイヤモンドが煌めくリングが輝いていた。
「…凄い。可愛い」
「…これは?」
年甲斐もなく、まるでおもちゃに釘付けになる子供のように、ピカピカのショーウインドウに手をつき見入っていると、頭上で声が揺らぐ。はっと意識を引き戻され、いつの間にか隣に立っていた煉獄さんを見上げると、大きな瞳が、じっとリングを見つめていた。
「ごめんなさい。突然」
「いや、構わない。…これは、指輪…か?」
「あ、はい。そうなんです。これはエンゲージリング…あ、結婚を約束する婚約指輪ですね。今の時代は、婚約指輪を渡して男性が女性に求婚するんです」
言い終えてハッとする。私は一体何を言っているのだろう。こんな会話はまるで恋人みたいではないか、と自分の発言を後悔していると、煉獄さんは顎に手をあて興味深そうに頷いた。
「なるほど、それは初耳だ。求婚に贈る物は、時代によって随分と違うのだな」
「そ、そうなんですね。あの、煉獄さんの時代はどんなものを――」
「――名前!」
「きゃっ!」
意外にも話に喰いついた煉獄さんに尋ねようとすれば、名前を呼ばれ肩をぽんぽんと叩かれる。予想外の展開に驚き悲鳴にも近い声が出て、体がびくりと跳ねる。
「あ、ごめんごめん、驚かせちゃって。ずっと連絡したかったんだけど、スマホ変えたら連絡先が消えちゃってメッセージが送れなくて。会えて良かった!煉獄さんにも、また会いたいなって思ってたんです」
煉獄さんと一緒に後ろを振り返れば、そこには、満面に喜色を湛えた倫子が、私達に向かって手を振っていた。