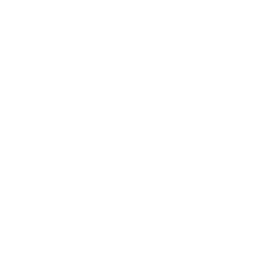
相思
初枝さんの道場を出る頃には、さらに夜も深まっていた。先ほどまでは散見していた帰宅途中のサラリーマンやOLの姿も、今はもういない。袴から私服に着替えた煉獄さんと肩を揃え、公園内の遊歩道を電灯の微かな光を頼りに歩く。
昼間は賑わいを見せる公園も、夜は樹海――実際に行ったことはないが――のように森閑としていた。時々、風に吹かれた木々の葉が擦れる音が聞こえてくる以外は、まるでこの世から一切の音が無くなってしまったようだった。
「もう食事は済ませたのか?」
先程の煉獄さんの雄姿が頭から離れてくれず、相変わらず肋骨の内側で跳ねる心臓を抑えようと躍起になって言葉を発することが出来ないでいると、彼が先に口を開いた。
「あぅっ、は、はいっ!今日は絢斗と会っていたので、軽く食べてきてしまいました」
情けなく声が裏返る。そんな挙動不審な私の様子に煉獄さんは一瞬面食らったような表情を浮かべていたが、直ぐに小さく息を吐いて笑みを作る。
「それなら良かった。実を言うと俺も、夕方の稽古と稽古の合間の時間に、初枝殿に随分ご馳走になってしまったのだ」
「煉獄さんの気持ちのいい食いっぷりを見たら、初枝さんも腕が鳴るでしょうね」
「彼女も同じようなことを言っていたな。…ところで、絢斗という者は…」
煉獄さんが控えめに問うてきて、彼に絢斗の詳細を話したことはなかったことを思い出す。
「あ、ごめんなさい。絢斗は医者をしている私の友人で、前にも話したかもしれませんが、煉獄さんがこちらの世界に来た日、怪我を診てくれたのが絢斗です。煉獄さんがお礼を言っていたと伝えたら、良かったとのことでした」
「なるほど。そうだったのか」
鷹揚に頷いた煉獄さんだったが、その後暫しの沈黙が訪れる。何か余計なことを言ってしまっただろうかと不安になって、ちらりと彼の凛々しい横顔を盗み見る。すると、神妙な顔をした煉獄さんが、ゆっくりと口を開いた。
「…絢斗というのは…男…なのだろうな」
「…えっ?」
煉獄さんの声が、ワントーン低くなる。ひょっとして、絢斗のことを気にしている?と思うのは、私の都合のいい解釈なのだろうか。
「…その男は、名前と好い仲ではないのか?名前は俺に、妻や子がいないかと聞いてきたことがあったが、君はどうなんだ?…俺と一緒に住んでいることが知れたらまずいのではないか?もしそうであれば俺は」
しかし、続いた言葉に一気に膨れ上がった気持ちが萎んでいく。煉獄さんの一挙手一投足にいちいち胸を高鳴らせてしまう私と違い、彼にとっては、私如きは関心の外にあるように聞こえてしまったから。やはり、私の都合の良い解釈だったのだろう。
煉獄さんには組織の幹部として、鬼を討つという大切な役割があるし、そのためにいつか帰らなければならないし、その日のために腕が訛ってしまわぬよう真剣の練習をしている訳で、男とか女とか、愛とか恋とか、好きとか嫌いとか、気づけばそちらに思考がいっている私なんかとは次元が違う人であることは分かっている。
でも、煉獄さんの口から絢斗を気にする言葉が出て、一瞬でも舞い上がってしまったのだ。だから、悔しかった。
「違います!絢斗は…煉獄さんには理解し難いかもしれないですけど…男でも女でもどっちでも恋愛対象っていうちょっと変わった中性的な友人で…学生時代からの腐れ縁って感じで、本当にそれだけで…」
大袈裟に声を張り上げ必死になって否定した後の空気は、先ほどよりもずっと気まずいものになっているような気がした。
「そ、そんなことより、煉獄さんはどうなんですか。さっき…道場で女の子達に囲まれてましたよね。…食事にも誘われてたじゃないですか」
ぐっと重くなってしまった空気を解きたくて、無理やり話題を転じる。そうしたいわけでは毛頭ないのに、どうしても声が尖ってしまう。
「む…あれは」
「私の許可なんか取らずに、勝手に行ってくればいいじゃないですか。私は煉獄さんに住む場所は提供してますけど、煉獄さんも初枝さんの道場で働いているわけで、結局お金だって自分で稼いでるんですから、私に遠慮することなんて何もないじゃないですか」
「名前、どうしてそんなに気が立っているのだ。…俺が何か余計なことをしたのなら謝る」
イライラした調子で言った私とは対照的に、煉獄さんはいつもと変わらず落ち着いた口調で窘めるように言う。それがまた悲しくて、無性に腹立たしかった。
「そういうわけじゃないですっ!…っ、ごめんなさい。コンビニに寄ってから帰るので、先に家に戻っててください」
「名前!」
煉獄さんが大きな声で名を呼ぶのを無視して、私は彼を振り返ることもなく、そのまま最寄りのコンビニまで全力で走った。
煉獄さんと別々に帰宅し、何か言いたそうな彼を無視して逃げるように浴室へ逃げ込む。身体や髪を一通り洗い終えると、四十二度と少し熱めの湯に身を沈める。
先ほどの自分の発言を思い出し、首を垂れてさらに深く湯船に浸かる。狭い浴室に立ち込めるバニラの甘い入浴剤の香りに本来であれば癒されるはずなのに、私の心は沈むばかりだ。
あんなことを言いたい訳ではなかった。いつもみたいに、互いの一日の出来事を笑って話したかったのに。真剣を振った煉獄さんが、凄く素敵だったと、素直な気持ちも伝えたかったのに。
なんでこんなことになってしまったのだろう。多分、煉獄さんが道場で女性に囲まれていたのが一つ関係しているはずだ。私は、妬ましかったのだ。煉獄さんは私が保護したというだけで自分の物でもなんでもないのに、他の女性が彼に近づくのが面白くないのだ。
それはつまり、どういうこと?私が、煉獄さんに特別な感情を抱いているということなのか。確かにこのひと月煉獄さんと生活して、紳士で優しい彼に何度胸をときめかせたか分からない。でもそれは、アイドルや漫画のキャラクターで推しがいるような、そんな気持ちだと思っていたのに。
口許まで湯に浸かった顔を左右に振り、そんなはずはないと言い聞かす。しかしそう言い聞かせば言い聞かすほど、心臓が妙な打ち方をする。結局私はそうして、三十分以上も釈然としない気持ちで熱い湯に浸かり続けた。風呂から出て、煉獄さんと顔を合わせる心の準備をする時間も必要だったから。
全身が火照ってきて、フウッと小さい息を吐く。流石に頭がぼーっとしてきた。このままでは湯あたりを起こしてしまう。慌てて立ち上がって湯船から出ようとすれば、急激な眩暈が襲ってくる。追従するように胃部の不快感が込み上げてきて、私は立っていることが出来ずに、激しい音を立てて洗い場の床に倒れ込んでしまう。
長時間の入浴を心から反省する。どうやら逆上せてしまったようだ。眩暈と嘔気で到底独りで立ち上がれそうにない。助けを呼ぶべきなのだろうが、煉獄さんにこんな情けない、しかも一糸纏わぬ姿を見せるわけにはいかない。
「名前、凄い音がしたが大丈夫か?何かあったのだろうか」
這いつくばって、浴室を出て脱衣所まで行こうとすれば、扉の向こうから焦ったような、しかしどこか戸惑った様子の声が聞こえてくる。それは勿論煉獄さんのもので、大きな音に心配して来てみたが、浴室という場所に躊躇しているのだろう。
「大丈夫じゃ…ないです。気持ち悪くて…ぅっ…動けな…っ」
大丈夫です。そう言って強がりたかったはずなのに、ぜいぜいと喘ぐような声で紡がれたのは、情けないことに救助を要請する言葉だった。
「悪いが失礼するぞ」
煉獄さんが言うが早いか、浴室が消灯する。視界が真っ暗になったことに驚いている暇もなく、勢いよくドアが開いて身体をふわりと柔らかい何かが包んだ。それがバスタオルだと気がついた時には、爪先が宙に浮き、私は煉獄さんに横抱きにされていた。
「っ…あっ…」
「すまない。だが何も見えていないから安心してくれ。このまま君を寝室まで連れていく」
耳元で安心させるように言うと、そのまま煉獄さんは宣言通り私を寝室へと運んで、壊れ物を扱うようにベッドに身体を横たえ、タオルの上からタオルケットをかけてくれる。
「あっ…あのっ…」
煉獄さんが、心配そうに私の顔を覗き込んで、先月の花火大会の時のように額に貼り付いた前髪を避けてくれる。こうして煉獄さんに助けてもらうのは二回目だ。お礼を言わなければと思うのに、頭がぼーっとして、言葉は舌に乗せたようにたどたどしいものになってしまう。
「ごめなさい…煉獄さ…ん」
「随分長い風呂だと思って心配していたが…湯あたりしてしまったようだな。身体が熱い。今、氷を持ってくる。水分も取った方がいい」
「迷惑かけて…すみませ…っ」
謝罪の言葉を絞り出しているうちに、情けなくて涙が滲んでくる。煉獄さんに気づかれてしまわぬようにと腕で両目を覆う。彼が、子供をあやすように私の髪をひと撫でしベッドから離れていく気配がした。
「っ…さっきは…ごめんなさい。…よく分からないけど、嫌だったんです。…煉獄さんが、他の女の子と仲良くしてるのが」
意識がはっきりしない頭で、ぽつりと水滴が落ちるように呟く。だが、もう煉獄さんは氷と水を取りにリビングへと戻っているだろうから、きっと私の言葉は届いていない。それでいいんだ。煉獄さんに特別な感情を持ったところで、どうしようもない。だって彼は、いつ帰ってしまうのかも分からない人。きっと、ずっと一緒にはいられない人。証明は出来ないけれど、彼が流星と一緒に私の元に突然やってきたように、きっと私の元から帰る日も突然にやってくるような気がした。
そして私は、いつの間にか眠りの世界へ引き摺りこまれていく。
――名前、名前!眠る前に水分はとれそうか?
微睡の中で心地よい声を聞いた気がした。しかし、岩のように重くなった瞼を開けられない私の耳元で、もう一度声が揺らぐ。
――俺も一緒だ…名前
そして、唇に温かいものが触れ、それとは対照的に酷く冷たい液体が注ぎ込まれたような気がしたが、きっとそれは私の夢の中の話だろう。