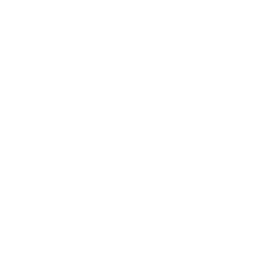
恋人疑似体験
煉獄さんは、初枝さんの自宅の玄関で、既に着替えを済まして待っていた。浴衣に着替えた私の姿を視界に捉えると、煉獄さんは凭れていた壁から背を離し、薄い唇に笑みを浮かべた。
「やはり、名前は和服が似合うな」
私の姿を見るなり、煉獄さんは開口一番そう言った。少しも躊躇ない様子から、彼にとっては挨拶をするようなものなのかもしれないが、私の心臓に直接触れるような切ない痛みをもたらすには十分過ぎる言葉。
「お…お待たせしてごめんなさい」
言いながら、ちらりと煉獄さんを見る。洋服を着た煉獄さんも素敵だったが、和服を纏う彼はその数倍の破壊力だ。初枝さんの旦那さんの物であるという、控えめで細やかな縦縞しじら模様の浴衣は、和服の繊細な雰囲気があった。恐らく普段から着物や浴衣を着慣れているであろう煉獄さんが着ることにより、一層品の良さを感じさせる。明るいトーンの色合いは、見目も爽やかで涼し気だ。
「あら、煉獄さん、自分で浴衣を着られるなんて流石ねぇ。ふふ、名前ちゃんはどうかしら?私の若い頃の着物だけど、凄く素敵だと思わない?」
煉獄さんの浴衣姿を褒めちぎった後、初枝さんはずいと彼の前に差し出すように私の背を押して楽しそうに言う。
初枝さんが着せてくれた浴衣は、ややくすんだ白地に淡藤色や菖蒲色の花が描かれていて、上品さの中に華やかさが散りばめられた魅力的な一着だった。なんでも、明治時代から続く老舗の呉服店で、一枚一枚職人の手によって伝統的な技法で染め上げられたものらしい。確かに、昨日ショッピングモールで見た浴衣と比べてより上質なものであるということは、素人目の私から見ても一目瞭然だった。
「ああ、本当によく似合っている」
「煉獄さん…そんなにお世辞を言っていただかなくても大丈夫です。ほら、初枝さん。素敵だと思わないって言われて『似合わない』だなんて言えないですから」
駆け引きも小細工もない真っ直ぐな一言が、心に突き刺さる。居た堪れなくなって隣の初枝さんに縋るように言う。しかし彼女は、口角の笑い皺を深め、「お世辞なんかじゃないわよね?」と煉獄さんに確認するように問うた。
「勿論、お世辞などではない。それに俺は、思ったことをそのまま口にしてしまう性分で…嘘が吐けないのだ」
煉獄さんは、ボールを打ち返すようにスパンと明快に答える。恥ずかしさや照れくささが自分の顔から駄々洩れになっているのが分かる。
「もっと言ってあげて、煉獄さん。名前ちゃんね、本当にいい子なのに自己評価が随分低いのよ。ほら、女性は恋人に褒められれば褒められるだけ自分に自信がついてさらにいい女になるものだから。そういうわけで、煉獄さん。名前ちゃんを宜しくね」
あとは若い人達で。そう言い残し、初枝さんは私達を送り出して玄関の戸をぱたりと閉めた。
似合っているとか、嘘は吐けないとか、そんな歯の浮くような台詞は躊躇なく言うくせに、初枝さんの私達の関係を勘違いする発言に、煉獄さんは決まりが悪そうな表情を浮かべていた。一方私も、体が火照って仕方がない。本来浴衣は涼しいものであるはずなのに、これでは花火大会に行く前に汗で浴衣が使い物にならなくなってしまうのでは、と不安になるレベルだ。
「……では、行くか」
「は、はいっ!」
擽ったいような沈黙が数秒続いたが、その空気を霧散させるような、夕方の気配を乗せた生温かい風が吹いた。その風に釣られたのか、煉獄さんが苦笑を漏らしながら言う。ぱっと顔を上げた私は、上擦った声で勢いよく返事をした。
日本一人が集まると言われている花火大会は、今年も御多分に漏れず多くの人で溢れ返っていた。親子連れに、恋人同士に、女子グループに、学生達。様々な人々が花火大会に共通するこの雰囲気を楽しんでいる。頭上に広がる夏の空は、漸く陽が傾き始めたが、花火を打ち上げるには少し早そうだ。
おもちゃ箱をひっくり返したような混雑ぶりに、隣の煉獄さんは驚いた表情を浮かべていたが、それ以上に、通りの両端に隙間なく並ぶ屋台に興味を引かれているようだった。
「煉獄さんの時代では、祭りに屋台はなかったんですか?この時代では祭りと言えば屋台です!皆これを目的に来ているようなものですから」
花火が打ちあがる河川敷に向かう人々の流れに従って歩きながら、煉獄さんに問う。
「勿論、俺の住んでいた時代にも屋台や露店といったものはあったのだが…こことはまるで規模が違う。こんなにも色々な種類の店があるのだな」
「まぁ、大半の屋台が同じようなものを扱っているんですけどね。多いのはやっぱり粉ものかなぁ。その次にチョコバナナ…あ、勿論食べ物だけじゃなくて、射的とか金魚すくいとかそんなのも――」
通りの左右の屋台に忙しく視線を巡らせ、身振り手振りをつけて説明していると、突然後ろからやってきた軍勢のような集団の波に巻き込まれ、人込みに揉まれてしまう。こんな場所で、携帯もお金も持っていない煉獄さんと逸れてしまっては厄介だ。ふと焦燥感を覚え、恥を忍んで「煉獄さん!」と叫ぼうとすれば、腕を引かれた。
「名前、大丈夫か?」
「煉獄さ」
「こうしていた方が良さそうだな」
私を人込みから連れ出してくれたのは煉獄さんだった。礼を言う間もなく、煉獄さんはそのまま私の手を握って苦笑した。確かにこの混雑だ。彼の提案は適切だし、それは母親が小さな子にするような気持ちだったのかもしれないが、先ほど初枝さんの家で感じた火照りが舞い戻ってくる。
「あ…あの」
屋台の、水槽を模したビニールプールの中で窮屈そうに泳ぐ金魚のように、真っ赤な顔で口をぱくぱくしていると、煉獄さんが「すまない、嫌なら離すが」なんて言ってくるものだから、私はぶんぶんと首を左右に振って、自分の気持ちを示した。
「名前、あの食べ物はなんだろうか?」
安堵したように笑った煉獄さんは、ちらりと視線をある屋台に走らせながら私の手を引いた。
「あ、あれはドネルケバブですね」
「どねる…けばぶ…」
「確かにケバブは大正時代にはないですね。えっと…日本ではない外国から入ってきた料理なんですけど、ああやって垂直に串に刺したお肉を削いで、パンに挟んで食べるんです。凄く美味しいですよ。…食べてみます?」
屋台に近づくと、芳ばしい香りに食指が動かされ、私達は同時にぐぅっと腹の虫を鳴らす。そして、顔を見合わせ噴きだして、次の瞬間には肉を削ぐトルコ人風の店主に声を掛けていた。
「すみません。ケバブサンド、二ついただいてもいいですか?」
「はい、ありがとう。いいね、お姉さん達デート?浴衣似合ってる。彼氏も男前」
流暢とは言えない日本語を話す店主は浅黒い肌とは対照的に真っ白な歯を見せながら笑い、サービスだとたっぷり肉を挟んだピタを渡してくれた。礼を述べそれを受け取りながら、先ほどの初枝さんといい、周りの人々には、煉獄さんと私は恋人同士に見えているのだろうかと、ふと考える。不思議と嫌な気分はしなかった。寧ろ、嬉しさに心が弾むような気持ちにさえなった。
煉獄さんは、私の彼氏に見られることは嫌じゃないだろうか。包みを渡しながら彼の大きな双眸を探るように見れば、眩しい笑顔が向けられる。
「ありがとう!」
「あ、い、いえ!食べてみてください。…煉獄さんのお口に合うといいんですけど」
言いながら自分もケバブサンドを齧る。一口で、大好きな香辛料の味が口内に広がりじわじわと唾液が滲む。美味しい!思わず感嘆の声を漏らした私の横で、煉獄さんも端正な顔に笑みを浮かべ「美味い!」と感動したように大きな声を出した。それは、思わず周囲の人々が私達を振り返ってしまうくらい。
「この時代には、こんなに美味いものがあるのだな。名前の料理も美味いが、屋台の食事も筆舌に尽くし難いな」
「ふふ、煉獄さん大袈裟です」
仰々しく感想を述べる煉獄さんに私はまた吹き出した。
「しかし、本当のことだ」
「いいと思います。私、どんな食事でも美味しいって言って食べてくれる人、凄く好きです」
無意識に唇から零れた言葉に、煉獄さんが一瞬動きを止めた。はっとして口を押え彼を見ると、照れくさそうに耳朶を染めていた。
咄嗟に自分の言葉を訂正しようとしたが、どう訂正したらいいか分からず、結局私は口を噤んだ。