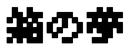
ぱりん、と音が聞こえたような気がした。
「やあ、久し振り」
にんまりと唇を三日月型に変えて、ソレは僕に甘えた声を出した。ソレの背後には夕日を反射しているひびの入った黒い画面がある。オレンジ色のセロファンを被った大きな箱形のブラウン管テレビ。もうすぐ薄型テレビに買い換える予定の、幼い頃から居間の角に陣取っていた家具。
ソレは人とは思えなかった。長らく狭いところに詰め込まれた長いコードのような、ぐちゃぐちゃに絡み合う紐状のモノが三日月型の唇の上に山を作っていて、それが人の頭の形と極似している。けれど目らしい目はないから、ただの唇お化けだ。人ではない。
「いやあ、久し振りだというのに感動の抱擁もなしかい?」
呆然とする僕は今、先程まで使っていたリモコンを手にソレの前に座り込んでいる。いつも通りの夕方、いつも通り高校から帰ってきて、いつも通りテレビをつけて、何か面白い番組はないものかと(そして大抵ドラマの再放送ばかりでつまらなくて、テレビを消して見飽きた漫画にふけるのだ)チャンネルをぐるぐる回していたはずだ。
「……えっと……?」
ほら、早くこの胸に、と言わんばかりにソレは、コード頭からにょきと何かを生やす。これまたぐちゃぐちゃのコードで形作られた二本の腕のようなものを頭の両脇から左右に一本ずつ広げて、ソレはしばし黙り込んだ。僕も何も言えなくなって黙っている。変な沈黙が居間に満ちて、その間聞こえてくるのはカチカチという静かな壁時計の音だけ。
「……もしかして」
しばらくして、時計の音に似た声が唇お化けから囁かれる。
「……覚えてないの?」
「覚えてるも何も、あんた誰、いや、何?」
「うっそーん……」
どこからかガビーンという効果音が聞こえてきたような気がしなくもない。コードの腕をコード頭の天辺に置いて、ソレは唇を逆三日月型に変えた。
「あんなに、あんなにボクのことを思ってくれてたのに! しばらく会えなかったから寂しかったけど、今日久し振りに会えてボクちょー嬉しかったのに!」
「誤解招くような言い方しないでよ」
「そっか……そっか……もう君は子供じゃなくなったんだね……そうか……」
「人の話聞いて」
「じゃあボクは君の成長を祝して、素直に立ち去るとするよ……勘違いしてごめんね……」
「だから、人の話! 聞いて!」
勝手にじめじめと背筋(があるのかどうかわからないけれど)を丸めて、ソレは僕に背を向ける。どうやら奴はブラウン管テレビの中から出てきたらしい。やっとそれに気付いて、僕はソレを引き留めようと手を伸ばす。納得はできないけど、映らなくなったテレビに割れた画面、コードをしっちゃかめっちゃかにまとめたようなソレの見た目とくれば、嫌でも理解してしまう。
「あんた何なんだよ! まずそこから説明!」
「えーめんどっちい」
先程までのじめじめ感はどこへやら、ソレは鼻をほじるような仕草で唇の上のコードの塊にコードの腕の先を突っ込んだ。
「おれっちコードの塊だから話すとか聞くとか向いてないんすよー」
「さっきから勝手に一方的に話しておいて? 僕の言葉に答えておいてそれ? 言い訳はいいから、説明!」
「説明たってなあ……見ればわかるでしょ?」
「わかんないから訊いてる!」
「えー? ボクがブラウン管テレビの箱の中にいる住民だってこと、見ればわかるじゃーん、言わせないでよ照れるなあ」
「いやいや全然わかんなかったから! ていうかどこに照れる要素があるんだよ!」
ブラウン管の中の住民。これは悪い夢かな、とふと思う。見た目も悪いし。唇お化けを夢に見るなんて、僕疲れてるんだな。どうせファンタジーな夢を見るなら、超絶可愛い胸のある妖精ちゃんに会いたかった。
そんなことを思っていたけれど、コード野郎にツッコミながら、頭の片隅で何かに気付いた予感もあった。
ブラウン管テレビ。幼い頃から居間にあった家電製品。プラスチック質の色とりどりの光を放つ板を、大きな箱を取り付けたかのような物体。テレビのしくみがわからなかった頃、僕は、この箱に何か妄想をしていた。
画面に手を突っ込めば、テレビの向こうの空間に移動できるんじゃなかろうか。小さなネズミが、箱の中でいろんなボタンを押したりしているんじゃなかろうか。
――箱の中に何かがいて、そいつがチャンネルを切り替えたりしてるんじゃなかろうか。
「テレビの中は快適さ、何も見なくていいし何も聞かなくていい」
ブラウン管の中から出てきた化け物はそう言ってテレビに寄りかかって僕に向き直る。ひびの入った画面に映るソレの背面には、やはり目も耳も見あたらない。ただコードがごちゃっと固まりからまっているだけだ。目も、耳もない姿。必要ないからついていないのか。
「この口だってほんとは必要ないんだけどさ、音声だけはスピーカー駆使してボクが出さないといけないんだよねえ。男も女もオカマもガキも。めんどくさい。けど、耳も目もないけど、コードだからさ、伝わってくるのよ。今が2011年で、今までの放送の仕方が変わって、ボク達の家の大半が買い換えられるってこと」
寂しいもんよ、と彼は呆れた様子を示すように、コードの腕を上下に揺らす。
「時代の流れは悲しいもんよ。こうやって冷蔵庫も洗濯機も、姿を変えて買い換えられて。昔の家電って無駄にデカイって思ってるでしょ? 違うのさ、その”無駄なデカさ”の理由は、ボクのような住民がそこでお仕事をしているからなの。居住空間ね。今じゃ仕事の何もかもをキカイがやっちゃうから、ボク達は無職どころかお邪魔モンよ」
突拍子もない夢だな、と思うしかなかった。こんなへんてこで現実的で不可思議な話、今までの夢で見たことはない。何も言えない。だって、こんなこと、考えたこともない。
妙なリアル感に戸惑いながら、僕は目の前の怪物を眺め続ける。三日月の形を失った唇が煙草を吸って煙を吐いた後のように、物足りなげにふやふやとたゆむ。
「あんたは」
ふと僕の口から声が出る。歯の奥から出た、と言っても良いかもしれない。夢の中だからかな、とぼんやりとした頭で思う。勝手に動く舌。何を言うつもりなのか僕自身にもわからなかった。
ただ、何かを言いたくて。
「あんたは、ずっと、うちにいてくれてたんだな」
瞬間、僕は彼が僕を見据えたのを感じた。目はなかった。けれど、確かに。
彼は、僕を見て、そして、
翌日さっそく父親が買ってきたテレビは大安売り中の薄型テレビだった。現在、それは居間の隅を陣取っている。ブラウン管テレビはいつの間にかいなくなっていた。あの夢の後、気がついたら彼はいなくなっていて、テレビにはひびひとつなかった。夢だったのだ。
だけど、と僕は思わずにはいられない。
あの夢は、白昼夢というよりは、別の。
いつも通り高校から帰ってきた僕は、いつも通りテレビをつけて、鮮やかな画面に映るお笑い芸人を眺める。そして、立ち上がってテレビに歩み寄り、その背後を覗き込んだ。
薄型テレビはその名の通り、薄い。ブラウン管テレビとは違って、”無駄なデカさ”がない。
僕は知っている。テレビが遠くの映像を映すしくみを。それが誰かや何かの仕業ではないことを。
だから、気付いた。
彼は――睡魔による夢ではなく、僕が幼い頃にブラウン管テレビに抱いた、小さな夢だということを。
彼にはもう会えないだろう。うちにブラウン管テレビはもうない。箱の形をしていない薄型テレビに、箱の夢は妄想できない。時代の流れだと彼は諦めたように言っていた。
けれど。
――あんたは、ずっと、うちにいてくれてたんだな。
僕の言葉に、目を持たない彼は、泣いていた。
「ずっとここにいたよ。今までね」
そう言って。