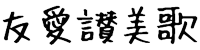何したってつまらない。自暴自棄になって鞄を放り出し、床に寝転がる。
──冷たい。
一人暮らしの狭いマンション。暖房をつけなきゃなとぼんやり思ってはみたが気力もない。ただ、悲しいだけだった。体が鉛のように重くて動かない。
理由は至極簡単だった。
『君は、こんなこともできないのか』
相手にとっては些細な一言にすぎないのに、縛られてしまうなんて凄く馬鹿馬鹿しい。
だけど、必死でがんばってきた努力を無駄だと言われているようで悲しかった。
(何もそこまで言わなくてもいいじゃない)
些細な失敗だったのに、どうしてそこまで言われなきゃならないの。私、そんなに悪いことしたの。
でも、この失敗でクビになったらどうしよう。いらないって言われたらどうしよう。何もできないって言われたらどうしよう。
些細な一言をきっかけに浮かび上がる失敗の数々。子供の頃から気にしていた悪い癖や振る舞い。全部一気に思い出して泣きたくなった。
ああ、ああ、ああ、もう。
──どうにでもなってしまえ。
呟いた一言をきっかけに、私は不貞腐れるように眠りについた。
****
「よう」
「……お疲れ様です」
夢の中で現れたのは優しい先輩だった。いつも気を使ってくれて朗らかな先輩だった。
「なあにしょげてるんだ。らしくないぞ」
「すみません……」
「謝ったらいいってもんじゃないぞ。もっと笑え。でないと今から行く飯が不味くなるだろ」
「……へっ」
「へっじゃない。お前一人言で『飲まなきゃやってられない』って落ち込んでたろ」
「……聞かれてたんですね」
誰にも知られないよう、見せないよう心掛けているつもりだった。仕事だから迷惑かけてはいけないと。
「お前、まだ一年目だろ。一年目なんか失敗ばっかするんだって。優しくできりゃいいんだがなあ」
もっと優しく言って欲しかった。聞いて欲しかった。どうして聞いてくれないんだとさえ恨んだ。
「でも、ビシッと言わないとさあ、過信するんだ。過信したら取り返しのつかないミスをして、俺らでカバーしきれなくなるだろ?」
「……」
「小さいミスで済んでるうちに、嗚呼絶対ミスしないようにって、ここは絶対気をつけないとって思わせる失敗を重ねるのが新人の仕事なの。あの上司、今めっちゃ仕事できるけど昔はお前みたいな感じだった」
先輩……。そう、先輩の勤務年数はもう六年になるとか。上司もそのくらいだと聞いたことがある。仕事上でも付き合いの長い仲ならよく知っているのだろう。
「な、うまいだろ?」
「話ばっかして全然食べれてないんですけど……」
「食べながら話すのも仕事だぞ」
「何ですか、それ」
「俺の特技」
──こんな人が近くにいて良かった。
──こんな風になりたいなあ。
朧気な憧れは明確な形になって、嗚呼こんなにも勇気づけるのかって。
「先輩の奢りですよね?」
「えー金ない」
「何に使うんですかー」
「色々あるんだよ」
****
朝、目覚めたら意外とスッキリして驚いた。あんなに落ち込んで、泣きたくなった筈なのに今はそんなことはない。
昨日は不思議な夢だった。でも、凄く愛しい夢だった。
「さあ、今日も負けないよ!」
がんばった向こうには、楽しみがあるのだから。
『おはようございます、先輩!』
『お、おう。どうしたんだ、滅茶苦茶元気じゃないか』
『でしょ。先輩、がんばってるんで奢ってください』
『何を生意気な』