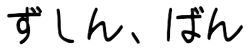1
父親に憧れていた僕の目の前に現れた、父親のような人――それが、ヒロさんだった。
ヒロさんとの出会いは、一カ月前。二学期が始まった、九月のはじめの土曜日のことだった。
母親と喧嘩をした日だった。些細なことだったのだ、原因は。僕が、母親の注意を受け入れなかったから。
「隆和(たかかず)! どうして言うことがわからないの!」
「うるせえ、こんな家出てってやる!」
リビングから、玄関まで駆けて、靴を履きかけたまま、外へ飛び出した。
母親の怒鳴り声が、だんだんと遠くなる。あてもなく、ただ走った。
走っているとなんだか、いろいろなことが頭に湧き上がってくる。
母子家庭で育った。母親はつまり、シングルマザーということになる。
小さいころは、母親しかいなくても、それが普通だと思っていた。けれど、小学校に入ると――違った。
友達の家に、遊びに行けば、そこには。
父親が、いた。
小学生にして僕は知ったのだ。家族には父親がいるものだと。
それでもまあ、どうにか母親とは暮らしてきたのだけれど、中学一年生になった僕は――母親を嫌っていた。
同時に、父親に強く憧れていた。
母親独特の、こう、自分の理想を押し付けるような。そんな、ものの言い方、怒りかたに、強い反発心を抱いた。
それで、さっきも――
2
気が付いたら、公園についていた。遊具がいくつかあって、ベンチが一つだけ置いてある小さな公園だ。
ベンチに座ろうと思い、そちらに目を向けた。六十歳くらいの白髪のじいさんが一人で座っていた。まだ一人は座れそうだ。
じいさんの隣で、ベンチに腰掛けた。
ため息をつく。一回、二回、三回、四回、五回。勢い余って外に出てきた自分に、少し後悔した。感情の制御がきかずに、子供みたいに、母親を嫌い、反発し、当たってしまう自分を恨めしく思った。
「なあ」
誰かの声がした。突然だったから、心臓が震えたように驚いた。隣から聞こえたような気がした。
「おまえさん、大丈夫か」
隣に座っていた爺さんの声だった、やっぱり。
「あ、いや、その、大丈夫、ですけど」
動揺を隠しきれず、たどたどしく言葉を返す。
「大丈夫じゃないだろう。さっきから、ため息ばかりついて。おまえさん、名前は」
どうやら、話を終わらせることは、できないようだ。
「……木高(きだか)です。木高、隆和」
渋々、というかぶっきらぼうに答えた。
「おまえさん、歳はいくつだ」
「十三ですけど……」
「それで、今日はどうしたんだ」
非常識だと思った。自分の名前も名乗らずに、聞いてくるなんて。
「あの、あなたのお名前は」
「ああ、そうだったな。悪い、悪い。俺は、勝谷広之(かつやひろゆき)。数年前に定年退職した。ヒロとでも呼んでくれ。それで、どうしたんだ今日は」
「ヒロさん、ですか。どうしたって言われても……特になにもないですけど」
嘘をついた。プライバシーの自衛だ。
「あんなに何回もため息をついて、何もないわけがないだろう、隆和君」
いきなり、隆和君と言われ、少したじろいだ。その隙を狙うかのように、ヒロさんは続けた。
「なにか悩んでるんじゃないのか、なあ。どうなんだ」
赤の他人なのに、こんなにしつこい人は好きじゃない。けれど、不思議と悪い気分にはならなかった。
「いや、その、感情の制御がきかなくて……」
「おお、それで」
思わず喋ってしまった。そこをヒロさんは見逃さなかった。
「母親を嫌って、反発しちゃう自分が嫌いで……」
「ほおほお」
しばらく沈黙が続いた。
「……どうすれば、いいですかね」
思わず口に出していた。助けを求めていた。赤の他人であるはずの人間に。
「うん、うん、よくわかった。難しい問題だな。これは」
「そう……なんですか?」
普通に会話するようになっていた。自分でも不思議だ。これが、出会いというものなのか。
「そうだ。大人でも難しい問題だ」
「それで、ヒロさんはわかるんですか」
「いや……わからない。だけど、見つけようと思う。答えを」
「はあ」
「答えを見つけたら、必ず隆和君に教える。絶対にだ」
普段だったら、こんなに暑苦しい人は嫌うはずなのに、やっぱりどこか気分はよかった。
「はい、待ってます」
それで、その日はヒロさんとは別れた。
少し気まずかったけど、家に帰って、一目散に自分の部屋に飛び込んで、考えた。なぜ、赤の他人であるはずのヒロさんにあそこまで、本音を話せたのだろう。
答えは、少し考えればすぐにわかった。
父親のような人だったのだ。ヒロさんは。僕にとっての父親になり得る存在だったのだ。だから、あれだけ、話せたんだ。
自分で勝手にそう、納得した。
それからというもの、毎日ヒロさんと会った。学校のある日は、学校が終わってすぐに公園に行った。おかげで、宿題が深夜まで毎日かかって母親には怒られたけれど。毎日雑談をして、楽しかった。父親と話しているような気がした。けれど、問題の答えはまだヒロさんもわからないようだった。
3
そして、今日。十月のはじめの土曜日。今まで、ヒロさんがいない日はなかったのに、初めていなかった。一時間くらい待ってみたけれど、やっぱりヒロさんは公園に現れなかった。
次の日も公園に行った。けれど、ヒロさんはいなかった。
それでも僕は毎日、公園に通った。けれど、ヒロさんの姿が公園に現れることはなかった。
僕と話すのが嫌になったのか。自己嫌悪に陥った。それとも、なにか、別の理由が――
4
めっきりと寒さも増し、年の瀬感じつつあった、十二月の半ばの日曜日。
公園に行くと、ベンチに座る、ヒロさんの姿があった。だいたい、二カ月ぶりくらいの再会だった。
ヒロさんは僕に気づくと、こっち、こっちと手招きした。ヒロさんは少しやせたような気がする。僕は、ヒロさんの隣にいつも通りに座った。
「久しぶりですね、ヒロさん。少し、痩せました?」
「ああ、ダイエットしてるんだよ、少し。それにしても悪かったね、突然いなくなっちゃって」
「いえ、まあ、そんなことは……」
僕の言葉を遮るようにして、ヒロさんが口を開いた。
「今日は、隆和君に、大事な話をしたくて、あと答えもわかったんだ。それを言いたくてね」
「答えがわかったんですか!」
自分でもわからないが、僕は興奮気味に反応した。
「ああ、それじゃあ今から答えを言うよ。答えというか、一つの方法なんだ」
「方法ですか」
「そう、自分の感情が抑えられなかったり、凄く不安なとき。それから、自分が嫌いになりそうなときは、受け止めるんだ」
「受け止める?」
「こうやって、受け止めるんだ」
そう言うと、ヒロさんは立ち上がって、腰を落として、両手を大きく広げて、タックルを受けるようなポーズをした。
「腰を、ずしん、と落として、ばん、と大きく手を広げるんだ。そうすれば、自分の気持ちを受け止められる。絶対に」
馬鹿らしい。こんなポーズごときで。けれど、やってみようと思った。少し、恥ずかしいけれど。
「ほら、隆和君、立て。一緒にやるぞ」
ベンチから腰を上げて、身構える。
「いいか、隆和君。やるからな」
「はい」
「ずしん!」
僕は大きく腰を落とした。
「ばん!」
大きく両手を広げた。
「いいぞ、もう一回だ。今度は俺に続いて声を出せよ」
「はい!」
久しぶりに、大きな声で返事をした。公園でやることに対する恥じらいとか、そう言った感情は全部捨て去った。
「ずしん!」
「ずしん!」
「ばん!」
「ばん!」
大きな影が二つ、両手を開いて腰を落としていた。
「どうだ、これで受け止められるだろう」
効果は正直、よくわからない。けれど、受け止められそうな気がした。
ヒロさんは、一息ついて、ベンチに腰掛けた。少し遅れて、僕も。
「隆和君、受け止めるについて少し言っておきたいんだけど、受け入れる必要はないんだぞ」
どういうことだろう。頭が混乱した。
「受け入れてばかりいたら、苦しくなっちゃうし、それが爆発して、誰かに当たっちゃたりしたら、最悪だろ?」
「それは、そうですね」
「だから、受け入れなくていいんだ。さっきの、ずしん、ばんをやってから受け止めればいいんだ。受け止めるだけでいいんだ。誰かの気持ちも、なにより自分の気持ちも」
そうか、よくわかった。受け止めれば、いいのか。
受け止めよう。父親がいない現実も。母親との二人の暮らしも。なにもかも、全部。そう思った。
「隆和君、最後に大事な話がある。俺は、もう、ここへ来ることはできない」
脳の思考回路が停止した。どういうことだ。
「いったい、どういうことなんですか、ヒロさん」
「いや、理由は……言わない方が、楽しく別れられるだろう? だから、言わないよ」
「そんな……理由のわからない別れなんて、理不尽じゃないですか!」
「ああ、そうだね、理不尽だ。けれど、隆和君、わかってほしい。君を傷つけることはできない。だから理由も言えない。けれど、これだけは覚えてて、ほしいんだ。受け入れるんじゃなくて、受け止めること。それと、ずしん、ばん。この二つだけは忘れないでほしいんだ。約束して、ほしいんだ」
「……わかりました。絶対に忘れません。約束します。でも、やっぱり、もう会えないなんて――」
目から涙が溢れた。家族以外の相手で、泣いたのは、これが、初めてだった。
「泣くな、隆和。泣くんじゃない。その気持ちを全部受け止めるんだ」
少し涙声でヒロさんが言った。
「立て、隆和。受け止めるぞ」
ヒロさんの声はもう、涙声ではなかった。僕の涙も、止まっていた。
立ち上がる。二人で、構える。これが二人でやる最後の――
「ずしん!」
「ずしん!」
腰を落とした。
「ばん!」
「ばん!」
両手を大きく広げた。
受け止める。別れの気持ちを、受け止める。
「じゃあな」
ヒロさんが僕に背を向けて歩き出した。
「ヒロさん! あの」
ヒロさんを呼び止めた。伝えたかったから。
「ありがとうございました!」
深く一礼した。
頭を上げると、ヒロさんはにっこりと笑って、歩き出した。
ヒロさんの背中が遠くなっていく。いつまでも、見えなくなるまで、ヒロさんの背中を見つめていた。
5
ヒロさんと別れてから二年がたった。中学三年生になっていた。受験生だ。
母親とはあれから、それなりにうまくやっている。
父親に対する憧れも、少しは消えた。
あれからも、僕はときどき公園に行ったけれど、ヒロさんが公園にいることは、絶対に、なかった。
風のたよりでは、ヒロさんは大病を患って……と聞いた。もう、二度と会うことはできない。
最後に会ってから、会いたいとは、思ったけど、ヒロさんは会うことを喜ばないだろうなと思った。あのときに、会えないと決めたから。
僕は今でも、約束を守っている。ずっと、永遠に守り続けるだろう。
今日は高校受験だ。試験会場の入り口の前で、構えた。
ずしん、ばん。
受け止める。気持ちを全部。
それでも自分に問いかける。
僕は受け止められているだろうか――
僕は信じる。受け止められていると。
会場のドアに手をかける。もう一度、受け止めておこう。そう思った。
ドアの前でもう一度。
ずしん、ばん。
腰を落として、両手を大きく広げた。