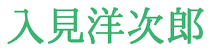
あの男は剥製師としては一級の腕であった。人気のない時計屋の奥で一人黙々と、皮を剥ぎ臓と肉とを湯で煮落とした獣を、沈黙はせども生きた姿によみがえらす、彼の剥製の瞳はまるで血が通ったいきもののように生々しかった。僕はただそういうものは見ているだけだのでその知識には明るくないが、あの男の作った羆の剥製を初めて見たとき、その雄々しい姿にはもちろんのこと、僕を真っ直ぐに射留める捕食者の瞳に、背中を這いあがるような思わぬ寒気を感じたものだった。ひと呼吸のあいだに顔から血の気がいくらか失せて、それを見たあの男はといえば、控えめにも得意げな微笑をして「どうだ」といくらか蠱惑的な表情をした。
僕はあの男とそう特別なつながりがあったわけではないのだ。僕が彼の時計屋によく行くので、多少の顔見知りになって多少の世間話をする程度なのだ。あの男の苗字は入見といった、入見の店は、彼が時計の修繕のできるのをよしとされて二年ほど前に祖父から受け継いだものであった。僕は薄い色眼鏡をかけた品の良い老紳士が店番をしていた時に、今の腕時計を買ったので、それが水をかぶって動かなくなってしまったとき修理のために店に足を運んだら、店主が代替わりをしていて、若い男が机の上に古時計の中身を広げて手を微細に動かしていたのですこし驚いたが、僕が声をかけ静かに振り向いたその顔に、あの老紳士の面影を見留めた。祖父のと同じ形をした、だが色は入っていない銀縁の眼鏡を細い指が押し上げた、その挙動はわずかにも女性的であった。「何か…」彼、入見が僕に呟くので、咄嗟に、「あ、ああ」とだけ返事にもならない返事をし、右のポケットに無造作に押し込んでいた腕時計、文字盤に水がまだ貼り付いているのを差し出した。入見は時計を裏返したり、文字盤をじっと見たり、とかく眺め、顔を上げて僕に言う、
「派手に濡らしたものだ」
「や…誤って風呂に落としまして」
「…乾かして、分解と掃除をすれば、運が良ければ直る。三日後にまた来なさい」
入見はそう言うとすぐに机に向かってしまったので、僕はもう帰らざるを得ないような気もして、そのとき昼の二時だか三時だか、それくらいの日の光を受けながら家に帰った。言われた通り三日後になって店に行くと、「運が良かったですね」と元のように動いている時計を差し出された。代金は時計を買った値段と同じくらいであった。(もとより聞くつもりであったので)元の店主、あの老紳士はどうしたのかと訊いてみると、入見いわく胸を患い病院に入ったのだという。それほど残りも長くないのだとも聞いた。入見は表情の動かない寡黙な男であった。
それからあまり日も経たない頃に、どういうわけだか家の壁掛け時計が動かなくなったので、夜も近かったがまた入見の店に行った。入見はそのとき店の奥に引っ込んでいた。僕が呼んでしばらくすると入見は出てきて、時計の用を話すと一週間後に取りに来いとだけ言い、また奥に引っ込もうとした。いつも入見が時計をばらしている机の上はえらく整然と片付いていて、今日の作業はもう終わったとでも言うようだった。僕は好奇心から入見を呼び止め、奥で何をしているのか問うてみた。入見は僕をじ、と見てひとこと、
「剥製を作っている」
とだけ言い、奥の部屋に隠れた。
時計を取りに行くのは一週間後だったが、僕にはどうにも好奇心という邪魔があり、加えて仕事のない日がたびたびあるので、僕はそのたび入見の店に寄り、何をするでもなく少し話をした。僕がなにを喋っても、入見はなにも言わないことがよくあったが、しかし、作っている剥製とは、と僕が尋ねるや、入見はぼそぼそと何事か語り始め、僕は初めて彼の好奇心を掴むことばを見つけ得、うれしさに少しの達成感があった。入見の語ることには、彼は時計屋の前に博物館の仕事をしていただとか、子供の時代、つまるところ戦前、親に連れられて鹿を狩ったことが何回もあるのだとか(すなわち富裕層の出身であるのがうかがえた)、狩った動物をまた別の祖父にもらった知識で標本にして、それを家に飾るのが楽しみなのだと、それを元手に博物館に職を得たが祖父の危篤で店に入ったのだと、いうことだった。今作っているのができたらば、見せてもらう約束すら、交わすことができた。
そして時計を取りに行った日、入見は僕を奥の部屋に通した。彼がそのとき作り終えた剥製とは、三メートルにも及ぼうかという、それは大きな羆であった。
「標本だの剥製だの、死骸を加工して見世物にするのは同じだがね。剥製はね、目なんだ、目が生きていなくては、良い剥製にはならんのだ」
羆を見せてもらったとき、あるいは、世間話のたび、折々、入見はそう語ったが、あるときの彼の手元には、骨格に躍動を持たせた栗鼠が時を止めてあった。愛くるしい黒い瞳は濡れたような輝きを持ち、まったくその言葉を体現していた。入見の作る剥製は美しかった。時計に目を落とす傍らで彼の細い指は剥製となる手前の、あるいはなった後の、柔らかく硬い獣の毛皮をいとおしげに撫でていた。彼はあるときぽつりと言った、「人間で剥製を作りたいと思ったことが、一度だけあるんです」。その先を訊かなかったので彼は何も語らなかったが、その時彼の目線の先には、三段の棚がひとつあって、その真ん中の段に、古ぼけた小瓶がひとつだけあるのだ。ラベルも何も貼らない小瓶の中には、どの動物ともわからないが一対の眼球があって、その意味することはわからなかったが、入見の限りなく大切にしているものだというのは彼の目を見ればすぐにでもわかることであった。その話を聞いた数週間後、入院していた入見の祖父が亡くなった。
喪中だというのでしばらく店は休みであったが、一週間もするとまた営業は再開されていたので僕はすぐに出向いた。かわらずそこにいた入見に、お悔やみを、と型通りなことを言ったが、彼はそれほど気にもしないで、乏しい表情を眼鏡に隠していた。「祖父は安らかな死にかたをした」入見は呟くように、参列する人のたいへん少ない慎ましき葬式であったことを言った。墓は近くの寺にあるので、時間があれば行ってやってくれとも言った。彼は、誰かが持ち込んだ腕時計の中身を、歯車を見つめ、小さな針のような器具をそこできいきいと鳴らしていた。わずかな手の動きを追いながら、僕はふと彼に訊いた。
「…人を剥製に、と言っただろう、いつだったか」
「それがどうした」
「何をきっかけに、と思って」
「………」
入見は話してくれた。
母が死んだ折に、死に顔がたいへんに美しいと思った。父と二人の姉は嘆き悲しんだが、幼い僕はその死に顔に惹かれた。もとより母は美しい人であり、白く澄みきって半ば青白いとも思える肌を持ち、慎ましく均整のとれた目鼻立ちをしていて、伏し目にすると長い睫毛が頬に影を差し、その性格の優しいのが表情からも滲んでいるような女であった。母が死んだわけとは肺炎で、一度だけ見た彼女のレントゲン写真、肺のあたりには黒い影が渦のようにわだかまっていた。その頃には僕は栗鼠のような小動物の剥製作りには手を出していたので、寝台の上で目を閉じた母の胸元を見て、この胸を開けば真っ黒な肺臓があるのだろうかと夢想していた。
父に、この母をどうするのか訊くと、しきたりがあるので火葬するのだと言うので、僕はそのとき非常なもったいなさを感じてやまなかった。あの美しい母の死骸を、写真に収めることもせず燃やしてしまうなんてことは、それこそ、国宝級の芸術品を無惨に毀してしまうことと同義に思えた。しかし父に逆らうことは幼い僕には考えられもしないことであった、なので諦めるほかはないのであった。
通夜の前、僕はずっと母を剥製にするのを考えていた。あのつややかな肌を、美しい顔を、永久にそこに留め置ける手段としては、最適であるように思われた。僕が何よりも好きなのは母の瞳で、黒く濡れた大きな瞳が、優しさを湛えて彼女の子どもたち――すなわちは僕を映すとき、それは無上の美しさを誇るのである、僕はもし母を剥製にするならば、瞼を少し伏せた形にしようと思っていた。長い睫毛に覆われた形にするのがきれいなのだ。
剥製にした母は、一番に僕の部屋に飾るのだ。傷つかないように大きなガラスでケースを作って、そこにもたくさん装飾をして、母に見合うほどのそのなかに、美しい姿を留めた彼女を仕舞っておくのだ。母の好きだった飾り気のないワンピースを着せて、長い黒髪は綺麗に結い上げて、まるで人形のようであるが、そうして僕の部屋の真ん中に、祭壇に祀る神さながらに、飾っておく。そうできたらどれほどか良いだろう…せめてその目だけでもくれないものだろうか。きっと頼んでも無理であろうことはわかっていた。
考えている間に夜になるので、皆母がおさまった棺の周りに布団を敷いて寝るのであるが、僕はいつまでもいつまでも起きていた。棺についた小さな小窓をいつまでも開けておいて、僕は母の死に顔を眺めていた。
片手に小さな銀の匙を携えて。
葬式が滞りなく終わり、母が火葬場に送られるとき、僕だけが、僕ただ一人が、彼女の遺体に欠けているものを知っていた。彼女の瞳は燃やさせはしない、あれほど美しい宝石を僕は今までも、これからも、知ることはないであろうし、あれが僕以外の目に触れることもあってはならないと思った。家に帰ったら、はやくあれを保存するように処理しなくてはならない。あれは今、冷蔵庫の中で眠っている。
「動物の目は長持ちしないのさ。二日もすれば水分が抜けて萎んでしまうから」
入見はごく冷静に語る。
「…その母親の瞳っていうのはまだあるのか」
「ある。目にはつきこそすれ、誰にも触らせないがね」
入見はそこで初めて僕を見て、透き通った瞳を以ってしてシニカルに笑んだ。入見は中性的ながら顔立ちはやたらと均整なもので、一般から見ればそれは美人のたぐいである。僕は入見にふと、まだ人間で剥製を作りたいと思うか、と訊いたが、入見は考える素振りをしてこう言うのだ、「あの死んだ祖父というのは母方のほうだ。母は父親によく似て生まれてきたらしい」と。僕はわずかほども考えず、彼の言いたいことがどことなくわかって寒気がした。
「……それで」
「…数年前の白内障で、目がすっかり濁っていたのさ。あれでは初めから作りようがない」
そうして、何が可笑しいのか、くつくつと喉の奥で笑うのであるが、入見が話題にはよれどもそれなりによく笑う人間だというのを僕は初めて知った、それをなかなかに意外に思った…。