来し方行く末
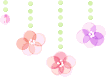
「いつかまた、あの木の下で」
誰かに何度も念を押された。会うたびにいつも、まるで縋るような眼差しで見つめられ、愛おしげに、名残惜しげに、すっぽりと腕の中へ抱き締められた。
きっと、見ず知らずの他人ではないはずだった。
にも関わらず、少女は何度でも、言われたことを忘れてしまう。
憶えていてあげよう、憶えていてあげなくちゃ──心優しい少女の意思に反して、それを言ったのがどういう顔をした、どういう背格好の人であったのかさえも、跡形なく記憶から消し去られてしまう。
「おまえの匂いが、やっぱり好きだ」
羞じらうように目を伏せながら、誰かがつぶやいた。けれど、自分の匂いというのは、自分自身にはわからないものだ。少女は、──これまで幾度も同じやり取りを重ねてきたことを忘れ、また、訊ねてみる。
「どんなにおいがするの? 花のにおい? お日さまのにおい? それとも」
「いい匂いだよ。……すごく、いい匂いがするんだ」
誰かが少女の柔らかな髪に鼻を寄せていた。シャンプーのにおいかな、と言って少女は屈託なく笑った。嬉しいような、くすぐったいような気分だった。誰かの頬が少女のまろい頬をかすめ、生温かい水気がしっとりと肌に感じられた。
「会いたかった。ずっと前から……待っていたんだ」
誰かが涙を流している。少女は、ほとんど無意識のうちに、さくりもよよともらい泣きをしている。そうすると、その誰かは驚いて涙を引っ込め、親指で不器用に少女の頬をぬぐった。
泣くな、ほら笑ってみろ。──そのほうが、おまえに似合うから。
そして飽きもせずに少女を見つめる。太陽に透けるような蜂蜜の瞳。何度見ても忘れてしまう、その温かい眼差しが、ほんのつかの間、少女の心に染み入る。
「いつかまた、あの木の下で」
あなたを見たことがあるような気がする。
いつだったか、あの木の下で──。
19.04.17