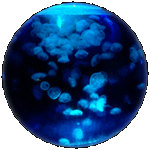 | |
| クラゲの骨 | |
昨日、海水浴に行ってきたのだという彼女は、うなじのあたりをしきりに気にしていた。
「海でクラゲに刺されちゃったみたいなの。なんともないけど、たまにピリッてするんだよね」
蒸し暑いクラブ棟に冷房装置はない。換気のためにと一日中窓を開けてはいるが、心地よい風はなかなか吹いてはくれない。ただ座っているだけで汗がにじんでくる。りんねは地区の夏祭り会場を通りかかった時にただでもらったうちわを、桜はバッグに入っていた扇子を、終始手放すことができずにいる。
「クラゲには毒があるそうだが、大丈夫か?」
「大丈夫だよ。たいしたことないから」
みやげ物のガラスの風鈴が、窓辺でちりん──とかん高い音を鳴らした。
今日は桜が家から冷やし中華の差し入れを持ってきてくれた。猛暑と空腹とで干上がりかけていたりんねには、まさに天の恵みである。さらに彼にとっては運の良いことに、ちょうど六文があの世へ出かけていて留守だった。この暑い中、いつまでも食べずに置いておいては食べ物が傷んでしまうからと、もっともらしい理由をつけて二人分の冷やし中華にあずかることができたのだ。
「海のクラゲは刺すから怖いね。中華クラゲは、あんなにおいしいのに」
「中華クラゲなら、確かにうまいな」
「きゅうりと和えるとおいしいんだよね。ちょっと酸っぱくて。うちのパパがよく、おつまみに食べてる」
あまり意味のない会話をしていても、彼女と過ごす時間はあっという間だ。
今日ももう、いつの間にか、日が暮れかけている。
氷がたくさん入った麦茶を、魔法瓶から紙コップに注ぐ。まだきんきんに冷えていて、とてものど越しがいい。クラブ棟の水道の水がぬるいと知っての配慮なのだろう。
「クラゲに刺されたところ、まだ気になるのか?」
桜はまだうなじを押さえている。
「ちょっとだけね。六道くん、見てもらってもいい?」
「ああ」
近い距離がさらに縮まる。彼女が長い髪を片側に寄せると、白いうなじにぽつんと残る小さな赤い痕があらわになった。
「どう?やっぱり、ちょっと腫れちゃってるかな」
思わずうなじに見とれてしまった。
彼女はどんなシャンプーを使っているのだろう。髪から香る甘い花のような匂いが、彼の鼻孔をくすぐる。
後ろからそっと抱き締めると、彼女の身体はぬいぐるみのように柔らかかった。
「暑くない?六道くん」
「──暑くない」
女子の甘さも柔らかさも、すべて桜から教わった。
こうして触れられるようになるまで、どれほどの時間を要したことか。
りんねはほてる頬を冷ますため、再びうちわを手に取る。
「やはり、少しばかり暑いな」
「でも、離さないんだ?」
桜が笑っている。早く帰りたいのかと早とちりしたりんねは、あせってしまう。
「あと三分だけ、このままでいてもいいか?」
「ふうん。三分だけでいいんだ?」
「えっ……。では、五分?いや、欲を言えばもう十分──」
結局りんねには勝ち目のないかけひきは、六文が帰ってくるまで延々と続いた。
桜が帰るのを見送るなり、黒猫は恨みがましく主につめ寄ってくる。
「ぼくが死神道具の安売りセールでもみくちゃになっている間に、りんね様は二人分の冷やし中華食べて、冷たい麦茶飲んで、桜さまといちゃついていらしたんですね?」
「す、すまん、六文」
冷やし中華の恨みは海よりも深いらしい。
「今度、中華クラゲ食わしてやるから」
「……どうして中華クラゲなんです?」
クラブ棟の下に降りた桜が笑顔で手を振ってくる。
振り返すりんねの頬は、今にもとけ落ちそうになっている。
「りんね様。『クラゲの骨』って言葉、知ってます?」
「うん?」
「クラゲに骨はないじゃないですか。だから、ありえない出来事って意味らしいんですけど」
何度も振り返っては手を振る桜に、りんねは気もそぞろだ。
欄干にちょこんと腰かけて、六文は苦笑した。
「きっと、桜さまのいない毎日なんて、りんね様にとっては『クラゲの骨』なんでしょうね」
back
2016.09.05
×