conversation piece
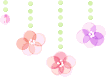
「マルクル、あの棚の三番目の引き出しに、ジャカランダの花の塩漬けを詰めた瓶があるからとってきてくれないか?」
「わかりました、ハウルさん」
マルクルが椅子から元気よくとびおりると、床がしたたかに揺れた。驚いたハウルは「おっと危ない」と倒しかけたフラスコを掴み、ほっと胸を撫で下ろす。中にはいっているラベンダーの色をした液体は、彼の瞬発力のおかげでどうやら一滴たりともこぼさずにすんだようだ。
「新しい魔法薬は衝撃を与えるとどんな結果をもたらすかわからない。もっと慎重に扱わなくちゃいけないよ、マルクル」
「ごめんなさい。今度からは気をつけます」
マルクルが申し訳なさそうに肩を竦める。ハウルはなにやら泡を吹いているビーカーの中身を攪拌しながら、ちらりと弟子の顔を見て、
「わかればいいんだよ」
と優しく笑った。
「あの二人、いったいなんの薬を作ってるのかしら」
ソフィーは暖炉でちらつくカルシファーのそばで編み物をしながら、薬作りに没頭する恋人の横顔をなんとはなしに眺めていた。テーブルの上には色とりどりの、様々な形をした小瓶が並べられている。遠い国に行かなければ手に入らないめずらしい材料やらハウル特製の調合薬やらがはいっているらしいが、魔法音痴のソフィーにはどんなものか見当もつかない。
今朝おろしたての真新しい薪に抱き着きながら、カルシファーがやれやれという顔をした。
「なんの薬かはおいらにもわからないね。まあ、とにかく今回は、大爆発なんかを起こさないことを願うよ。こんな空中で爆発なんかしてみろ、空飛ぶ城が王都に真っ逆さまだからな!」
「──薬作りってそんなにひどいことになるの?」
火の悪魔は凍えることなどないだろうに、ぶるりと身震いする。
「ハウルときたら、後先考えずにしっちゃかめっちゃかにするもんだから大変なんだぜ?おいら、暖炉ごと吹き飛ばされそうになったこともあるんだからな」
不安になったソフィーは眉をハの字にさげてしまう。
「ちょっとハウル、お願いだから、あたしの掃除の手間を増やさないでちょうだいよ?」
「大丈夫だよ、ソフィー。カルシファーは大げさなことを言ってるようだけど、僕は大事な恋人を大爆発に巻き込むようなへまはしないさ」
ハウルはフラスコを振りながらにっこりと笑いかけてきた。その注ぎ口からはぶくぶくと泡が吹き出していて、気が気ではないカルシファーが「気をつけろよ!」と金切り声を上げた。
「ハウルさん、ジャカランダの花の塩漬けってこれですか?」
「そうそう。それをピンセットでふたつ、このなかに入れて」
マルクルがさんざん戸棚を引っかき回したあとを見て、ソフィーはそっと溜息をつく。彼女が来てから少しは改善されたとはいえ、この魔法使いの師弟は、部屋をきたなくすることにかけては一人前と言えた。
「そういえばソフィー、僕が初めて作った魔法薬はなんだと思う?」
さいわい、花の塩漬けを入れると薬の泡がおさまった。カルシファーが悪魔らしからぬ安らかな表情になるのを横目に、ソフィーは魔法使いの恋人の問いかけに答えた。
「さあ、なにかしら。女の子にもてる薬とか?」
「惚れ薬のこと?」
「それくらい、魔法使いハウルにはお手の物でしょう?」
「作ったことは作ったけど、誰かに試したことはないよ。──ソフィー、もしかして怒ってる?」
ソフィーは編み目に苦戦して難しい顔をしているだけで、べつに腹を立てているわけではないのだった。
「過去は過去だもの。あなたがどれだけ多くの女の子の心臓をとって食べたかなんて、今のあたしには関わりのないことだわ」
星の子と契約を結ぶために心臓を失ったハウルは、他人の心を得ることで、自分が失ったものを埋め合わせようとしたのだろう。そのことを、ハウルの過去をかいま見たソフィーは誰よりも理解している。
「でも、今はあたしの心臓だけを食べてね?ほかの子の心を奪ったりしたら、いやよ」
パチパチ、と火の悪魔がはぜている。ソフィーはそのかたわらで黙々と編み針を動かしている。
ハウルはマルクルにフラスコをあずけると、暖炉のそばまで近寄っていった。椅子の背もたれにかけられていたショールでソフィーの肩を包み、そのまま後ろから腕を回して抱きしめる。
「ねえソフィー。僕が初めて作った薬は、惚れ薬なんかじゃないよ」
「あら。じゃあ、どんな薬?」
ハウルの顎が彼女の頭のてっぺんに載っていた。二人で、カルシファーが小ぶりの薪をもぐもぐ食べている様子をながめた。
「あれはね、髪の色を変える薬だったんだ」
「──金髪になる薬?」
ソフィーが編み物の手をとめると、ハウルがその左手をとった。細い人差し指に光る守りの指輪は、ソフィーを過去へ導く役目を終えると一度は壊れてしまったものの、ハウルの魔法でまた元通りになった。
「君のきれいなプラチナブロンドに釣り合いたくて、いてもたってもいられなくなって、僕も薬で金髪にしてみたのさ」
ハウルはソフィーの柔らかな髪を指にからめてもてあそんでいる。ソフィーもくすくす笑いながら、首を少し後ろにひねって彼のつややかな黒髪に触れた。
「ハウルの髪、あたしは黒のままのほうが好きよ。金だと明るすぎるけど、黒なら銀とうまくとけあうじゃない?あたしが星なら、ハウルはきっと、星を抱く夜空ね」
みんなが暖炉に集まっているので人恋しくなったのだろう。マルクルも作りかけの魔法薬をほうり出して、ソフィーの膝に甘えてきた。
「マルクル、薬から目を離すなと言ったじゃないか」
「だったらハウルさんが見ていてくださいよ」
「さみしがりやさんだなあ、僕の弟子は」
「お師匠様だって、人のことは言えませんよね?」
マルクルの小さな鼻の頭についた煤をぬぐってやりながら、ソフィーはふたりのさみしがりやを声音柔らかになだめた。
「まだおばあちゃんが寝ているわ。起きるまで、静かにしていてあげましょうね」
「だったらソフィー、僕達もちょっとだけ昼寝しようか?薬はマルクルにまかせて──」
けれど魔法使いは弟子のさみしそうな目を見ると、さすがに心を改めざるを得なかった。
「──マルクルも一緒に、三人で休もう。きっとソフィーが子守唄を歌ってくれるよ」
作りかけの薬に蓋をすると、ハウルはソフィーの腰に手を添えて寝室へ連れていこうとした。マルクルもソフィーと手をつないでついていくが、
「待ってくれよう。おいらだけ置いていくのか?」
三人は振り返った。暖炉で哀れっぽい声をあげているのは、すっかり人心地のついてしまった火の悪魔だ。燃え方までしょぼくれて元気をなくしている。
「ひとりにしないでくれよう」
やれやれ、とハウルが首を振った。キッチンにフライパンを取りに行き、その上に乗せて連れていってやることにする。
「悪魔のくせに人恋しいなんて、妙な話だよ」
「悪魔じゃないわ。カルシファーだって、あたし達の大事な家族じゃない?」
ソフィーは腰をかがめ、フライパンにちょこんと乗せられたカルシファーにキスをした。嬉し恥ずかし、火の悪魔は真っ赤に燃え上がり、魔法使いの師弟は口を揃えて「ずるい!」と叫ぶのだった。