head over heels
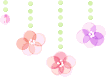
「そなたのような男を、是非とも我が娘婿に迎えたいものよのう」
千尋は危うく運んでいた膳を引っくり返してしまうところだった。転びそうになったのをなんとか踏みとどまったはいいが、まずいことにお吸い物が椀の淵から少しこぼれてしまった。姉貴分の咎めるような視線を逃れて、おそるおそる発言の主を盗み見る。
さる大河の主だというその客人は、最高級のもてなしを受けていた。あてがわれた湯殿も客間も食膳も、すべてがこのうえなく贅を凝らしたものだった。
白拍子の手酌を受ける客人の傍らには、いつもの簡素な水干ではなく、上質な衣を纏ったハクの姿がある。帳簿係の彼が客をもてなすことは滅多にない。しかし今回ばかりは彼も客人と眷族であることから、恰好の話し相手として呼ばれたのだった。
ほんの少し話をしただけで、客人はハクをいたく気に入ったようだ。秀麗な顔をほころばせ、まるで実の息子に接するように親しげに肩などを叩いたりしていた。
「我が娘はうら若き乙女ぞ。ここ百年ばかり、この父が婿となる相手を方々捜し回ってはおるが、一向に見つからなんだ。近頃の若造ときたらどうも調子者ばかりでいかん。可愛い娘を任せるにはどうにも心許ないのだ。されど、よもやかような場所で相応しい丈夫を見つけようとはな。どうだ青年、我が姫を娶る気にはならぬか?」
ハクはさりげなく客人との距離をとり、静かに頭を下げた。
「私のような未熟者には勿体なきお言葉。姫君におかれましては、父君がさぞ慈しみ大事にされていることでしょう。そのような姫君でしたら、何も私のごとき者でなくともよろしいはず。早まったご決断はなさらず、もうしばしお待ち下さい。姫君に添うに相応しい青年が、きっと現れるはずです」
客人は眉を持ち上げた。気分を害されたというよりは、単純に理由が知りたいという表情だ。
「私がかの大河を統べる主であることは、知っておろう」
「存じております」
「そなたは己が川を再興させたいと申した。我が一族と姻戚関係を結べば、そなたの悲願も遂げられようぞ」
「お気遣い痛み入ります。しかし貴殿の意に添うことはできません。──何故なら私には、とうに心に決めた女子がいるのです」
ハクの視線が、リンの後ろにこそこそと隠れようとする千尋を捉えた。リンが嫌そうな顔をするが、千尋はお構いなしだ。客人もまたハクの視線を追い、驚いたように目を丸めた。
「我が目が節穴でなくば、あれは人間の小娘ではないか?」
「その通りにございます」
「そなた、よもや人間を嫁にもらう心積りではあるまいな?」
「いずれはそのようにしたいと望んでおります」
白拍子達の楽の音も歌声も、踊り子の舞いも止み、客間は水を打ったような静けさだった。誰も彼もが、口をぽかんと開けて千尋を見ていた。帳簿係と小湯女の恋の噂はとうに油屋中に広まっていたものの、当事者であるハクがみずから彼女との仲を公言するのはこれが初めてのことだった。皆我が目を疑っているのだろう。たまらなくなった千尋はその場から逃げ出そうとする。が、それを察したリンに首根っこをつかまれてしまった。
「では若造。そなたは我が娘よりも、あの人間の小娘が優れていると申すか?」
今度こそ柳眉を逆立てる客人に、ハクは表情ひとつ変えずに返した。
「決して貴殿と姫君を軽んじてはおりません。ただ、私の花嫁は何があろうとただ一人であるということを、ご理解頂きたいのです。あの娘と私は浅からぬ縁によって結ばれています。これまでも、そしてこれからも、この目はあの娘だけを見ている。他の女子が映ることは決してありません」
二柱の龍神はしばらくの間、見つめ合った。睨むような客人と、その視線を静かに受け止めるハク。周囲は固唾を呑んでその無言のやりとりを見守った。そしてついに、客人が長い溜息をついた。
「まこと惜しいことよ。ようやっと、孫の顔が見られると思ったのだが……」
ようやくハクが酒宴から解放されたのは、遠くの街に朝日が見え始めた頃のことだった。襖を開けると、待ちくたびれた千尋が蹲ってうつらうつらとうたた寝しているのが目に入った。
起こさないようにそっと、ハクは彼女の軽い身体を抱き上げる。が、首がかくりと後ろに反ったかと思うと、次の瞬間にはぱっちりと閉じていたはずの目が開いていた。
「こんなに長い間、待っていてくれたんだね。寒かっただろうに」
申し訳なさげなハクから、千尋は決まり悪そうに目を背ける。
「心配だったの。わたしのせいで、何か大変なことになってるんじゃないかって」
「何故千尋のせいだと?そなたは何一つ悪いことをしていないのに」
目を細めて笑いながら、ハクは暗い廊下を歩き出した。急なことだったので、その首に咄嗟に腕を回してしまう千尋。慌てて離そうとするが、そのままでいなさいと目線で制された。
客間は襖がぴっちりと閉じられ、簾のおりた吹き抜けの湯殿はしんと静まり返っていた。ほの暗い階段をゆっくりと下りていきながら、ハクは囁くように告げる。
「心配はいらないよ。あの方は、私の意を汲み取って下さったから」
「……そう。良かった」
千尋が安堵の溜息をつくと、一瞬ハクの目がきらりと輝いた。
「私が根負けして姫君の婿になってしまうかもしれないと、心配した?」
「そ、そんなことないよ」
「では、何故あんなところで待っていてくれたの?」
「こんなに長い間お酒を飲んでたら、酔っ払っちゃうんじゃないかと心配で──」
ふふ、と薄い唇がほころんだ。
「私は龍だ。どれほど飲んでも酒には飲まれない。そなたもとうに知っているはずだろう?」
いつもこうだ。ごまかそうとしてもことごとく失敗する。どうやら彼に見破れない嘘はないらしい。悔しくて、千尋はハクの肩口に顔をうずめた。みっともない顔を見られたくなかった。
「わたしって、呆れちゃうくらいハクに首ったけよね?」
「いや、私が千尋に夢中なんだよ。愚かな怖い物知らずになってしまうほどにね」
「違うよ。見て?今だってこうやって、わたしがハクにしがみついてる」
「いいや。私がそなたを抱いて離さないんだよ」
夢中になっているのは、さてどっち?
ハクが千尋を女部屋に送り届けるまで、他愛のない押し問答は延々と続いた。