flowergarden
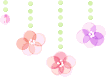
からりと晴れた青空の下、色鮮やかな花畑の細道に千尋の姿はあった。背の高さをゆうに超えるほど生い茂った躑躅や夾竹桃や空木が辺りに甘い香りをふりまいている。豚舎の掃除当番を終えて油屋に戻る千尋の髪や水干にも、花の匂いがしっとりと染み込んだ。
花道を抜けたところにちょうどハクがいた。庭師をともなって、剪定の指示を出している。黙っていれば花や木が伸び放題になるので、見栄えをよくするために時々こうして整えてもらうのだという。
「こんにちは。ハク様、庭師さん」
外部から来た職人の手前、千尋は下働きの身分をわきまえて上司であるハクにも丁寧におじぎした。気がついたハクが表情をほころばせる。
「ご苦労だったね、千。今日は早番?」
「いえ、豚小屋のお掃除当番です。今戻るところでした。庭師さん、花はどうですか?」
口元を布で覆った色白の庭師は目元を和らげ人の良さそうな笑みを浮かべた。鶴の化身らしく、額のところが赤く、背がひょろりと高い。
「いつも花の手入れをしてくださっているそうですね。お陰様で、皆とても元気ですよ」
「良かった。色々な花がまざってるから、どれか枯らしちゃったらどうしようって心配してたんです」
時の流れからはかけ離れているせいか、この油屋では四季にかかわりなく様々な花が咲いている。桜の隣に萩、紫陽花の傍らに椿が咲いているのもごく自然な光景だ。ここを訪れる八百万の神々はこういった花々をことに愛でる。手入れを間違えて駄目にしてしまえば、癒やしを求めてやってくる神々ががっかりするだろう。だからお客様思いの千尋は花の世話にはとくに気を使っているのだ。
手入れに不備がなかったことに、ほっと胸をなで下ろす。
「では、私はそろそろ作業に取りかかりますので、これにて失礼します」
言うなり庭師は軽く会釈し、花畑の細道にひょっこりと紛れていく。
千尋がいつまでも手を振っていると、待ちかねたようにハクが腕を伸ばし、後ろから彼女を抱き締めた。驚いた千尋の手から空の桶がすとんと落ちるが、気にもとめない。
「千尋。そなたは、今日も花の香りがするね」
ふさふさとした千尋の髪に鼻を近づけて、彼は心地よさげに目を閉じる。
「いい香りだ。とても落ち着く」
千尋は頬のほてりを抑えつつも、黙ってされるがままになっていた。人の目がなくなった途端にこうして甘えてくるのだから、困った恋人である。本人は誰にもばれていないつもりかもしれないが、きっと油屋の中でこの帳簿役の本性を知らないものはいないだろう。色恋沙汰に関する噂が広がるのは本当に早い。近頃風呂釜掃除をしていると、大湯女のおねえさま方ににやにやと意味ありげな含み笑いを向けられるのも、番台役がやけに親切になって薬湯の札をたくさんくれるようになったのも、きっとそのせいだ。
ハクにとっても、公私混同は避けるべき、とは所詮建前でしかないらしい。周りに人気がないと思えば、仕事中であろうが平気で近付いてくる。不意打ちのように迫られて、心臓がもたないのは千尋のほうなのだ。
「──あの、ハク様?」
「どうしたの、千尋?」
「お仕事中は『千』ですよね?」
「そうだね。でも今は、周りに誰もいないだろう?」
口ではかなわない。千尋は苦笑する。
「ハクとわたしのこと、すっかり噂になっちゃってるよ。それでいいの?」
「私がそなたの恋人だという噂?事実なのだから、何も問題はないよ。言わせておけばいい」
「でも、噂に色々尾ひれがついてるみたいだよ」
言うなり千尋は赤面してしまう。おや、とハクが首を傾げた。
「どんな噂を聞かされたの?」
「い、言えない!口が裂けたって言わないんだから……」
「おや。口が裂けてしまったら、これは食べられないね」
千尋の目が輝いた。水干の懐からハクが取り出して目の前に見せたものは、薄紅の懐紙に包まれた練りきりだった。桃と紫陽花の形をしたものが二つ、ちょこんと乗っかっている。
「あの庭師に貰ったんだ。──さ、千尋?どんな噂を聞いたの?」
見かけによらずこの龍はとんだ策士だ。目の前の可愛らしい菓子につられて、言うまいと思っていたにもかかわらず、つい千尋の口が滑ってしまう。
「──わたし達は、実はひそかに結婚して、夫婦になったんだって。でも誰にも知られないように、秘密にしてるに違いないって」
恥ずかしくなった千尋は目の前の練りきりに手を伸ばし、食べることに専念した。餡のほどよい甘さが疲れた身体には嬉しい。
「そ、そんな訳ないのにね!もう、おねえさま方ったら……」
背後でハクがふふ、と笑った。どこか嬉しそうな、楽しげな笑い方。
「そんな訳ない、か。そうだね、今のところは」
「──今のところは?」
その物言いが気になり、千尋は振り返る。ハクはいつものように、ただ静かに笑っているだけ。
彼が言葉にして伝えてくれることはあまり多くはない。心が通じ合っているから口に出すことはないという。言葉が言霊として独り歩きしてしまうこの世界では、心の底から思っていることを安易に口にすることは好ましくはないのだ。
「千尋。私とて色々と考えているんだよ?そなたとのことを」
ハクの手が垣根に伸び、桃色に色づいた躑躅の花を手折る。それを彼は千尋のポニーテールの結び目にそっと挿した。肩をつかんで彼の方へ向き直らせ、
「節会の踊り子のようだね」
と言って笑い、今度は正面から優しく、繊細な菓子を包み込むように彼女を抱き締めた。
ちぎれ雲がゆったりと青空を流れていく。天を衝くかというほど伸びた煙突からは、まだ煙は昇らない。不夜城であるこの建物も、昼間は一転して静謐に抱かれる。皆が起き始めるのはまだ先のこと。
はさみを動かす庭師のゆるやかな歌声が、花畑の中からかすかに聞こえていた。