1月も終わろうとしているある日。
「うーっ…やっぱりあたしも行きたいよぉ…」
「駄目だよ。うさぎちゃん。あんまり大勢で行ったら亜美ちゃんがゆっくり休めないし、気を遣っちゃうだろ?」
「そうだぞ。それ以前におだんごと愛野は補習だろ?」
「星野もね」
「うっ…」
「こーなったら三人寄ればもんじゃ焼きよ!あたしとうさぎちゃんと星野君の三人で、古典なんてちょちょいのちょいよ!」
「それを言うなら“文殊の知恵”だよ。ちょちょいのちょいって出来なかったから補習なんだよ美奈…」
いつものにぎやかなやりとりを繰り広げるメンバーに、大気は静かに声をかける。
「皆さん。では、私はそろそろ行きますね。星野、月野さん、愛野さん補習頑張ってください」
普段なら大気もみんなの会話に交ざるところだが、今日はそうもいかない。
「大気さん、亜美ちゃんのお見舞いお願いします」
まことがペコリと頭を下げる。
「「あたしからもおねがいします!」」
うさぎと美奈子が見事にハモる。
「はい。伝えておきます。それでは」
「あぁ、じゃあな大気」
「風邪移るような事しちゃダメだよ?」
夜天の言葉に大気はくすりと微笑み教室をあとにする。
大気は職員室に寄り、プリントを担任から預かると素早く学校を出て亜美のマンションへ向かう。
今朝いつものように、亜美にメールをしても返事がなく、学校に行っても彼女が現れる事はなかった。
もしや何かあったのだろうか?と、不安に思っていたら朝のホームルームが始まり、そこで担任から亜美の欠席を知らされた。
今日は、幸いな事に仕事はなかったので、帰りは彼女のお見舞いに行こうと決めた。
それを見越した担任に行く前に職員室に寄るように言われた。
昨日は一日仕事で、終わったのも遅かった為、連絡出来なかった。
昨日から体調が悪かったのだろうか?
熱は?
病院には行っただろうか?
食事は摂れているのか?
そんな風に色々と考えていると、いつの間にか亜美のマンションの前に着いた。
――亜美
大気は部屋番号を押しチャイムを鳴らそうとしたところで、ふと気付く。
「何か、喉の通りが良さそうなものでも買ってからの方がいいですよね…」
一度来た道を戻り、フルーツゼリーを購入して再び亜美のマンションに戻る。
チャイムを押すと、しばらくしてから『はい』と、返事が聞こえる。
大気が初めて聞く、女性の声だ。
「こんにちは。水野さんのお見舞いに来ました」
『――どうぞ』
ロックを解除する音が聞こえる。
「ありがとうございます」
大気は礼を言い、開いたドアをくぐり、エレベーターに向かう。
(今の人が、亜美の――“母親”)
(あぁ、“彼”が、亜美の――)
いつも元気な娘の友人である少女達が見舞いに来るのだろうと、勝手に思っていた。
ところが、聞こえたのは落ち着いた青年の声で一瞬の驚きの後、合点がいった。
(なんだか緊張するわね)
亜美は母に友達の事は話をするが、恋人の事はあまり話してはいなかった。
母が聞いても「秘密」と、言って頑なに口を開かなかった。
母が知っているのは『同じクラスの男子』だと言う事だけだった。
(亜美の“彼”ね。どんな子かしら?)
考えていると、チャイムが聞こえる。
カチャリと鍵を開け「どうぞ」と、声をかけると「失礼します」と先程のインターホン越しに聞こえた声がして、静かにドアが開く。
入ってきた長身の少年を見た亜美の母は、驚きで目を丸くする。
「貴方、は……」
「こんにちは。初めまして。私は亜美さんのクラスメイトの“大気光”と言います」
「…そう。初めまして。私は亜美の母の“頼子-ヨリコ-”です。よろしくね。大気君」
「はい。よろしくお願いします。……あの、亜美さんの容態は?」
「風邪というほどではないんだけれど疲れが出たのか、熱が出てしまってね。
でも今は熱も下がって眠っているわ。そうね。立ち話もなんだし上がって下さい」
「あの、お邪魔になりませんか?」
大気は亜美の様子を自分の眼で確かめたかったが、彼女が眠っているのならプリントとゼリーを渡して帰ることを考える。
「あら?わざわざ亜美の様子を看に来てくれたんでしょう?」
「はい」
「じゃあ遠慮せずに上がって色々お話聞かせてもらえるかしら?」
この言葉に大気は目をぱちくりさせる。
「え?」
その年相応の少年らしい大気の反応に頼子はくすりと笑う。
「ふふっ。さ、どうぞ?」
「――失礼します」
用意されたスリッパを履き、大気は頼子の後ろをついていく。
リビングの椅子に座って待っていると、頼子が紅茶を淹れてくれる。
「どうぞ」
「ありがとうございます。いただきます」
二人、向かい合わせに座り紅茶を飲む。
当たり障りのない話を少ししたところで、頼子は聞く。
「ねぇ、大気君」
「はい」
「亜美とは夏休みから付き合ってるのよね?」
「はい」
「そう」
大気はクラスメイトだと名乗ったものの、やはりと言うべきか、頼子には気付かれていた。
「驚いたわ。まさか亜美の彼が“スリーライツの大気光君”だなんて思ってなかったもの」
この言葉に大気は、小さく息をのむ。
「あの」
「ん?」
「私は“スリーライツの大気光”としてではなく、“大気光”という一人の人間として亜美さんとお付き合いさせていただいてます」
頼子の瞳をまっすぐに見つめて大気は言う。
「――そう。亜美の事を本気で想ってくれてるのね」
頼子は大気の言葉に込められた真意を汲み取りそう言う。
「はい。突然すみません」
「いえ、いいのよ。こちらこそ気分を悪くさせたわね。ごめんなさい。そんなつもりはなかったの」
頼子はそう言って、申し訳なさそうに謝る。
(大気君の
まっすぐな視線。
まっすぐな言葉。
まっすぐな気持ち。
亜美への想い。)
頼子は大気と話をして、すぐにわかった。
大気が亜美を“大切”に思ってくれている事を。
心から“愛しい”と、思ってくれている事を。
彼の言葉に偽りは感じられない。
(いい人に巡り逢ったのね、亜美)
薬の副作用でぐっすり眠る娘を想い微笑む。
「ねぇ、大気君?」
「はい」
「亜美は、貴方に――」
「はい」
「我儘を言ってるかしら?」
頼子の言葉に大気は少し驚き、彼女を見つめる。
その瞳は真剣そのものだった。
「――いえ。亜美さんとお付き合いして半年程が経ちますが、私は彼女の“我儘”らしい“我儘”を聞いた事はありません」
「そう…」
一言呟き、瞳を伏せる頼子の顔に浮かぶのは───寂しさ。
大気はなんと言っていいのか分からず、黙りこんでしまう。
「ねぇ、大気君」
「はい」
「まだお時間あるかしら?」
「はい。大丈夫です。今日は空いているので」
「そう。じゃあ少し昔話に付き合ってもらってもいいかしら?」
「はい」
「亜美はね――」
小さい時から、聞き分けが良くて、手のかからない子だった。
私も別れた主人も、亜美が我儘を言わないのをいいことに、仕事を優先していて、遊びに連れて行ってあげたのなんて、本当に数える程しかなかった。
それどころか、家族で遊びに行こうと約束していた日に仕事が入ってしまう事も珍しくなくてね……
そんな時も、亜美は泣き言ひとつ言わなかったわ。
「ごめんなさい」って私達が謝ると、あの子はいつも笑ってた。
「どうしてあやまるの?だってパパもママもおしごとだもん。
だからいいの。あみはちゃんとひとりでおるすばんしてるよ。
だいじょうぶ。だから、いってらっしゃい。おしごとがんばってね」
そう言って、玄関の所で小さな手をふって、いつも私達を見送ってくれてたの。
まだ小学校にも上がらない子を一人残して…。
私もあの人も亜美に、自分達の娘の優しさに甘えてたの。
本来なら私達が亜美を甘えさせてあげないといけなかったのに…
冬のある日、亜美が体調を崩したの。風邪をひいていて、それでも私は亜美を置いて仕事に行ったの。
別れた主人も北海道の方に行っていて、まだ5歳の亜美を一人残して家を出たの。
朝から、少し食事もして薬も飲んで熱も下がっていたからって…
「お昼には戻るからね」って言って…
「ママがおしごとからかえってくるまで、ちゃんとねてるね」って亜美の言葉に甘えて。
結局、仕事が長引いてしまって夕方近くになって、急いで帰ってきた私が目にしたのは――
そこまで話した頼子が言葉に詰まる。
大気が彼女の表情を見ると、ここで口を挟んではいけない空気があり、黙って次の言葉を待つ。
「私が目にしたのは、キッチンで倒れている亜美だった」
「え?」
「私は急いで亜美を抱きかかえて体の熱さに驚いたわ。熱を測ったら40度近い高熱があって……、急いで病院に連れて行こうとした時に熱で意識が朦朧とした亜美がね――」
『マ...マ?』
ぼんやりと眼を開けた亜美が母を呼んだ。
『亜美。ごめんなさい。すぐに病院に連れて行ってあげるからね』
『びょういん?おしごと?』
小さな娘を抱きしめていた母は、亜美の言葉に息をのんだ。
『っ…違うわ。お仕事じゃないのよ。亜美が病院に行くのよ』
『あみが?』
『そうよ。亜美が行くのよ』
あやすように背中を撫でながら、亜美に告げた。
『ママも...いっしょ?』
『えぇ。ママも一緒に行くわ』
『そっかぁ』
亜美は嬉しそうにえへへと笑うと、甘えるように小さな手でギュッと母の服にしがみついた。
『亜美?』
『ママと...いっしょに...おでかけできるから...うれしい……』
「そう言って、気を失ったの。病院で目が覚めた時、亜美はその事を覚えてなかったわ」
「……」
「そんな極限状態になるまで、あの子が本音を言えないほどに、私達は自分の事ばかりだった。
親失格だってすごく悔やんだの。その時、私達はすごく後悔して反省したわ。
でも結局は離婚してしまって、あの子に悲しい思いをさせてしまったけれど……ね」
「……」
「ふふっ、突然こんな話をしてしまってごめんなさいね」
「いえ…」
大気は相槌を打つことしかできない。
「まぁ、そんな経緯もあってね、亜美はあまり我儘を言わないの。
だから、せめて恋人である大気君にくらい我儘を言ってくれてたらいいなっていう、私の身勝手な“願い”ね」
そう言って頼子は紅茶のおかわりを淹れる為に、ティーポットを持つと椅子から立ち上がり、キッチンに消える。
“我儘”か…
確かに亜美は、我儘を言わない。
何度か『我儘を言ってもいいんですよ』と言った事はある。
その度に彼女は少し困ったような笑顔を見せていた。
「あたしは、今のままで充分なんです」
そう言って笑っていた。
さっき亜美の母が――頼子さんが語った事を聞いて納得した。
亜美は“我儘を言ってはいけない”と思っている。
寂しいと言って、両親を困らせたくなかったのだろう。
それがいつしか無意識に癖になっていったに違いない。
きっと一人の部屋で寂しさを抱えていたのだろう。
まったく――頭はいいのにそう言うところは誰よりも不器用で、愛しさがこみ上げる。
「お待たせしてごめんなさいね」
考えていると頼子さんがティーポットを持って戻ってきた。
亜美の知性的な雰囲気は母譲りなんだろうと思いながらも、この人もきっと亜美に対しては不器用なんだろうと思う。
それぞれのカップにお茶のお代わりを注いだ頼子さんはくすっと笑うと
「私ばかり昔話をしてしまったわね。大気君は亜美のどこが好きなのかしら?」
と、聞いてきた。
「え?」
突然の会話の方向転換に驚いて間抜けな声が出てしまった。
目の前に座る頼子さんはくすくすと楽しげに笑っている。
「あら、亜美と真面目なお付き合いしてるのよね?」
「もちろんです」
「亜美ったら貴方の事を聞いても“内緒”って言って、なにも教えてくれないのよ?だったら大気君本人に聞くのが一番だもの」
「はぁ…」
「それで?亜美のどこが好きなの?」
どこか楽しそうに頼子さんは聞く。
改めてどこが好きかと聞かれると――困る。
むしろ、好きじゃないところなんてない。
私は亜美のすべてが愛しくてたまらない。
だからと言って、彼女の親に『全部好きです』と言ったら、嘘っぽいと思われかねない。
頼子さんは“亜美の恋人”である“大気光”を信頼して、初対面である私に亜美の事を真剣にあそこまで話してくれた以上、こちらも上辺だけで話すなんて失礼なことはしたくない。
誠意には誠意をもって返したいとおもう。
さて、どう話をすればいいだろう――
「そう…ですね。私が亜美さんに惹かれるようになったきっかけは――」
ワタル彗星を通して、亜美とはじめてきちんと会話を交わし、意見が対立したことをはじめとして。
その時だけでなく、他の局面においても亜美の言葉に動かされたこと。
いつの間にか気になる存在になっていたこと。
――戦士としての自分達の関係を隠しながら、できるだけ当たり障りがないように頼子さんに話した。
彼女は口を挟まずに、私の話を真剣に聞いていた。
「そう――だったの」
私の話を聞いた頼子さんは、ゆっくりと頷いた。
「大気君」
「はい」
「亜美の事を、とても大切に想ってくれているのね」
そう言って微笑んだ頼子さんの瞳は亜美に似て優しい色をしていた。
「はい。亜美は――あ、っと、失礼しました。亜美さんは」
「ふふっ。わざわざ言い直さなくていいわ」
「すみません」
「大気君」
「はい」
「ありがとう」
「え?」
「亜美を、愛してくれてありがとう」
そう言って頼子は大気に微笑んだ。
「いえ、そんな…」
「ふふふっ」
その笑い方は亜美によく似ていて、あぁ親子なんだなと大気は思った。
それから、多愛もない話を少ししていると、頼子の携帯が鳴った。
一瞬で、“亜美の母”から“医者”の顔になる。
「ちょっとごめんなさい」
そう言うと、電話に出る。
話しながらリビングから出ていく。
何を話しているかまでは聞こえないが、声音はさっきまでとは違っていた。
「ごめんなさい大気君。急に仕事に行かないと行けなくなってしまったの…」
「そうですか」
「えぇ」
大気に謝罪すると頼子はパタパタと部屋に戻ると、素早く着替えを済ませて出てくると、冷凍庫からジェル状になったアイス枕を取り出すとそれを手に亜美の部屋に向かう。
大気も立ち上がり部屋に向かうが、中に入る事はしないで入り口のところから中の様子を伺う。
頼子は亜美のアイス枕を取り替え、そっと髪を撫でる。
「亜美、ごめんね…」
「マ...マ?」
「起こしちゃったかしら?具合はどう?」
「ん。もう、大丈夫」
「そう?」
「うん。だから――いってらっしゃい」
「――えぇ、そうね」
甘えられない不器用な娘と、甘えさせてあげられない不器用な母親。
「おかゆ作ってあるから」
「うん。ありがとう。あとで食べる」
「薬、ちゃんと飲むのよ?」
「はい」
「汗かいたでしょ?」
「あとで、お風呂入る」
「ちゃんと髪は乾かすこと」
「はい」
「それじゃ、行って来ます」
「行ってらしゃい」
頼子は亜美の部屋を出ると、一度扉を閉める。
「大気君」
「はい」
「初対面の貴方にこんな事を頼むなんて、どんな母親だと思われるかもしれないけれど…」
「……」
「亜美の事、お願いしてもいいかしら?」
真剣な表情で頼子にそう言われた大気はひとつ頷く。
「はい、任せてください。実はお願いされなかったとしても、そう申し出るつもりでした」
「そう、ありがとう」
「いえ」
「大気君」
「はい」
「亜美をよろしくお願いします」
そう言って頭を下げる頼子を見ながら亜美はこの人のこういうところを受け継いだんだなと思った。
「はい」
「これ、私の名刺なんだけど、何かあったらこの番号に連絡貰えるかしら?」
「分かりました」
「おそらく今夜は戻れないと思うの…」
「そうですか」
頼子は大気をじっと見つめる。
「大気君は」
「はい?」
「身長何センチ?」
「……180です」
「やっぱり大きいわねぇ」
「はい?」
「ほら、うちは亜美と私の女所帯だから男性物の服がなくてね」
「はぁ」
「泊まってもらうにも着替えがないのよね」
「それなら心配いりません」
「どうして?」
「同居人に電話して持ってきてもらうか、買いに行くので」
「そう。ごめんなさいね」
「いえ、まさか泊まることまで許可を戴けるとは思っていませんでした」
「あら、大気君なら亜美を一人にしないんじゃないかと思ったんだけど?」
「もちろんです」
二人は顔を見合わせて笑い合う。
「それじゃあ、申し訳ないけど、亜美をお願いね」
「はい。任せてください」
「今度またゆっくりお話聞かせてもらえるかしら?」
「はい。ぜひ」
頼子は大気にもう一度頭を下げると、慌ただしく仕事に向かった。
(さて――と)
頼子を見送った大気は亜美の部屋をノックする。
返事はない。
「亜美?入りますよ?」
声をかけてからそっと扉を開けて中に入る。
「寝てる…」
さっき起きたあと、またすぐに眠ってしまったんだろう。
『うん。だから――いってらっしゃい』
さっき頼子が何かを言うより先に、亜美はそう言った。
きっと何度もこんな事があったんだろう。
大気はそっと亜美の碧い髪を撫でる。
ふわふわと柔らかい。
「んっ」
亜美が小さく身じろぎした
「っ!」
次の瞬間、大気は息をのむ。
瞳を閉ざしている亜美がこぼした一粒の涙。
「亜...美?」
大気の呼びかけには答えない。
起きてはいない。
(どうして、そんなに
独りで、涙をこぼすほどに
――亜美)
大気は亜美のこぼれた涙をそっと指の腹でぬぐう。
「っ、ぁ……?」
「目が、覚めましたか?」
「……?」
「亜美?」
ぼんやりと大気を見つめている亜美に声をかける。
亜美はのそりとベッドに体を起こす。
「たい...き...さん?」
「はい」
「……?」
まだ意識が朦朧としているのだろう。
亜美は状況を理解できていないようだ。
「学校に行ったら、先生から亜美が風邪で休んだと聞いたのでお見舞いにきたんです」
「おみまい…」
「はい」
「お仕事は?」
この言葉に大気は息をのむ。
「今日はお休みです」
「学校?」
「もう終わりました」
「……」
「だから、今日はずっと亜美の傍にいます」
「……」
「亜美」
「……っ」
大気は涙を流す亜美をそっと抱きしめる。
いつもより体温が高い亜美の小さな体を、壊さないように優しく抱きしめる。
「亜美は“独り”じゃないです」
「……」
「みんなが、います」
「……」
「月野さんも愛野さんも木野さんも火野さんもいるでしょう?」
「……っ」
「星野も夜天も、他にもたくさんの人が亜美を想ってます」
「っ」
「もちろん、亜美のお母さんもです」
「っ!」
「それに、私にとって亜美は誰よりも大切な人です」
「ーーっ」
「だからっ」
亜美を抱きしめる力を強める。
「そんな風に、独りで声を殺して泣かないでください」
「っ」
大気は胸が張り裂けそうになる。
亜美はこんな風に、今まで独りで泣いてきたのか?
一人の部屋で、声を殺して。
「亜美っ」
「っ…ーっ」
こんなに近くにいるのに、亜美が遠い。
大気は腕の中にいる亜美を抱きしめ続ける。
泣きたいのなら、いくらでも泣けばいい。
けれど、こんな風に声を殺して、心を殺して、
自分を抑えこむみたいに泣くのは――あまりに悲しい。
「亜...美?」
誰かの声が聞こえた気がした。
夢なのか、現実なのか、わからない。
ただ、ママが仕事に行って家にいない事だけは“現実”だと理解できていた。
『いつもの事』
小さい頃から、何度も何度も、何十回も経験して解ってる。
『“お医者様としてのママ”はたくさんの人に必要とされているから…
だから“亜美のママ”として、求めちゃいけない』
そう気付いたのはいつだったか、もう思い出せない。
『亜美、ごめんね。すぐに帰ってくるから』
そう言って、髪を撫でてパパもママも謝って、いなくなる。
『ウソツキ』
パパとママが出ていって一人になった時に、いつも小さく呟いてたコトバ。
ねぇ、すぐってどれくらい?
1時間?2時間?
時計の長い針が何回、てっぺんに来たら帰ってくるの?
ソファでじっと待ってても、パパもママも帰ってこない。
大好きな本を読んだり、お勉強をしてると、時間が早く過ぎる気がすると気付いたのはたしか四歳の時。
元々、本を読むことは好きだったし、お勉強も楽しかった。
一人の時間を過ごすのにこんなにうってつけのものはなくて、一人の時間が多ければ多いほどあたしは勉強にのめりこんだ。
あたしは、別に頭が良くなりたかったわけじゃない。
ただ、独りだと感じたくなかっただけ。
独りの時間を忘れるために“勉強”という手段を選んだ。
それが結局はあたしの唯一の“とりえ”になってしまっただけのこと。
なんて、なんて
――クダラナイ……
オネガイダカラ
ヒトリニシナイデ
イイコデイルカラ!!
ワガママナンテ
イワナイカラ
――ダカラ…
頬にだれかのぬくもりを感じた。
「っ、ぁ……?」
息を吸い込もうとしたけど、思いの外うまくいかなかった。
「目が、覚めましたか?」
「……?」
「亜美?」
あたしの心を激しく揺さぶる声が聞こえる。
優しくて、暖かくて、時々ちょっと意地悪で…。
大好きな人の声。
「たい...き...さん?」
「はい」
「……?」
なんで大気さんここにいるの?
あたしの疑問に大気さんが答えてくれて、そう言えば学校を休んだ事を思い出した。
「だから、今日はずっと亜美の傍にいます」
この言葉にあたしは息がつまりそうになった。
優しい声で。
どうして、今、それを言うの?
大気さんに抱きしめられて、優しくあやすように言葉を紡がれる。
「亜美は“独り”じゃないです」
そう、なのかな
「みんなが、います」
みんな?
「月野さんも愛野さんも木野さんも火野さんもいるでしょう?」
あぁ、そうだ。あたしには“大切な仲間”が、“親友”が、いる
「星野も夜天も、他にもたくさんの人が亜美を想ってます」
うん。
「もちろん、亜美のお母さんもです」
そうだった。ママはいつもあたしを想ってくれてた。
どれだけお仕事に急いでても、部屋に来て、髪を撫でてくれて抱きしめてくれた。
「それに、私にとって亜美は誰よりも大切な人です」
大気さんの言葉があたしの鼓動を早める。
「だからっ、そんな風に、独りで声を殺して泣かないでください」
「っ」
あたし、泣いてるの?
「亜美っ」
どうして、泣いてるの?
大気さんの声が切なそうで、すぐに「違うんです」って言わなきゃと思ったけど、言葉にならなくて。
結局あたしは、大気さんの腕の中でひとしきり泣いた。
「大気さん」
今までにないくらい、大気の腕の中で泣いた亜美が静かに彼の名前を呼んだ。
「はい」
「もう大丈夫なので…離して、ください」
「嫌です」
「……っ」
はっきりと拒絶された亜美は小さく息を飲む。
「理由を聞かせてはもらえませんか?」
「っ...」
「もちろん無理にとは言いません。でも…」
大気の言葉のあとに、亜美からの答えはなく、部屋が静寂に包まれる。
無理に聞き出すのもどうかと思い、諦めようと思った時だった。
「聞いたら、きっと軽蔑すると思います」
この言葉に大気は一瞬驚く。
「亜美?」
「あたしはみんなが思ってるようないい子じゃないんです」
「……」
「勉強も好きで始めたわけじゃない…」
「……」
「全部、現実から逃げるために身につけた手段なんです」
「聞かせて、ください」
「……あたしは――――」
亜美が小さな声でゆっくりと話し始めた言葉を、大気は聞き逃さないように務める。
小さい頃から感じていた“孤独”
それを忘れるために“好き”だった読書や勉強を始めたこと。
求めてはいけないと思った“親の愛情”
だから聞き分けのいい子の“フリ”をしていたこと。
子どもの頃の“経験”は、そのまま亜美の人格形成に大きな影響を及ぼした。
「大気さん……」
「はい」
「がっかりしたでしょ?」
亜美が顔を上げずに、ポツリと呟く。
「あたしは、つまらない人間なんです…」
「っ!?」
「あたしから“勉強”をとったら、なんにも残らない…」
この言葉を
「それは違います」
大気は反射的に否定する。
「…………」
「亜美」
「……」
「亜美」
「っ!?」
名前を呼んでも自分の方を見ようとしない亜美の顎をくいと持ち上げ、無理矢理に視線を合わさせる。
「亜美」
「っ」
瞳を潤ませる亜美を、大気はそっと腕の中に閉じ込める。
「いつも一生懸命で」
「っ」
「友達想いで、優しくて」
「……」
「しっかりしてるかと思ったら、天然で無防備で、危なっかしくて」
「……」
「すぐに自分だけで抱え込んで、一人で苦しんで」
「…っ」
「甘えベタで、意地っ張りで、強情で、頑固で」
「っ」
「頭は良くて要領もいいのに、人付き合いはうまくなくて」
「ーっ」
「そんな不器用な亜美のことが、私は愛しくて大切で仕方ないんです」
「っ!?」
「亜美、知ってますか?」
「なに…を?」
そっと上目遣いで自分を見上げる亜美に大気は優しく微笑みかける。
「私はどうしようもないくらいに亜美を愛してるんです」
「ーっ///」
「そうやってすぐに恥ずかしがって赤くなるところも、ね?」
亜美は俯くと大気の服の裾をキュッと握り締める。
「――ごめんなさい」
小さく謝罪の言葉を口にする亜美にくすりと笑う。
「亜美」
大気に優しく名前を呼ばれて、泣きそうになった亜美は俯いて彼の胸に顔をうずめる。
「…っ」
「聞かせてください」
「っ」
「亜美の言葉を、心の声を」
その言葉に怯えるように亜美の小さな体が強張る。
「たまには“我儘”を言って私を困らせて下さい」
「ーっ…そん、なの…ダメ」
「どうしてですか?」
「だって、大気さん。困るでしょう?」
「……」
「迷惑だって、煩わしいって、思われたくないんです…っ!」
亜美は青い瞳を潤ませる。
「亜美は、私がそんな風に思うと思ってるんですか?」
「っ」
「亜美の事を『迷惑』だとか、『煩わしい』とか、そんな風に思うと本気で思ってるんですか?」
「ーっ」
大気は小さくため息をつく。
「バカですか」
「なっ!?」
「私の話、ちゃんと聞いてましたか?」
「聞いて、ました」
「じゃあ、どこをどうすればそんな風に思うのか聞かせて欲しいですね」
「なんっ…」
大気の言葉に亜美は二の句が継げない。
「亜美、もう一度言います」
「……」
「よく、聞いてください」
「……っ」
こくんと小さく頷く。
「私は、どうしようもないくら「それはもう分かりましたから、言わなくていいですっ///」
思わず大気の言葉を遮る。
「私は亜美の心の声を聞きたいんです。我儘を聞かせて下さい」
「……いきなり、そんな事を言われても…」
大気は困ったようにうつむく亜美を見つめる。
「あ、そうだ。亜美」
「はい?」
「今夜、泊まりますから」
「え?誰がですか?」
「私がです」
「どこにですか?」
「ここに、です」
「……泊まるん、ですか?」
「はい」
「泊ま...るんです...か?」
「えぇ」
頷く大気に亜美は驚いた表情を見せ固まる。
「…………なんで?」
「そんな状態の亜美を放って帰れません」
この言葉に亜美は、どこかぼんやりとした頭で考え、答えを導きだす。
「あ、の…、えっと大丈夫なんで…遠慮無く帰って下さい」
「……亜美」
少し苛立ちを含んだような大気の声。
「はい?」
「本当に帰って欲しいですか?」
「え?」
「亜美が私にいて欲しくないって言うんなら、帰ります」
「っ」
「でも、そうじゃないなら……」
大気はそこまで言って真剣な瞳で、亜美をまっすぐに貫く。
「っ」
亜美はひくりと息を飲む。
さっき大気に言われたばかりなのに……
頭で分かっていても、亜美はこんな時になんて言ったらいいのかが分からない。
「亜美」
「〜っ」
「どうして欲しいか、言ってごらん?」
大気は優しく亜美を見つめている。
「ぁ、っ」
「ん?」
(迷惑に、ならない?)
「……っ」
「亜美」
(“我儘”言っても、いいの?)
「傍に、いてください…」
「うん」
「一人にしないでっ」
亜美がそう言った瞬間、大気は彼女を力いっぱい抱きしめる。
「っ!」
「やっと亜美の我儘を聞かせてくれましたね」
(どうして、そんなに嬉しそうなの?)
「これからはそうやって、もっと私に我儘を言ってください」
「っ」
「寂しいなら寂しいって言っていいんです」
「っ…でも」
「仕事で、会えない時もあります。寂しい思いをさせてしまう時もあります。
だけど、だからこそ、ちゃんと言ってください」
「っ」
「聞かせて下さい。亜美の“言葉”を」
「〜、はいっ///」
大気の言葉に亜美は恥ずかしそうに笑顔を見せる。
亜美の笑顔に、大気はほっと胸をなでおろす。
「たくさん泣いたらお腹すいたでしょう?」
「っ/// はい///」
「お母様が作っていかれたおかゆがあるので温めてきますね?」
「えっと…お願いします」
「亜美はお布団で大人しくしててください」
「はい」
亜美の髪をくしゃりと撫でて、部屋を出ると大気はくすりと笑う。
『傍に、いてください…』
『一人にしないでっ』
(やっと聞けた――亜美の“心の声”)
大気は亜美のおかゆを温めながら携帯を取り出し、星野に電話をする。
下着や着替えとを持ってきてくれるように頼むと快く了解してくれた。
その後、荷物を届けてもらい、食事をすませお風呂に入った。
時間はまだ夜の十時を回ったところだったが今日は早めに眠ることにした。
「ここで寝るんですか?」
「はい」
「えっ…と///」
「大丈夫ですよ」
「?」
「何もしませんから、ね?」
「ん」
「さぁ、また熱が上がったらいけません。寝ますよ?」
「あ、はい」
「おやすみなさい。亜美」
「おやすみなさい。大気さん///」
薬が効いたのかすぐに眠りについた亜美をそっと抱きしめて、大気もそのまま眠りに落ちた。
翌朝、5時半に帰宅した頼子は娘の部屋のドアそっと開き目を丸くした。
亜美を抱きしめて眠る大気にも驚いたが、それよりも――大気の腕の中でぐっすりと眠る亜美に驚いた。
再びそっとドアを閉める。
久しぶりに見た、亜美の子どものように安心しきった寝顔。
大気の存在はそれほどに亜美にとって大きいということを、改めて知った。
不器用な娘が心から寄り添える人に出会えたことを嬉しく思う反面、少しの寂しさも覚えるのは随分と身勝手だと思いながら、頼子は二人の朝食を用意するためにキッチンに立ちエプロンをつけた。
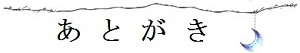
ここまでお読みいただきありがとうございました。
このお話は半年前くらいからちまちま書いてて、一度途中で諦めかけて放置していたものです。
亜美ちゃんは両親が家にいることがほとんどなかっただろうなと思って書きました。
我儘を言わないんじゃなくて、言えない。
我儘ってどう言えばいいのかわからないんじゃないかって思ったんです。
そして、それを引き出せるのはきっと大気さんだけだろうって思ったんです。
今、9月に向けて亜美ちゃんのバースデイ小説を書いてます。
その前に亜美ちゃんのママを出しておきたくて。
名前は最初、悠美-ユミ-にしていたんですが、あみとゆみってどこかのユニットみたいになるのでやめましたww
あ、ちなみに2年生の頃のお話なので、大気さんと亜美ちゃんはまだそういう関係にはなっていません。
では、ここまでお読みくださってありがとうございました。