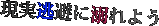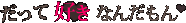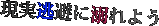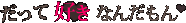
3
その証拠に烈の息が弾み、時折押し付けるように体が軽く仰け反る。
「はぁ…もう、そろそろか?」
帯を解き袴を引きずり下ろして足を広げ、指で探る。
「ん…あんっ」
「準備万端だ」
「ああっ」
勢いよく指が潜り込み擦り上げてくると、烈は堪らず声をあげた。
「すまん、もういいか?」
先程からすでに我慢の限界が近い状態なのだ。熱く硬くなる一方で、早く妻の胎内にこの身を沈ませたくて仕方がない。
「ええ…きて…」
膝裏から手を入れて自ら大きく足を開き夫を迎え入れようと誘う。
「烈…」
十四郎は誘われるままに圧し掛かり一息に身を沈ませた。
「ああ…ん…あん」
「ふう…ん…気持ちいい」
「ん…あなた…」
口付けをねだるように肩へと手を置くと、十四郎は素直に唇を重ねた。
久しぶりに体を重ねることと、十四郎の体調が良いこと、更には烈の甘えたいという気持ちに、執務室という環境の中からか、二人は何時になく激しく愛し合うことになった。
「はあ…治まらない…」
十四郎は強引に烈の体を持ち上げ、長椅子に座るような格好をさせて足を大きく開き、腰を下から激しく突き上げた。
「ああっ!あ、あっ、ああっ」
烈も滅多にない刺激に喘ぎ声をあげ、十四郎にしがみ付く。
「烈…」
唇を貪るように求めながらも、腰の動きは激しさを増す一方だ。
「あ、あんっ、あなたっ」
烈も夫の唇を貪るように求め、首にしがみつく。
「ん、ふあっ、ん」
「あん…」
一度十四郎が体を離すと、烈が残念そうな声を漏らした。
「すまん、ちょっと息切れが…」
長椅子に座り謝るが、まだまだ立派に反り返っている身が目に留まる。
「動いてくれ」
「ええ…」
膝を軽く叩いて自分の上に乗るように促すと、烈は笑みを浮かべて頷き素直に十四郎の上へと圧し掛かった。
自ら花弁を広げ、胎内奥深くへと誘い、長椅子の背に手を付いた状態で髪を振り乱し腰を激しく叩きつけるように動かしはじめた。
「あ…ああん…」
「ふっ、ん…」
十四郎は目の前で激しく揺れる豊かな乳房を揉みながら、妻の乱れる姿を目を細めて見上げる。
艶めかしく揺れ動く腰の動きに、堪らずうめき声が漏れてしまう。
「う、うう…凄い動きだ」
「うふふ…だって、あなたが凄く熱いんですもの」
「今日の烈は淫らだな」
流れる様な髪に指を差し入れ梳くように撫で降し、髪が指の間から抜けると今度は背中を撫でるように這い上がる。
「あ…あなた、こそ…こんな…」
「何故かな…今日はこんな気分だ…」
「ええ、私も…」
十四郎は腰を強く抱き寄せ、下から突き上げて見せると、烈は仰け反りながらも腰を引き強く押し付け返した。
「ああ…素敵…」
「本当だ…」
笑顔で互いの行為を認め合うと、再び唇が重なった。
再び十四郎が烈を下へと組み敷くと、指を絡ませあい、腰を強く叩きつけ始めた。
「あ、ああっ!あ、あ、あっ」
「ん、ふ、もう、そろそろ…」
「あ、あっ来てっ、ああああ!」
「いっ…くぞ」
「あ?あああああ!!!」
十四郎の動きが早くなりやがて止まり腰を震わせ奥深くへと精を放つと、烈の体も震え嬌声をあげたのだった。
汗を拭いようやく体が落ち着くと、二人は羽織を羽織っただけで長椅子で寄り添い手を繋いで余韻に浸っていた。
「…今日は、どうしたんだ?」
「…ふふ、今日はなんだか無性にあなたに側にいて欲しくって…そんな時にタイミングよくいらしたから」
「…そうなんだ。俺もだ。なんか無性に烈に会いたくなってな…」
素晴らしい巡り合わせだと、十四郎は嬉しそうだ。
「なあ、今度は俺の執務室でどうだ?」
「あら、でも、十三番隊では邪魔が入りやすいのでは?」
四番隊は烈の一声で人払いが簡単だが、十三番隊は十四郎の身体を気遣い常に誰かしらの気配があるのだ。
「む、それもそうだなぁ…」
烈は考え込んでいる夫に甘えるように、肩に頭を預けると目蓋を閉じた。
[*前] | [次#]
[表紙へ]