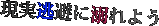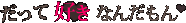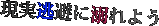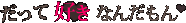
2
見下ろし妻の様子を見守っていた十四郎だったが、ふとあることに気がついた。
邪魔にならないようになのだろうが、烈は髪を三つ編みにしたままである。
床に伏せる回数が増えたころから十四郎は、以前は結んでいた髪をそのままにしておくことがいつしか当たり前になっていた。枕に結った部分が当たるので、結わなくなったのだ。このまま横向きにとは言えど首周りに髪があっては、寝苦しくないだろうかと考えたのだ。
起こさないように、三つ編みを解いて行く。
美しい黒髪が波打ち流れている。
「……しまったな…俺がやばい…」
眠る妻に欲情してしまうのはいかがなものか。溜息を吐きだし首を振る。
邪魔にならないように、流れる黒髪をまとめて背中の方へと流す。
「ん…何…」
流石に烈が目蓋を開けた。
「…あなた?」
上体を起こし寝ぼけ眼で首を傾げる。
髪がさらさらと肩へと流れ落ちていく様は、色っぽいと言う表現がとてもよく似合う。
生唾を飲み込み烈を凝視している夫を見つめ返し、視線を顔から下へと滑らせていくと、非常に珍しい光景が目に入った。
「あら、まあ」
驚いたように口に出しつつも、目を細め口元には笑みが浮かぶ。
「いけない方ね?」
手を伸ばしてちょっとだけ頬をつねってみせる。
「すまん」
十四郎もさすがに申し訳ない気持ちで頬を赤く染め、視線を反らした。
そんな愛らしい仕草をする夫に対し、烈はますます笑みを深めると頬をつねった指を滑らせて唇を撫でる。
「…烈?」
「愛して、下さる?」
視線が十四郎の唇に吸い寄せられるようになり首が小さく傾く。
「…ああ、勿論だ…」
十四郎は烈の指を取って軽く舐めると、唇を重ね合わせた。
「ふふ、もうこんなにして…」
「すまん…烈があまりに色っぽくて…」
袴の帯を解き雄々しい状態を見て悪戯っぽく指先で触れて見せると、十四郎は照れながらも素直に認めた。
「あ、執務室で大丈夫か?」
ようやく今の状況に思い当たり辺りを見渡す。
「大丈夫です」
烈の指先が動くと室内の鍵が全て掛った。
「便利だな。俺の部屋もそうしようかな?」
霊圧で調節しているのだろう。指先一つでというのは非常に便利だ。
「あら、執務室で何をなさるおつもり?」
十四郎の襟元を開け指先で胸板をなぞると、ちらりと睨みあげる。
「執務室じゃなくって、俺の部屋の方。寝ながらでも襖や障子を閉めたり」
「あらあら、それくらいはなさらないと」
寝込んでいる時間が長い故の不精と言えよう。
「そうかな?」
「今だってそうじゃないですか?私にばかりさせて」
烈が指摘するように、十四郎は長椅子に座り背もたれに右腕を預けて、脱がされるがまま楽しげな表情で観察しているのだ。
「だって、烈が楽しそうにしているから邪魔をしてはいけないなと思って」
「まあ…あなたは私の死覇装を脱がせたくないと?」
驚いたように目を見張り、よよと長椅子に縋るようにしてちらりと十四郎を睨む。
「そんな訳ないじゃないか。脱がせてその豊かな胸に顔を埋めて、さらには烈の中に入りたくて堪らないというのに」
「あらまあ」
実際、あらまあである。十四郎がここまで素直に、熱く説明してくれることはないのだ。これは相当体の調子が良いに違いない。そもそも、体調が良くなければ興奮などできる状況ではないのだから。
十四郎は立ち上がり半端に脱がされた死覇装を全部脱いでしまい、下帯を外してしまい全裸になると、長椅子に圧し掛かって烈の死覇装を脱がせに掛った。
口付けを交わしながら手探りで襟元を開け、掌で乳房を包み込む。
「ん…何?」
「ん?手で揉むのも良いんだが…やっぱりこうしたい」
乳房を露わにすると片方の手では揉みながらも、もう片方にはしゃぶりついた。
「ふふ…美味しい?」
「ちゅ…ん、うまい」
子供のように素直な夫に思わず笑みが浮かんでしまう。それでいながら指先や舌は器用に動き烈の女としての部分を刺激する。
「ん…ふ…」
仮令離れている時間が長くとも、長年夫婦なのだ。十四郎は当然妻の弱点は知り尽くしている。
[*前] | [次#]
[表紙へ]