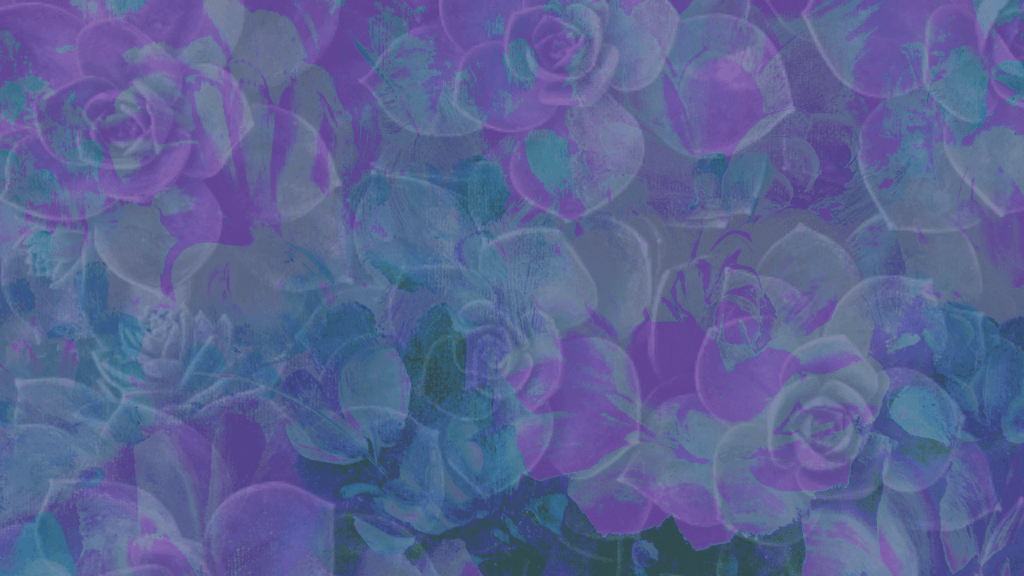夜月はこの世界について全くと言っていいほど知らない。赤子同然と言っていい。だから座学の授業に付いて行くのも一苦労だ。周りにとっては常識の範囲内、エレメンタリースクールで習ったことだろうが、夜月にはそれがない。結果、夜月は魔法が使えないこと以外でも苦労を背負うことになった。分からないことがあるとエースやデュースがフォローを入れて教えてくれることはあるが、いつまでも頼ることはできない。
その日から夜月は図書室に籠ることが多くなった。放課後に用事がない時、エースやデュースが部活に行って1人することが無くなった時は必ずと言っていいほど図書室に向かった。最初はグリムもついてきて隣で寝てたこともあったが、退屈だといって夜月が図書室に籠るときはエースかデュースに付いて行くことが多くなった。
図書室で夜月はひたすら本を読み漁った。この世界での常識や授業で使う最低限の知識をかき集めるように。それは放課後の図書室に留まらず、借りて夜遅くグリムが眠った後になど1人で読みふけることもあった。そのたびグリムはうわぁ・・・・・・とした目で見てきた。
正直なところ、夜月は勉強が嫌いではなかった。新しいことを知ること、知らないことを知ることは楽しいし面白い。人間は思考する脳も考える脳も知識を蓄える脳も持っている。人間とはそういう生き物だ。この世界は自分の知っている常識とはかけ離れている。だから見聞きするものすべてが楽しかった。
けれど楽しいという感情だけが、夜月に本を漁り読みふけることを促したのではない。
此処は知らない世界。身寄りもない。お金もない。今は学園に置いてもらっているけれど、此処から立ち去らねばならなくなったら住む場所もない。いつ帰れるかもわからない。帰れるかどうかもわからない。夜月には、この世界で生きていくすべを持たなかった。この世界には魔法が使える者、魔法が使えない者が共存しているが、身寄りもお金もないただの人間がそう易々と生きられるわけがない。世界とはそういうものだ。そういった不安が、夜月にそれを促している要因の1つともいえる。
それは夜月自身も理解していた。それを自覚するたび、大概わたしも人間らしいと思った。そして今日もまたひとり、少しの心細さを抱きながら図書室に逃げ込むように籠った。
* * *
微睡みの中、瞼を上げた。ぼんやりとする思考。視界にうつるのは積みあがった本と開かれたノートそして転がったペン。視線をずらすと窓が見えた。外はもう真っ暗で夜だった。ああ、寝落ちたのか。わずかに戻った思考で状況を把握し、夜月は手をついて机から起き上がった。
「起きたか、仔犬」
視線を向けると、机に肘をついて本を片手にしたコートを脱いだクルーウェルが向かい席に座って足を組んでいた。夜月が起きたのに気づくとパタンと本を閉じ、視線を向ける。「よく眠っていたな」目を丸くする夜月にフッと笑う。夜月はなぜクルーウェルが此処に居るのかと困惑していた。
「勉強に熱心なのはいいが。夜遅くまで学園に残るなと、以前に忠告したはずだが?」
「そんなに躾をご所望か?」目を鋭く細めるクルーウェルに夜月は慌てて謝罪した。「す、すみません・・・・・・」肩をすくませ身を縮める夜月。申し訳なさそうに眉尻を下げて顔をうつ向かせた夜月に「ふん、まあいい」と手に持った本を机に置いた。
「魔法史に魔法薬学や錬金術・・・・・・雑学まで。まとまりのないくらい幅広いな」
机に積み上げられた本を見詰めてクルーウェルが独り言のように呟いた。「一気に詰め込んだところで成果は出ないぞ」と告げるクルーウェルに「勉強するのは嫌いじゃないので・・・・・・知れるだけ知っておきたいです」と夜月は愛想よく笑って答えた。その様子を眺め、クルーウェルは夜月と向き合うように逸らしていた身体を正した。「何をそんなに焦っている」真っ直ぐと問いかけてくる言葉に、夜月は言葉が詰まった。柄にもなく焦っていた自覚はあった。夜月は視線を泳がせたが、真っ直ぐと見つめてくる視線からは逃げることはできなかった。
「・・・・・・授業だけじゃなくて、この世界に付いて行くだけで・・・・・・精一杯、なので・・・・・・」
小さな声で、困ったように笑いながら夜月は言った。魔法が使えないだけで授業に付いて行くのもやっとなのに、それ以前に常識さえ理解していない。生活するだけで精一杯だ。それは夜月の事情を知る1人として、クルーウェルも理解している。「そんな赤子同然が、本を読むだけで補えるわけないだろう」やれやれとクルーウェルは言った。
「分からないことがあれば聞きに来ればいいだろう。なんのための教師だと思っている」
「え?」
目をパチパチと瞬きをしてクルーウェルを見た。暗にともいえないが、教えてくれるとクルーウェルは言っているのだろう。夜月は教師陣に聞きに行くのをためらっていた。どの先生も忙しそうだし、そんな1人に構ってられないと思ったからだ。だからクルーウェル本人がそういってきたことに、夜月は驚いた。
「明日の放課後に来い。分かるまで手取り足取り教えてやる」
「え、でも・・・・・・」
「返事は?」
「は、はい」
じろりと睨まれ咄嗟に返事をする。返事を聞けば目元を緩ませ「グッガール」と頭に手を伸ばして犬のように撫でまわした。「なら、さっさと片付けろ」机を指さし、夜月は椅子から腰を上げ本を片付けようとする。その時、肩からスルリと何かが滑った。椅子に押したものを見ると、白と黒のクルーウェルがいつも着ていたコートだった。寝ていた時に掛けてくれたみたいだ。返そうとコートを手に持って振り返ると、振り返った先にクルーウェルはいつのまにか立っていて、フワッとコートをなびかせ夜月の肩に羽織らせた。
「夜は冷えるからな、身体を冷やさないことだ」
ふわふわのコートに包まれる。スッと片手に持った鞭を振ると積み上げられた本が浮き、勝手に本棚に戻っていく。机に散らばった勉強道具を片付けるよう促され、急いで手に抱える。「仔犬の散歩ついでに寮まで送ってやる、来い」夜月を確認するとクルーウェルはそういって踵を返した。その後を素直についていく夜月の姿はまるで仔犬のようで、クルーウェルはそっと笑みを零した。
後日、クルーウェルは授業の手伝いや補習などを積極的に開いてくれるようになり。無駄に図書室に籠って時間を浪費することはなくなった。
Chapter1の後半、クルーウェルの補習する前の話です。
私の最推しはクルーウェル先生なので、クルーウェル先生の話を書くとテンションが上がってしまいます。一応クルーウェル先生は主人公のことを珍しい毛並みということで他より気に入っている。それに加え問題児のNRC生徒と比べ素直で純粋で単純な主人公を可愛がっている、という認識です。主人公も事情を知っている頼れる大人で何だかんだで一番やさしいクルーウェル先生にこれ以降懐いていきます。クルーウェルも懐いてくる主人公が仔犬みたいで可愛くてあっという間にお気に入りになるって感じです。これからも主人公と絡ませていきたい。クルーウェル先生は大人だから大人の余裕で基本放してくれるけど他の人に尻尾振り出したら絶対首輪持って躾けなおしてくる束縛強め(願望)。でも大人だから逃げ道は残してあげちゃう。
話は変わりますが、先生の「グッガール」とかカタカナ表記がいいのか英語表記がいいのか迷う。見栄えでどっちも使ってるけど、統一するならどっちがいいですかね。