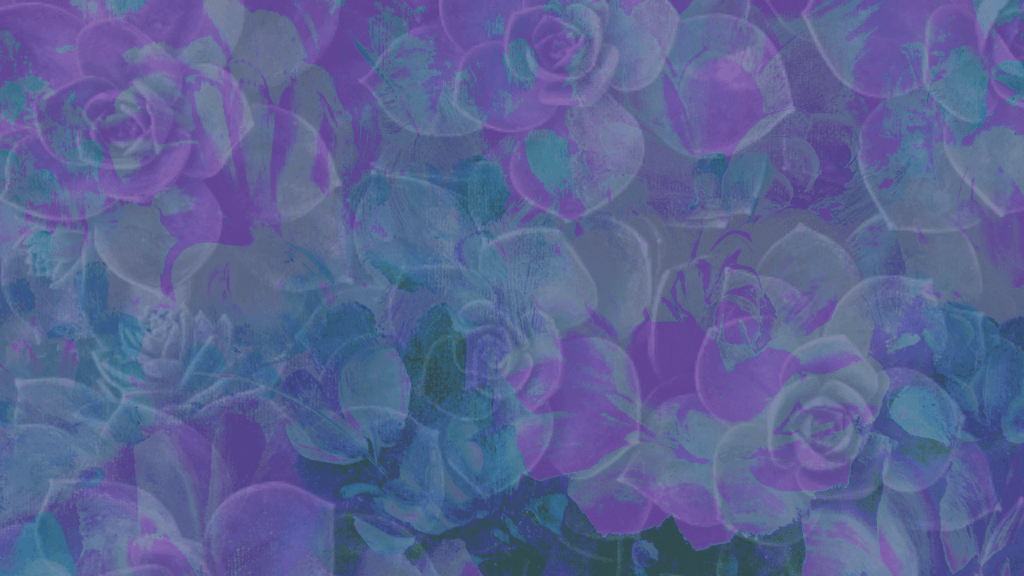
フェアリーガラの会場となった植物園に入れば、きらびやかな飾り付けや、美味しそうな料理に目を奪われる。そしてランウェイを確認すると、正面に一つ特別な特等席が用意されていた。おそらく女王が座る場所だろう。ランウェイの正面でティアラをすり替えなければいけないことに、ラギーに緊張が走った。
ショーに出る3人とは別れ、ラギーとグリムと夜月は亜熱帯ゾーンに身をひそめた。
「ヨヅキくん、グリムくん、よく聞いて」
「女王の頭から本物のティアラを取って、偽物を乗せるのは、一番手が器用なオレがやるッス」3人は顔を近づけ、作戦を立てる。「グリムくんは警備員が来ないか見張るかかり。夜月くんはショーよく見て、ティアラをすり替えるタイミングでオレに合図してください」
「オレのスマホに、1秒コールして。番号はコレ。音は切ってるから安心していいッス」
ラギーはそう言ってポケットから紙切れを出し、それを夜月に渡した。折りたためられたそれを開けば、ラギーの電話番号が書かれていた。「女王の注意が他に強く引かれた瞬間・・・・・・会場が一番盛り上がった瞬間に合図をください」
「ヨヅキくん、勝負は一瞬ッス。気を引き締めて」
「き、緊張してきた・・・・・・」
「シシシッ! 大丈夫ッスよ。ヨヅキくん、案外肝据わってますから」
緊張する夜月に、ラギーはそう言って緊張を和らげようとした。
ラギーとグリムは女王の特等席である場所へ、夜月は会場を見渡せ女王を確認できる場所へ移動した。スマホを出し、ラギーの伝は番号を打ち込んで、いつでも連絡できるように準備をする。
いよいよショーが始まり、会場中は賑わいを見せた。ランウェイを見ていると、そろそろ3人の番が来ていた。準備をしている3人を見ていると、夜月を見つけたカリムが笑顔で大きく手を振ってくる。それに続いてジャミルやレオナも気づき、軽く手を上げる。夜月も小さく手を振り返した。
そして3人の番がきてついにショーが始まった。カリムとジャミルの華麗な切れのあるダンスに、会場中の妖精たちは目を奪われていた。そして中心を歩くレオナのウォーキングに、女王までもが見惚れていた。そして会場のすべての視線を奪うようなパフォーマンスをしたレオナによって、会場中は一番の盛り上がりを見せた。
夜月は手に持ったスマホをタッチして、ラギーに1秒コールを送った。ラギーは合図により素早くティアラをすり替える。3人のショーも終え、役目を終えた夜月は急いで亜熱帯ゾーンへ急いだ。
亜熱帯ゾーンへ戻ると、ティアラを持ったラギーとグリムがすでにいた。
「おっ、夜月くん、おかえり! タイミングバッチリだったッスよ」
「よかった、上手くいって。女王も全然きづいてませんでした」
「シシシッ。ま、素人と一緒にされたら困るッス」
「よし、早くここを離れよう」作戦は成功し、魔法石を取り戻すことはできた。ラギーの言葉に頷き、3人は急いで裏口へと駆けだした。「ほら、早く早く!」先頭を走るラギーは後ろから追いかけてくる2人に言い放つ。「ちょ、ちょっと待つんだゾ・・・・・・」「ラギー先輩、足はやすぎ・・・・・・」ラギーの足についてこれず、2人はヘトヘトになっていた。植物園は案外広い。裏口までももう少し距離があった。
すると突然、3人がいた場所に水が降り注いだ。「なんだ!? 雨が降ってきたんだゾ!?」グリムは驚いて辺りを見渡す。「違う、これは・・・・・・植物園のスプリンクラーッス!」しまった、とラギーは声を上げた。
「やばい、亜熱帯ゾーンにはスコールタイムが設定されてたの忘れてた!」
「このままじゃ水で『妖精の粉』が全部落ちちゃいます!」
その直後、ラギーの耳は小さな音を拾上げた。「やばいっ、誰か来る! ひとまず物陰に隠れるッス!」ラギーは急いでグリムを腕に抱えた夜月の腕を引っ張って、物陰に身をひそめた。身体を小さくして潜むために、ラギーは咄嗟に夜月を抱え込んだ。「シーッ」と人差し指を口元で立て、辺りを伺った。
「なんだ・・・・・・? このあたり・・・・・・すごく、人間臭い!」「妖精の祝祭に人間が紛れ込んでいたのか? なんと不敬な」やってきたのは2人の小さな妖精だった。妖精の粉が落ちてしまったため、人間だということが妖精に一目でバレてしまう。「このままじゃ見つかっちまう・・・・・・!」人間の匂いを嗅いで辺りを探す妖精たちを見て、ラギーは冷や汗をかいた。その時、思わぬ声が耳に届いた。
「おい、お前」
「ん? あっ、あなたは・・・・・・さっきのショーで会場中を感動の渦に巻き込んだ・・・・・・」
「どこぞの高貴な妖精様!!」
2人の妖精に声をかけたのは先ほどまでランウェイにいたレオナだった。「レオナさ〜〜ん! ナイスタイミングッス〜〜!!」レオナの登場に、ラギーはほっと安心する。「気づいて助けに来てくれたんですかね?」タイミングよく現れたレオナを見て問えば「たぶんそうッス」とラギーは答える。もしかしたら様子を見に来てくれたのかもしれない。レオナは妖精の気を自分に集中させ、口パクでラギーたちに「早く行け」と伝える。
「よし、今のうちにこっそり行きましょう」
「はい」
「今のうちに脱出なんだゾ!」
レオナが気を引いているうちに、3人はそそくさと裏口へ急いだ。裏口まで行くのに他の妖精に会うこともなく、植物園を出ることができた。「フェアリーガラの・・・・・・植物園の、外に・・・・・・出たんだゾ!」走って植物園を出たため、主にグリムと夜月は息を整えた。「ここまでくればもう安心ッスかね。後ろは・・・・・・よし、誰もいない」背後を振り向き、誰もいないことを確認しほっと息を吐く。
「作戦大成功です! ラギー先輩!」
「これで快適な学園生活が戻ってくるんだゾ!」
「「「イエーーーッ!」」」作戦を成功させた3人は両手を高く上げてハイタッチを交わす。あれだけ時間をかけて準備をしたのだ。大喜びをするのも当然だ。
「そろそろショー組も表の出口から出てくるはず。合流しましょう!」
「はい!」
3人は植物園の表口に急いだ。