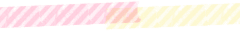▼sherbet time  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ もう何度も読んだ本を、暇潰しに開いてはぱらぱらと頁をめくる。文字列を目で追うものの、視線は何度となく壁に掛けられている時計に向けられていて、そんな自分に気が付いて撫子は苦笑する。 最近では政府内であれば自由に歩き回っても良いと許可を貰っていて、息抜きがてら部屋を出て散歩に出掛けることもあるものの、廊下などですれ違う人達は皆忙しそうで、邪魔になってはいけないと自分から話しかける事はなかった。 だから撫子は、この部屋に時折訪れては話し相手となってくれる鷹斗や円、レインの存在を、言葉には出さないけれど感謝していた。 特にレインは、何かしら理由をつけてはちょくちょく撫子の部屋にやってくるので、撫子にとって細やかな楽しみになっている。 今日もそろそろ彼が来る筈だ。何度も見上げていた時計の針が3時を示したのを見て、本をぱたりと閉じて傍らに置く。それと同時にドアが遠慮なく開かれ、レインが入ってくる。 「撫子くん、お邪魔しますよー」 「いらっしゃい、レイン」 自然と顔が緩んでしまうのは仕方ないと思う。腰掛けていたベッドから立ち上がってレインを出迎えると、いそいそとテーブルと椅子を出してお茶の準備を始める。 「あら?今日はカエルくんいないのね」 「カエルくんならボクの部屋でお留守番ですー。たまにはキミと二人きりで、というのも良いですよねー」 レインの左手が定位置のカエルくんがいないと、なんだか物足りなさを感じて、その事を指摘すれば、そんな台詞を意味ありげな笑みを浮かべて言うものだから、撫子の心臓はさっきからどきどきしてばかりだ。 レインの顔が見れなくて、うろうろと視線を彷徨わせていると、それが視界に留まった。 「その手に持ってるのは何なの?」 「ああ、これですかー。何だと思います?」 「……質問に質問で返すのはずるいと思うわ」 笑顔ではぐらかすレインに、頬を膨らませて文句を言うけれど、彼は結局答えてくれないままテーブルの上にそれを乗せた。 レインが座った椅子の向かいの椅子に撫子も座ると、テーブルに乗せられたガラスの器を見る。そこには、ピンクと黄色のアイスクリームのようなものが入っていて、小さな銀のスプーンが二本添えられていた。 「アイスクリーム……?」 「まあ、それに近いもの、ですかねー。これはシャーベットです。今日のおやつはこれですよー」 「へえ、美味しそうね。これって何味と何味なのかしら」 「それは食べてからのお楽しみですー」 レインの言葉に、それもそうかとスプーンを手に取って、さてどちらのシャーベットを先に掬おうか迷っていると、不意に目の前にスプーンが差し出されて撫子は反射的にぱくりと咥えてしまった。ひんやりとしたそれは舌の上で直ぐに溶けて、口の中に甘い桃の味が広がる。 「撫子くん、こっちもどうです?」 「……レイン、私自分で食べるわよ」 今度は黄色いシャーベットをスプーンで掬って撫子に食べさせようとするレインを制して嘆息する。少し残念そうな顔をしたレインは、今度は何を考えたのか、口を開けて何かを期待するような目で此方を見る。 レインが何を求めているかは一目瞭然だけれど、だからと言って実行に移せるかはまた別だ。先程レインにされたのも恥ずかしかったけれど、するのはするでまた恥ずかしい。出来るならば、遠慮させてほしい。 けれどレインの口は一向に開いたままで、シャーベットは段々と溶けていく。撫子はやけくそになってスプーンを握るとシャーベットをざくりと山盛りに掬った。桃色と黄色のシャーベットがそれぞれ乗っかって溢れそうになったそれは、まりでレインの髪のようで。撫子は小さく笑うとレインの口の中に山盛りのシャーベットを突っ込んだ。 「撫子くんも意地悪しますねー…」 「あーんして欲しそうにしてたのはレインじゃない」 「それはそうですけどー…まさかあんな山盛りで、しかも桃味とレモン味を一緒にするなんて…」 恨めしそうに此方を見るレインに、撫子は肩をすくめて温くなったお茶を飲む。すっかり冷たくなった舌に温いお茶はちょうど良く、ほっと息をつく。 「さて、まだシャーベットが少し残ってますけど…」 「私もういらないから全部あなたが食べてちょうだい!」 ちら、と懲りずに此方を見ながらスプーンを差し出すレインに、首を振りながら決してあーんされるまいと口を死守する。何が楽しいのかにこにこと笑うレインの笑顔がとても空恐ろしく感じられた。 (終) (あとがき) レインの誕生日に書いた作品です。誕生日のお話ではないけれど。暑い日が続くので、シャーベットで涼しくなるたらなあ、なんて。 [BACK] 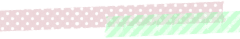
|