2月。容赦なく体を襲う寒さに、季節を混じる時期。怪盗業も大分慣れてきて、体力もついた。相変わらず生傷は絶えないけど、応急処置ぐらいなら一人でもできるようにもなった。なんとか、怪盗が板についたという感じだ。
一面を飾った昨夜のキッドの働きを端末越しに流し読みしながら、これで、先輩も少しは今のキッドを見てくれるだろうか…なんて考えて、いちごみるくの紙パックを吸った。三限の直前のことだ。
「ッ、快斗!!!!」
「どうしたんだよ青子、そんな大声……」
「いいから、来て!!!柚木先輩が!!!」
青子の一言に緊急事態を察し、急いで後についてくと、そこは保健室だった。心のうちに渦巻いていた嫌な予感が大きくなる。オレと青子の他にも上級生が数人いて、話を聞いていた。櫻井先生の方を向くと、落ち着いた声で「黒羽くんも来たのね。」と声をかけられる。
「櫻井先生!!柚木先輩、大丈夫なんですか!?」
涙目の青子の訴えに、櫻井先生の回答は「外傷は擦り傷ぐらいで済んでるわ。」なんて淡々と返す。状態がわからなくて、とにかく今は、一刻も早く元気ないつもの先輩に会いたかった。
「あの、何があったんですか!?」
「ああ――倒れたのよ。柚木が。」
*
すぐに三限の始まるチャイムがなったが、先生が全員を追い返す中、オレだけは頑なにその場所を動かなかった。オレがなかなか折れないと知っていた櫻井先生は、ため息を漏らしながらも「そばにいてあげて」と保健室の滞在を許された。
保健室のベッドで静かに横になる先輩の手を温めるように両手で包み込んで、先ほどの櫻井先生の話を思い出していた。
朝から学校に来ていた先輩は、いつも通りに二限の体育を受けていたそうだ。しかし運動後のランニング中、少しずつ走るスピードが落ち、そのまま地面に倒れて運ばれたらしい。三限の始まる前に先輩に用があった青子は、二年生の先輩の教室でその事情を聞いて、真っ先にオレのところへ飛んできたらしい。幸い、肩から地面に倒れたようで、擦り傷はあれど頭部への強打の心配はないようだ。
死んだように眠る先輩は、病人そのものみたいに青白い。櫻井先生の話では、生理と睡眠不足に、熱中症が重なったようだ。最近の先輩の生活サイクルから危惧していたことではあったようだが、想像以上にストレスを溜め込んでいたのかもしれない、とのことだった。
「……。先輩…、」
なんで、オレのこと頼ってくんないの?
そんなことを考えた。でも、今のオレは、先輩に頼られる存在にはほど遠くて。だって、オレと先輩はただの先輩と後輩で。ただの、サボり仲間で。――それ以上でも、それ以下でもないんだから。
オレだけは、先輩の特別になったような気がしていた。でもそれは単なる思い過ごしで、先輩は、オレには背中を任せられないって判断したんだ。だから誰にも頼らず、誰にもすがらず、自分の抱えた何かを一人で背負いこんで、倒れた。
それが、どうしようもなく、悔しかった。
「――…、」
「…先輩?起きたんですか?」
わずかに体を揺らした先輩に向かって静かに声をかけると、先輩は薄く目を開いてオレを見た。
「…ぃ、とくん……?」
「はい、オレです。
具合大丈夫ですか?先輩、体育の時間に倒れたんですよ。」
ゆっくりと起き上がろうとする先輩の背中を支えて、上半身を起こす。
「はは……、情けない姿見せちゃったね。」
そう言って弱った笑顔を向けられた瞬間に、どうしようもなく、頭に血が上った。
「……っ!
なんでそうやって何もかもかかえ込むんですか!!」
感情よりも先に言葉が出た。言った後についてくる後悔よりも、止められない言葉がただただ募って、追随するように怒鳴っていた。
「先輩は、いつもそうやって、一人で抱え込んでたんでしょう!?
何でオレや青子に頼らないんです?!オレじゃ力不足ですか……!!?
それとも、たかが後輩のオレじゃ、先輩には到底頼ってもらえないんですか!?」
「っ、私が倒れたからって、カイトくんには関係ないでしょ!!?」
「……!」
それは、初めて聞く先輩の怒鳴り声だった。オレに向けるのはいつもの飄々とした笑顔じゃなくて、これは明らかな敵意だった。そのあとすぐに我に返った先輩は、怒鳴ったことでめまいを起こしたのか、こめかみを押さえて下を向いた。
「……ごめんなさい。今の、忘れて。」
「…。いいから、とりあえず今は寝てください。」
「……、うん。」と返事が返ってきて、先輩はもう一度静かに布団に入った。今度はこっちに背中を向けて。やがて安定した呼吸運動が始まって、入眠したことが確認できる。
確かに、オレには何にも関係ないことだ。先輩にどんなことが起きようと、オレは先輩を怒鳴る資格なんてないのかもしれない。
――でも。でも、やっぱり納得なんてできなかった。放っておくことなんて、できはしなかった。
「ねえ……先輩?
先輩はやっぱりわかってないです。オレがどれだけ、先輩のこと、好きなのか。」
先輩がオレとの間に引いた一本の境界線は、いくら越えたくても、どうすれば超えられるのか、わからなかった。
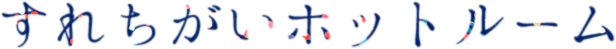
先輩をもう一度寝かせてから、次に先輩が目を覚ましたのは、すっかり日が暮れて、完全下校の時間が迫っていた時だった。
櫻井先生にはオレが送っていくと告げて、住所を聞き出した。(元々住所は去年の夏休みに調べていたけど、念のためだ。)気まずい先輩との間に流れる空気になんとか立ち向かって、先輩に背中に乗るように促した。
「先輩、乗ってください。」
「…いいよ、大丈夫。」
「……はぁ。じゃあ言い方を変えます。
途中で倒れられたら迷惑なので、オレの背中に乗ってください。」
いよいよ口をつぐんだ先輩は、やがて遠慮がちにオレに背中を預けた。立ち上がって、先輩の重みを感じながら、寒い冬空の下を歩く。
引き裂かれるぐらい、心臓が痛かった。先輩の温もりはこんなにも近くにあるのに、少しも嬉しくはなかった。謝罪の言葉は喉の奥につかえて、出てこない。暖かかったあの夏の日のオレと先輩は、一体、どこに行ってしまったんだろう。
あの時よりもずっと体力も精神力も増した。先輩への想いも、ずっと強い。
でも今、そばに居たくて仕方なかったはずの先輩と一緒にいるのに。
どうしてこんなにも、心が痛いんだろう。先輩の心は、どこにあるんだろう。
どうすれば、幸せだったあの頃に戻れるんだろう。
「ねえ、先輩?」
「……うん。」
「オレの前ぐらい……オレの前でぐらい、繕わないでください。
オレ、もっともっと、先輩に頼られるぐらいしっかりするから。だから、…っ」
辛い時は、笑わないで。
そう言いたかったはずの口からは、それ以上何も漏れなかった。
きゅ、とオレの首に回された先輩の腕がわずかに震えていて、それ以上の言葉を遮断していた。
あぁ、と思う。
この人はこうやって、何もかも抱え込んで、抱え込むことで、すべてのものから自分を守っているんだと。
一度でも誰かに弱みを見せたら、今にも崩れて立ち上がれなくなりそうだから。
だからこうして、壁を作って自分を保っているんだと、わかった。
そうわかったから、なんだか無性に、泣きたくなったんだ。