私は雷門中学校二年生の秋雨紫苑である、あの伝説の雷門中に通えることは心からの誇り、サッカーは昔から大好きで見ていたし、あの伝説を知らないわけではないし、何より名門中の名門に通わせていただけることは本当にありがたいことなのです、しかしそれは、秋雨の名を授かった私秋雨家令嬢としてここに通うこと、ここで学ぶことは当たり前のことなのです。
そんな私は冒頭の通り令嬢で、敬語でいることが癖、と言いましても人を選んでおりますが、そして令嬢だという肩書きの所為で、ついこの間知り合ったばかりのご子息とも仲良くならなければいけない、どんな悪い性格のご子息ご令嬢から自分なんかが仲良くしていいはずがない眩しいぐらいのご子息ご令嬢全ての方と、しかしついこの間知り合ったご子息は後者だったにしても出会った瞬間に息を飲みました、そう出会った瞬間私は彼に見惚れ恋心というものを抱いたのです、名のある家柄とは皆仲良くしていくのは将来的に仕方のないことだけれど、彼だけは将来を預けてしまいたいと今日この頃から思ってしまうのです。
しかしそんなことはどうでもいいのです、私、秋雨紫苑は、ついこの間知り合った、そうそれも本当にたった一週間前の話、お父さんに言われついて行った先のパーティーで出会った神童家のご子息の拓人さんに、分かりやすいまでに好意を抱いてしまったのです。
…と、先程も申したのですけれど。
そのパーティーには知った家もいたけれど、初めて出会った拓人さんに、あの笑顔と芯のある声に、見え隠れする人間の本性に、何よりも気さくなところに、ものの見事に心を奪われてしまい、ぽっかりと空いた自分自身にこの頃寂しく思うぐらいなんですもの。
こういう時だけです、自分も令嬢で良かったと思えるのは。
そしてこういう時だけです、丁寧な言葉を選んで話せる喜びを感じたのを。
だけど、ええ、そうです、人気者で、成績優秀で、所謂才色兼備、そんな彼がこんな自分に釣り合うはずなんてなく、今日も私は一言も言葉を交わすことなく、拓人さんを二年生の後者から遠い遠いサッカーグラウンドを見つめるだけです、豆のように小さい拓人さんに、必死こいて目を向けるのです。
それはとても惨めで、彼と最近知り合ったという事実を塗り替えたいぐらいで。
「…今日は、雨が降りそうですね、拓人さん」
珍しくもない稲妻の響く音を耳にしながら、迎えを断ったことを今後悔する、そう今日こそは一緒に帰ろうと声をかけようとしていたのです。
でも一年生のころも今現在進行形の二年生も私は同じクラスではなくて、彼を誘って帰る、なんていうイベントは頂点にも等しく難しく実行に移すことなどできないわ。
「…ああ、もうこんな時間なのですね、帰らなくてはいけません」
誰かが聞いてるわけでもいないのに独り言を呟いてしまうなんて寂しくって仕方がない。
普段なら迎えのくる時間まであのグラウンドを見つめているけれど、今日はと思って迎えはいらないと行ってきたの、それは決意を表すため、だけれど空はどんより空気も重苦しい湿気も出てきてこれ以上長居してしまったら鼻につく雨の匂いにまぎれ濡れてしまうかもしれない。
関さんに連絡するべきなのかしら、ええそうです拓人さんにじいやがおられるように、私にもお付の人ぐらいいるのです。
なんてぐだぐだと静かな廊下でしても仕方がないので大人しくここは帰ることにしましょう、そう思い早めに部活を切り上げている様のサッカー部を数秒見つめたあと、静かに下駄箱へ足を運ぶ。
今日も何もできないまま、これはきっと明日も出来ない、そして明後日もその先もずっと、出来ないままなのかもしれない。
拓人さん、私は貴方に恋をしました、あの日あの時叶うはずがないと言われる、そう所謂初恋というものを、貴方にしてしまったのです、家柄を求めてくる人たちは多かった、だけれど私は自分の気持ちを尊重してくださった父に甘えて、我が儘ともとれる断りをしてきたの、だけれど、貴方には、そのままを伝えたつもりでいました、あの日、あの時。
「拓人さん…」
恋焦がれるものほど鬱陶しいと思ったことはない、時に面倒くさいこれにため息が増えたのは言うまでもなく、だ。
駐車場がそびえる裏門から帰ろうと二年校舎から出て、一年校舎と繋がる渡り廊下に足を出したとき、酷い稲光と雨が今にも私を攻撃して、すぐに雨に濡れて帰れという言葉が脳内を走った。
好きなものに忠実であるが故の失敗、またため息をついて、屋根から出てしまおうとしたとき、帰る方向から車の甲高く独特な注意音と水を弾くびしゃりとした音、目の前に真っ黒でそれでいて立派なリムジンが、タイミングよくきたではないか。
ナンバーがよく見えない、けれど自分の家のものに似ているそれに疑問が浮かび上がると一人の男性が降りてきてリムジンの扉を開いたので、若干の怖さを隠して、一歩後ろへ下がると、数日前に聞いた声がそっと後ろから聞こえた。
声の主は私の両肩に手をそっとそえ、私より背の高い声の主がきっと少しかがみながら私の耳元に「乗って」と囁きかける。
そのまま押されるがまま乗ったのは運転席からだいぶ離れた後ろのリラックスできる部分で、奥に座ってきょとんと扉を見ると、あの優しい声が男性と話し終えて乗ってきたのです。
嗚呼、きっと私は彼のそんなところも好きなのかもしれない。
男性がいなくなり、急いできたのだろう汗や雨を滴らせる彼も一段落着いたとでも表すかのように息をつき、私の隣にゆっくり腰をかけゆっくりと肩を抱いてくる。
「遅くなってすまない」
「…え、あ…えっと、」
「どうかしたのか?」
「いいえ、その、どうして…」
「俺の名を呼んだだろ?…もしかして俺の聞き間違いだったか?」
「あ、いえ、…はい、呼びました、拓人さん」
「ならいいんだ…こんな形で済まないが、一緒に帰ろう、紫苑」
「はい」
どんなに好きでも上辺である彼の気持ちに、私は分かっていても縋っている。
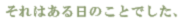
運命だと思える相手にであったのです。
(世間一般とは無縁な)
(それも幸せの始まりではない)
(彼からしたら迷惑なもので)
(でも逆らっていいものでもない)
(そうこれは所謂)
(世で言う政略結婚というもの)
(…拓人さん)
(どうかしたのか?紫苑)
(…いいえ、呼んでみただけです)
(おかしな奴だな)
そう言って笑う笑顔が自分には勿体無いのです。
そんな私は冒頭の通り令嬢で、敬語でいることが癖、と言いましても人を選んでおりますが、そして令嬢だという肩書きの所為で、ついこの間知り合ったばかりのご子息とも仲良くならなければいけない、どんな悪い性格のご子息ご令嬢から自分なんかが仲良くしていいはずがない眩しいぐらいのご子息ご令嬢全ての方と、しかしついこの間知り合ったご子息は後者だったにしても出会った瞬間に息を飲みました、そう出会った瞬間私は彼に見惚れ恋心というものを抱いたのです、名のある家柄とは皆仲良くしていくのは将来的に仕方のないことだけれど、彼だけは将来を預けてしまいたいと今日この頃から思ってしまうのです。
しかしそんなことはどうでもいいのです、私、秋雨紫苑は、ついこの間知り合った、そうそれも本当にたった一週間前の話、お父さんに言われついて行った先のパーティーで出会った神童家のご子息の拓人さんに、分かりやすいまでに好意を抱いてしまったのです。
…と、先程も申したのですけれど。
そのパーティーには知った家もいたけれど、初めて出会った拓人さんに、あの笑顔と芯のある声に、見え隠れする人間の本性に、何よりも気さくなところに、ものの見事に心を奪われてしまい、ぽっかりと空いた自分自身にこの頃寂しく思うぐらいなんですもの。
こういう時だけです、自分も令嬢で良かったと思えるのは。
そしてこういう時だけです、丁寧な言葉を選んで話せる喜びを感じたのを。
だけど、ええ、そうです、人気者で、成績優秀で、所謂才色兼備、そんな彼がこんな自分に釣り合うはずなんてなく、今日も私は一言も言葉を交わすことなく、拓人さんを二年生の後者から遠い遠いサッカーグラウンドを見つめるだけです、豆のように小さい拓人さんに、必死こいて目を向けるのです。
それはとても惨めで、彼と最近知り合ったという事実を塗り替えたいぐらいで。
「…今日は、雨が降りそうですね、拓人さん」
珍しくもない稲妻の響く音を耳にしながら、迎えを断ったことを今後悔する、そう今日こそは一緒に帰ろうと声をかけようとしていたのです。
でも一年生のころも今現在進行形の二年生も私は同じクラスではなくて、彼を誘って帰る、なんていうイベントは頂点にも等しく難しく実行に移すことなどできないわ。
「…ああ、もうこんな時間なのですね、帰らなくてはいけません」
誰かが聞いてるわけでもいないのに独り言を呟いてしまうなんて寂しくって仕方がない。
普段なら迎えのくる時間まであのグラウンドを見つめているけれど、今日はと思って迎えはいらないと行ってきたの、それは決意を表すため、だけれど空はどんより空気も重苦しい湿気も出てきてこれ以上長居してしまったら鼻につく雨の匂いにまぎれ濡れてしまうかもしれない。
関さんに連絡するべきなのかしら、ええそうです拓人さんにじいやがおられるように、私にもお付の人ぐらいいるのです。
なんてぐだぐだと静かな廊下でしても仕方がないので大人しくここは帰ることにしましょう、そう思い早めに部活を切り上げている様のサッカー部を数秒見つめたあと、静かに下駄箱へ足を運ぶ。
今日も何もできないまま、これはきっと明日も出来ない、そして明後日もその先もずっと、出来ないままなのかもしれない。
拓人さん、私は貴方に恋をしました、あの日あの時叶うはずがないと言われる、そう所謂初恋というものを、貴方にしてしまったのです、家柄を求めてくる人たちは多かった、だけれど私は自分の気持ちを尊重してくださった父に甘えて、我が儘ともとれる断りをしてきたの、だけれど、貴方には、そのままを伝えたつもりでいました、あの日、あの時。
「拓人さん…」
恋焦がれるものほど鬱陶しいと思ったことはない、時に面倒くさいこれにため息が増えたのは言うまでもなく、だ。
駐車場がそびえる裏門から帰ろうと二年校舎から出て、一年校舎と繋がる渡り廊下に足を出したとき、酷い稲光と雨が今にも私を攻撃して、すぐに雨に濡れて帰れという言葉が脳内を走った。
好きなものに忠実であるが故の失敗、またため息をついて、屋根から出てしまおうとしたとき、帰る方向から車の甲高く独特な注意音と水を弾くびしゃりとした音、目の前に真っ黒でそれでいて立派なリムジンが、タイミングよくきたではないか。
ナンバーがよく見えない、けれど自分の家のものに似ているそれに疑問が浮かび上がると一人の男性が降りてきてリムジンの扉を開いたので、若干の怖さを隠して、一歩後ろへ下がると、数日前に聞いた声がそっと後ろから聞こえた。
声の主は私の両肩に手をそっとそえ、私より背の高い声の主がきっと少しかがみながら私の耳元に「乗って」と囁きかける。
そのまま押されるがまま乗ったのは運転席からだいぶ離れた後ろのリラックスできる部分で、奥に座ってきょとんと扉を見ると、あの優しい声が男性と話し終えて乗ってきたのです。
嗚呼、きっと私は彼のそんなところも好きなのかもしれない。
男性がいなくなり、急いできたのだろう汗や雨を滴らせる彼も一段落着いたとでも表すかのように息をつき、私の隣にゆっくり腰をかけゆっくりと肩を抱いてくる。
「遅くなってすまない」
「…え、あ…えっと、」
「どうかしたのか?」
「いいえ、その、どうして…」
「俺の名を呼んだだろ?…もしかして俺の聞き間違いだったか?」
「あ、いえ、…はい、呼びました、拓人さん」
「ならいいんだ…こんな形で済まないが、一緒に帰ろう、紫苑」
「はい」
どんなに好きでも上辺である彼の気持ちに、私は分かっていても縋っている。
運命だと思える相手にであったのです。
(世間一般とは無縁な)
(それも幸せの始まりではない)
(彼からしたら迷惑なもので)
(でも逆らっていいものでもない)
(そうこれは所謂)
(世で言う政略結婚というもの)
(…拓人さん)
(どうかしたのか?紫苑)
(…いいえ、呼んでみただけです)
(おかしな奴だな)
そう言って笑う笑顔が自分には勿体無いのです。