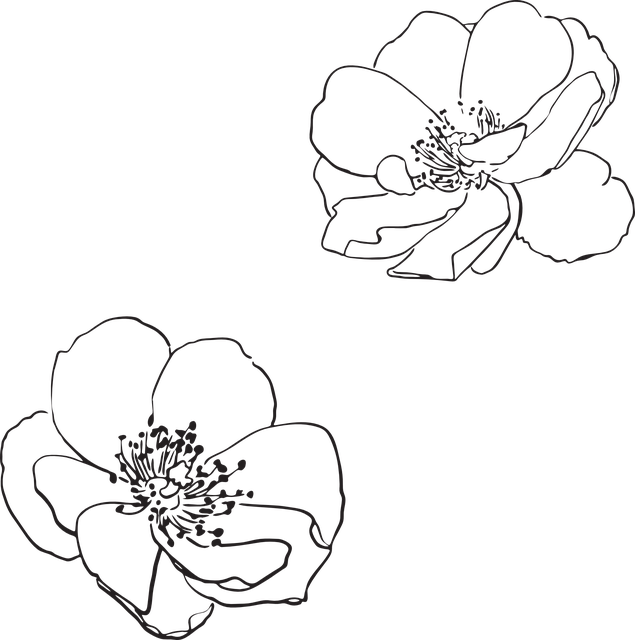
悪童の精度
「月島軍曹。網走へ出発するぞ」
「はい。鶴見中尉殿」
月島は馬車の御者台に乗った。そして手綱を握り、馬を走らせる。彼は振り切るように、まっすぐ前を見据えていた。もう迷わない。前へ進むしかないのだ。その先が地獄だろうとも。
※
ざぁざぁと空から降る大きな雨粒が、月島の身体を一層冷やす。雨が地面に叩き付けられ、泥色の飛沫となり脚絆を汚す。月島は気にも留めず、厳しい表情のまま大股で歩く。彼は今、虫の居所が悪い。
上官である鶴見は、アイヌが隠した金塊の手がかりである刺青人皮を集めている。網走監獄に収監された“のっぺらぼう”という囚人が、金塊の隠し場所を記した暗号を囚人達に彫ったものだ。刺青囚人集団が脱獄して以降、行方を探している。相手を騙し時に裏切り――出し抜く。血生臭い争奪戦を有利に進むため、一計を案じた。
夕張にいる腕利きの剥製屋に、偽物の刺青人皮を作らせたのだ。
五枚の偽物が完成し――九死に一生を得た後、やっと鶴見に届け終えた。任務は無事に完了した。それなのに、月島の心境はすっきりするどころか、頭上に広がる黒く凄む空と同じくらい澱んでいる。
「芸術家の本懐は、作品を世に遺すことだ」
五枚の偽物人皮に頬擦りする鶴見を、月島は感情を殺して眺める。本物と見間違う程の精巧な偽物が出来るまで、月島は数週間とある剥製屋の家で過ごした。
『集中、集中!』
『僕は鶴見さんの言うことしか聞きませんから!』
監視という名目だが、言うことを聞かない幼子をお守りするようなものだった。剥製屋――江渡貝は、昨日起きた夕張の炭鉱事故で命を落とした。彼は死んだ母親と、墓場から掘り起こした複数の死体を剥製にして、静かに暮らしていた。
狂気の安寧生活を終わらせたのは鶴見だった。江渡貝親子の歪んだ関係を断ち切らせ、刺青人皮争奪戦に関わらせた。おかげで江渡貝は、対抗勢力に狙われ――夕張炭鉱内へ逃げる最中、爆発事故に巻き込まれたのだ。
無関係だった人間を、こちら側に引き込んで死なせてしまった。その事実が、月島の傷だらけの心に滲みるのだ。まるで、膿んだ傷口に塩を塗りたくられたみたいに。
頭によぎるのは、偽物を託す江渡貝の顔。爆発で落ちた木材で脚が潰され、身動きが取れない彼は既に死を受け入れていた。自分に課せられた役目を終え、吹っ切れたように見えた。
『これを鶴見さんに! 鉄と伝えて下さい! 鶴見さんなら、あの人ならそれだけで分かるはずです!』
もう少し上手く立ち回ることが出来たら、彼を死なせずに済んだかもしれない。既に終わったことを、無意味に考えてしまう。江渡貝の死を聞いた鶴見は、特に何も言わず顔色すら変えなかった。
暫し沈黙した後、ご苦労と月島を労うだけだった。口封じの手間が省けたと思ったのか――定かではない。曲者同士が繰り広げる金塊争奪戦において、数歩先を見据える上官が何を考えているのか、月島が知る由もないのだ。
遣る瀬ない気持ちを押し込み、降りしきる雨の中を歩く。鶴見にとって、月島も江渡貝も駒の一つにすぎない。月島自身はそれでも構わないと思っているが、江渡貝はどう思っていたのだろうか。それを知る術は、もうない。
かつて月島は尊属殺人を犯し、死刑囚だった。彼を監獄から出すために、鶴見は世情を上手く利用した。
当時の国際情勢では、日本と露西亜は敵対しており、近い内に戦争が始まるだろうと誰もが予想していた。おまけに鶴見は月寒の特務機関に所属しており、露西亜へ駐在する予定であった。月島を露西亜語通訳ということにして、監獄の外へ連れ出そうとしたのだ。
来るべく露西亜との戦争を見据え、露西亜語に精通している者を、みすみす殺してしまうのは憚られる。鶴見はそういった事情を全て汲み取り、画策した。
無論、月島は外国語など話せない。故郷の佐渡島でも勉強したことがない。露西亜語なんて以ての外だ。ならば死に物狂いで勉強しろ。嘘が真実になる瞬間まで、月島はやり遂げた。何も失う物がない人間ほど、怖いもの知らずだ。鶴見が行った
それから九年の月日が経ったが、今も月島は鶴見の腹心として働いている。鶴見に謀れたと分かっていても、月島には帰る故郷はない。待っていてくれる家族も、
いご草と呼ばれたあの子。
悪童。荒れくれ者。糞ガキ。人殺しの息子。故郷の佐渡島で鼻つまみ者だった彼の名前を呼び、普通に接してくれた女性だ。彼女の癖っ毛が、いご草そっくりだと島の連中は揶揄った。だけど月島は彼女の髪が好きだと伝えた。
日清戦争が終わったら、二人で駆け落ちする予定であった。
極寒の満州という地で、繰り広げられる殺戮の日々。生きるか死ぬかの極限状態の中、故郷で待っていてくれる人がいる。帰る場所がある。月島にとって、生きる希望だった。たったそれだけでも、生き残って故郷へ帰るに値する十分な理由になる。
幸せとは指の間から零れ落ちる、砂粒である。やはり人殺しの息子は、人並みの幸せを手にすることも難しいのか。せめて純朴な人生を送ることが出来れば良い。分不相応な暮らしは望んでいないのに、それすら求め過ぎなのだろうか。
彼女は月島が帰郷する前に、忽然と姿を消してしまった。小さな狭い島から出て、自分達のことを誰も知らない場所で新たに生きていく。それが叶わぬ夢となってしまったのだ。
月島基は日清戦争で戦死した。あの子は
ふとした瞬間、我に返った。
デマの出処はどこなのか。火がないところに煙は立たないと言うように、必ず出処があるはずだ。人の口には戸は建てられない。周囲を問い詰めると、出処が判明した。
犯人は人殺しの噂がある、素行の悪い父親だった。父親のせいで島の連中に、幼い頃から悪童と謗られ嫌な思いを数え切れないほどしてきた。どこまで人生の足を引っ張るつもりなのか。気が付いたら
固く握られた拳と着古した着流しは、洗っても落ちそうにない程べったりと血が付着している。鉄錆の臭いはもはや悪臭と言っても過言ではなかった。周囲に脳梁らしきものが飛び散り、父親は変な鼾をかいて脱力していた。放っておいても、その内勝手に死ぬだろう。父親という輪郭は喪われ、ただの物体へ成り果てていた。現場に駆けつけた官憲は、陰惨な光景を目にして顔を青ざめていた。
あの子を死なせた父親を、この手で殺すことが出来て満足だ。もうこの世に何も思い残すことはない。陸軍監獄で死刑執行を待つ日々は、恐ろしいほど穏やかに過ぎ去る。月島は死刑を受け入れていたのだ。そんな時に、当時陸軍少尉だった鶴見が訪ねて来た。
鶴見と二度目の邂逅で、微かな光を見い出すことになる。
『
佐渡金銀山を見に来た財閥企業の男から、是非息子の嫁にと見初められて東京へ嫁いだという。彼女の両親にしてみれば、玉の輿か悪童だ。大事な娘を、悪評まみれな男に嫁がせるわけにはいかない。突如舞い込んだ縁談話を、両親は何が何でも破談させるわけにはいかなかっただったろう。
島全体を巻き込んだ大芝居が始まった。月島の父親に大金を握らせ、息子が戦死したと吹聴させたのだ。そして彼女は極秘の内に東京に連れ出され、両親も娘の近くに揃って移住した――。彼女の両親に問い詰めたら真相を吐いたそうだ。鶴見は淀みなくそう語った。
あの子は崖から身投げしていない。その事実に、月島は深く安堵した。生きている事実だけでも知れて良かった。遠く離れた東京で、彼女が幸せに暮らしているのなら良い。寧ろ結婚相手が、醜聞の悪い自分でなくて良かったとさえ思った。父親を殺し、陸軍監獄で過ごした毎日を通じて、月島は悟りの境地に至ってしまったのだ。
鶴見は東京で暮らすあの子に会いに行き、月島の上官だと伝えたそうだ。すると彼女から、ひと房の髪の毛を託された。月島の遺骨があれば、一緒に埋めて欲しい。好きと言ってくれた髪の毛だから、と。月島は掌にある、いご草に似た彼女の髪を眺めた。あの子にとって、既に月島は戦死者なのだ。
『俺の名前を呼んでくれる、おめが好きらすけ。その髪も俺にとって、いとしげら。おめの髪をからかう奴は、俺がしゃつけてやる』
『だすけん、基ちゃんは嫌われたっちゃね』
七瀬海岸にある夫婦岩。ゴツゴツした岩礁に波が打ちつけられ、真白い飛沫を上げる。海鳥の鳴き声と迫り来る波の轟音が鼓膜に響き、懐かしさを覚えた。かつて月島が手放した、大事な思い出の光景だ。
『遺体が見つかったんだ』
日露戦争末期。満州にある奉天という地で、日本と露西亜は最後の陸上戦を繰り広げていた。月島は野戦病院で、佐渡島出身だと言う男と出会った。濁った魚みたいな色の目をした男だった。
月島がずっと信じていた内容とは真逆の情報。あの子の骨が、殺した父親の家の下から見つかった。骨が掘り返されるのを、島の連中が見ていた――。
その言葉によって、月島は絶望の底に叩きつけられたと同時に、腹の底から怒りが湧き上がったのだ。
あの髪は、埋まっていたものなのか?
彼女は生きている。東京で幸せに暮らしている。そう信じることで月島は、自分の感情を上手に折り合いをつけていたのに。頭の中でプツンと、糸が切れる音が聞こえた。
『どうしても助けたかった。誰よりも優秀な兵士で、同郷の信頼出来る部下で、そして私の戦友だから』
『あの子で、俺を騙して欲しくなかった……!』
心の底から上げた悲痛の叫びは、露西亜側から振り落ちる砲弾と共に砕かれた。
月島を監獄から助け出すためには、露西亜語の通訳という方便だけでは弱い。裁判を行なっても、上手くいかないだろう。だから鶴見は更に一計を講じた。
殺されても当然の父親像が若干足りなかったので、島の連中の前で月島の実家から遺骨を掘り出してみせた。幼い頃から虐待され、過去に殺人も犯した噂もある素行の悪い父親によって、出征中に婚約者を自殺に見せかけて殺された。月島は逆上したあまり、殴った末の過失致死だった――。鶴見が企てた工作は、情状酌量の余地があると判断された。
だから月島は、今も生きているのだ。
あの子は月島の聖域だ。例え鶴見が月島を助けるために取った行動だとしても、冒涜行為に他ならない。穢されたと思った。心の一番柔らかい部分を、鋭利な刃物で滅多刺しされた気分だった。
結局あの子が生きているのか、死んでいるのか今も分からない。真相は深い海の底に沈んだまま。もう、どうでも良い。今更真相を知ったところで後の祭りである。
激昂の末、父親を殴り殺した瞬間。鶴見が施した甘い嘘を信じた瞬間。救われた命を無駄にしないために、月島は足がけ九年間鶴見の期待に応え続けた。
人生の分岐路を誤った結果、今があるのだ。
あの子にまつわる真相を解明する気力は、鶴見が注ぎ込んだ
滅私奉公ではない。崇拝や信奉でもない。怨恨とも違う。月島が抱く鶴見への感情は、例えるなら大きな鍋の中でそれらの感情がごちゃ混ぜにされて、ぐつぐつ煮詰められたものだ。一言で簡単に言い表せるものではない。鶴見が織り成す甘い嘘にかぶりつく。この表現が月島にとって、一番しっくりするのだ。
月島に出来ることと言えば、それくらいしかない。後生大事にしていた――あの子の髪の毛だと思っていた物が、小樽運河の底へ沈みゆく。余生は鶴見劇場のために使うと決めた瞬間だった。
だから、汚れ仕事は何だってやった。今まで、鶴見が目指す野望の邪魔になる者は全て葬って来た。江渡貝の死を、今更哀しむ理由はないのだ。もし彼が不慮の事故で死ななかったら。口封じのために手を汚すのは、月島だったかもしれない。