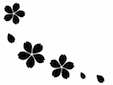しとり、しとり。
暖かさを連れた雨が静かに降る。
この雨では春を知らせる花も濡れて多くの花弁を散らしているだろう。生憎自分の部屋からはその様子を知ることは出来ない。
随分と暖かくはなってきたもののやはり雨が降れば空気が冷やされ、ぶるりと身体が震えた。春の雨を見るのも一興かと思っていたがこのままでは風邪を引いてしまう。立ち上がり窓と閉めようと手をかけたとき、ふと僅かに開いた襖の向こうに視線が止まった。この襖の先は廊下で、さらに先は庭になる。だから目に映ったものを疑った。
臙脂の傘。
ここから庭の向こう、ましてや塀の向こうが見えるわけがない。さらにその傘の色を愛用していた人物はもういないはず。
嘘だ、と思って勢いよく襖へと駆け寄り思い切り開けた。
「これはこれは、いらしていたのですね」
傘の持ち主は予想通りで、記憶に残る姿をしていた。突然開かれた襖から自分が飛び出てきたことに驚きつつもすぐに柔らかい笑みを浮かべている。
何故ここに、という疑問は問えば消えてしまうのではないかという根拠ない不安に喉の奥で止まった。
「このような天気ですが、桜を見に行きませんか?」
彼の誘いに遠い記憶が蘇る。
確かその日もこのような雨の日であった。部屋に籠もりがちな友人を外に引っ張り出そうと相談していたときに、彼が嬉しそうにそう提案した。そうして3人で雨の中、桜を見に行ったのだった。
これは夢か現か。
いや、幻なのはわかっている。彼は死んだのだ。あの初夏の日に。名前と引き換えに死んだのだ。
「先にいってますね」
彼の言葉にいつの間にか俯いていた顔を上げると、もう彼は背中を向けて歩き出していた。じゃり、じゃり、と水分を含んだ地面を踏みしめる音の合間にぱしゃりと水が跳ねる音が鳴る。
「待て!行くな!」
転がるように部屋を飛び出し草履も何も履かないまま庭へと降りた。小さな庭である。彼の行く先には塀しかないというのに、不思議と先が霞んで何も見えない。
「いくな!私を、置いて逝かないでくれ…っ」
その霞の先に消える彼に向かって叫ぶも振り向かない。言葉は、もう届かない。
『桜が咲く頃にまた参ります』
姿がすっかり見えなくなった頃、耳元で聞こえた彼の声。
姿は見えなくとも笑っている姿を容易に想像出来た。
「…そうか。ならば今度はあいつと一緒に来るといい」
また3人で花見をしよう。
頬を伝う雨を拭うと、目の前に数枚の桜の花びらが水たまりに浮いているのに気づいた。
幻だが幻ではない。
何かをするというわけでもなく、ただ姿を現したのは彼らしい。
雨が止み、雲の切れ間から光が差し込み出した。太陽の光を浴びた花弁が3枚、寄り添うように水面をたゆたっていた。